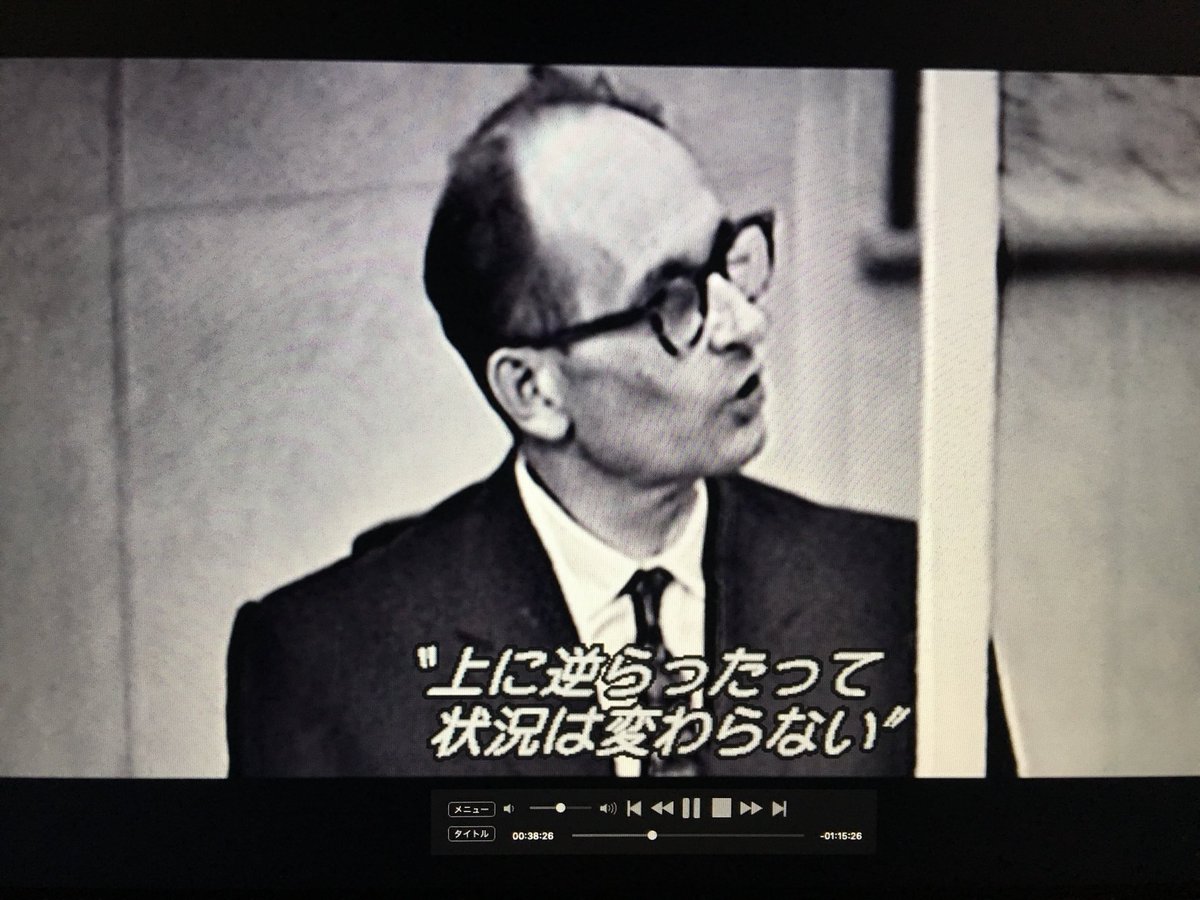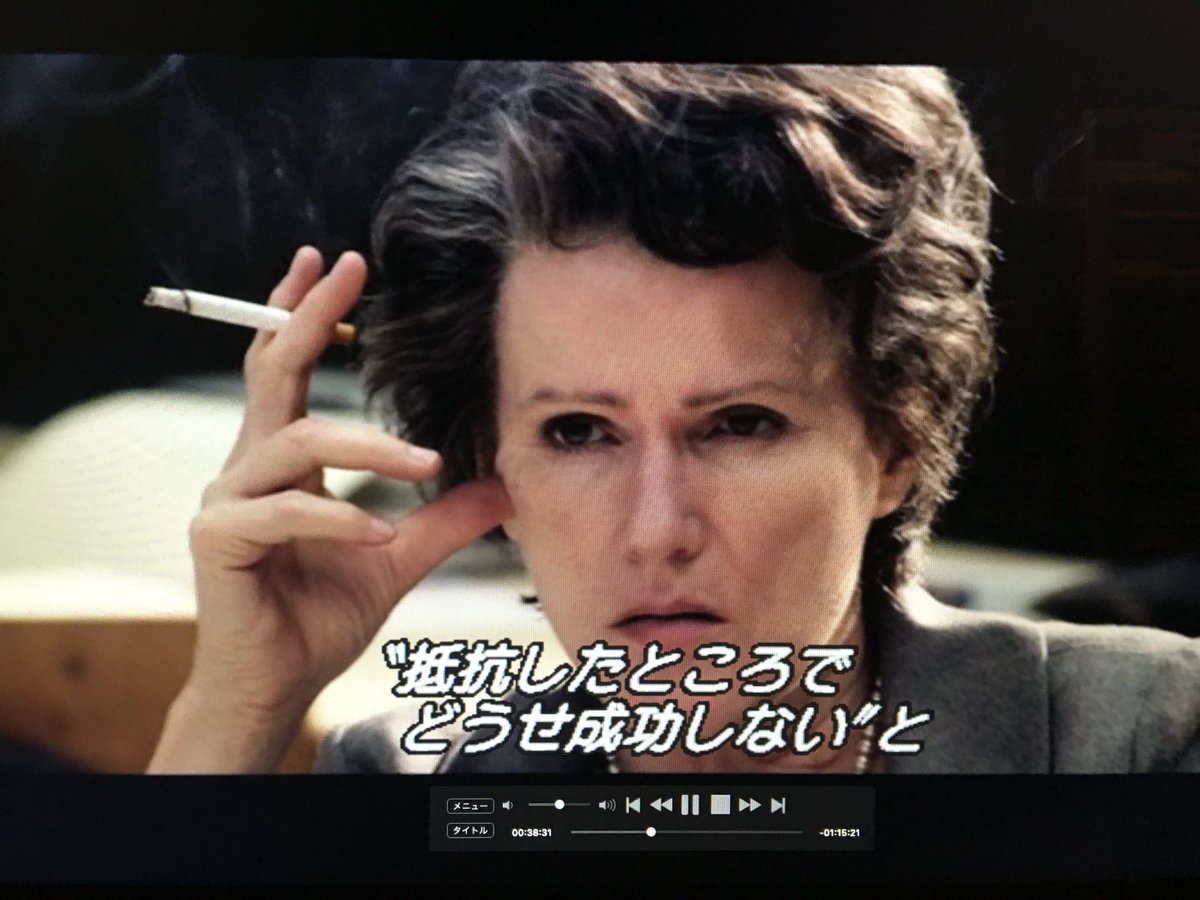626
映像よりも音の方が人は感情を動かされやすい。ナチスもラジオで急成長したし、マッカーシズムの怨嗟はラジオによる煽りで燎原の火のように広がったけどテレビが活用されてから急に萎れてしまった。マクルーハンはラジオを熱いメディア、テレビを冷たいメディアと言ってますね。
627
縦軸に「戦略のある、なし」、横軸に「根性のある、なし」を取る。最悪なのは「戦略はないけど根性はある」という組織で、これは「徒労感ばかり募って成果はさっぱり出ない」という状況を招きます。かつての日本軍の「死の行軍」ですね。
628
正解がない時代こそ当たり前なんです。「生き方の正解」があった時代の方がずっと短いし、そもそも健全でない。ヴァレリーの詩「風立ちぬ、いざ生きめやも」って、そういう意味でしょう。不確実性に身を投げ出すのは怖い、でも身を投げなければ何も始まらない、ということです。風、吹いてますものね。
629
誰もが「株式会社オレ」の経営者です。自分で経営しなければ、誰かに勝手に経営されてしまう。それは自分の運命を他人にコントロールされてしまうのと同じことです。
630
仕事の質は二極化する傾向があります。面白い仕事をやるとそこにスジの良い人が集まり、その人が次の面白い仕事を呼ぶので仕事のポートフォリオはどんどんキレイになる。逆は悲惨です。「人と仕事」って人生そのものですから、無理してでも面白い仕事をしないと人生がつまんなくなりますね。
631
よく「偽善だ」と批判する人がいますけど、偽善で何が悪いんでしょうか。「批判するだけで何もしない人」より「偽であっても善をなす人」の方が遥かに社会にはありがたい。偽善すらできなければ人類に救いなんかありません。
632
これはチェスタトンが言ってることですけど、普通、私たちは「理性を失うこと」を「狂気」と思ってるわけですけど、真逆で、実際は「理性だけになること」が「狂気」なわけですよね。だから高偏差値の人が学生運動やカルト宗教に没頭して理性に導出された教義に則って人をリンチして殺すわけです。
633
モノは二回創造される。一度目は構想として、二度目は実現として。一度目の創造はリーダーシップが、二度目の創造はマネジメントやスキルが鍵になる。音楽も絵画も同じですが「二度目の創造」のスキルばかり高めても「一度目の創造」がなければ虚しい。
634
自分のことをあんまり無垢だ思わない方がいい。マネジメントが米国で発達したのは綿花農園で数百人の奴隷を管理するという必要があったからです。ビジネスやマネジメントにはそういう原罪性がある、自分の手は血まみれなのかも知れない、という恐れを持たない人が一番怖ろしい。 twitter.com/shu_yamaguchi/…
635
競争には必ず勝者と敗者が生まれますが、創造には勝者しか生まれません。企業の活動もまた、競争から創造へとシフトすることで、敗者のない多様な世界が開けていく。これこそ21世紀の社会が目指すべき方向です。競争戦略論なんて「競って戦う」という前提のフレーム自体がもう時代錯誤だと思いますね。
636
日本は本当に「茶番社会」になりつつありますね。バカなことには「バカじゃないの」とみんな声をあげてください。 joband.biz/505?fbclid=IwA…
637
よく勘違いされてますが「ブルシットジョブ=クソ仕事」は仕事そのものより、仕事の「意味づけ」で決まる側面があります。この「意味づけ」は本来リーダーの仕事なのですが、統計からいうと全管理職の一割程度しかやってない・・・なので私たちは自分の仕事の意味を自分で作っていく必要があります。
639
過去を振り返ってみてあらためて思うのですが、「何かを選択する」というとき、結果的に正しかったと思える選択は、常に「自分が選択する」という主体感覚より「何かに選択させられてる」という受動感覚の方が強かったように思います。
640
競争において「時間軸の捉え方」はとても重要です。スプリントの戦い方でマラソンを戦えば惨敗は目に見えてる。人生はとても時間軸の長いゲームなのに多くの人は非常に短く捉える傾向があります。これは長期目線でマイペースに歩を進める人にとっては有利なことで、あんまり焦らなくて良いと思います。
641
少ない順に並べると1:難しいことを簡単に言う人、2:難しいことを難しく言う人、3:簡単なことを難しく言う人、4:簡単なことを簡単に言う人。一見すると「3」の人はとても頭がよく見えるけど、時間をかけて読解しても得られる洞察は「当たり前だろ」ということが多いので要注意ですね。
642
圧倒的な成果を出す人はなにか必殺技の様なものを持ってると考える人がいますが、そんなものはありません。個々の行動に大した違いはなく、本質は「適切な順番」なんですね。「ビンタ」と「抱きしめ」。「抱きしめてからビンタ」と「ビンタしてから抱きしめ」では結果はまったく違う。文脈が全てです。
643
日本のリーダーはよく「知らなかった」を言い訳に使うんだけど重職の人選はリーダーの最重要責務なんでインテリジェンス=情報を集めてチェックするのが海外では常識です。お友達関係で仕事を回したということなんでしょうけど運動会じゃないんだから勘弁してよ、と言いたい。
nikkei.com/article/DGXZQO…
644
デザイナーでもない人がデザインの考え方を学ぶことに、やっぱり意味があると思うんです。このような世界では誰もが「社会デザイン」に携わっていると考えるべきだからです。問いを立てて課題を見つけてそれをエレガントに解くデザイナーの考え方はあらゆる仕事にも有用だと思うんですよね。
645
貴方は私が思ってるような人ではなかった、ということを批判がましく言う人がいますね。恐らく本人が「他人が期待する自分でありたい」と強く考えているので、これが批判になると思っているのでしょうが、元より「他人なんてどうでもいい」と思っている人は「はあ、だから何ですか?」と思うだけです。
646
揚げ足を取ろうと思ったら相手の足元を見なければなりません。そうすると目線が下がってしまうんですよね。本当は「相手が見ているもの」を一緒に見ることが大事なんですけどね。
647
これは企画書とか提案書も同じです。僕はコンサル時代、コンペに負けたことがないというのが自慢でしたけど、自分が対話をベースに提案書を作ってるのにたいして、競合が一方的主張をベースに提案書を作ってるわけですから、そりゃまあ負けませんよね。 twitter.com/shu_yamaguchi/…
648
そういえばアランも「幸福論」で「悲観は気分の問題だが楽観は意志の問題だ」と言ってましたけど、ホイジンガ の指摘を合わせれば「楽観には知性と意志の両方が要る」ということなのかもしれません。スピノザっぽいですね。
649
この本、ここ十年で読んだ戦略論の本の中で最も学びが大きかったです。低成長の時代に大きく成長した企業の特徴は何か?それがまさに「然るべき時に、然るべき場所にいること」だというんですね。分析や論旨の運び方など、非常にマッキンゼーらしい本です。
amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%8…
650
どんなに安かろうとランキングが低かろう知名度がなかろうと「自分はこれが好き」と言って堂々と選んで幸福になっている人は非常に強いですね。そういう人は攻略も支配もできません。 twitter.com/shu_yamaguchi/…