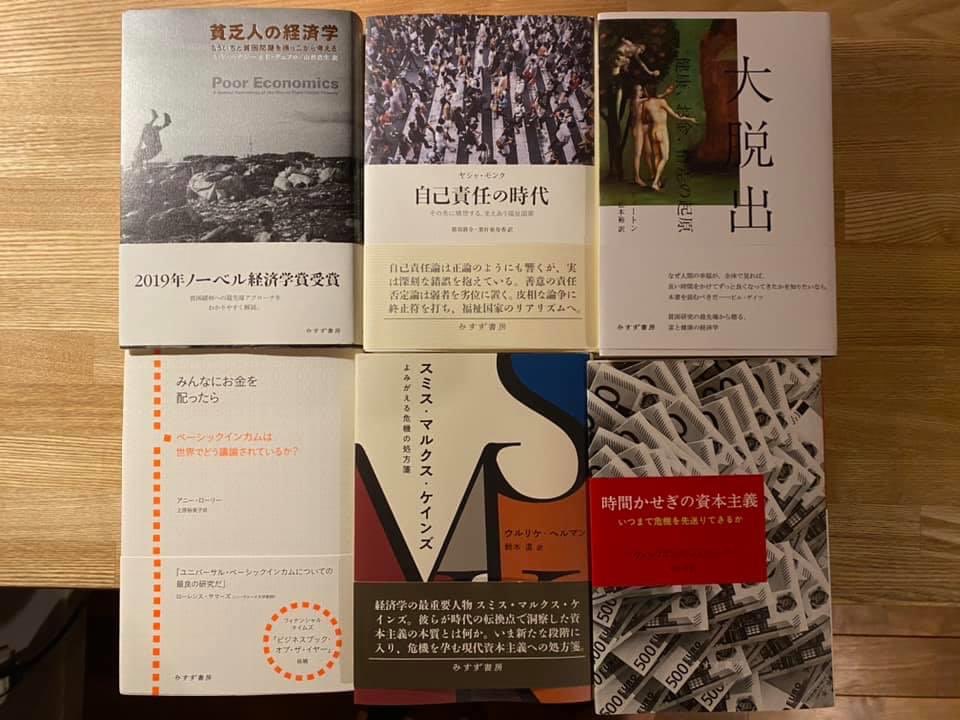501
これはさすがに酷いと思います。そもそも一体なんのための産休・育休制度なのか?子育ての現実も制度のコンセプトも全くわかっていない。残念すぎる。
news.tv-asahi.co.jp/news_politics/…
502
賢くなろうと考えるよりも愚かなことはやめようと考える。普通に考えて無益なことは止め、有益なことに時間を使う。そうすることで結果的に賢明に生きられるのではないでしょうか。
504
自分の幸福にしか興味がない、という人がもっと増えると、世の中は随分と良くなると思うのですけどね…
505
コロナ後にリモートワークを解除するかどうかで会社が社員をどのように考えているかがはっきりする。報酬を支払わない通勤という過酷なシャドウワークを仕事人生に渡って強いるのか?あるいは別の可能性を模索するのか?社員にどんな人生を歩んでほしいと思っているのかがはっきりします。刮目相待。
506
首都圏の平均通勤時間は1時間。コロナ後に毎日の通勤を義務付ける企業は毎日2時間分の無報酬の労働=シャドウワークを義務付けることになる。リモートワーク可能な企業と比較すれば実質、報酬は2割減です。そりゃあ嫌ですよね。労働市場での競争力は確実に低下するでしょう。
507
オリジナリティを気にしてる人が多いようですが、そもそもオリジナリティという言葉そのものが相対性を前提にした概念ですよね。だからオリジナリティということを意識するほど他者を意識しなければならなくなって「素」で居られなくなる、結果本質的な意味での独創性は失われるというジレンマ。
508
残念な人ほどヘンな例外を持ち出して反論する、と指摘しましたけど、これって受験エリートにすごく多いんです。なぜなら受験は例外をどれだけ知ってるかが勝負だからです。動詞の活用とか、試験に出るのは例外的なものばかりですよね?モノすごい悪影響の大きい訓練をヒタスラやってるという…
509
自分の意思を持つこと。家畜の反語である野生を意味するWildという語は、もともと「意思する」を意味するWillの過去分詞形である。つまり野生というのは自ら意を決することで、その逆は他者に阿る、委ねること、つまり家畜となることである。
510
企業再生が「大変な仕事」だということは理解しますが、だからと言って「価値ある仕事」だとはいえません。本来であれば市場から退出すべき企業を再生させることで社会の新陳代謝を阻害するという弊害もある。コロナによって危機に陥る企業を全て再生させるという考えは長期的に禍根を残すと思います。
511
利益には「目に見える利益」と「目に見えない利益」があります。前者ばかりを追いかけていても、それなりに会社は続きますが、やっぱりツマラナイ会社になっていきますね。「魅力的な不良」のような面白い会社は「目に見えない利益」をわかっているし、そういう会社には素敵な人が集まってきますね。
512
問題を見つけるのは確かに難しい。でも「世界が改善の余地がない素晴らしい場所だと思いますか?」と訊かれれば多くの人は「否」と答えるでしょう。ではなにが「否」なのか。その「否」に新しいビジネスのヒントがあります。みんな知ってるんです、あとはやるか、やらないかだけ。
513
老子もディオゲネスも「足るを知る人は幸福だ」と説いたけど、皆がそうなってしまうと需要は飽和して経済成長はストップします。つまり経済成長を求め続けるというのは「永遠に幸福になることを永遠に延期する」ということなんですよね。
514
経営者は自分が交代するまでの数年先までしか考えていない人が殆どですが、新入社員は自分が管理職になる数十年後まで考えます。今日、もっとも長期的な視野で企業の行く末を思考してるのは実は組織の若手層なんですよね。
515
たよーせーたよーせーと最近はよく言われますが、多様性の増大はエントロピーの増大を招く。「砂糖だけ」より「砂糖と塩」のほうが料理の幅は広がるけど、砂糖と塩を混ぜてしまうとゴミになる。この点を理解せずに多様性だけを増大させれば単なるカオスがうまれるだけ。
516
にわかには信じがたい数値ですが本当だとしても違和感はありません。僕は幼少期から非常にクリティカルな人間でそのために学校の先生から徹底的に意地悪された思い出があります。親が謝りに来なければ内申書かない!と騒いでた先生、どうしてんのかな。newsweekjapan.jp/stories/world/…
517
ボルボが経営危機に陥った際、フォードから救済を打診されたスウェーデン政府は「産業シフトの弊害になる」と言って断り、代わりに失業者を手厚く保護して補償・教育を施している。昭和型の産業構造からなかなか抜け出せない状況で脊髄反射的に「元の状態に戻す」ことを志向するのは馬鹿げてます。
518
寛容って面白いですよね。肯定してる対象には寛容になりようがないわけで、初めに否定がなければ寛容は成立しない。否定した上で認めるわけです。寛容のあるところには必ず分断や否定が前提として存在するということです。
519
子供がクレヨンで好きな絵を描くように、大人たちもビジネスをするようになれば、もっと世の中は瑞々しい多様性に満ちたものになると思うんです。いま見習うべきなのは子供です。ニーチェも言ってますね、「超人とは幼児だ」って。
520
目前の難事にどう対応するか、ということにマインドシェアが集中しがちな状況ですが、こういう時こそ、その先にどういう社会を作っていきたいのか、ということを考えることが大事だと思います。
521
「役に立つけど意味がない」と「意味があるけど役に立たない」。今後、価値があるのは後者。スキルを高めるのも良いけど「役に立つ」は高く売れません。スキルからセンスの時代。logmi.jp/business/artic…
522
会社評価のサイクルカーブ。1=入る前は二倍良く見える。2=働いてる時は二倍悪く見える。3=辞めた後で等倍の真実が見える。特に危ないのが1と2の落差でここで幻滅して会社を辞めてしまう人が多いんですけど、このサイクルカーブを意識して過ごすと色々とラクになります。
523
「移住」という時、多くの人は「物理的な場所の移動」を思い浮かべます。でも、本当の「移住」というのは「モノサシの違う世界に移る」ということだと思うんですね。もちろん、その両者が一緒に起こることはよくあるのですが・・・昔のモノサシを捨てる。
524
「わかる」は「かわる」。「わからない」が「わかる」になるとき、その人は「かわる」。だから「わからない」を排除してしまえば「かわる」こともできません。人間はいくつになってもかわることができますが、そのために「わからない」と思うことをすぐに排除するのではなく玩味することが必要です。
525
子供に英語や楽器や絵画を習わせようとしたって、子供だってバカじゃありません。親が語学も楽器も絵画もやらずに週末はゴルフで時間を垂れ流してれば「面白いのはゴルフで語学も楽器も絵画もツマンナイんだ」と思うのは当たり前です。親自身が身をもって「ツマラナイ」ことを示してるわけですからね。