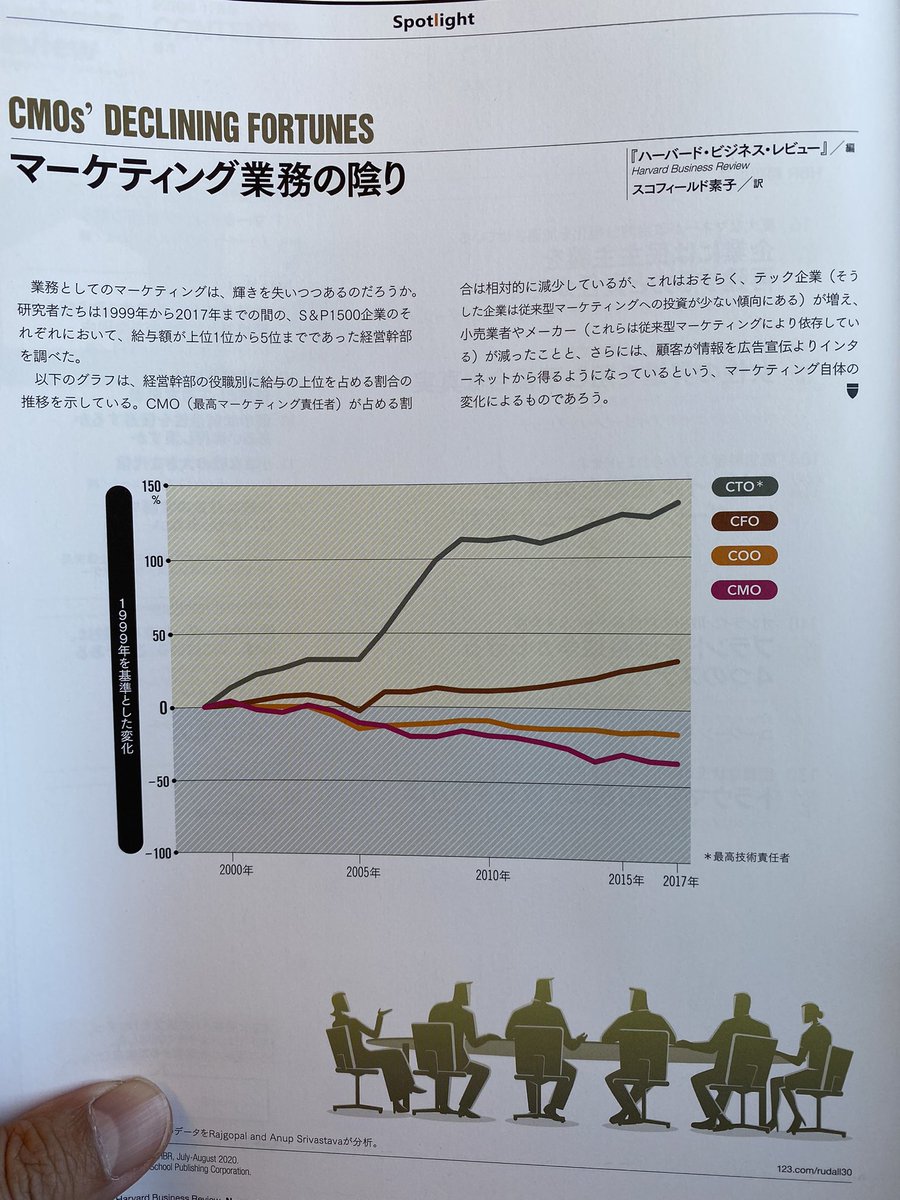451
「オトナの事情」とか「オトナの配慮」といった言葉が出てくる状況では、だいたい「コドモっぽい事態」が発生してる。成熟したオトナが居る状況には「オトナの事情」も「オトナの配慮」も必要ありませんこら。
452
スマートシティとかウェアラブルとかへの違和感、やっぱり20世紀の議論、つまり「どれだけ便利で快適になるか」の延長線上でしかない感じがするんですよね。古いなあと。決定的なのは「環境をどう変えるか」という議論に終始していて「人間がどう変わるか」という論点が抜けてる点です。
453
ミュージシャンなのに学校の音楽の授業が嫌い。理由は「答えが最初から決まってるから」。僕もまったく同じでしたね。日本の教育、いい加減にこの「正解を教える」という考え方から脱却しないと。
news.yahoo.co.jp/articles/59247…
454
最近よく「じゃあどうすればいいのか」「どうしたら意味をつくれるのか」と聞かれます。答えは「知りません」。だいたい、その問いに答えがあるなら誰もがやることになるので優位性を生みません。できる人が少ない上に言語化も難しいからこそ強みなんです。
455
世の中には自分の知らない「オイシイ情報」「オイシイ方法」「オイシイ投資」があって、自分はそれを知らないから不遇なんだチクショーと考える人が多いようですが、そういうのが一番カモになりやすい。自分の頭で考えて汗を流すという以外に抜け出る方法はありません。
456
457
「生きていく」というのは創造活動ですから創造性は誰にでも必要です。そしてさらに言えば、誰にでも備わっています。もし自分には創造性がないと思われるのであれば、それは備わっていないのではなく自分で呪いをかけて封印しているからです。
458
ヤフーさん、アクセルをさらに踏み込みましたね。何度か指摘してますけど、この期に及んで未だ都心にオフィスをおいて毎日出勤させるということは社員に「家を持てない人生を送れ」と言ってるのと同じことです。
watch.impress.co.jp/docs/news/1379…
459
創造性はよく「認知に関する能力」だと思われています。でも創造性の研究に一生を捧げた心理学者、チクセントミハイは「感情に関する能力」だと言っていますね。僕が「わがままを回復しよう」と言ってるのはそのためです。だから成功したアーティストや起業家にはわがままな人が多いでしょう?
460
「自分に何が起きるか?」という不安に苛まれたのが近代だったとすれば、現代は「自分に何も起きないのではないか?」という不安に苛まれています。これはツライですよ、だって「何も起きないゲーム」を24時間、一年365日やってるわけですから。普通は発狂しますよね。
461
ビジョンで人を鼓舞するには言葉の力=レトリックが必要です。これは教養を必要とするのでとても難しい。ということで諦めた人はだいたい「仮想敵」を作ります。仮想敵をやっつけろと鼓舞すると一時的には盛り上がりますからね。競合企業のシェア、ナチスのユダヤ人、旧日本の鬼畜米英ですね。
462
後ろ向きっていう批判がありますが、そうじゃない、あなたと向いてる方向が逆なだけで、こちらはこちらで前向きなんですよ、という。
463
Authenticity=オーセンティシティは「軸がある」ということ。「軸がある」というと「頑固」というイメージをもたれるかも知れないけど、それは真逆で、むしろ軸があるからこそ方法論においては柔軟に対応できるんです。瑣末なことに頑なになる人は軸がないので自信がないんです。
464
アメリカでベストセラーになった「Fuzzy and Techie」が日本では全然売れない。これは「日本でこれから先に何が来るのか」ということをわかりやすく示してくれます。わかっている人にはある意味で「とても美味しい状況」がしばらくは続く、ということでしょうね。
465
Youtubeは無料と思っている人が多いですけど、時間資本という希少な富をせっせと払っていることは忘れないほうがいい。だからこそYoutuberはあれだけ稼げるわけで、何が元手かというと「人から奪った時間資本の転売」です。別のものに払っていたら「自分の富」になったかもしれないわけでね。
466
「これから十年で何が変わるのか?」を議論してばかりいますけど「これから十年で何が変わらないのか?」の方が実は問いとして重要なんですよね。「変わるもの」に取り組んでもすぐ変わりますから。大事なのは「変わらないこと」をきちんと押さえることです。
467
ビジョンじゃないミッションだ、いやミッションじゃないパーパスだ、パーパスじゃない志だ、とかいう議論がありますけど非常にROIの低い考察だと思います。ひっくるめて「のようなものが大事」という整理でいい。サッサと仕事しましょう。
468
アメリカがあれだけ酷いことになっているのに、未だにアメリカをベンチマークにして考える人が多いことに驚いてしまいます。1950年代ならまだしもね。これから日本のベンチマークになるのは明らかに北欧だと思います。
469
皆、シンプルなことを忘れてると思う。それは「要らない会社は要らない」ということ。売上が下がる、利益が減る、赤字になる…いろんな手で抗おうとするけど、経営の本質は「要らない会社」を「要る会社」にする、「要る会社であり続けさせる」ということに尽きると思う。
470
タイやフィリピンは物価が安いから給料も安いと思ってる人がいるようですが、すでに十年ほど前から部長・役員クラスの給与は抜かれてます。記事にもありますが、日本は職位が上がるほど報酬の相対水準が低くなる。若い人は本当にこの国で働き続けるのか考えた方が良い。
diamond.jp/articles/-/278…
471
正解を出すことにこだわりすぎると「正解がわからないから動けない」という状態に陥り、そのままゲームオーバーしてしまいます。大事なのは何が正解かはわからないけど、同じ場所に居続けることはほぼ不正解だ、という前提で動くということでしょうね。
472
成毛さんはマイクロソフト社長退任の記者会見で理由を聞かれ「飽きた」と答えたところ総ズッコケだったそうですが、それこそ人生を変える最重要の理由だと思います。「飽きた」ということは刺激も充実もない、つまり成長していないということですから非常に不味い状態なわけですよね。
473
健全な家庭というのはGDPにとって最悪の存在です。海で釣った魚と地元の農家からもらった野菜を使って自分達で調理して夕食後には家族で語らう。GDP貢献ゼロの家庭です。調理済みの食事をUberに届けてさせて食後はゲームやYoutubeに子供の相手をさせればGDPは跳ね上がります。
474
「学んでから動く」と「動いてから学ぶ」。システムが大きく変わると蓄積された学びのコンテンツが役立たずになるので「学んでから動く」はとても不利になります。こういう時代では、まずは「動く」。動いて経験から学ぶ人ほど強いでしょうね。
475
直近15年間で中小企業が多い東証二部の平均株価はプラス67%なのに対して東証一部の「TOPIX Core30」はマイナス24%。よく「失われた20年」というけど、この20年で本当に停滞しているのは「大きくて古い会社」で、中小・中堅企業には成長している会社がたくさんある。権力の終焉を感じさせます。