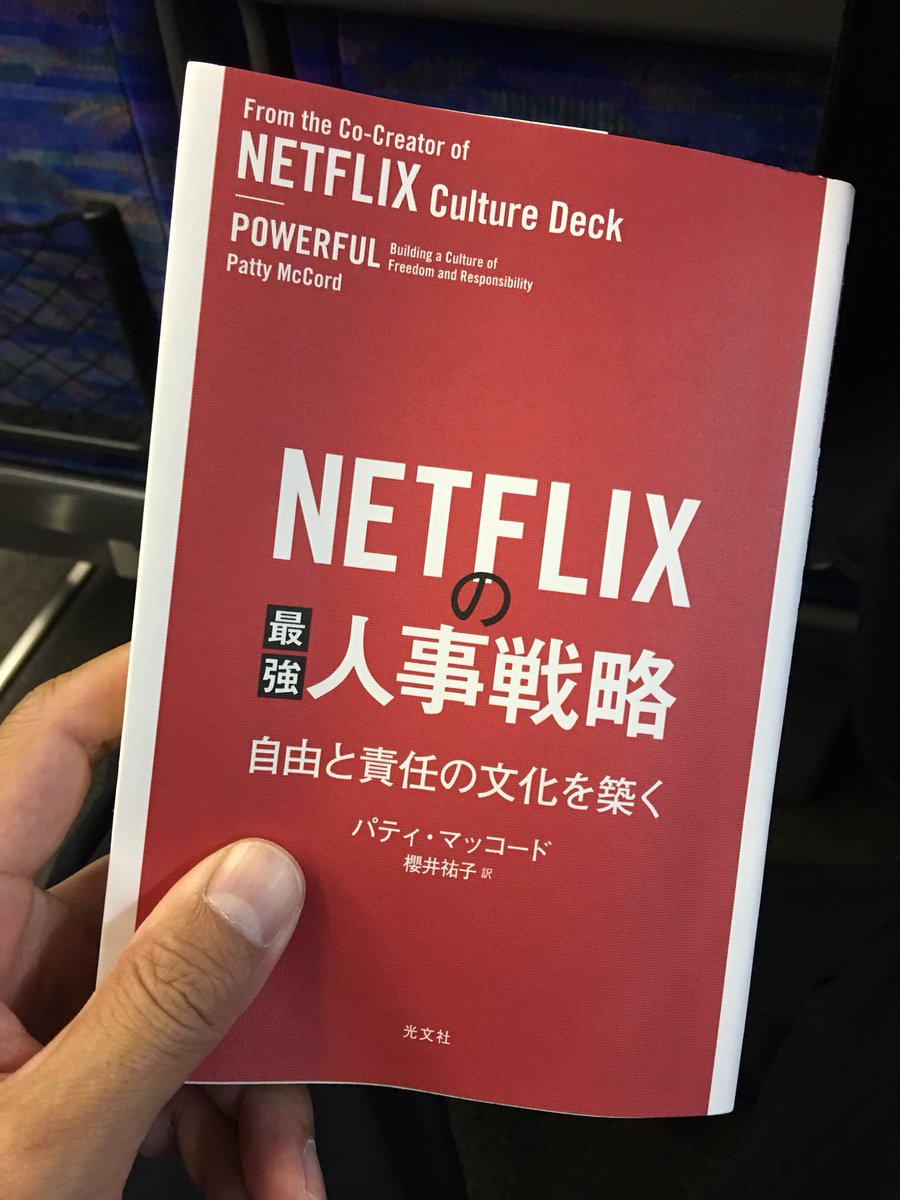376
マーケティングのカンファレンスに行くと僕なんかにはよくわからないすごいテクノロジーを駆使した事例をたっくさん見せられるんですけど、ふと思うのはそこまでやらないと売れないような商品やらサービスは、そもそもそんなに求められてないんじゃないの?と。
377
身分制度廃止も国民皆教育も女性参政権も150年前には「無理、不可能、あり得ない」ことでした。これから150年後、いま「無理、不可能、あり得ない」と言われて実現してるのは何かを考える、実現するために社会に働きかける、ということをしていきたい。
378
きたきたきたきた。
gendai.ismedia.jp/articles/-/690…
379
僕はいろんなところで「正解のコモディティ化が起こっている」と言っていますが、では「正解に価値がないのなら、これから何に価値があるのですか」と聞かれれば、それは「問題」ということになります。
380
他人と比較することでしか自分の幸福度合いやステータスを確認できない、というのは致命的な悪癖です。「成功してるのに不幸な人」という人はみんなこの思考様式に人生をハックされてる。
381
国の仕事が「経済を成長させること」なのであれば、日本は米国に大敗しています。一方、国の仕事が「寿命を伸ばし、犯罪を抑え、格差を正し、教育を施し、社会インフラを維持すること」なのであれば、日本は米国よりもずっと上手くやっています。モノサシの当て方次第ですよ。
382
193ある国連加盟国のうち1945年以降戦争を経験していないのはアイスランド、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、スイス、ブータン、 日本の8か国しかありません。この事実はもっとプライドをもって語られても良いと思うんですけどね。
383
支配というのは「自分は支配されていない」と思っているときにこそもっとも有効に働いているわけです。逆に言えば「自分は支配されてる」と意識された段階で、支配の解除は始まっている。「自分は別に支配されてない」ともし感じるのであれば、支配は非常に有効に働いている、ということです。
384
この多様性の時代に「男系後継者に限定する」のは時代遅れだ、という意見がありますね。ではこういう反論はどうでしょうか。この多様性の時代に「男系後継者に限定する」という独自文化を否定し、グローバルの価値観を一方的に押し付けることこそ画一的であり、まさに多様性の否定ではないか、と。
385
「意味」が価値をもつ世の中になると多くの企業にクリエイティブディレクターが必要になるわけですがなかなかこれが進まない。原因は人材不足にもありますが、より深刻なのは「マネジメントの構造・仕組みがクリエイティブディレクターを活かすようにできていない」ということです。
386
五年前の自分に戻ったら何をするか?新しい語学は身に着ける、楽器をマスターする、ある分野について博士号並みの知識を持つ・・・何か思うところがあるのなら、今日からそれをやりましょう。五年あれば人生はまったく変わります。年末年始はそういうこと考えるのにいい機会ですしね。
387
社員意識調査のギャロップ社によると、日本で仕事にやりがいを感じている人はなんとたったの6%しかいません。人生を無駄遣いしている人がそんなにいるのか・・・そんな仕事すぐ放り出して面白おかしいことをやればいいのにと僕は感じるわけですが、みんなワガママじゃないんですよね。
388
なぜ打席の数が大事かというと、成功は基本的に運だからです。運というのは確率ということですから、出力を大きくするには、率よりも数を増やすしかない。堀江さんはこれを多動力と言ってますが、成功してる人ほど色々やってるし、だから失敗もたくさんしてる。
390
その人にはその人特有の「生きるリズム」というのがあって、これが「仕事のリズム」と合致するかどうかがすごく大事だ、ということにこの歳になってやっと気づいた。振り返ってみれば電通のリズムも戦略コンサルのリズムも、僕には合っていなかったですね。ものすごく無理していたように思います。
391
感性をいくら磨いても、周りの意見を意に介さずに堂々と「これはイイ!」と言える自信がなければ、結局は感性の鈍い周りに同調せざるを得ないわけで、意味がありません。感性と自信は両輪となってその人のクリエイティブリーダーシップを生み出すわけで、片側だけだとむしろ辛くなると思います。
392
浅薄な「働き方改革」が横行している今の状況は「一頭抜き出るチャンス」でもあります。こういう時代だからこそ、一日24時間、思いっきり楽しめる仕事を見つけた人は有利です。だって「周りが勝手に失速していく」んですからね。
393
昨晩の遠山さんとのディープな議論、最後は酔っ払ってなにも覚えていないんだけど、前半で言われた「コンサルと代理店が知的に惰弱になるのは当たり前だよ。だって「課題」と「お金」が、お客さんから与えられるんだから」というのが言葉がアタマから離れない。
394
いまの時代に必要なのは地図ではなくコンパスなんですが、ほとんどの人は「最新の地図」を手に入れることに狂奔してますね。だからこそコンパスを持ってる人がますます有利になるわけですが
395
多様性という観点から最も問題ある組織が国会です。例えば自民党の世襲議員の比率は30%を超えている。「親が議員」という特殊な環境で育った人からなる特殊な集団が、多様な人からなる社会の運営を議論してるわけで、これは相当にマズイ状況だと思います。まあ選んでいる僕らの問題なんですが。
396
箕輪さんと対談して一番「ホエエエ!」と思ったのが、箕輪さんの「最近ドタキャンしてない、やっぱり嫌だなと思ったミーティングは直前でもドタキャンしないとダメですよね」という一言。全くその通りだよなあ、と。会いたくない人には会わない、これは忘れられがちな鉄則です。
397
「問題」を見つけられる人に大きな価値がつく。Airbnbの創業者二人は「部屋がこんなに余っているのにどうしてホテルは一杯なのか?」という問題を発見して大きな富を生み出しています。アインシュタインも「60分時間があれば55分を問題の発見に使い、5分を解決に使え」と言ってますね。
398
クソ仕事の生産性を上げてどうするの、という。生産性生産性生産性って喚かれてるけど、そもそも問われるべきなのは「何を生産するのか?」でしょう。生産性(=プロセス)と価値(=アウトプット)を分けて考える。
399
GAFAのうちアマゾンを例外として残りの三社に共通している要素があります。それは「好奇心や遊びからスタートしており、最初は事業化を考えてなかった」ということです。新規事業がうまくいかないと悩んでいる人は事業化を考えず、まずは「こんなことができたら面白くない?」からスタートしてみては?
400
自分には才能がない、というのは、自分が自分にかける呪いの最たるものと言えます。