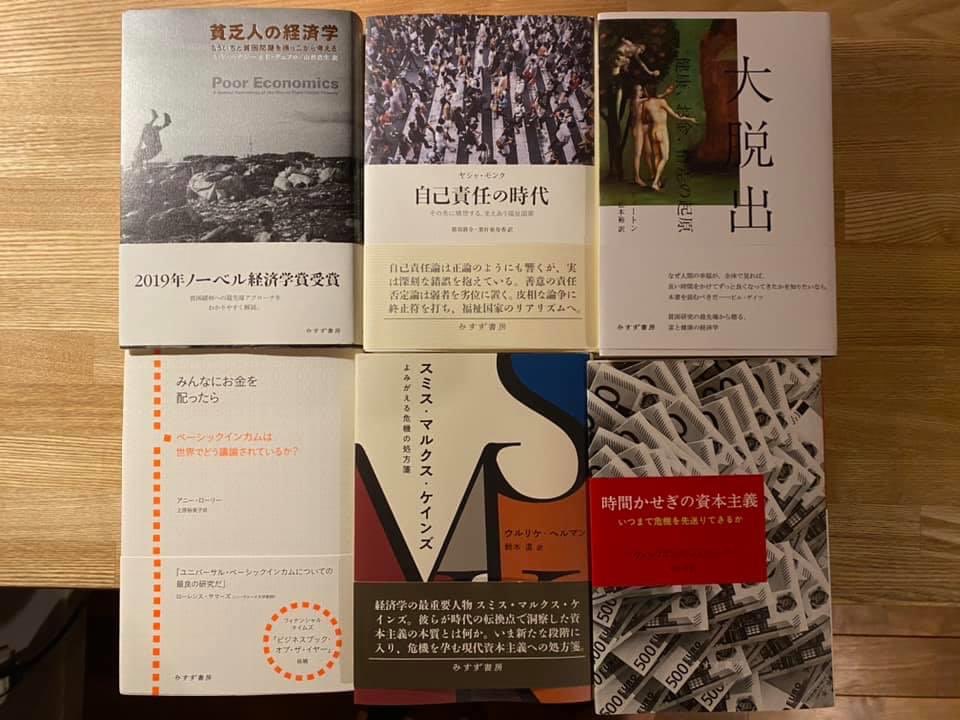502
物質的・量的に衰退しながら、精神的・質的な豊かさを高めていく。これが日本の今後の大きな指針になると思うのですが、どうしても「量的衰退」を認めようとしない人が多いのですよ。「衰退ではなく成熟と言うべき」とかね。旧日本軍が「全滅」と言わずに「玉砕」と言いたがるのと似てるなあ、と。
503
基本的なことがちゃんとできずに問題を抱えている人ほど「高度なこと」を身につけてショートカットしようとする。テレビと同じで「必殺技」で挽回しようとするんですね。で結果はどうなるかというと、ほとんどは状況を悪化させるだけのようです。
504
自分で考える力のない人は「他人と同じこと」をするしかありません。現実に日本の物流で食品のバリューチェーンが途切れることはありえないわけですが「考えない人」にとっては「他人がどうしてるか」しか頭にない。これはバブル起きますよ、だって「他人が買えば買う、他人が売れば売る」なんだから。
505
スペインの哲学者オルテガは「大衆の反逆」で「大衆とは、自分になんらかの社会的役割や義務があるとは考えない一方で権利だけはあると考え、したがって他人と同じことをやっていないと不安で仕方がない、そのような人々である」と言っていますね。これも一つの「美意識の欠如」なんでしょうね。
506
「自分は○○の人間だから」とか「自分は□□の立場ですから」という風に自分のアイデンティティを規程してそこからはみ出すことをしない、分を弁えることばかり気にしている人がいるけど、端から見ていて「どうしてそんなに窮屈な状況に自分を縛るんだろう?」と思ってしまう。
507
「意味」が価値をもつ世の中になると多くの企業にクリエイティブディレクターが必要になるわけですがなかなかこれが進まない。原因は人材不足にもありますが、より深刻なのは「マネジメントの構造・仕組みがクリエイティブディレクターを活かすようにできていない」ということです。
508
「一見、優しいが実は冷たい」という人や組織が多い。実際は「一見、厳しいが実は温かい」の方が良いんですけどね。日本の大企業は多くが前者ですね。表面的な優しさに騙されないようにしたいものです。
509
こういう時だからこそ、普段は忙しくてなかなかできない「長期視点に立った未来への仕込み」を行いたい。
510
仕事と恋愛は似てますね。スーッと前に進んで豊かな実りをもたらすのもあれば、とにかくストレスばかりで何の実りももたらさないのもある。後者については「自分の問題」と考えずに「関係性システムの問題」と考えてさっさとリセットする方が良い場合が多いように思います。
511
ズームを使った会議が急速に普及してるけど、ズームを使うと「空気」を読むのが難しくなるので、かえってパフォーマンスが上がるかも知れない。会議は総じて「Candid=ざっくばらん」な方が生産性が高い。大和の沖縄特攻もスラックで議論してたらなかったかもしれない。
512
SNSの影響でこれからは「家の中のモノ」が承認欲求を満たすための商材になります。クルマや腕時計やバッグは「家の外のモノ」なので、みんな高いモノを欲しがってブランドが成立したわけですが、これからは家具・内装・アートなどの「家の中のモノ」も同じになる。リノベブームってまさにそうです。
513
考えて生きる。電通赤字のニュースで「辞めて良かったね」と言ってくる人がいる。会社はクジ引きでは選ばない。僕が電通を辞めたのは「この会社は近々利益を出せなくなる」上に「この会社では評価されない」と考えたからだ。想定通りのことが起きただけで「ラッキーだったね」的なことを言われてもね。
514
情報のことを文字と数字だと思ってる人が多い。でも世の中の大半の情報は「文字と数字」以外で記述されている。だからアート鑑賞が知覚を鍛えるのだ。キャプションを読んで作品を「わかったつもり」になってる人は大量の情報を日々無視して生きているのと同じだから、そりゃあ危ないですよ。
515
会社の戦略がなってない、と文句を言う人ほど自分の戦略がなってないように思います。人生は宝くじではありません。戦略のない船に乗っているのはあなた自身の戦略ですよね、という話です。
516
人生は宝くじではありません。どの会社で働くか、どこに住むか、誰と付き合うかは全て本人の自由です。これら選択の結果として何らか不利益があったとすれば、その原因の少なくとも一部は自分にあると考えなければなりません。
517
賢くなろうと考えるよりも愚かなことはやめようと考える。普通に考えて無益なことは止め、有益なことに時間を使う。そうすることで結果的に賢明に生きられるのではないでしょうか。
518
考えた通りに、生きなければならない。さもないと、生きた通りに、考えてしまう。by Paul Bourget
519
「今、一番話したくない人」と「今、一番話したくないコト」を考えてみる。それはだいたい「今、一番話さなくてはならない人」であり「今、一番話さなくてらならないコト」なんですよね…話さないとな。
520
知人に「運が良い」と自負してる人がいて、その理由が「いつも神社やお寺でお祈りしてるから」だって言うんですね。最初は「ハア?」と思ったんですけどこれって真実で、なぜなら「お祈りする時」って「一番大事なもの」を考えるんですね。それを日常的にやってるから優先順位を間違えないわけです。
521
最近よく思うのですけど、日本では「おそらく大丈夫」という人がアホ扱いされる一方で、能弁に「できない理由、やることのリスク」を指摘できる人がカシコイと評価される風潮がありますね。知的には後者の「具体化」より前者の「抽象化」の方が遥かに難しいんですけどね。
522
あれだけ「デキナイ理由」を挙げて二の足を踏んでいたリモートワークが一気に進んでいる。結果的に何か問題があっても「あの時はこうするしかなかった」と説明できる、つまり免責要件が担保されたので一気に進んでるのでしょうね。いずれにせよ元の世界には戻れない不可逆な変化の中に私たちはいます。
523
最近感じるのは「世間というのは5月の海に似てる」ということです。飛び込む前は「冷たいんだろうな」という気がしてなかなか踏ん切れないけど、いざ飛び込んでしまうと意外と暖かい。
525
20世期半ばまで、先進国の生産性の伸び率は恒常的に5-7%を記録したけど、この数値は21世紀に入って1%近くにまで落ち込んでいる。ビジネスは歴史的な役割を終えつつある、と考えた方が良いのかもしれない。