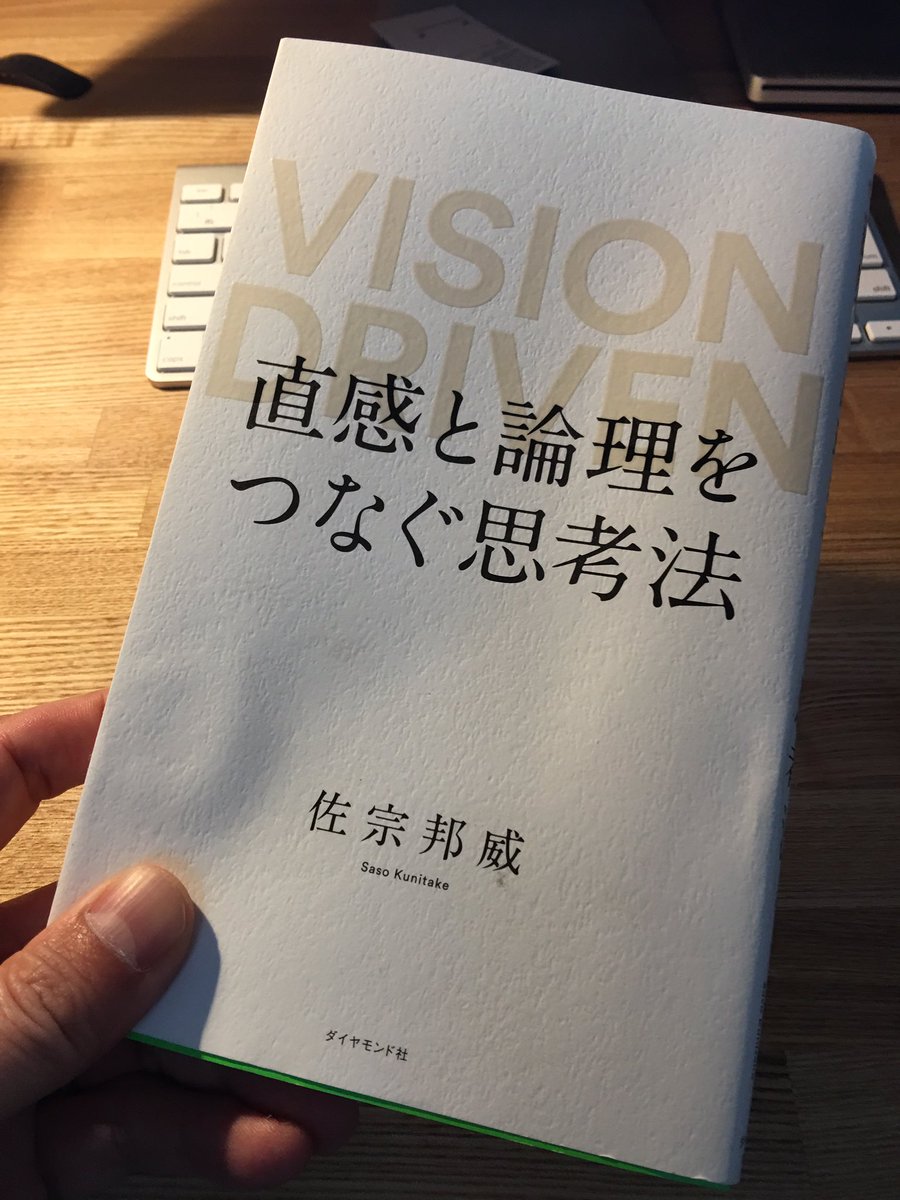201
ファーストペンギンがいないとよく言われますが、ポイントを外してるなと。本当の問題は「セカンドペンギンがいない」ということなんです。セカンドが出て初めて、最初に飛び込んだペンギンに「ファースト」の称号が与えられる。セカンドが出ないと単に「飛び込んだバカ」になっちゃうんですよ。
202
狼と犬を個体として戦わせたら犬は瞬殺されます。でも狼は絶滅し、犬は繁栄した。パワーをもつ存在に懐くことが生存に有利だからです。これは組織内の生き残りにも同様に働くメカニズムですが「狼みたいな人」がぜんぶ駆逐されて「犬みたいな人」ばかりになった会社なんて僕は嫌ですね。
203
運命論のように状況を卑下する人っていますよね。「家電はもう厳しい」とか「広告はもう人を動かせない」とか。そうじゃない、正しくは「私の作る家電はもう難しい」「私の作る広告は人を動かせない」ですよね。勝手に他者の運命を決めないでほしい。
204
「安くて便利」から「高いけど素敵」へ。
205
迷惑をかけてはいけない、というこの国の奇妙な道徳がイノベーションを阻害してる。イノベーションってまず確実に世間に迷惑をかけますからね。人様に迷惑をかけてないイノベーションならそれはイノベーションとは言わないわけでね。ラッダイト運動みたいなことになるわけだからすごい迷惑なんですよ。
206
哲学は役にたつのか?答えは「その人次第」です。「自分で考えて生きる」こと目指す人であれば必ず役に立ちます。しかし組織や社会のルールを所与のものとして、そのルールの中で勝ちたいと思う人にとってはあまり役に立ちません。
207
ビジョンはなぜ大事なのか?それは「困るため」です。ビジョンを描いて現状と比較して初めて「問題」が明確になる。つまり「困る」わけです。困ると粘り強い努力が生まれます。逆にいうと「困ってない人」は努力もしないし周囲も助けられません。
208
人も組織もビジョンが大事、という話をすると「どうせ実現しない」とか「現実は甘くない」とかいう反論をいただくのですが、そもそも実現するかどうかはどうでもいいんです。ビジョンを持って生きるというプロセスが価値を持つわけでね。イエスの神の国もキング牧師の差別なき世界も実現してません。
209
この人たちバカなんですかね。呆れてものが言えない。
asahi.com/articles/ASP7Q…
210
経済を成長させるために、という枕詞がついた教育議論が横行していますが、そもそも教育は、人が人らしく生きるための力を身につけさせるためのものであって、経済成長のためではありません。いかに子供たちを経済戦争の兵士に育てるか、といった議論には強い違和感を覚えます。
211
オトナが担っているコドモへの責任の筆頭は「オトナになるって楽しそうだな」と思わせることです。だからもっと笑わないといけないし背中を丸めずに颯爽と仕事に向かわなければならないしオトナの悦楽を知って人生を楽しまないといけない。オトナの責任ってそれだけだと思うんですけどね。
212
模倣には「良い模倣」と「悪い模倣」があります。自分より優れた人を真似るのが「良い模倣」で、過去にうまくいった自分のやり方を再現しようとするのが「悪い模倣」です。後者が始まると人生がどんどん尻つぼみになってしまうので要注意ですね。
213
直感力に優れている人ほどコンサルとして長続きしない印象があります。直感的に答えがわかる人は極めて短時間に問題を解いてしまうのでコンサルフィーがものすごく安くなるんですね。一方、ギリギリ論理で突き詰めれば詰めるほど時間はかかるのでコンサルとしてはこちらの方が良いわけです。
214
思いついたのだけど、飲食店のために「逆ツケ」ができないのかな、と。ツブれたら悲しい行きつけの飲食店に「コロナが収束したら行くよ」という分をいま支払っちゃう。ツケの逆、リバースデポジットですね。それでコロナが収束したら先払いした分にオマケしてもらうという。良いと思うんだけどなあ。
215
会社は近い将来バンドみたいになると思うんですが、そうなると掛け持ちとか再結成とか音楽性合わないから解散とか当たり前で、その時々で好きな仲間とバンドを組んで社会と関わればいい。人的資本も社会資本も「会社の外側」に蓄積するのでロックインされません。
216
「役に立つ人」と「モテる人」。「役に立つ」はスキルなのでスキルを学べば「役に立つ」。一方で「モテる」はセンスなので要素分解できません。会社も同様に「役に立つ会社」と「モテる会社」があって「モテる会社」は論理やスキルでは作れない。無印良品やパタゴニアのような哲学が必要になります。
217
仕事と恋愛は似てますね。スーッと前に進んで豊かな実りをもたらすのもあれば、とにかくストレスばかりで何の実りももたらさないのもある。後者については「自分の問題」と考えずに「関係性システムの問題」と考えてさっさとリセットする方が良い場合が多いように思います。
218
基本的なことがちゃんとできずに問題を抱えている人ほど「高度なこと」を身につけてショートカットしようとする。テレビと同じで「必殺技」で挽回しようとするんですね。で結果はどうなるかというと、ほとんどは状況を悪化させるだけのようです。
220
仕事のリモート化によって「教育・育成」が大きな課題になっていますけど、一つ確実に言えるのは「新卒」の魅力が大きく下がるということです。これだけ新卒の育成の難易度が上がるのであれば新卒の育成は他社にやらせて、コストはむしろ中途採用の広報と精度向上に回した方が合理的です。
221
面白いですよね。人生ってステージによって競争の種目が変わる。第1=受験、第二=就職企業のブランド、第3=年収、第4=社会的地位。でも最後は結局、第5=幸福度になりますからね。第4まで必死になってボロボロになってる人が多いけど、どのみち「幸福な人」に全員抜かれますから。 twitter.com/risktaker_0000…
222
アフターコロナは「何が正解がよくわからない時代」になります。こうなるととにかく早くいろいろ試してうまく行く方法がなにかを探り当てる一種の学習力が重要になるんでしょうね。
223
どうやったら目の前の面倒くさそうな仕事を意味のある面白い仕事に変えられるかを常に考える。最初から面白い仕事なんてそうそうありません。
224
つくづく「経済成長」というのは一種の宗教なんだと思いますね。望ましい水準と言われる4%の成長を続ければ経済の規模は100年後には現在の49倍、300年後には12万9千倍、1000年後には10京3826兆倍となります。科学的にあり得ないことを信じる、つまり「信仰」であり「宗教」だということです。
225
これだけ生産性が上がった(気がする)のに自分たちは豊かにならない。結論は明白で、生産性が上がって得をするのは個人ではなくシステムだということです。だからシステム側の人ほど生産性生産性生産性と言うでしょう?子供は決して言わない。なんでこんな単純なことにみんな気づかないのかな、と。