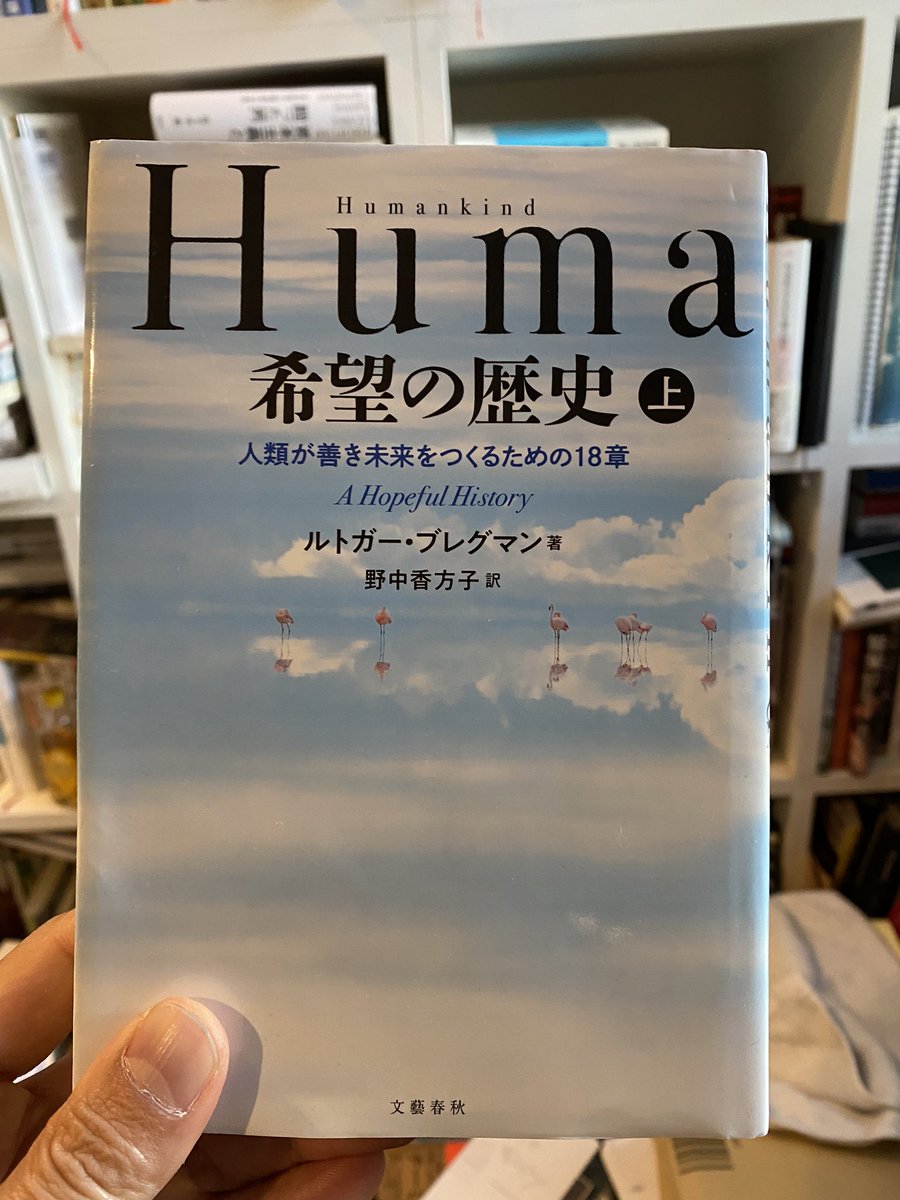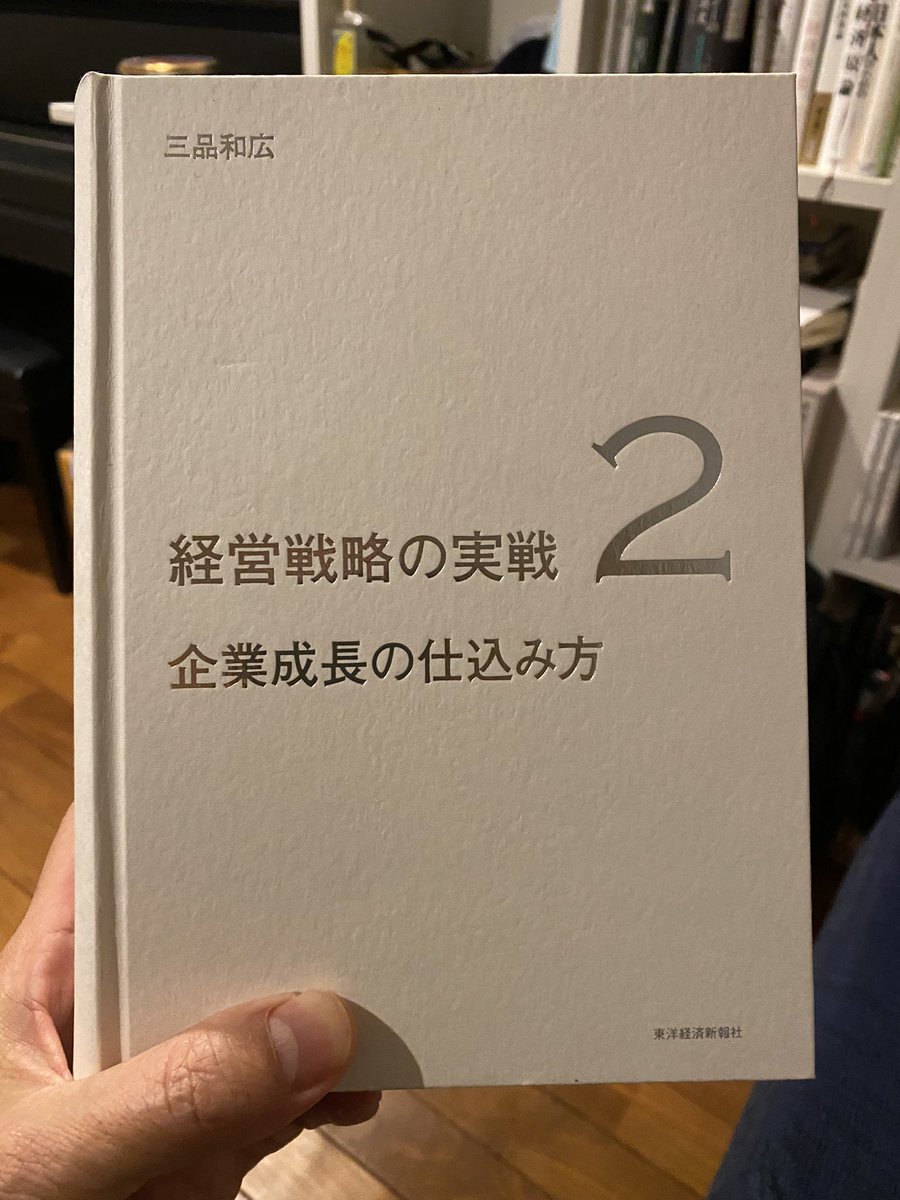226
思考とは言葉でするものですね。だから言葉を緩く、いい加減に扱う人には、緩い、いい加減な思考しかできません。言葉を、精密に、時計を組み立てるように扱えればいいのになあ、と。
227
最近よく思うのですけど、日本では「おそらく大丈夫」という人がアホ扱いされる一方で、能弁に「できない理由、やることのリスク」を指摘できる人がカシコイと評価される風潮がありますね。知的には後者の「具体化」より前者の「抽象化」の方が遥かに難しいんですけどね。
228
最近は二十代からヒッチャキに働いて成功するのが「イケてる人生の典型」みたいになってるようですが個人的には勿体ないなあと思っています。二十代ってあれこれ無駄ができるのが良い点で、それが後の人生を豊かにしてくれる。肥やしになるような「良い無駄」を織り込めるかが重要だと思いますけどね。
229
一点の迷いもなく「自分が居るべき場所」と感じられる場所を見つけられるかどうか。結局それで全部決まってしまう。そういう場所にまだ出会えていないという人は絶対的な移動量が足りてないんだと思います。
230
自分を現象として捉えてみる、と少し救われるように思います。今はあまりに「個人の意志」が前面に置かれますが、人の行為はすべて関係性の中で生まれる現象でそこには能動も受動もありません。宮沢賢治の「春の修羅」は「わたくしという現象は」という言から始めてますがすごい洞察だと思います。
231
「教えたがる」っていうのは、あれは何なんでしょう、もう病気ですね。
232
「働き方」と「豊かさ」の関係。有名な思考実験ですが、一週間働く漁師の漁獲高は、A=毎日8時間、B=毎日目標数だけ、C=穫れる日に沢山働いて後は休むで、C>A>Bの順になる。「ノルマ決めてガンバる」のが最悪、「定時間働く」が次善。企業組織の働き方はそもそも生産性が低いという。
233
男性だけのカンファレンスには最近「多様性がない!」との批判が殺到しますが、これも恐ろしい考え方ですよね。本来、同性の人間のあいだにも豊かな多様性があるはずで、それをないことにして異性を入れておけばそれでよし、とする考え方は「多様性の本質」からむしろ乖離する状況を生むと思います。
234
人生を浪費しなければ、人生を見つけることはできない。これはアンモロー・リンドバーグの言葉ですね。きちんと人生を浪費してるか、あらためて意識していきたいものです。宝物はえてして寄り道した時に見つけるものですからね。
235
仕事の一番の報酬って「お金」ではなく「ありがとう」っていう一言だと思うんですね。それがないとドンドンお金を増やす方向で飢餓感を満たそうとしてしまう。
236
イノベーションを「何か新しいこと」として考える人が多いけど、実際には「未来の当たり前」を引き寄せることで実現することが多い。この「未来の当たり前」を考える時にリベラルアーツが武器になる。「未来の当たり前」なのに「今はそうなってない」ことは何かを考える。
237
天才と努力型。よく「天才は努力型に比べて努力してない」と思ってるヒトがいますがそれは誤解です。努力の量は同じか、むしろ天才の方が多い。ただ天才はそれを努力と思ってやってない、遊びだと思って楽しんでるんですね。そう考えれば「努力型が天才に負ける」のは当たり前です。
238
副業には「クソ仕事に意味が生まれる」というメリットがあります。副業として「あまりお金にならないけどオモシロイ仕事」を続けるために「お金にはなるけどツマラナイ仕事」をちゃんとやる。ツマラナイ仕事にも戦略上の意味が生まれるのでモチベーションが上がり、結果的にパフォーマンスが上がる。
239
なんとなく素敵で洗練されたイメージの会社というと「ソニー」「資生堂」「サントリー」と思い浮かぶけど、こうして並べてみると、全て社名が「サ行」なのだということに気づく。そもそも「素敵」「洗練」も「サ行」なのだよなあ。
240
「すぐできること」は他人にも「すぐできる」。書店には「すぐできる系」の本が溢れてますが「すぐできる」をいくら積み重ねても「この人でないとダメ」と言われる人にはなりません。
241
女性の社会進出が進まない、という言い方自体に女性を下に見る含みを感じますよね。どうして男性の家庭進出が進まない、とは表現されないのか。以前から言っているように家事は総合芸術でルーチンになりがちなデスクワークより遥かに創造性が求められますんですごく鍛えられると思うのですけどね。
242
子供に教育の選択権を与えたら良いんですよ。僕は高校は殆ど通わずに図書館で好きな本だけ読んでました。先生の授業よりマルクスの方が面白かったからね。今になってつくづく思うのは「正しい選択をした」ということです。子供は大人が思っているような愚かな存在ではありません。
243
その人にはその人特有の「生きるリズム」というのがあって、これが「仕事のリズム」と合致するかどうかがすごく大事だ、ということにこの歳になってやっと気づいた。振り返ってみれば電通のリズムも戦略コンサルのリズムも、僕には合っていなかったですね。ものすごく無理していたように思います。
244
「成長」というウサンくさい言葉に注意したい。人が「成長」という時、その背後には必ず自分が大事にしてる価値観やモノサシを他人に押し付けるという欲求がありますね。でも本当の成長…というか成熟っていうのはモノサシが変わることであり、さらにはモノサシが要らなくなることですよね。
245
「空気を読む」組織が凋落する理由。タテマエの裏側にあるホンネを空気から読むようになると生産性が爆減します。「テキストを読む」のに比べて「空気を読む」のはとても脳のパワーを使う上に、結果的に「読み」が間違ってることも多く、多方面でロスが発生するからです。
246
五年前の自分に戻ったら何をするか?新しい語学は身に着ける、楽器をマスターする、ある分野について博士号並みの知識を持つ・・・何か思うところがあるのなら、今日からそれをやりましょう。五年あれば人生はまったく変わります。年末年始はそういうこと考えるのにいい機会ですしね。
247
249
クソ仕事の生産性を上げてどうするの、という。生産性生産性生産性って喚かれてるけど、そもそも問われるべきなのは「何を生産するのか?」でしょう。生産性(=プロセス)と価値(=アウトプット)を分けて考える。
250
アイデアを上司が認めてくれない、と腐ってる人の話を聞くと「ラインの上司二人から両方ともダメ出しされた」とか、そういうことを言ってるわけです。ちなみにGoogleはスタートアップ時の最初の資金調達に成功するまでに350回のピッチをやってます。まあ、そういうことです。