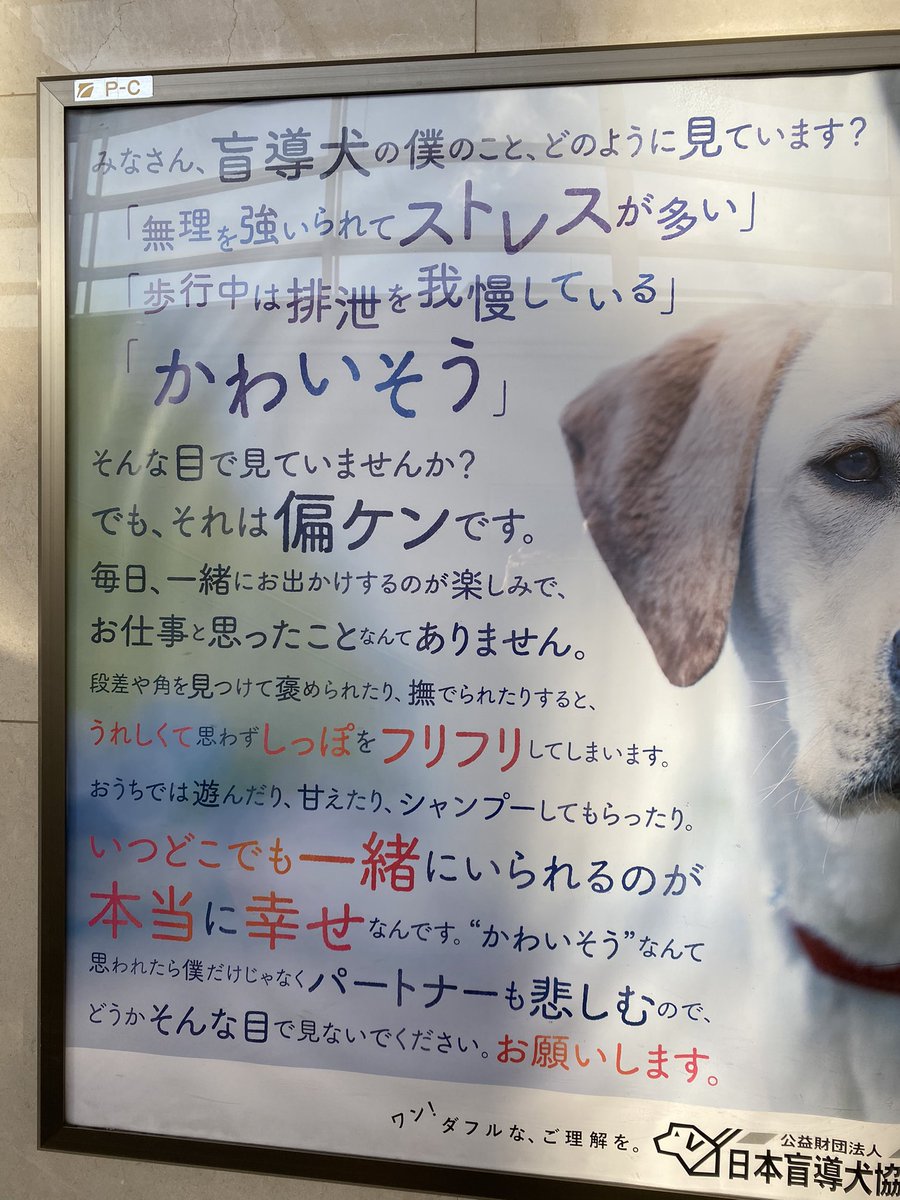251
さらに指摘すれば、言葉には自己暗示の効果もあります。ネガテイブで汚い言葉ばかり呟いているとやがては自分自身をそのような人間にしてしまう。そうなるとますますポジティブな光はそのから逃げて闇に沈み込んでいくことになる。聖書の福音書にもありますね、人は自分の放つ言葉に殺される、と。
252
状況を変えたければまず自分を変えること。自分を変えるにはまず「ものの見方」を変えること。備忘録です。
253
やることのリストが間違ってる人ってあんまりいないんです。じゃあなんで成果に大きな差が出るかというと「順番が違う」んですよね。あんまり言われてないですけど「なにをやるか」よりも「どういう順番でやるか」が大事だと思います。戦略の蘊奥だと思います。
254
ニュータイプは「答え=Answer」ではなく「問い=Question」を探す。「Questionには「Quest=冒険の旅」という言葉が入っています。Never stop questioning!
256
新卒一括採用について株主がなぜ何も言わないのか不思議です。大手企業の生涯年収は3〜5億になります。つまり書類+テスト+面接だけで数億の投資を決めてるわけです。しかも場合によっては数百人も採用してる。結果として大量の適性不適合も生み出してるわけで社会的損失が非常に大きい。
257
ではビジョンはどうやって作るのか?カギは「教養」ということになります。ビジョンとは「ありたい姿」のことですけど、現状を当たり前に受け入れてたらビジョンなんて作れません。目前の状況を「これっておかしくねーか?」と考える知的反逆心こそがビジョンの苗床です。
258
ピーター・ドラッカーは日本の明治維新を「歴史上、最も成功したトランスフォーメーション」と言っていますが、その成功要因として「藩の多様性」を挙げていますね。「各藩に独自の人材育成方針があって人材の多様性が高かった」と。現在は真逆になってますね。
259
好き嫌いをハッキリ明言するようになって一番良かったのは、趣味の合わない人は自然と遠ざかり、趣味の合う人が向こうから来てくれるようになったこと。経営では往々にして短期と長期の利益が相反しますが、これは個人においても同じです。好き嫌いをハッキリさせると長期的にはすごくラクになります。
260
あらためて気づいたのですが、人生はとても長く続くスローなゲームなのに、勝ち方を教示するコンテンツはそれをすごく短いファストゲームとして捉えていますね。でもスプリントの走り方でマラソンを走れば破綻は目に見えてます。両者の捉え方でゲームプランは全く変わってきますからね。
261
あと仮想空間にいると自分と意見の合う人ばかりと接触することになるので多様性を受け入れる力、異なる立場や意見に耳を傾ける寛容性が毀損される恐れがあります。こういう時代だからこそ、以前にも増して多様性を受け入れる寛容さ、共感する力、想像する力が求められると思います。
262
先日、韓国のある財閥系企業に請われて役員会に参加したんですが、冒頭に「今日の議論は英語にしますか?それとも日本語にしますか?」と聞かれ、あー日本キツイなこの先、と思ってしまった。
263
野村総研がまとめた経営者アンケートによると「次の経営者に求める資質」の三位に「不退転の決意」とある。ナニバカなこと言ってんの、と。アマゾンは上々以来70以上の事業に手を出して三分の一はすぐに撤退してます。たくさん試してすぐに諦める。これが令和の鉄則です。diamond.jp/articles/amp/2…
264
多くの人がTwitterを実名でやりたがらないのは「発言には責任を持つべきだ」と考えているからでしょう。そう考えれば怖くて実名でのホンネ発言なんて出せるはずがありません。別に責任なんて気にしなくて良いのに。ホンネで話さない人に敵はできないけどそれって味方もできないってことですからね。
265
いまの時代に必要なのは地図ではなくコンパスなんですが、ほとんどの人は「最新の地図」を手に入れることに狂奔してますね。だからこそコンパスを持ってる人がますます有利になるわけですが
266
「女性活躍」という時の「活躍」が「企業や行政において重職にある」という意味にほぼ限定されているのに強い違和感を覚えます。だって家事をしっかりやってるのも立派に「活躍」でしょ?しかも企業や行政のブルシットジョブに比較して家事は視覚・聴覚・味覚・触覚の全てを扱う総合芸術ですし。
267
お金を払わずに利用できる、という時は100%、自分が逆に利用されてるということですね。
268
自己実現を成し遂げた人は友達が少ない、というのがマズローの発見でしたけど、これって色々と考えさせられますよね。
269
人文科学系学部を廃止して社会で役に立つ学問に片寄せ寄せするよう文科省が指導してますが、最大の問題は「社会に最適化した人材」ばかりになってしまうと「社会そのもののあり方」を批判的に考え、新しい社会のあり方を提案できる人材が居なくなってしまう、ということです。
270
触れることで人生が豊かになるような、素敵で美味しくて肌触りの良いもの、に本能的に身を寄せていく能力の有無。住む場所、食べるレストラン、読む本、そして一緒にいる人、を世の中のモノサシを振り払って選べるか。
271
三日坊主でいい、と自分にいつも言っています。三日坊主を責めてるとそもそも自己嫌悪で「始めること」そのものが嫌になってしまいます。三日坊主でいい、それを何度もくりし返してればいつかは高いところに登れる、と思っていて良いと思います。
272
最近あらためて感じてるのが「話す」ということの大事さです。というのも、話してるうちに自分で考えていなかったような言葉や概念が出てきて自分で驚くことがあるんですよね。これは頭で考えているだけでは絶対に起きない現象です。ソクラテスも言ってますよね「対話にこそ叡智が生まれる」って。
273
今回のコロナ騒動は社会的に終わりつつあったものにトドメを刺すことに寄与するでしょう。もちろん罹患した個人や医療関係者にとっては大変な災難・ご苦労だと思いますが歴史はパンデミックが社会変革の契機となることを示しています。あまり「現状回復」に捉われず、これを社会変革の機会と考えたい。
274
理想は自分が前に進むためにあるのであって、人に押し付けて批判するためにあるのではない。不寛容の問題はここに尽きます。このことが腹に落ちると随分と楽になるのだろうなあ、と。
275
「考えて生きる」と「感じて生きる」。どっちが大事かずっと考えた結論が「どっちも大事」。「考えて生きる」は「地図を持って生きる」ことであり、「感じて生きる」は「コンパスを持って生きる」ことで、両方ないと遭難しちゃうのは当然だな、と自分で納得。