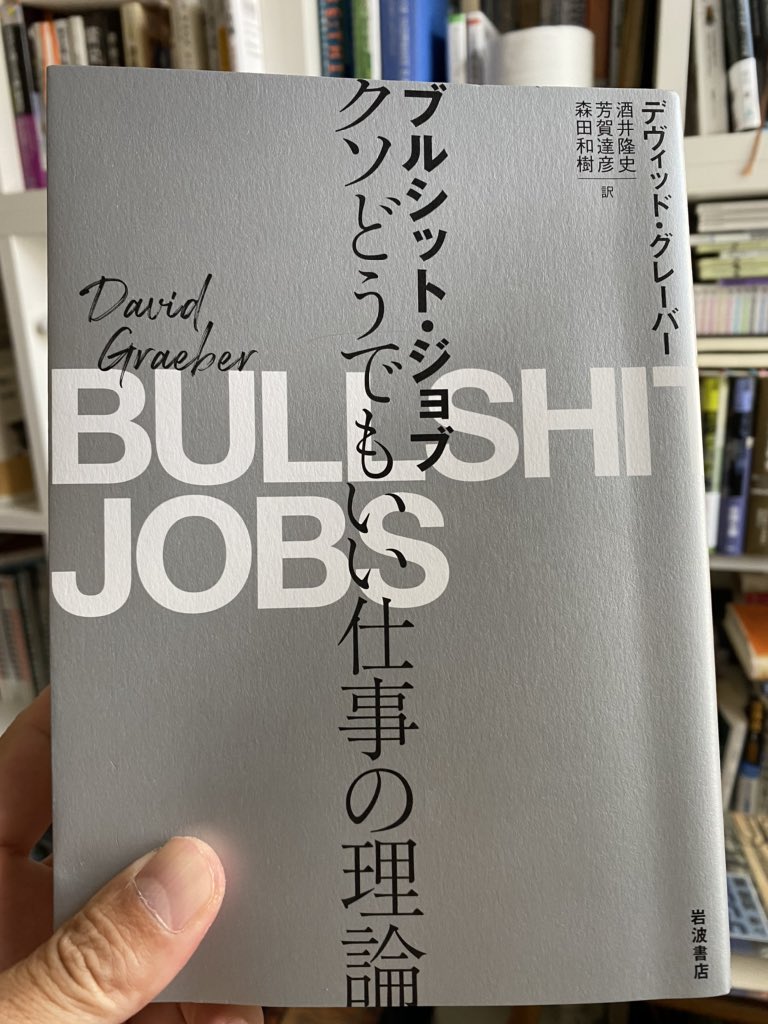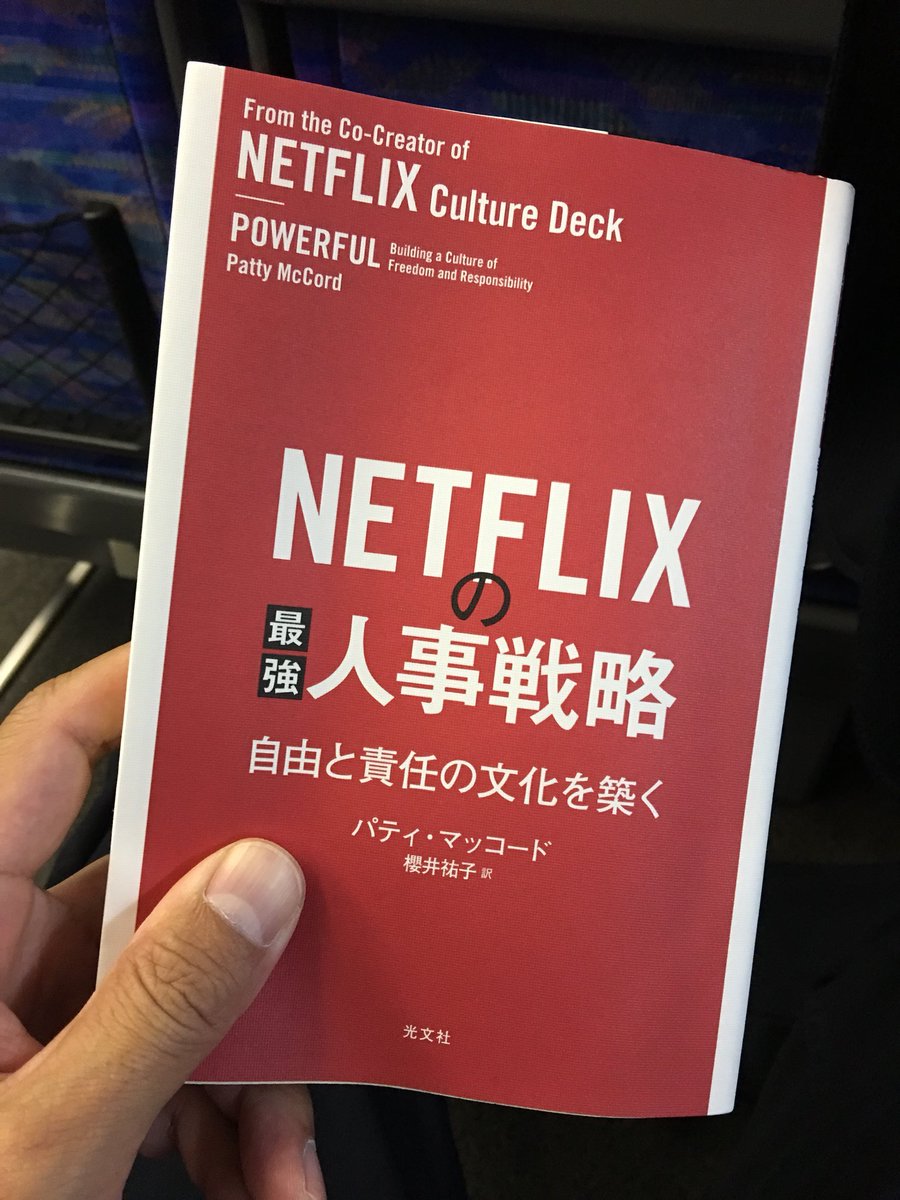176
人生は宝くじではありません。どの会社で働くか、どこに住むか、誰と付き合うかは全て本人の自由です。これら選択の結果として何らか不利益があったとすれば、その原因の少なくとも一部は自分にあると考えなければなりません。
177
自分の頭で考える習慣のない人の特徴は「すぐに事例を聞きたがる」ことですね。このような人が指導的立場にいると永遠に先行者になれません。
178
よく「今日は絶対に休めない」と言ってる人がいますけど、賭けてもいい、休んでも何の問題も起きません。個人的には、優秀な人ほど「え!?ここで休む?」というタイミングでポーンと休んで、周囲のテンションをうまく上げてる。「休むこと」を組織強化に使ってるんですね。自信がないとできませんが。
179
昔から一番嫌いな・・・というか困る質問が「尊敬している人は誰ですか?」という質問です。よくされる質問なので答えられない自分はアホなのかと思ってたのですが、先日、茂木健一郎さんから「それで良いんだよ、カリスマに心酔してる人って脳の活動レベル低下してるからね」と言われて、あああと。
181
逆に言えば「広告会社の影響力が強い社会」というのは、自分の好みに自信がない、流行に惑わされて右往左往する人が多い社会ということです。つまり「広告会社の影響力の強さ」は、「これダサい?」「流行遅れ?」と不安げにキョロキョロする人々によってこそ支えられているということです。 twitter.com/shu_yamaguchi/…
182
「タテマエ」と「ホンネ」をうまく使い分けられるのが「オトナ」だいったことを言う人がよくいますが全く逆ですね。「ホンネ」で話しながら建設的な対話ができる成熟したオトナが少ないから「タテマエ」と「ホンネ」の使い分けが必要なんであって、そんなことを言う人ほど「オコチャマ」なんですよ。
183
宗教は「行動様式を揃えるOS」なので、これを持たない日本人は「他人に迷惑をかけない」ことを基準に考えます。ところが「迷惑」は「受け取り方」で決まるので、常に「相手の顔色を見る」ことになり、これが生産性を大きく低下させてる。言葉より空気読むほうがそりゃ時間も労力もかかりますからね。
184
人が質問をする時、本当に質問してることは稀なんです。大体は1=私は貴方が嫌いだ、2=私はとても不安だ、3=私は怒っている、のどれかを伝えようとしているので、質問に答えても事態は収拾しない。僕はいつもジュニアコンサルタントに「質問に応えちゃダメ、真意を測りなさい」と言ってました。
185
他人と違うことをやる勇気がない、という人がいますけど、足りないのは勇気ではなく思考量なんですよね。自分の頭で考えて「どう考えてもこちらの方がいい」と判断できれば別に勇気がなくても他者と違う行動ができます。
186
環境問題や多様性について勉強すると理想に合わないものが目に付き、悪口を言いたくなります。悪口はその人の社会資本を毀損し、発言力や影響力を奪います。すると結局、理想は実現できません。だから、理想を知る人は、理想を学ぶのと同じ歩調で寛容を身につけなければなりません。
187
人生の質を左右する五要因。住む場所、やる仕事、身の回りのモノ、余暇にやるコト、一緒にいる人。それぞれ本当に好きなモノ・コトを選べば自然と人生の質は上がります。一方で、年収を上げる、一流企業で働く、高級車に乗る、ブランドエリアに住む、などは全く効果ありません…むしろ逆効果でしょうね
188
つまりこれから大事なのはPDCAではなくDCPAだということです。まず、とにかく何かを始めてみる、市場に投げてみる。その反応を見てすぐに構え改めてまた何かを投げる。それを繰り返すことでしか自分の居場所は見つけられないということです。
189
他人の批判ばかりしてる人の問題点は、批判アンテナの感度が高まるので最後は自分を批判してしまうことです。ツイッターで他者の批判ばかりしてる人って大体が実名を出してないでしょ?彼らは自分のことが大嫌いなんです。本当に気の毒です。
190
今日は久々に朝の東京なのですが、すれ違う人々の表情の暗いこと。先日、京都精華大のサコ学長が言ってた「マリから知人が来ると東京の人の目、特に子供の目が死んでるのにみんなビックリする」という話を思い出してしまった。
192
価値の抽象度を上げ下げして考える癖をつけること。「自動車を売ってる」と考えるのと「移動を売ってる」と考えるのでは競争に関する認識の範囲と感度がまったく変わってくる。「フィルムを売る」のと「記録を売る」。「DVDを売る」のと「映画鑑賞の時間を売る」。前者と考えた組織は消滅しましたね。
193
何か話さなきゃ、というプレッシャーに負けて失言を繰り返してきた人生なのですが、最近、シンプルに「その言葉を発することで、世界は少しでも良くなるだろうか?」と一呼吸のあいだ考えてみると、かなりの場合、静かで和かにいられると気づきました。これツイッターでもそうなんですけどね。
194
「逃げろ」というツイートに対して「責任」に着いての質問がかなり来てます。面白い。では、まずは「責任」について定義してから反論してください。きちんと定義できたら哲学史の教科書に載ると思いますから頑張ってくださいね。責任って虚構の概念ですから。
195
MITでは理系の学生にもプレゼンテーションやディベートを必修にしています。これは「先進的な技術を有する人材であれば、自分の考えを効果的に他者に伝えるコミュニケーションの技術が必要」という考え方です。「伝えられない」ということは「アイデアがない」のと同じだ、ということです。
196
「最初」にあまり拘らない方がいいと思ってます。「もうやってる人がいる」「もう言ってる人がいる」と批判する人が居ますけど、その「やり方」「言い方」がショボいのであればいくらでもハックすれば良い。電球の発明者はエジソンではないし検索エンジンの創始者はグーグルではありません。
197
ドラッカーが言ってることですけど、歴史上、最も成功したトランスフォーメーションは日本の明治維新であると。で、その成功要因は何かというと江戸時代の教育制度による「多様な人材」だというんですね。考えみれば坂本龍馬も西郷隆盛も、今の日本の偏差値教育では早期にドロップアウトしただろうと。
198
レベルの低い顧客に合わせるとレベルの低いモノしか生み出せない。可能性を制約してるのは多くの場合、本人の才能や能力より付き合ってる顧客なんですよね。良い意味で「難しいお題」をくれる顧客と仕事をしましょう。
199
神経科学者は筋肉と同じように脳も鍛えられることを明らかにしています。社会ビジョンを毎日考えていれば社会ビジョンを考えるのが得意な脳になり、Twitterで他人の挙足取りをしていれば他人の挙足取りが得意な脳になる。結局「人は使った時間の通りの自分になる」ということです。
200
成長という果実を与えてくれるのは「ハードワーク」であって「ロングワーク」ではありません。意味のないクソ仕事で徹夜を続けても成長は得られません。仕事や経験の「量」ではなく「質」を常に意識する。