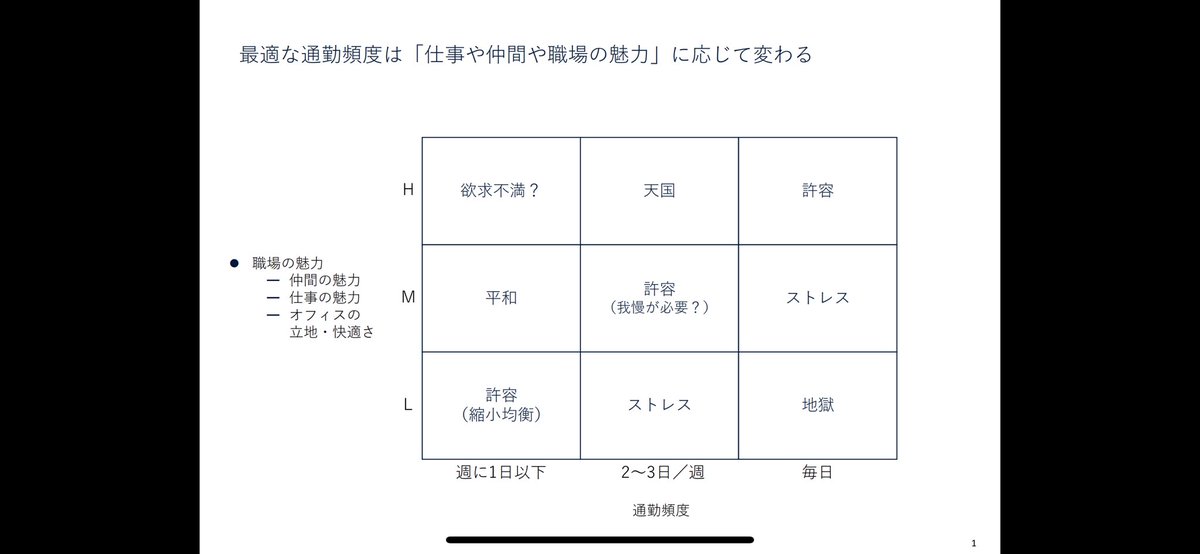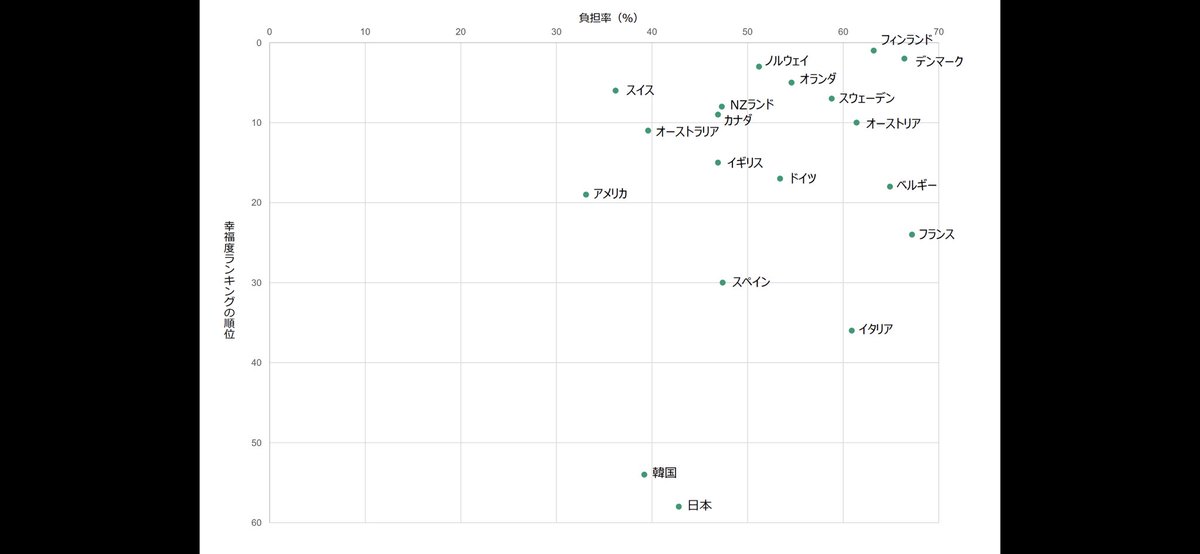726
イノベーションの停滞を教育の失敗と紐づけて語る人がいますが、全く逆で教育が大成功しているからイノベーションは停滞しているんです。システムの規定に従順でルールに従う素直な子を育てるという教育がうまくいけば、イノベーションが停滞するのは当たり前のことです。
727
正解がない時代こそ当たり前なんです。「生き方の正解」があった時代の方がずっと短いし、そもそも健全でない。ヴァレリーの詩「風立ちぬ、いざ生きめやも」って、そういう意味でしょう。不確実性に身を投げ出すのは怖い、でも身を投げなければ何も始まらない、ということです。風、吹いてますものね。
728
消費はアクティヴィストの武器だということをキチンと認識したい。どこから買うか、どこから買わないかという選択によって企業を市場から退場させる力が我々にはあります。Let's hack the capitalism.
729
デザインには「前」と「後」がある。みんな「後」に注目するけど本当に強いデザインをつくりたければ「前」が重要。headlines.yahoo.co.jp/article?a=2020…
730
731
ありとあらゆるモノが溢れている状態で「ハングリーになれない人」が多くなってくると、モチベーションが最も重要な「競争優位を左右する経営資源」になります。モチベーションはビジョンが与えられて初めて高まるのでここでもやはりビジョンが重要という。
732
個人の知的成長もシステムで考えるとわかりやすい。見る→感じる→考える→表現するの4モジュールで考えると、論理思考は「考える」に該当するけど、そこだけ鍛えても「見る」「感じる」が少なければ意味がない。だから「見る」力が大事という。
733
自信のない人ほど他人を笑う。自信のある人ほど自分を笑う。
734
勤労の道徳は勤労を必要とせず、他者の勤労によって裕福な暮らしをする階層の人々によって捏造されたものだ、とラッセルは言っています。勤労の道徳は奴隷の道徳である、しかし現代は奴隷を必要としていない、と。「一生懸命働くのは良いことだ」という価値観の根拠を疑うべき時代ですね、哲学です。
735
「役に立つけど意味がない」と「意味があるけど役に立たない」。今後、価値があるのは後者。スキルを高めるのも良いけど「役に立つ」は高く売れません。スキルからセンスの時代。logmi.jp/business/artic…
736
金利がゼロになると時間も消失すると書きましたけど、これは「勤勉」の終焉にも繋がります。「今の時間」と「未来の時間」で後者に価値があるから「今」を手段化するわけです。「永遠の今」が循環するだけなら、この瞬間を踊り、歌い、描き、愛することに使った方が良いとなりますよね。祝祭の高原。
737
49%というのは高い失敗確率に感じるかも知れませんがカギは「何度も繰り返す」ということです。49%の失敗確率であれば二つ試して両方失敗する確率は24%、三つ試して全て失敗する確率は12%。以下、五つなら3%、七つなら1%にまで低下する。不確実性の高い時代に「飛び込む」マインドセットは必須です。 twitter.com/shu_yamaguchi/…
738
福澤諭吉は『文明論之概略』で幕末から明治への転換について「 一身にして二生を経るが如く」と言っています。私たちの社会も然り。このとき「人生の前半」と「人生の後半」では「常識」が変わってしまう。特に「人生の前半」に過剰適応してしまうと後半でおかしなことになるので注意が必要です。
740
「役に立つ」と「意味がある」は人についても当てはまります。誰かに合うという時、その人は「役に立つ」のか「意味がある」のか。どちらでもないのであれば、その時間は人生の無駄使いである可能性が高い、ということです。逆に言えば、自分は他者に対してどうなのか、と。
741
子供に英語や楽器や絵画を習わせようとしたって、子供だってバカじゃありません。親が語学も楽器も絵画もやらずに週末はゴルフで時間を垂れ流してれば「面白いのはゴルフで語学も楽器も絵画もツマンナイんだ」と思うのは当たり前です。親自身が身をもって「ツマラナイ」ことを示してるわけですからね。
742
「役に立つ」より「意味がある」方が高く売れる。これは人についても同じです。論理思考も話し方も「役に立つひと」を目指す戦術だということをお忘れなきよう。diamond.jp/articles/amp/2…
744
マネジメントというのは特殊な技能を持たない人が高い報酬を得るための、殆ど唯一と言っていい仕事だったわけですが、実はこのマネジメントこそが最も人工知能に代替されやすい。彼らが人工知能に職を奪われた後、どのようにして「人間ならでは」の付加価値を再獲得するか。
745
行政や企業の方針を決めるエリートたちは「数値目標を与えられると意味も考えずにそれを達成したがる」「数値評価で人に負けるのが大嫌い」という、非常に迷惑な二つの特徴を有しています。暴走を阻止するには「残された人々」がきちんと声を上げないといけません。
746
カッコいいですねえー
sumatome.com/su/13174111604…
747
「個性を伸ばす教育」という掛け声がなぜいつも虚しく響くか?髪の毛の色にすら個性を認められないほどに「個性が大嫌いな教師たち」が居るんですから無理に決まってます。気が狂ってるとしか思えません。 twitter.com/mituru_ki0522/…
748
「しくじり先生」って反脆弱性そのものだよなあ、と。番組に出た人の多くはもっとパワーアップしてるでしょ。外乱やストレスを与えて弱くなるのが脆弱性、逆に強くなるのが反脆弱性。生物は反脆弱なシステムなので外乱やストレスを避けてるとどんどん弱くなる。
749
自分にとって有益な情報以外は無意味なので時間をかけなくていい、ということをかつて僕も言ってたのですが、そうすると「自分にとって何が有益かを判断する枠組みそのものを変換させる情報」を漏らしてしまうので、やっぱりグレーゾーンの曖昧さとか直感も大事だよなあ、と。すみません、独り言です。
750
本来面接というのは「あなたのことを知りたい」「オタクの会社を知りたい」というだけの場であるはずなのに、暗号のような「コードのやり取り」が横行してる。結局は新卒一括採用という「大量に面接して機械的に捌く」というシステムに問題があるように思います。壮大な茶番劇です。