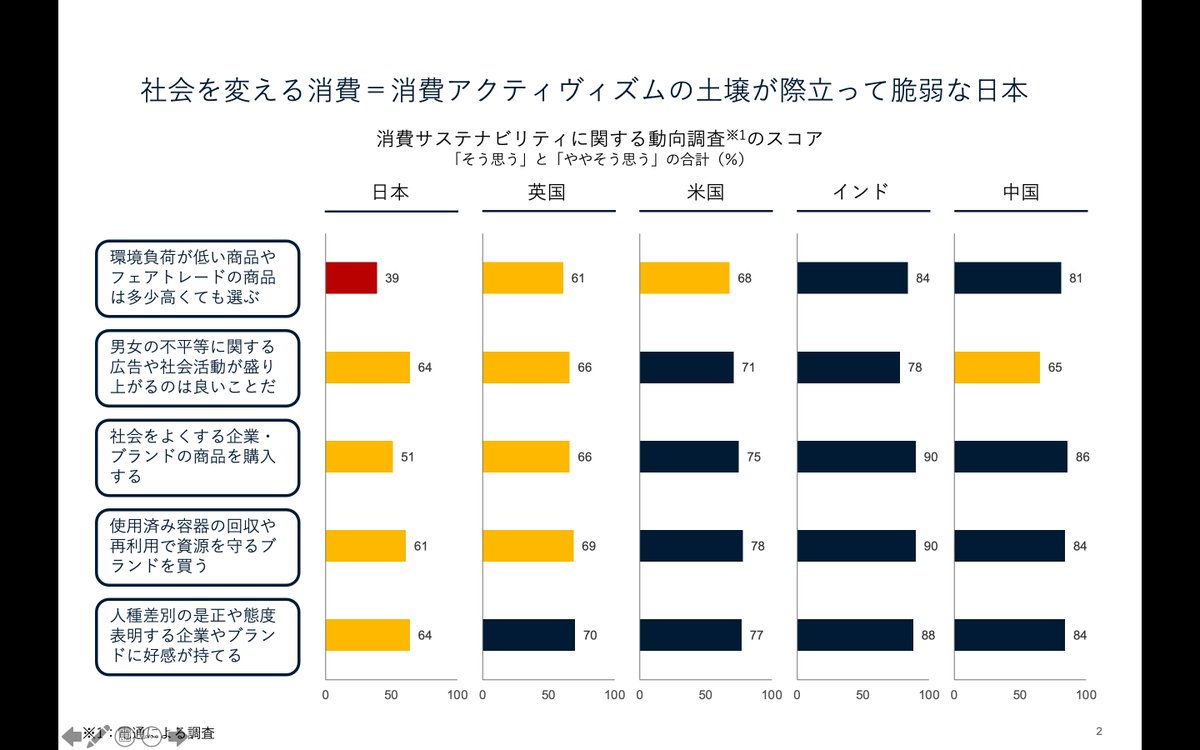551
建築家の隈研吾さんは、大学院に進学する際、当時、建築は作らずに未開集落の調査ばかりしていた原広司研究室に入っています。同期は「何の役に立つの?」と哀れんだそうだけど、隈さんは「役に立たないという確信があって進んだ」と自伝に書いてます。さすがというしかない。
552
最近、周りに俳句を始める知人が増えてるのですが、考えてみれば「その瞬間の感情や感覚を言語化する」ってマインドフルネスそのもので、最近ますます重要視されてるセルフアウェアネスやストレスマネジメントという点でも有効なんだろうな、と。
553
自分自身の必然性から出ていないことを「他人もやってる」「みんなやってる」ということでついやってしまう悪い癖。本当に自分に必要なことは何か、それを地に足をつけて考える。
554
ラグビーの平尾誠二さんの「良いパスの定義」が素晴らしくて、それは「そのパスによってチームの状態がより良くなること」なんですね。同じことを「言葉」にも当てはめてみる。その「言葉」によって受け手の状態が良くなるか?良くなれば必ずどこかでリターンが返ってきます。
555
人の能力は文脈依存的ですから、極端な「弱み」は同時に極端な「強み」にも繋がっています。他人の「弱み」を取り上げて批判するという非生産的なことをやるよりも、それが「強み」になるポジショニングを考える。自分についても同様です。
556
東京一極集中に歯止めをかけるためのアイデア。1:天皇陛下には京都に戻っていただく。2:官庁は多様な道府県に散り散りに分散させる。3:空いた霞ヶ関に絶対安全と言われる原発を作って東京の電力を地産地消にする。どうですかね?
557
計画=プランに意味が無くなる時代には原則=プリンシプルが重要になります。僕の場合、会いたくない人に会わない、やりたくないことをしない、住みたくないところに住まない、というのが三つの原則ですが、この原則を置くようになってから人生がホント楽になりました。
558
オリンピックに関連する日本批判を非常に嫌がる「日本が大好き」という種類の人がいますが、過去の歴史を振り返る限り、自己批判が行われなくなった国こそが衰亡への道を歩むということは知っておいた方が良い。逆に言えば自己批判・衰亡論が議論される国というのはまだ健全だということです。
559
プランBがあると平常心でいられる。漱石が「坊ちゃん」で書いてますよね「この学校がいけなければすぐどっかへ行く覚悟でいたから、狸も赤シャツも、些とも恐ろしくはなかった」って。
560
自己理解と他者理解は表裏一体です。自分が何が得意で何が不得意かは他者の評価によって決まるので、他者がどう感じているかを観て感じて理解する力なくして自己理解はあり得ません。その点で「内省で自己理解に至る」という考え方は片手落ちでミスリーディング、さらに言えば危険と言えます。
561
人も変わっていくのですから許してあげましょうよ。許すことで救われるのは相手よりも誰よりも自分なのですから、ね。
562
3年前の自分を思い返して「あの頃は何と愚かだったのか」と思えないとしたら、この3年間で何も学べなかったということです。
563
よく勘違いされてますが「ブルシットジョブ=クソ仕事」は仕事そのものより、仕事の「意味づけ」で決まる側面があります。この「意味づけ」は本来リーダーの仕事なのですが、統計からいうと全管理職の一割程度しかやってない・・・なので私たちは自分の仕事の意味を自分で作っていく必要があります。
564
バートランドラッセルは「怠惰礼賛」の中で「暇を楽しむには教養がいる」と言ってますね。この指摘を踏まえると、なぜ働き方改革が上手くいかないかがよくわかります。改革して浮いた時間をゲームとかテレビとかSNSとかで潰すしかない人にとっては「働き方を改革する」インセンティブが無いんです。
565
正解に価値はない、問題に価値がある。
nazology.net/archives/47433
566
567
僕の音楽に力なんてないですよ。役に立つこともない。役に立ってたまるか、とすら思います。
asahi.com/and_M/20200522…
568
ロジカルシンキングというのは確かに強力な武器になりますが、論理的な根拠がないと強く主張できなくなってしまう、という恐ろしい副作用を伴います。そして、人生の重大事はだいたい論理的にシロクロつかないことなので、重大な局面で主張できないという、決定的な欠落を抱えることになります。
569
刑務所は安全だから外に出るのが怖い。ショーシャンクで描かれた状況は示唆的でいまの日本社会そのものだなあ、と。多くの人が自分で作った安全な刑務所の中にいてそこから逃げようとしない。逃げるのってとても勇気がいるんですよ。
570
学校教員も企業管理職も従順で聞き分けの良い子を評価する一方、ワガママで扱いづらい子は排除します。しかしイノベーションは後者によって実現されますので、イノベーションを求める一方で、従順で聞き分けの良い人材を揃えようとするのは論理矛盾であり無い物ねだりです。
571
他人に迷惑をかけてはいけない、というお仕着せそのものが他人にとって迷惑です。これほど人の行動の自由度を奪う呪いはありません。
572
努力ってラクなんですよね、前に進んでるような気がするし。努力には階層性があって、僕はこう言うのをレイヤー1の努力と呼んでいます。必要なのはその上位にあるレイヤー2の努力。 twitter.com/shu_yamaguchi/…
573
二週間でテレワークシステムを構築して話題になってる登大遊さんのブログから。大事なのは「① 努力しないこと② 論理的に考えないこと③ 頭を使わないこと」だそうで、ここにもニュータイプがいました。softether.hatenadiary.org/entry/20070324…
574
会社が小さいバンドみたいになって、皆が複数のバンドを掛け持ちするような社会になるといいなと思ってるんですが、そうなると「他の人にできること」はいくらできても仕方がありません。ドラムが5人のバンドって意味がわからないでしょ。自分にできる楽器と音楽性を見つけていく。
575
そういえばアランも「幸福論」で「悲観は気分の問題だが楽観は意志の問題だ」と言ってましたけど、ホイジンガ の指摘を合わせれば「楽観には知性と意志の両方が要る」ということなのかもしれません。スピノザっぽいですね。