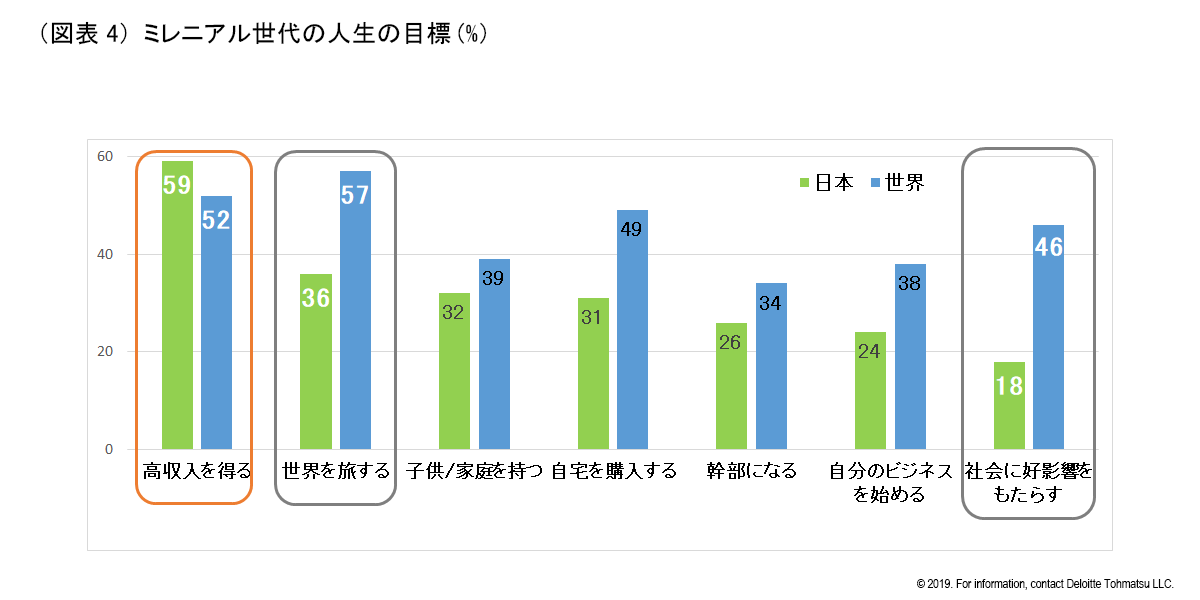351
顧客の奴隷になることが顧客志向だと思ってる人がすごく多い。人間関係で考えてみればわかるけど、奴隷みたいに振る舞う相手と建設的な関係は築けないでしょう?顧客に対する「愛」とか「共感」が本当の顧客志向なんだと思います。人間と同じ。
352
会社の戦略がなってない、と文句を言う人ほど自分の戦略がなってないように思います。人生は宝くじではありません。戦略のない船に乗っているのはあなた自身の戦略ですよね、という話です。
353
アメリカでベストセラーになった「Fuzzy and Techie」が日本では全然売れない。これは「日本でこれから先に何が来るのか」ということをわかりやすく示してくれます。わかっている人にはある意味で「とても美味しい状況」がしばらくは続く、ということでしょうね。
354
小泉進次郎さんに関する揶揄や批判を見るにつけ、この国には本当にフォロワーシップがないなと感じますね。リーダーになれないならせめてフォロワーになってくれればいいんですが、フォロワーにすらなれないんだからタチが悪い。客席からヤジを飛ばすだけの人生がそんなに楽しいんですかねえ。
355
他人と比較することでしか自分の幸福度合いやステータスを確認できない、というのは致命的な悪癖です。「成功してるのに不幸な人」という人はみんなこの思考様式に人生をハックされてる。
356
よく「全員経営」みたいな理念を掲げている会社がありますね。不思議なのは、こういう理念を掲げているくせに経営情報を現場には開示していない、ということです。「全員経営」なのに、なぜ現場担当者に全情報を開示しないのか?理由は単純で「本気ではそう思ってないから」ですよね。
357
リモートワークの浸透で地方移住は増えるか、増えないかといった議論が喧しいですが、とても視座の低い貧しい論点だと思ってます。議論されるべきは「リモートワークという労働形態を手にした私たちは、どういう社会・企業・労働をオルタナティブとして次の世代に提案できるか」という論点でしょう。
358
難局に直面したとき、会社や社会に裏切られたと考えるか、自分の思考が浅かったと考えるか。前者はただ恨み辛みのルサンチマンを生むだけですが、後者は「他人に流されずに自分のアタマで考えなきゃダメだ」という態度を育みます。
359
良いビジョンと悪いビジョンはどう判断するのか?などという驚天動地の質問がよく来る。そんなもの「自分がワクワクするかどうか」に決まってるだろ!と。自分がワクワクしてないビジョンにどうして他人がワクワクするのか。「心を動かす」ということをしてこなかったツケが回ってる人が多い。
360
あらためて「水戸黄門」って恐ろしい番組だと思います。暴力と権力によって「その場の問題」を潰すだけで、問題の根本原因を生み出すシステムには手を付けないという。
361
362
いま急速に「リモートワーク」が社会に浸透してますが、葉山界隈の人で話してるのは「通勤がなくなったので生産性が上がった」ということ。逆にいうと「環境はよくないけど便利」という場所の「利便性プレミアム」は減少することになりますね。不動産の市況にもいずれは影響が出るのでしょうかね。
363
暇を楽しむための技術を学ぶのが学校。だから学校=スクールの語源は「暇=ギリシア語でスコレー」なんです。暇を楽しめない人は何をするかというと要らぬ仕事をしてしまうわけです。これがケインズの「百年後には一日3時間の仕事で社会が回る様になる」という予言が外れた理由だと僕は思っています。
364
メンバーシップ型からジョブ型へという議論が喧しいですが議論が短絡的なように思います。雇用負担が大きいのであれば「メンバーシップ型だけど週三日勤務」といった働き方もあるはず。これからの世界はジョブ型からプロジェクト型へと進みます。残像を追いかけるよりショートカットしませんか?
366
自分の幸福にしか興味がない、という人がもっと増えると、世の中は随分と良くなると思うのですけどね…
367
戦争がなぜ絶滅したかっていうと、やっぱり価値と大地が分離したからですよね。シリコンバレーを占領してもシリコンバレーの富が手に入るわけではない。残された例外が石油と宗教でこれは未だに大地と紐づいてるので永遠に小競り合いが収まらないという。
368
需要は必ず飽和します。需要が飽和した世界で生産性を上げるイノベーションが起きれば、仕事は増えず、失業する人が増え、富はごく少数の人に集まり、格差が拡大します。イノベーションが貧困を生み出してるわけです。これがアメリカで起きてることですよね。簡単なロジックだと思うんですけどね。
369
一日が終わる時、どんなことがあっても「今日は素敵な一日だった」と
言ってみる。「落ち葉がハラハラ綺麗だった」とか「タクシーの運転手さんが面白かった」とか、どんな日でも良いことって必ずありますからね。それを拾い集めるようにして生きられると良いかな、と。
370
内容を読むと完全にサディストの異常者ですね。殺された少年には本当に気の毒です。スポーツ指導の資格すら取ってないシロウトが強圧的に指導することが許されている「部活」という異常な世界。この状況を放っておいてる教育委員会他の責任は非常に重いと思っています。
number.bunshun.jp/articles/-/849…
371
勉強のための時間が作れない、という悩みを聞くのですが、テレビありますか?と聞くと、ありますと。だったらまずテレビを捨てると、軽くて1日数時間の勉強時間はできますよ、と。これにSNSの禁止を加えれば、五年後には知識人として働く素地はできます。あとはやるかやらないか、それだけですね。
372
ワークとライフを分けて考えないといけない状況がそもそもマズイ。友人が大手SI会社に勤めながらイタリア食材の輸入をやってるんですが、彼にとって食材調達のためのイタリア出張は完全な趣味であると同時に完全な仕事でもあります。だからものすごく幸福そう。
373
多くのプロジェクトに携わっていて思うのは、この国はかつてより謙虚さを失っているのではないか、ということです。進んだ知見を持つ海外の組織や団体があるのに、人を招くなり、教えを乞うなりということをせず、日本人だけで固まって実行してコケてることが多いように思います。
374
会社評価のサイクルカーブ。1=入る前は二倍良く見える。2=働いてる時は二倍悪く見える。3=辞めた後で等倍の真実が見える。特に危ないのが1と2の落差でここで幻滅して会社を辞めてしまう人が多いんですけど、このサイクルカーブを意識して過ごすと色々とラクになります。
375
コロナ後は職場の学習のあり方も大きく変わる可能性があります。なんとなく先輩の仕事を見て覚えるという、いわゆる「正統的周辺参加」は職場が仮想化すると非常に難しくなります。コロナ前後では身体的な学習機会が大幅に減少するので人材育成、特に新人の育成に大きな格差が生まれると思います。