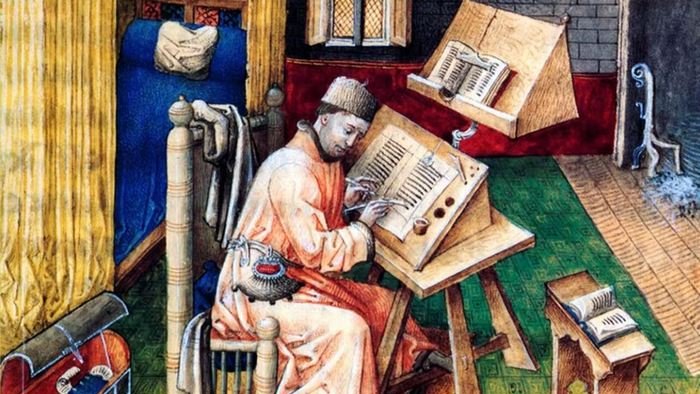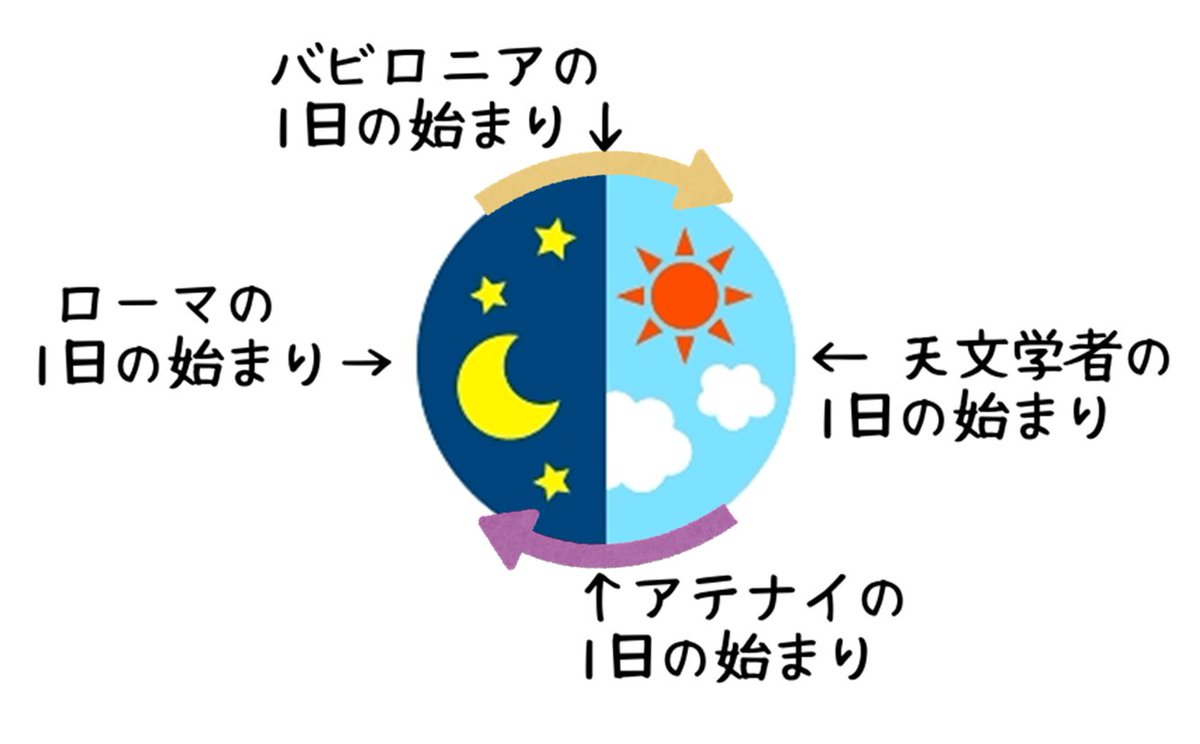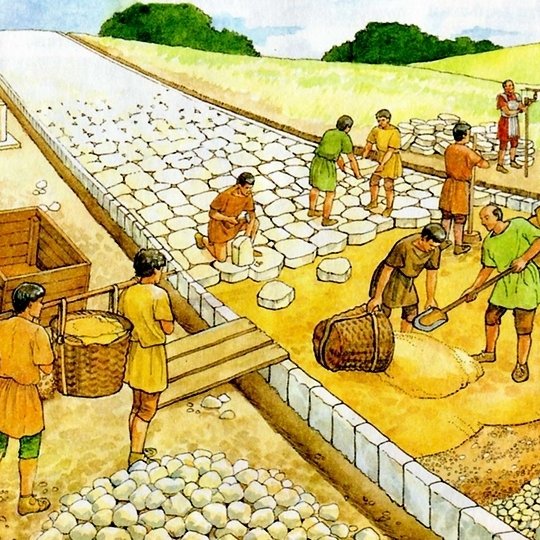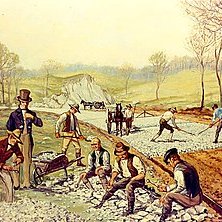101
ユークリッド『原論』にある初歩的な定理をみれば分かるように中学生でも理解できるような命題ですら当時の「哲学者」らは何ら貢献をしていないのです.ですから現代の「哲学者」ら(と一括りにするのは誤解を招きますが)が数理科学の勉強を怠っているとすれば「愛知」の精神に忠実であるといえます😂
102
103
104
105
ここはかなり際どい部分で,そもそも「過去とはなにか?」ということに関係するのですが,タイムマシンによる「観察」を史料として扱うとしても,最初に提起した,それは史料にある人物や事件と同一であると誰が担保するのか?という難題があるため,結局は史料を読む者の解釈の問題になります.
106
古代ギリシャ料理はおせちです😂😂😂
#謹賀新年
107
108
繰り返しになりますが,プラトンと名乗る人物をタイムマシンで尾行し,彼がエジプトへ行かなかったことを「観察」したとします.この「観察」をもとに「プラトンはエジプトへ行った」という史料を否定できたといってよいのか?そのためには「観察」を裏付ける別の史料と解釈が必要ではないのか?
109
本人の証言です⬇
『螺線について』序文
実はそれらの中に二つの間違ったものが紛れこんでいましたから.どんなことに関しても発見したと自ら称しながら,ただ一つの証明もすることのできない連中に,実は成りたちえないことを発見したといわせて後から化けの皮を剥ぐのに役だつこともあるでしょう😂
110
111
112
やはりタイムマシンに乗って「過去の何か」を確かめたい人もいるようですが,本能寺の変が起きた理由は明智光秀に直接聞けば分かると考えているのだと思われます.裁判で例えると絶対に嘘をつけない被告が存在しその「被告が語る動機」により事件発生の原因を知る事ができるという立場なのでしょうね.
113
なお「研究はしなくても勉強はしたのでは?」と思われる人もいるでしょうが,これも相当に怪しい.前4世紀に既に高度な数理科学が展開されていましたが,「哲学者」はその定理になんら言及しません.言及するのは決まって初歩的な定理です.また紀元後の「哲学者」も当時の先端科学へは沈黙を守ります.
114
115
116
117
118
119
歴史って基本「既存の知識を疑い検証すること」の積み重ねで出来てるんだけど,子どもにそのプロセス教えようとするとすごい手間なので高校までは「既存の知識を正しいと受け入れて覚える」形式で教えられており,故に歴史を「信じるか信じないか」ってものとして捉えてる大人が少なからずいそう.
120
121
123
タイムマシンという突飛な(そして矛盾をはらむ)思考実験は「歴史」=「史料編纂」ではなく,「史料」=「過去の(常に不足気味の)近似」ではないよ,ということをいいたいわけですが,この突飛な思考実験によりあまりにも自明である「歴史」を再考するヒントになれば嬉しいです.
124