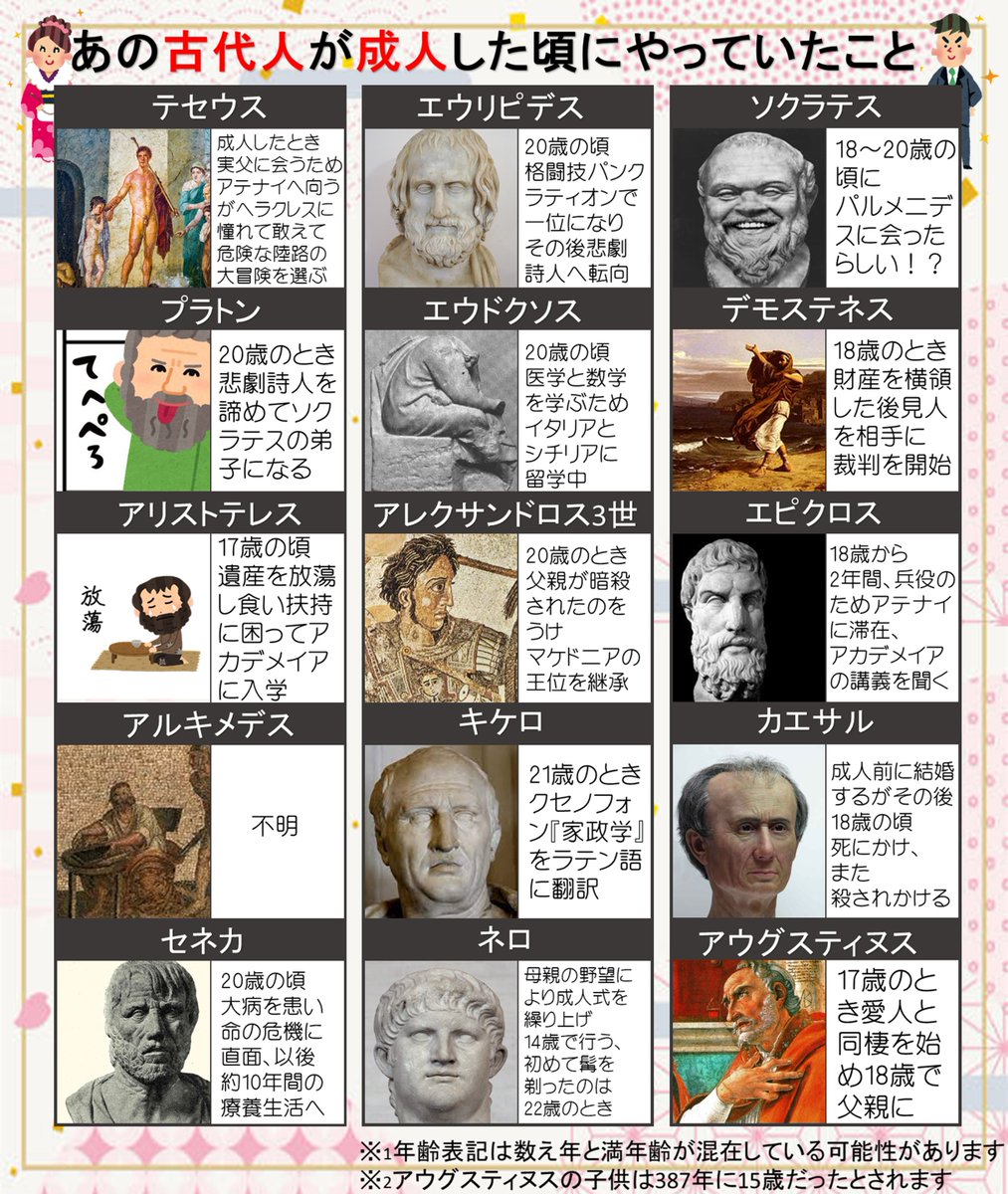26
28
29
30
31
32
「タイムマシンに乗って過去の出来事を調べるのがベストだけれども,まだ実用化されていないので,歴史研究者は仕方なく限られた史料をもとに歴史記述をしている」と思っている方は「歴史」という学芸について根本的に誤解をしていると思われます.
33
35
36
37
これはあくまでも一般論なのですが,古代の文献から「格言」や「座右の銘」として言葉を引用するときは文脈に要注意です.特に古代にない概念の場合は尚更です.どういうことかというと例えばアリストファネス『平和』という喜劇に「ムーサよ,戦争を遠ざけて親しき私と踊り給え」というのがあります.
38
39
40
42
43
44
45
46
「タイムマシン歴史観」によれば,現代に生きてる我々は,ウクライナ戦争の原因や経過について最も詳しい人ということになりますが,おそらくそんなことはなく,数十年,あるいはもっと後になって明らかになる「事実」もあると考えるのが自然ですよね.
47
48
恐い話をしますね.
以前,教科書に載っていたと思う話を,出典を確認しなままポロッとツイートしたことがあります.するとある専門家の方から「出典を教えてください」と引用RTがあったのです.恐い話はここからです.
49
50