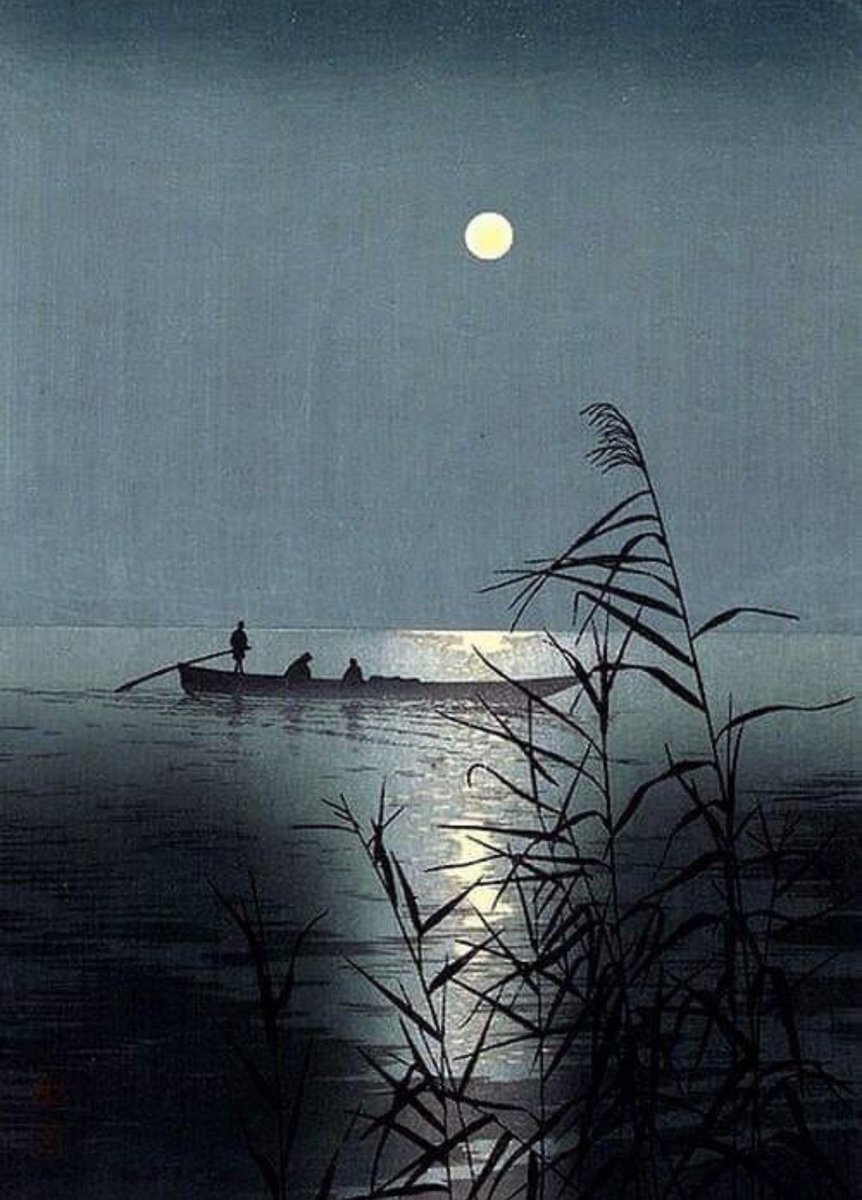176
177
米国では鉄道ではなく車での通勤が一般的だが、シカゴ市とその近郊ではメトラと呼ばれる通勤鉄道が機能している。その線路を冬に凍結させないために、カンテラで火を灯している場面の動画。最近は電熱式が増えたが、このようにガスや灯油を使う場所も残っている。 via @Metra
178
中国江西省にある鄱陽湖は、長江の流域に含まれる同国最大の淡水湖で、雨季と乾季で面積が大きく変動する。その際に水位も変動し、湖の一部を横切っている道路が冠水することがある。しかし走行に大きな問題がなければ閉鎖されない。その際の様子を示した動画。 via @lsjngs
179
イギリス南東部のラベンハム村には、大きく歪んだ木造の家が多数みられる。写真集 bit.ly/2WKmny1 15~16世紀に羊毛の布の生産で地域が急発展した際に建てられたもの。人口が急増し、切った直後の木も使って家を建てたが、それが乾燥した際に変形した結果。魔法の世界のような不思議な景観。
180
ロシアのバイカル湖で春先に湖面の氷が岸にせり上がってきた場面の動画。巨大な流氷が風により湖岸に打ち寄せられたか、御神渡と同様に温度が上がったために氷が膨張した結果と思われる。フランスの @myroques 氏が投稿したもので、ロシアの友人から提供された映像とのこと。
181
オーストラリアの Ryan Pernofski 氏は水中での撮影を得意とする写真家。彼が浅い海に入り、上方から差してくる日光を撮影した動画。長さは12秒間と短く、写っているのは海水と泡と光のみだが、水の揺らぎや視線の移動に対応した映像の変化が大変美しい。 via @RyanPernofski
182
ネパールの中部で今年の1月に発生したクラウド・アバランチ(雲なだれ)とよばれる現象の動画。手前の湖の標高は2500m台で、その上流域の険しい斜面で雪崩が生じ、雪粒が雲が湧くように高く舞い上がっている。撮影者も含めて人的な被害はなかったとのこと。 via @nowthisnews
183
白色のクジャクを紹介した記事。 bit.ly/39kMC2O カラフルな色で知られる鳥のため意外性がある。個体が遺伝子疾患で白くなったアルビノのようにも見えるが、ホワイトライオン等と同様に、種の全個体が白い白変種。白変種が存在する理由として、氷河時代に保護色だったことが指摘されている。
184
米国の企業が開発した道路の上り車線と下り車線の境を短時間で変更する車を紹介した動画。時間帯により上りと下りの交通量が大きく変わる場所で有用。作業時の車線閉鎖も不要。日本の駅のエスカレーターの一部が、時間帯で動く方向が変わるのと似た発想。 via @DigitalTrends
185
2018年6月にハワイ・キラウエア火山から多量の溶岩が噴出した際に撮影された、溶岩流に乗って大きな岩が流下した場面の動画。米国地質調査所は「溶岩のボート」と呼び、「溶岩の氷山」と呼んだ人もいる。カメラの近くで岩が二つに割れる場面も含めて圧巻。 via @MilekaLincoln
186
中国・雲南省の最南端に位置するシーサンパンナ・タイ族自治州は、仏教が盛んでゾウがいる東南アジアのような雰囲気の地域。そこの森の中で眠るゾウの群れを上方から撮影した動画。通常は見られない平和な感じの光景で、耳が時々動いたりするのも興味深い。 via @CBSNews
187
「砂の滝」と題された動画。場所はサウジアラビア・リヤドの南方約300kmの砂漠。通常は水のない涸れ川(ワジ)に雨で水が流れた際の状況。地表に植生や土壌がないために砂が一気に移動し、水に対する土砂の比率が非常に高くなり、あたかも砂のみが落ちているように見えている。pic.twitter.com/SMC9DI91iQ
188
コロンビア南部・グアタペ町の近郊にある巨大な一枚岩の空撮写真 bit.ly/2XxxHNm および地上写真集 bit.ly/36BUJH2 地質は花崗岩で、約7千万年前に地下で他の岩石の中に貫入し、その後に強度が低い他の岩石のみが侵食されて塔状に残った。比高は約200mで、649段の階段で登頂できる。
189
約1300光年の彼方にあるオリオン大星雲は、地球から見える星雲の中で最も明瞭なものの一つ。約1万年前の形成で、星が誕生している場所でもある。ハッブル宇宙望遠鏡が取得した三次元データを用いて作成された、同星雲の中を飛行する動画。SF映画の雰囲気。 via @NASAHubble
190
ドイツ・ハノーファー近郊の湖にある人工島の写真 bit.ly/39HFdfu テーマパークかゲームの世界のような雰囲気だが、元は18世紀に作られた要塞。当初は石垣が水に接する星形の島だったが、後に周囲が埋め立てられて四角形に。撮影者は ChristianSchd 氏。Googleマップ bit.ly/3wvbqjW
191
南極の氷床から古い氷を採取し、研究している大学院生が、ボーリングで生じた深さ93mの氷の穴にカメラを下ろした動画を公開。カメラはゆっくり下げたが、映像の一部を早送りして異次元にワープするような感じに編集したと思われる。最下部の氷の年代は約二百万年前。 via @ABC
192
ウェールズでは2018年の夏に雨が少なく、貧弱になった植生が土地の水分量の不均質を強く反映するようになった。その結果、約2千年前に当地を征服したローマ人が作った集落や道の遺構が空から見えるようになった。写真を分析した最新の論文 bit.ly/3fSzRyH BBCの記事 bbc.in/2V1P34h
193
英国南部のチチェスター市の近郊で撮影された、ロンドンへと続くローマ時代の街道が保存されている場所の写真2枚 flic.kr/p/N4EUFu flic.kr/p/zBDNNW トンネルのような印象的な景観は、下半分は切り通しの土の窪みで、上半分は木が構成。撮影者は Roman Popelar 氏と Steven Vacher 氏。
194
スウェーデン中部のエステルスンド市で撮影された真珠母雲の動画。高緯度~極地域の高空にできる虹色の雲で、色がアコヤガイの内側に似ていることにちなんで命名。この動画では明るい色彩が川の水面に反射するほど明瞭。地元の Göran Strand 氏が撮影。 via @Astrofotografen
195
米国イリノイ州の南部で撮影されたアーチ雲の動画。アーチ雲は棚雲とも呼ばれる細長い雲で、嵐の初期に積乱雲や積雲の底部に形成されることが多い。下部に滝のような雰囲気の雲の垂れ下がりができることもあり、この動画は、それがひときわ明瞭な事例。 via @LiveStormChaser
196
メルカトル図法の世界地図で高緯度ほど面積が誇張されている実態を示した秀逸なアニメーション。色が誇張の程度を示し、白に近いほど大。南北に長い日本では、北海道と九州で誇張の程度が数十パーセント違うことも示されている。英国の Neil Kaye 氏が作成。 by @neilrkaye
197
今月26日にUAEのドバイ付近の海岸で見られた部分日食をともなう朝日の写真。 bit.ly/352UBxI 水平線の少し上で太陽が二つ重なっているように見えるが、「だるま太陽」と呼ばれる蜃気楼現象の一種。 bit.ly/37e0zND 沖合の船との組み合わせも印象的。reddit の Jakdracula 氏が撮影。
198
動きに関する目の錯覚の例。建物の一部が回転しているように見えるが実際は動いていない。左下部の赤い色がついた部分が止まっていることに注目。場所はイタリア・ミラノのサン・シーロ・スタジアムで、らせん状のスロープを多数の人が歩いて降りている場面。 via @DrHercouet
199
部分的にオレンジ色に光る石を手で回している動画。熱い溶岩を素手で触っているような雰囲気だが、実際には石に含まれる方ソーダ石(ソーダライト)が紫外線により蛍光を発している。紫外線を当てていることは、指の一部が青色になっていることでわかる。 via @GeologyTime
200
アラスカ南部のカトマイ国立公園で、三頭のクマが滝を登ってくるサケを捕まえようとしている場面の動画。左のクマが捕獲に成功した際に他の二頭が嫉妬したような表情をし、さらに成功したクマが去る際に横のクマが「あっち行け」的に脚を動かす様子が興味深い。 via @CBSNews