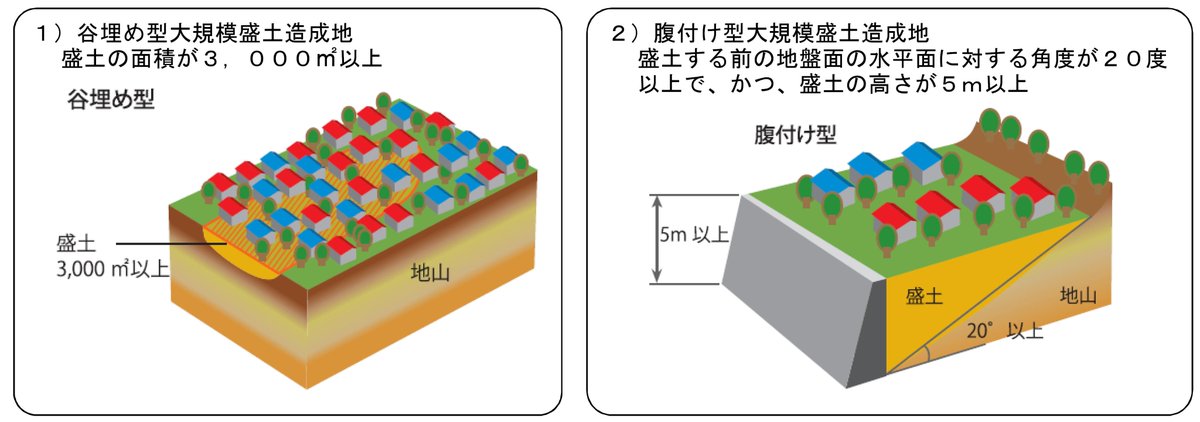1426
1427
豪州の旅行保険会社のバジェット・ダイレクトは、世界各地の全壊もしくは半壊した歴史的な建物をCGで復元する有意義なプロジェクトを実施している。最近発表されたアジアの6つの復元例。 bit.ly/38VOcJh イラン、中国、アフガニスタン、インドの事例と日本の萩城および竹田城が含まれている。
1428
欧州の国々などがチリに設置したヨーロッパ南天天文台(ESO)で観測され、オランダの AJ Bohn 氏らが昨年公開した太陽系に似た系の画像。 bit.ly/3ACCIpi 中央やや左が恒星で、中央やや下と右下が2つの惑星。他の星は遠方の系外にあるもの。過去に例がない画像とのこと。位置ははえ座の方向。
1429
アフリカの各国で電気を利用できる人の比率を示した地図。 bit.ly/3rZsvQ4 国際エネルギー機関のデータに基づく。緑の色が濃いほど比率が高い。最北部では先進国のように約100%の国が並ぶが、中部では1~9%の国もあり、大半が60%未満。電気が使えて当たり前の我々とは全く違う状況がある。
1430
日本の国旗の色で日本を人口が等しい二つの地域に分けた地図。 bit.ly/3b9okKb 米国の地理マニアの LordPhoenix99 氏が作成。東京周辺への一極集中ではなく驚いたというコメントが記されている。確かに首都圏は世界で最も人口が多い都市圏だが、赤い範囲では人口が少ない山地の比率も高い。
1431
世界の各国で過去に記録された最高気温の分布を示す世界地図。アルジャジーラ社が今年の7月に作成。北緯30度付近で赤茶色の50℃以上が帯状に並ぶことと、赤道付近は意外にも相対的に低い傾向が明瞭。島国や半島状の国など、陸が海に近い地域でも相対的に低い傾向がある。出典 bit.ly/3wuJdew
1432
ドイツの行政単位ごとに最多数の住民が属する宗教の分布を示した地図。 bit.ly/2MECJFM 青はプロテスタント、赤はカトリック、黒はその他で、濃い色ほど比率が高い。黒は無神論者が主体。旧西ドイツと旧東ドイツの地域の差が明瞭。両地域の経済格差は有名だが、宗教観も大きく異なっている。
1433
U.Sプレイング・カード社は19世紀に遡る企業で、トランプの売り上げが世界最大。同社が第二次大戦中に製造し、ヨーロッパ戦線の米国や英国の兵士に渡された特別なトランプを紹介した記事。 bit.ly/2AU4l4o 水に浸すと二つに開き、ドイツの地図が出てくる。捕虜になった際に逃げる道を図示。
1434
インドのコルカタに上陸した史上最強レベルのサイクロンに関するCNNの記事。 cnn.it/3e22Mza 大規模な避難が行われていることと、避難生活や救援活動の際にウィルス感染の防止を考慮していると報告。災害と感染の両方に完全に対応することは困難で、バランスをどうとるかの判断が重要と指摘。
1435
東京・浜松町にある40階建ての世界貿易センタービルは、1970年3月から翌年6月まで日本一高いビルだった。その前の日本一は36階建ての霞が関ビル。その次に日本一になったのは47階建ての新宿・京王プラザホテル。高度成長期の日本を象徴する建物の解体は、半世紀という長い時間の経過を感じさせる。 twitter.com/robo1954/statu…
1436
米国カリフォルニア州で地震防災に取り組んでいる団体が、地震と津波から身を守るための行動を示した子供も理解できるようなポスターを制作。移民の多さなどを考慮し、日本語を含む11の言語で整備。公開ページ bit.ly/2Z5bfjb 同じサイトにある諸資料を含めてパブリックドメインの扱い。
1437
海中で古代の採掘場が発見されたことに関する詳しい報告が、米国、メキシコ、カナダの研究者の共著論文になり、サイエンス誌の姉妹誌に掲載された。 bit.ly/3iJT6wg オープンアクセスで、誰もが全文を閲覧できる。興味深い地図や写真も掲載されている。
1438
鉄道の路線のみを示した世界地図。 bit.ly/3dE4fwW 灰色と青色の線は緩速の路線で、他は緑色系、黄色系、赤色系の順に、より高速となる。日本、中国東部、ヨーロッパでは高速な路線が密で、インド、ミャンマー付近、米国東部では緩速の路線が密。アフリカや南米では疎な分布になっている。
1439
雪が降った場所で見られた興味深い現象や風景の写真を50枚集めた記事。 bit.ly/34KoW71 ネコが屋内から雪が積もった屋外に一足だけ出してつけたスタンプのような足跡や、強風の影響で車の前面に帽子のつばのような形の雪ができている風景など、ちょっと驚くような写真が並んでいる。
1440
スペイン領カナリア諸島のラ・パルマ島では9月19日から火山が噴火し、多量の溶岩が流出している。数百軒の家屋が溶岩に飲み込まれたが、一軒だけ周囲が溶岩に覆われたにもかかわらず残っているものがあり、「奇跡の家」と呼ばれている。その家の空撮を含む動画。 via @dwnews
1441
今滞在中の米国でA4用紙のコピーをとると、やや縦が短く横が長いレターサイズの紙しかなく、紙面のバランスが崩れる。Crissov 氏による国ごとの紙のサイズの世界地図。bit.ly/2Xzkunv 濃い青ほどA4を厳密に使い、濃い赤ほどレターを厳密に使う。例外的なフィリピンは1946年まで米国の植民地。
1442
東京の地下鉄路線図で用いられている抽象的な表現を、各路線の実際の位置と対応するように変形させたアニメーション。1931年にロンドンの地下鉄で抽象的な路線図が初めて使われ、利用者に有用なため世界各地で採用。東京の路線図は最も複雑なものの一つ。 via @MapScaping twitter.com/MapScaping/sta…
1443
北米が極域からの強い寒気に覆われていることを示した地図を含むNASAの記事。 go.nasa.gov/2NAQEx8 2月15日のデータで青色は氷点下。米国の南端部に位置するテキサス州とアラスカ西部の気温がほぼ同じことを示す。熱容量の大きな海は冬でも冷えにくく、大陸の内部ほど冷えやすいことも読み取れる。
1444
フィンランドではトナカイの角に夜光塗料を塗り、車との衝突を防ぐ試みが行われている。紹介記事 bit.ly/3i6bsbC 2014年頃からSNSで紹介されていたが、最近再度話題に。実は効果は限定的。車の運転者が反射材のついた人の服と勘違いし、道の中央付近に居続けないはずと思うことなどが理由。
1445
パキスタン・パンジャーブ州で数日前に見られた竜巻の動画。土を多く巻き上げて茶色になっているため、竜巻と背後の空を覆う雲を明確に区別できる。巨大な仏塔が回転しているような状況に圧倒される。あまり横に移動しないので、見物人が集まっている。 via @Pak_Weather
1446
NASAが公開した三日月に似た「三日地球」の写真 go.nasa.gov/3t7g5ph 元の写真は1972年に地球に帰還するアポロ17号の船内から飛行士が撮影。その写真を最近、英国の Toby Ord 氏がデジタル技術を用いて修復。氏はアポロ計画で撮られた他の地球の写真も修復・公開している bit.ly/3ny9Jho
1447
情報を消そうとすると逆に拡散することを「ストライサンド効果」と呼ぶ。解説 bit.ly/2PWtK10 その由来となった空撮写真 bit.ly/320BHYD カリフォルニア州の海岸侵食の調査で撮影・公開されたが、邸宅が写っていたバーブラ・ストライサンドが公開中止を提訴。敗訴のニュースで拡散。
1448
地球上で陸地に接しない最長の直線と、海に接しない最長の直線を示した図。 bit.ly/2CjSMnT 根拠の論文(pdf) bit.ly/2CklIw4 最近後者について、より長い直線が提示された。 bit.ly/2ZJzelB 以前は海抜0mのスエズ運河を海としていたが、開削の前は陸地であることを考慮。
1449
先日英国で、蜃気楼のために海上で浮上しているように見える船の写真が撮影された。 bbc.in/3qWmCC9 その写真と理由を説明したイラストを含むBBCの天気予報担当者のツイート。下層の大気が海面に冷やされて密度が高くなっていたために、光の進む方向がアーチ状に湾曲して生じた一種の錯覚。 twitter.com/weatherbraine/…
1450
トマトは野菜か果物かという論争に対し、米国の最高裁が1893年に野菜だと判決したという記事。 bit.ly/43TiSVW 野菜には10%の関税がかけられたが、果物にはなかったために生じた裁判。判決によると、トマトは生物学的には果物だが、野菜として食べられているので、商業活動では野菜となる。