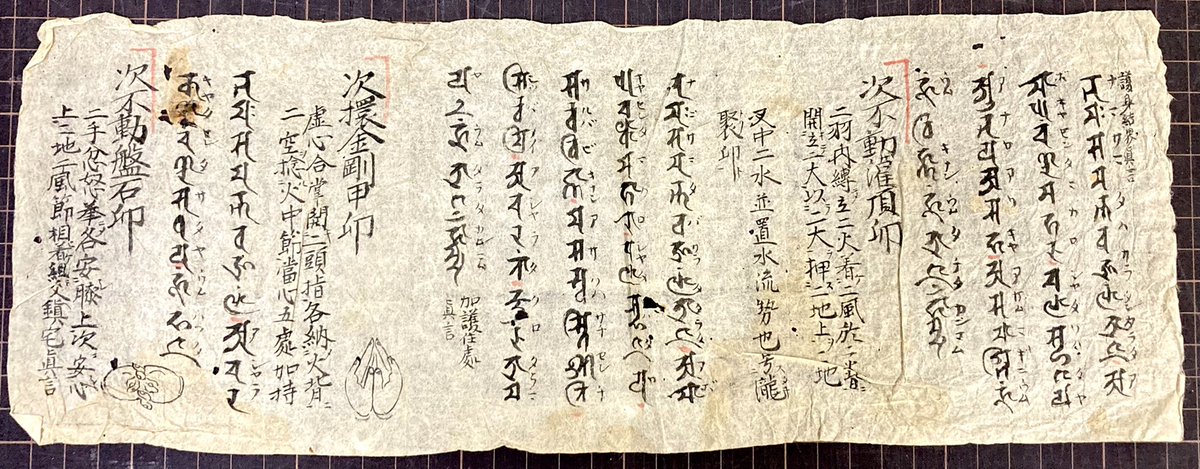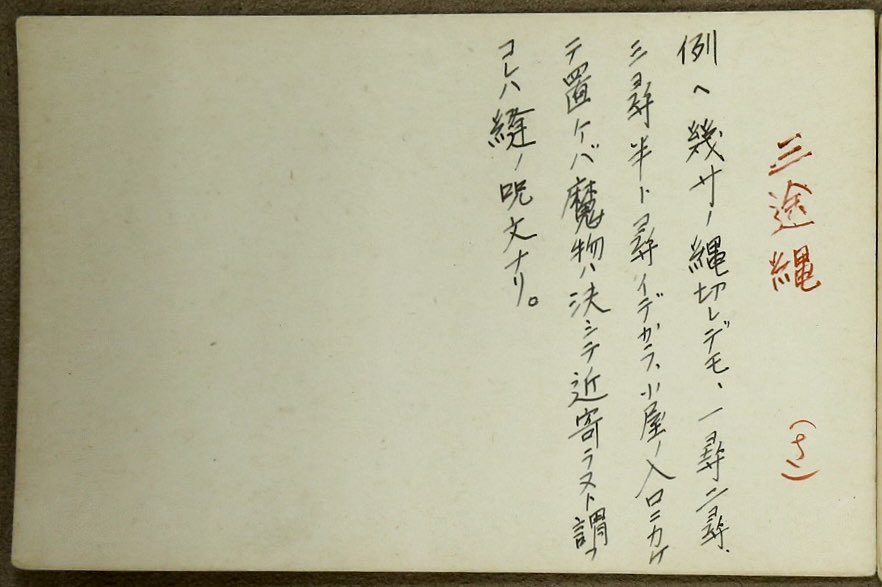702
704
705
707
錦絵「猫の湯」
遠野ではひな祭りに錦絵を飾る風習があり、大正2年(1913)の新聞「上閉伊新報」には、家々ではひな人形や絵画を飾り「小なる美術展覧会」のようであったと記されています。
「遠野のひな人形」展示資料
#猫の日
708
709
ガタンコガタンコ、
シュウフッフッ、
さそりの赤眼が 見えたころ、
四時から今朝も やってきた。
遠野の盆地は まっくらで、
つめたい水の 声ばかり。
宮沢賢治著「シグナルとシグナレス」大正12年(1923)より
遠野盆地
猿ヶ石川の鉄橋を走る軽便鉄道
(大正時代)
#鉄道の日
711
鍋倉城跡本丸付近にて
712
713
715
716
718
719
【柳田國男と泉鏡花】
『遠野物語』が出版された1910年代にこの書を最も高く認めたのは、柳田が一高時代から敬愛していた泉鏡花であり、自身の「遠野の奇聞」にて大きな賛辞を送っている。
ちなみに、『遠野物語』の話者である佐々木喜善は鏡花に憧れ「鏡石」という筆名を使用していた。
723
725