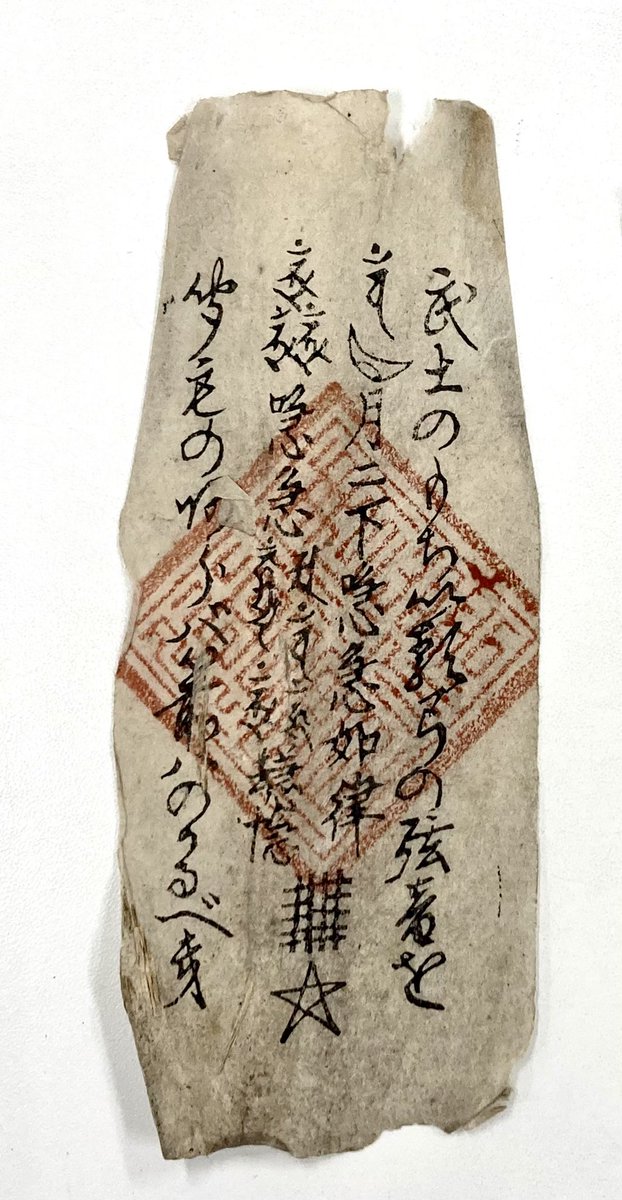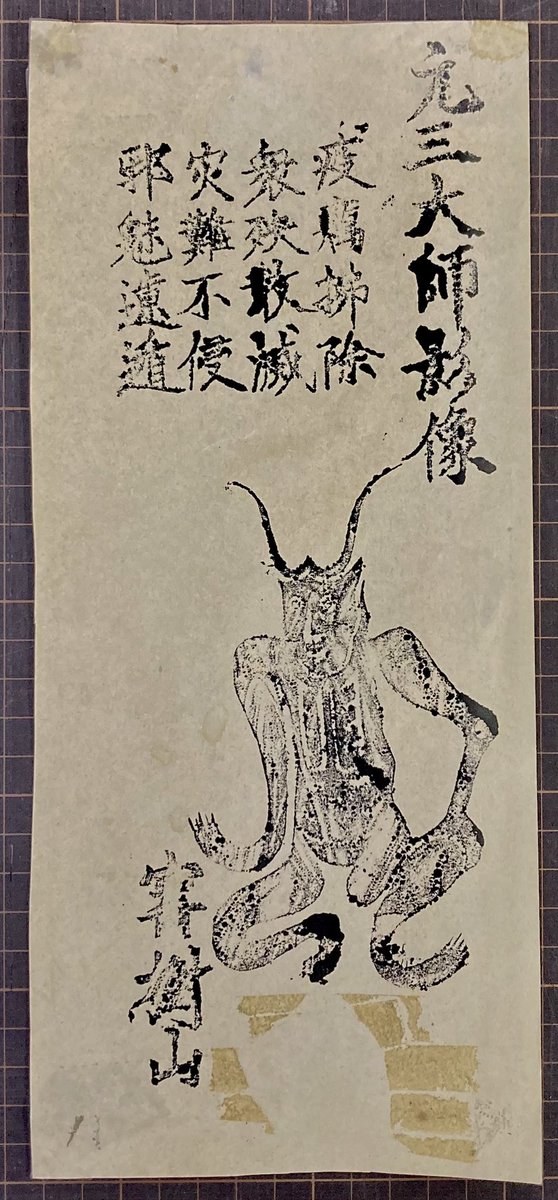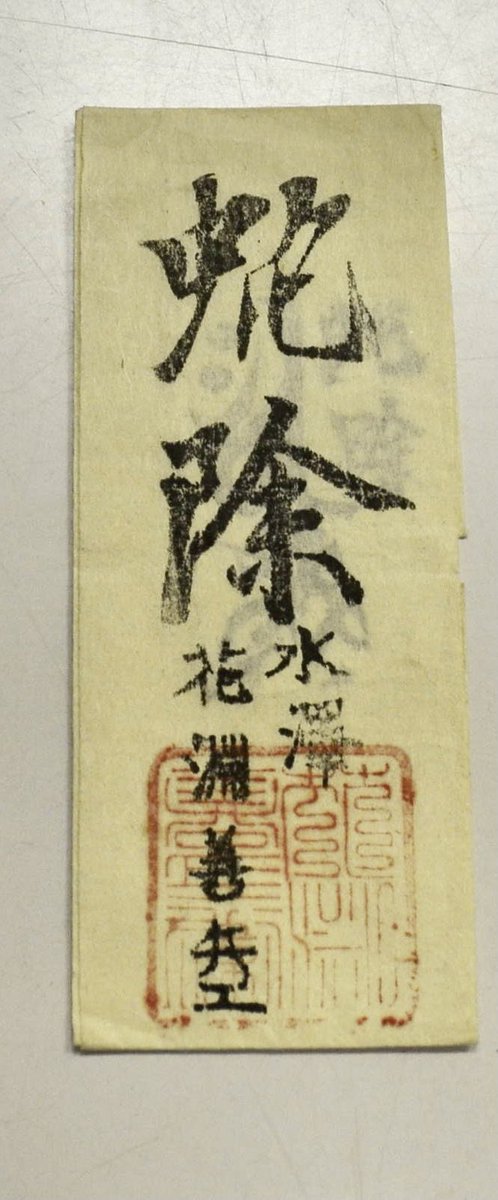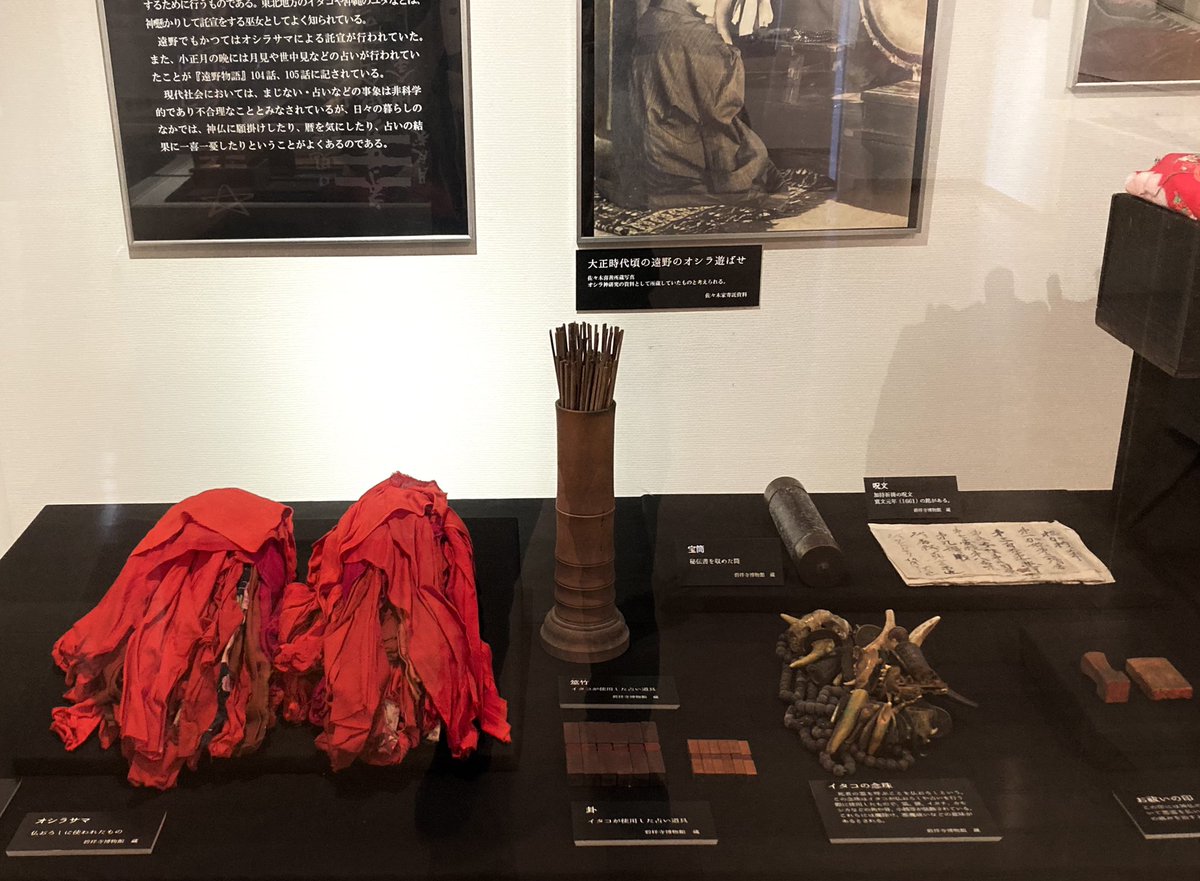626
627
628
629
630
633
636
637
638
639
640
641
644
646
647
「まめ本遠野物語」本日再販開始です! twitter.com/tonomuseum/sta…
648