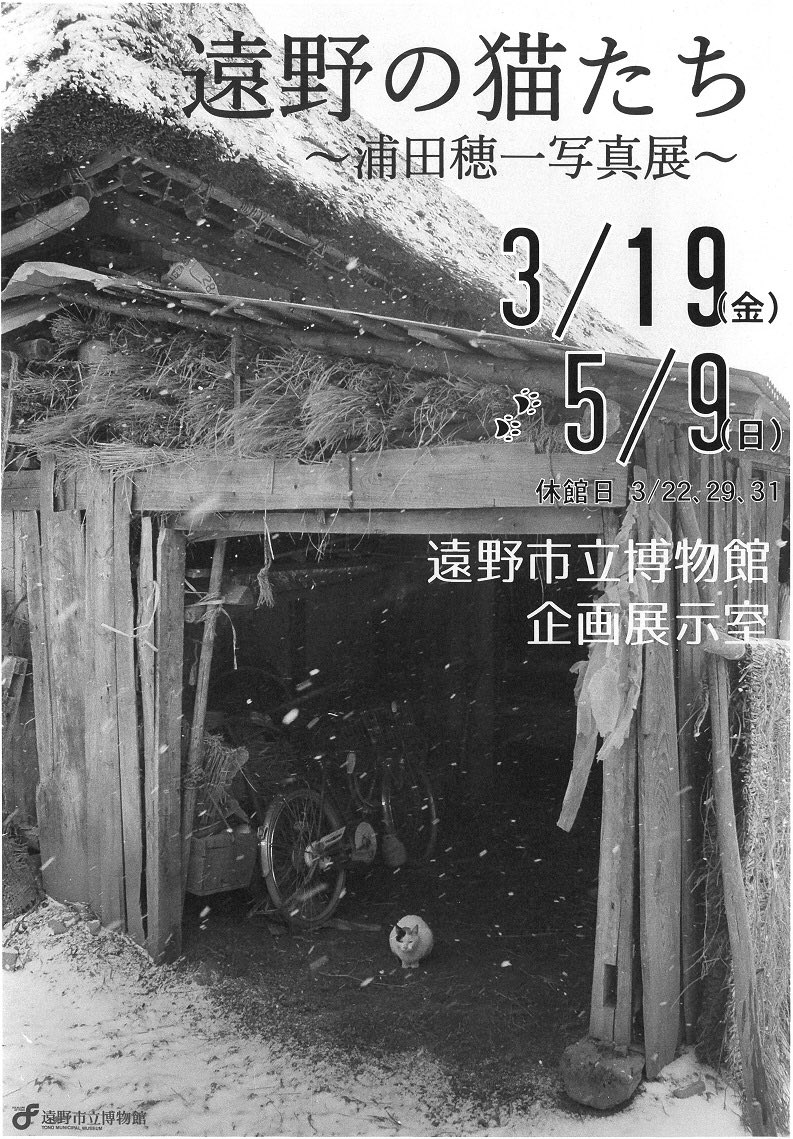577
579
580
582
583
584
589
590
592
599
600