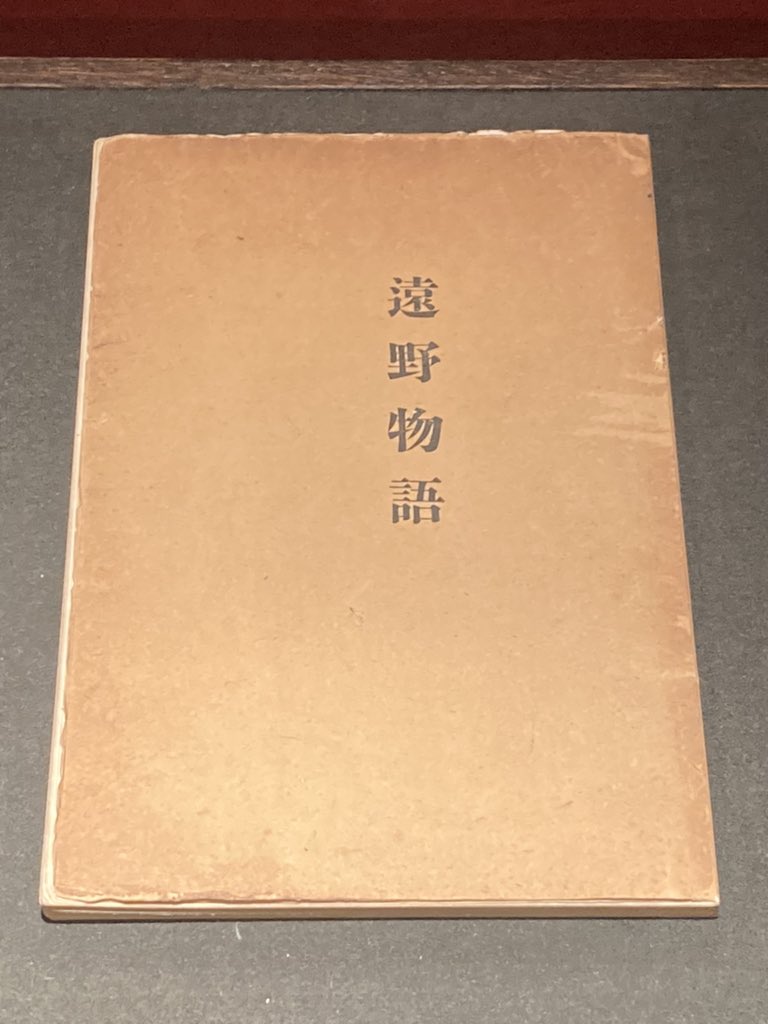551
552
554
555
558
559
561
562
563
564
565
566
569
570
573
574