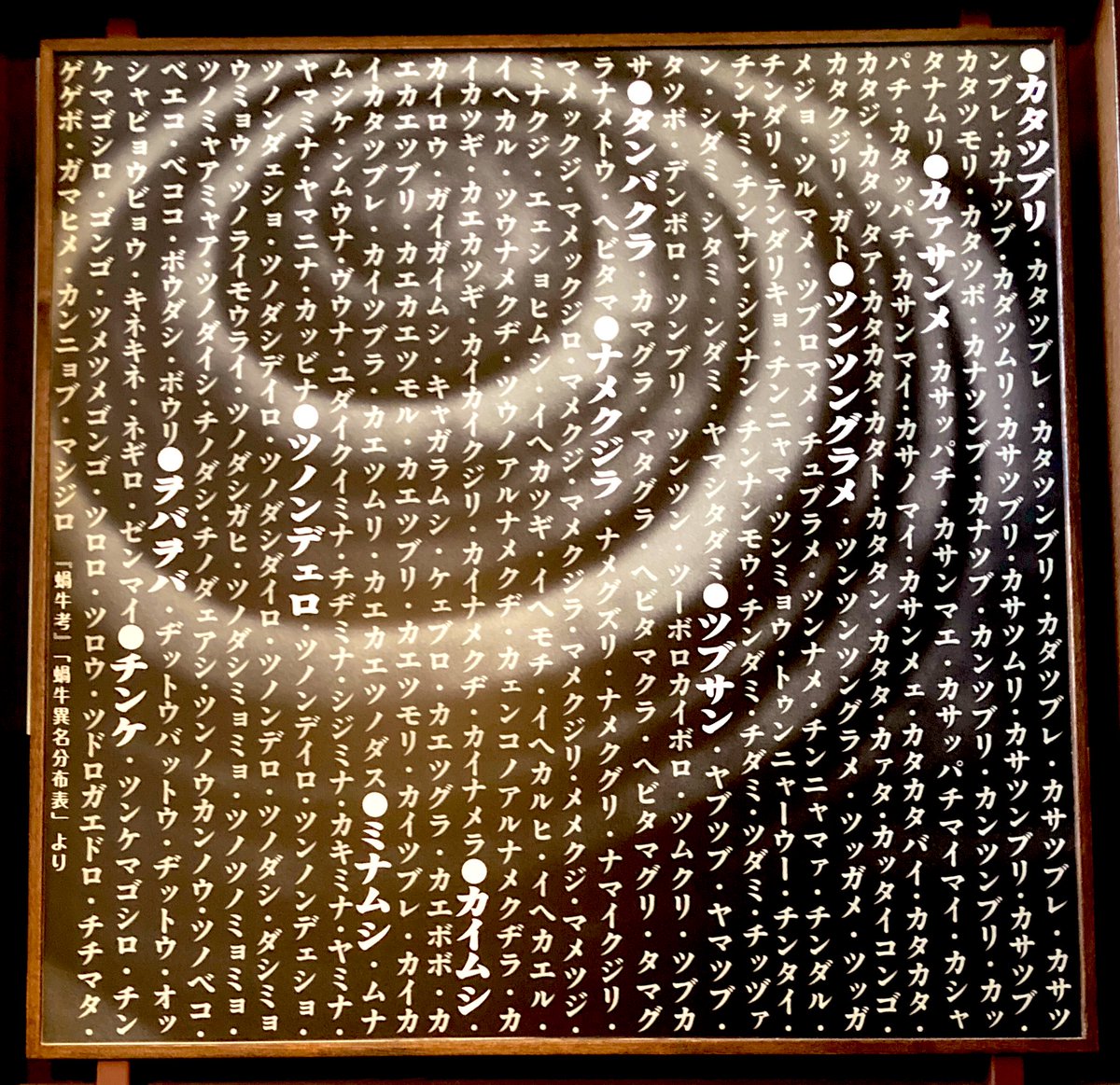402
403
405
407
本日から荒神神社の田んぼに水が入り、田植えの準備が始まりました。
408
410
411
414
415
417
418
419
421
422