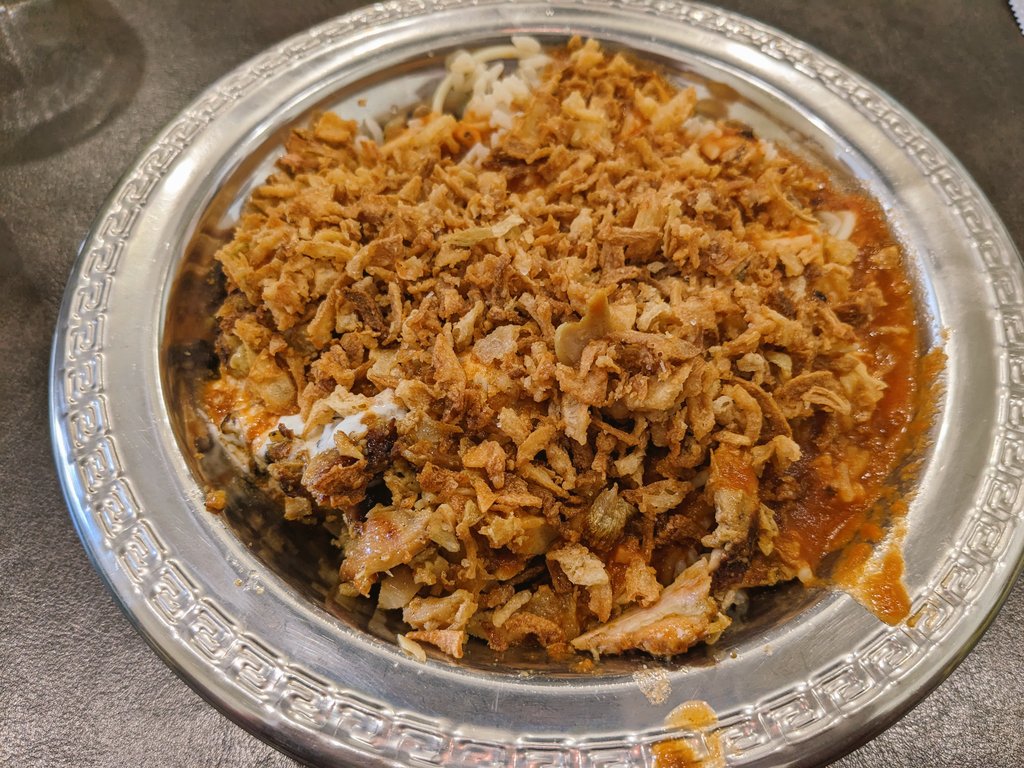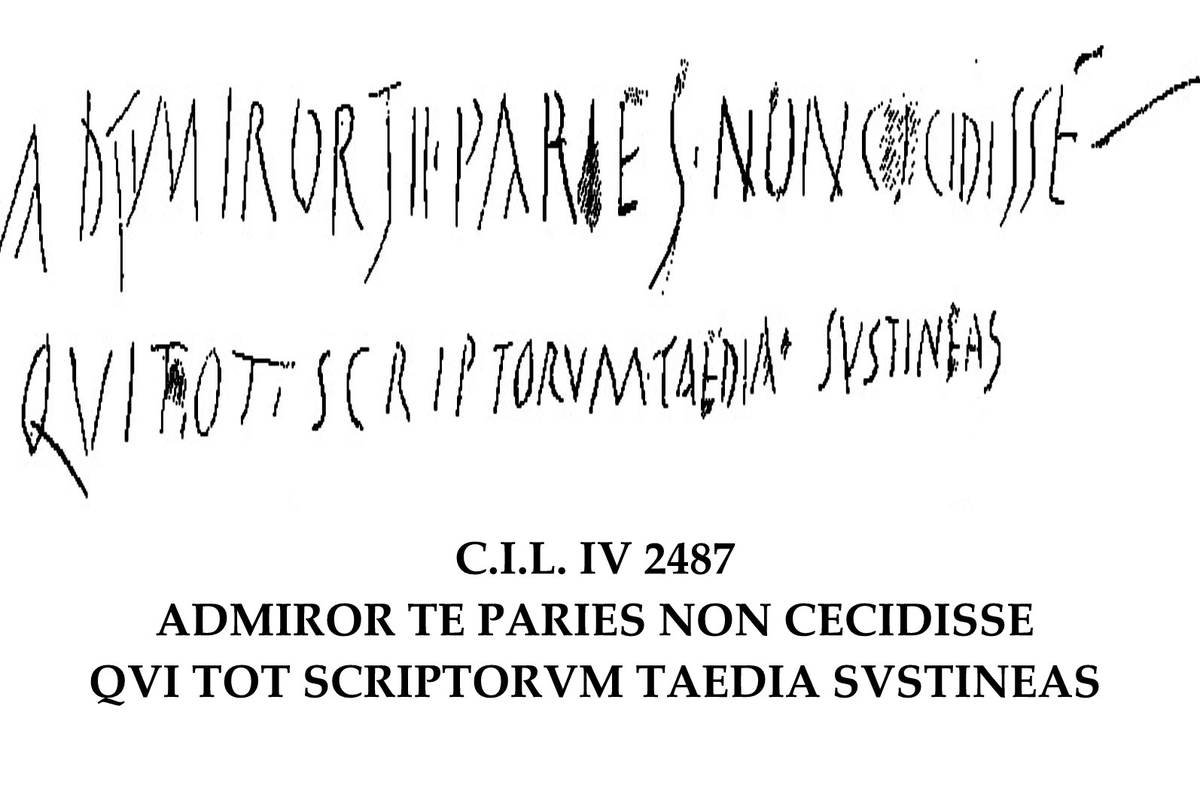1326
歯科検診で耳にする"C"は、一時期まで英語のcavity「虫歯の穴」だと思っていました。
このCは、ラテン語caries「腐蝕、虫歯(カリエス)」の略です。こんなところにもラテン語が隠れています。
1327
オーストリアにある古代ローマ時代に建設された「異教徒の門」はかなり変わってしまいましたが、そこに設置されている透明なアクリル板を通して見ると、当時の姿がはっきり分かります。すごくいいアイデア。 reddit.com/r/pics/comment…
1328
1329
スキー場を指す「ゲレンデ」は、ドイツ語の"Skigelände"「スキー場」が短くなったものと思われます。"Gelände"単体では、ドイツ語で「土地」という意味です。
「ゲレンデが溶けるほど恋したい」とはいいますが、もし"Gelände"が溶けたら地球の終わりです。 twitter.com/BURGERKINGJAPA…
1331
このツイートはこあたんさんが以前も書いており、その際に私は辞書なども参照して調べたところ「ケチュア語で七面鳥は『トルコの鳥』という成り立ち」だとは確認できませんでした。
非常に影響力のある方が、根拠の薄い「ネタ」でバズらせるのはただただ残念です。 twitter.com/KoalaEnglish18…
1333
「コーラス(chorus)」と、振付けを指す「コレオグラフィー(choreography)」の語源が同じなのは、語源である古典ギリシャ語khorósが古代ギリシャの劇において歌ったり踊ったりする人たちを指す単語だからです。
ちなみにkhorósが踊る場所は"orkhḗstrā"といい、これが「オーケストラ」の語源です。
1334
2月3日は節分です。
ちなみに古代ローマ時代には「レムーリア祭」という死霊をなだめるお祭りがあり、その際には家長が夜中に家の中で豆をまき、まき終わったらラテン語で"Manes exite paterni."「父祖の霊よ、家から出よ!」と言っていました。
1335
節電で思い出したのですが、英語で電気を指す"electricity"の語源は古典ギリシャ語のḗlektron「琥珀」です。これは琥珀をこすると静電気が発生するからです。 twitter.com/livedoornews/s…
1337
1339
ドイツ語では(傷ついてる人を)さらに痛めつけることを、「傷口に塩を振る (Salz in die Wunde streuen)」といいます。日本語の「傷口に塩を塗る」と同じものを感じます。
1340
1341
1342
1343
ラテン語にligioという動詞は無く、仮にreligo「結ぶ」と関連付けるにしてもreligoからreligioという名詞を作るのは語形的に無理であり、religioの本来の意味が「ためらい」であることや、relego「再び集める」が元だと考える方が確からしいことから↓の説はÉmile Benvenisteにより否定されています。 twitter.com/kamiumach/stat…
1344
1345
1347
ちなみに「バレンタインデー」の由来になっている、当時は禁じられていた兵士の結婚式を執り行って2月14日に処刑されたと伝えられている殉教者「ウァレンティヌス」が実在したことは疑わしく、現在ではカトリックの聖人暦(一般ローマ暦)から削除されています。 twitter.com/livedoornews/s…
1348
「お箸」はフランス語では、意外かもしれませんが「バゲット(baguettes)」といいます。
"baguette"は元々「細い棒」という意味なので、あのパンが「バゲット(baguette)」と呼ばれるのも棒みたいだからです(語源はラテン語baculum「棒」)。
1349
今日のラテン語
Ningit. (ニンギト)「雪が降っている。」
1350