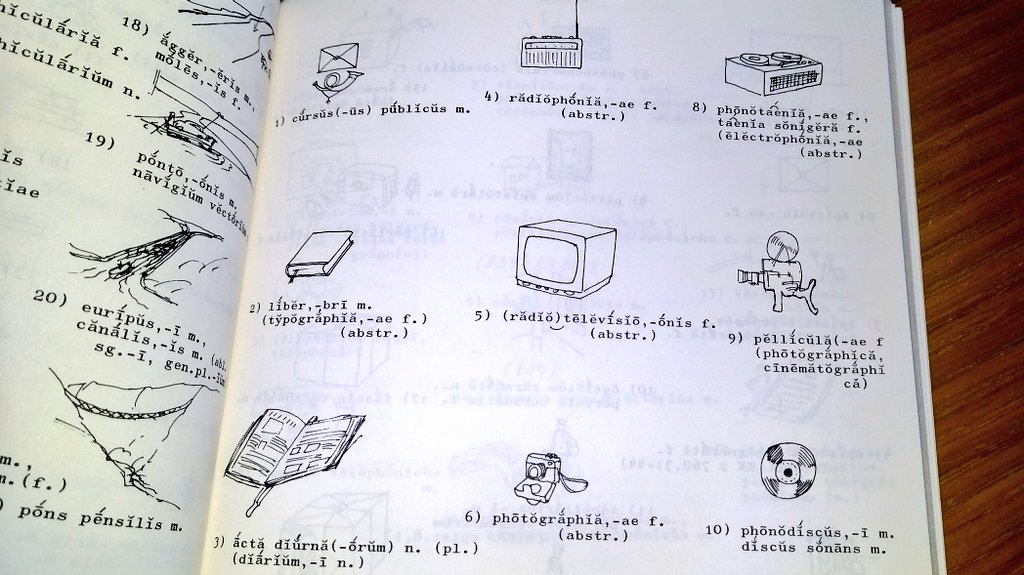726
ラテン語は「死語である」と呼ばれますが、果たしてそうでしょうか。私を含め世界中のラティニストたちはラテン語でコミュニケーションをとっています。例えば昨日はフランスとドイツのラティニストと、先週はチェコ人とやりとりをしました。使う人がいる以上、ラテン語は死語でないと強調したいです。
727
「プリン体」の「プリン」は、デザートのプリンではありません。
プリン(purin)は化学用語で、ラテン語の"purum"「純粋な」と、"uricum acidum"「尿酸」の前半の"uricum"を合わせて作られたものです。
728
729
リーチサイトのリーチはreach「達する」ではなく、leech「ヒル」です。
"leech"は、その生き物のイメージから「他人が作ったものをタダで使いながら利益を得る人」という意味も生じ、「リーチサイト」の「リーチ」はその意味で使われています。 twitter.com/itm_nlab/statu…
730
フジテレビの番組「今夜はナゾトレ」にて「ミネストローネの意味はイタリア語で『具だくさん』である」という説明がありましたが、ミネストローネの語源は以下の通りです。
ちなみに、イタリア語にてこのスープ名から転じて「ごた混ぜ」という意味が生じました。 twitter.com/latina_sama/st…
731
「ロマンス(romance)」はローマと関係があります。
語源の中世ラテン語Romanicusは「(古代ローマのラテン語から発達した)俗語」という意味で(フランス語等は「ロマンス諸語」と呼ばれています)、俗語で書かれた文学に騎士物語が多くあり、romanceが"騎士物語"、後に"恋愛物語"を指すようになりました。
732
近年、患者が劇的に減った「インフルエンザ」はイタリア語から入ったことばで、語源は中世ラテン語influentia「影響」ですが特に星の影響のことを指しています。
大昔のイタリアでこの病気が流行ったときに、天体の運行の影響によってこの病気が発生したと考えられていました。
733
734
「ディスコ」は水樹奈々さんの曲にもある"discothèque"(ディスコティーク)の略で、"disco-"の部分は「レコード」で"thèque"の部分の語源は古典ギリシャ語θήκη (thḗkē)「箱」です。
クラブのことを「ハコ」と呼ぶことがありますが、ディスコの語源に通じるものがあります。
735
736
日本や英語圏などでは「ミッフィー」と呼ばれますが、ミッフィーが生まれたオランダでは「ナインチェ(Nijntje)」という名前です。これはオランダ語のkonijn「うさぎ」から派生したkonijntje「うさぎちゃん」の後半を元にしています。
日本でも、このキャラの絵本では「うさこちゃん」という名前です。 twitter.com/miffy_japan/st…
737
英語の"children"は二重複数です。
中世ではchild「子供」の複数形はchildreでしたが、さらにoxen「牛たち」等に使われる複数語尾"-en"を足した結果、childrenという二重複数の形になりました。
また、日本語「子どもたち」も二重複数です。
738
「エンカウントする」は和製英語です。
「遭遇する」という動詞、あるいは「遭遇」という名詞は"encounter"で、たしかにこの語尾は動詞っぽくないかもしれません。encounterの語源は同等の意味の古フランス語encontrer、その核となる部分の語源はラテン語のcontra「相対して」です。
739
2月3日は節分です。
ちなみに古代ローマ時代にはレムーリア祭という死霊をなだめるお祭りがあり、その際には家長が夜中に家の中で豆をまき、まき終わったらラテン語で"Manes exite paterni."「父祖の霊よ、家から出よ!」と言いました。
740
「アヘン」という単語は結構道筋が長くて、
語源は同じ意味の古典ギリシャ語のὄπιον (ópion)で、そこから
→ラテン語"opium"
→英語"opium"
→中国語"阿片(ā piàn[あーぴえん])"
→日本語「アヘン」
という流れになってます。
741
Godspeedという英単語は神的に速いことではなく、「うまくいきますように」という意味です。
これは中世の英語God spede「神が(あなたを)栄えさせますように」が元で、現代の英語で「速さ」を意味するspeedも元々は「成功」や「繁栄」という意味でした。
742
743
ラテン語charta「パピルス紙」のポテンシャルすごい。
この"charta"から
ポルトガル語を通じて「かるた」
英語を通して「カード」と「チャート」
ドイツ語を通して「カルテ」
フランス語を通じて「(ア・ラ・)カルト」が日本語に入ってるのです。
745
746
テレンティウスの劇に「私はオオカミの両耳をつかんでいる(auribus teneo lupum)」という言い回しが出てきます。
オオカミから手を離せば喰われ、かといってそのままずっとつかみつづけるのも難しいです。このフレーズは、あることをやめてもそのままにしてもいずれ苦しくなることを指しています。
748
749
一般教養という意味で「リベラルアーツ」という言葉が使われることがよくあります。
リベラルアーツの語源はラテン語のliberales artes「(奴隷でない)自由身分の人にふさわしい学問」で、中世では特に文法学、論理学、修辞学、幾何学、算術、天文学、音楽が「リベラルアーツ」だと考えられていました。
750