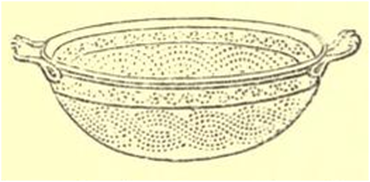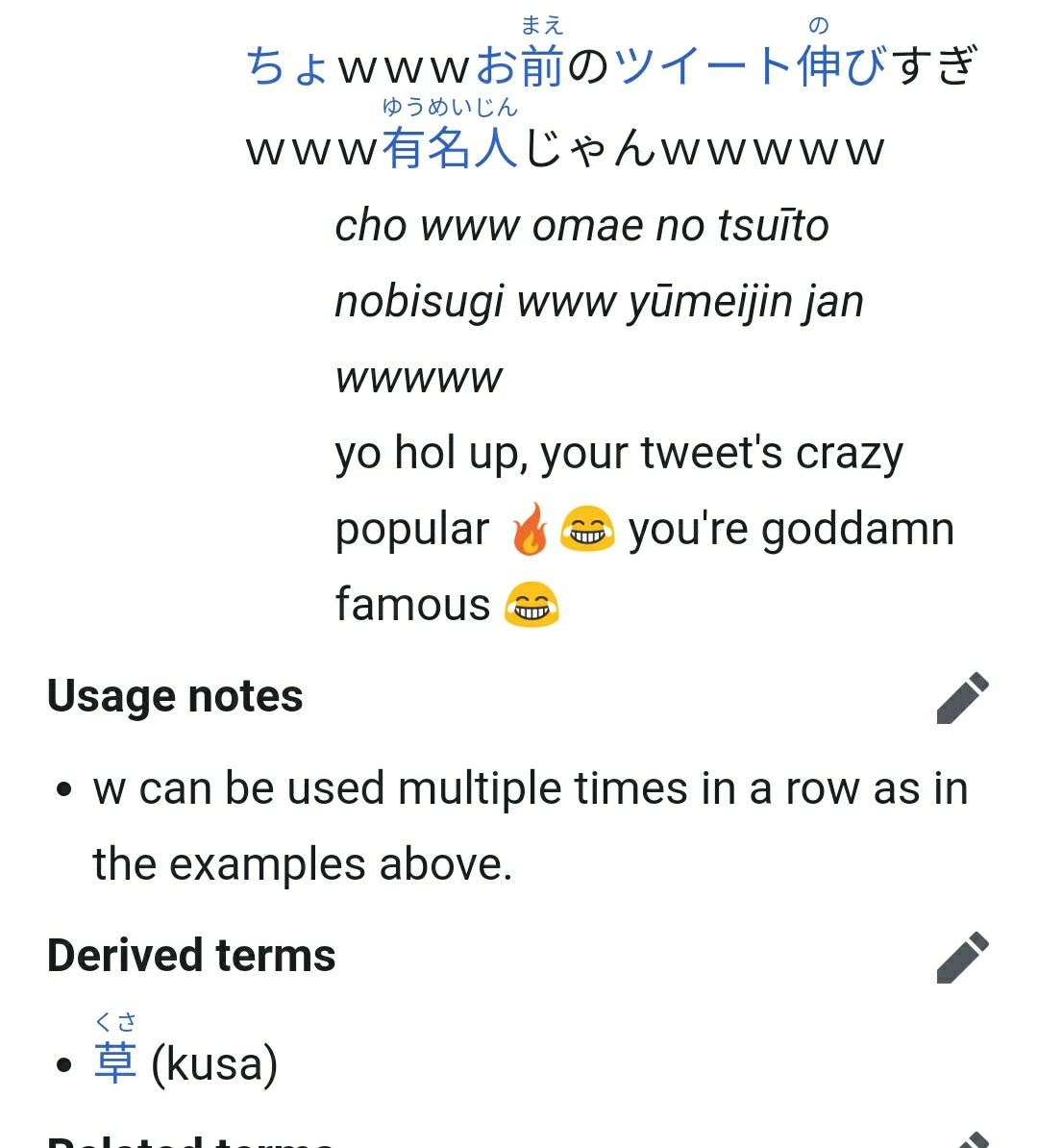651
「モンスター(monster)」の語源はラテン語"monstrum"「怪物」ですが、monstrumの元は"moneo"「警告する」という動詞です。
これは、奇怪な生物は「悪い出来事がこれから起こる」という神々からの警告であると考えられていたからです。
653
"Oxford"「オックスフォード」という地名の語源は、「牛(ox)が歩いて渡った浅瀬(ford)」です。
ちなみにトルコにある「ボスポラス海峡」のBosphorusの名前も、古典ギリシャ語のboós「牛」とpóros「浅瀬」が合わさってできたもの(つまりOxfordと同じ語源)であるという説があります。
654
655
私の中学では修学旅行で「外国人に英語で話しかけてサインをもらいなさい」という課題があり、話しかけた1組目はスウェーデン人、2組目はオランダ人でした。
どちらも英語母語話者ではないですが、英語話してそうに見えるという理由で非英語話者に声かけるのってどうなんだろうと思えてきました。
656
「ネギトロの由来は『ねぎ取る』である」という説はTwitterでも度々バズって複数のテレビ番組でも取り上げられている話題ですが、デマと言っていいほど根拠に乏しい説になります。
「実は○○ではなくて△△」というタイプのデマ語源は広まりやすいので、注意が必要です。 poc39.com/archives/7396 twitter.com/ArturGalata/st…
657
658
怪物の「チュパカブラ」は、元々「チュパカブラス」でした。
元のスペイン語chupacabrasの意味は「ヤギたちを(cabras)吸う(chupa)もの」で、最後のsは怪物としての複数形でなくヤギの複数なのですが、英語に入った時にchupacabrasのsが怪物の複数形だと誤解されてchupacabraという語が生まれたのです。
659
キャバクラはキャバレークラブの略で、フランス語のcabaret「キャバレー」の元はフランスのピカルディ地方の古い方言のcambrete「小部屋」(cambre「部屋」+指小辞)で、cambreの元はラテン語camera「部屋」です。
カメラはラテン語camera obscura「暗室」が元なので、キャバレーとカメラは同語源です。
660
頭字語には2タイプあり、それぞれ名前があります。
まず FBI(エフビーアイ)など、それぞれの文字の名前をそのまま読むタイプの頭字語はinitialismといい、
それとは違ってFIFA(フィファ)のように、普通の単語のように読む頭字語はacronymといいます。
661
662
ヴォイニッチ写本はこのサイトで全部無料公開されています。ぜひ解読してみてください。archive.org/details/TheVoy…
663
664
今でも結構多くの方がローマがカルタゴを侵略した後に塩を撒いたと書いているのを見ますが、実は古代に書かれた文献にそのような記述は無く、近代の人たちによる作り話だと考えられています。 twitter.com/NanJ_Sekaishi/…
666
667
668
669
昨晩もこの話題について書きましたが、「正確に訳した」と言う割に«Toutes ces sales gueules pour jouer à PES mon frère,,, t'as pas honte ?»をなぜToutes ces sales gueules pour jouer un PES bordel! Ils n’ont pas honte?と書いてるのでしょうか。訳す前にそもそもフランス語が聞けてないです。 twitter.com/TsujiHitonari/…
670
アルジェリアの「ジェリア」とナイジェリアの「ジェリア」は全然違います。
アルジェリアの語源はアラビア語al-Jazāʾir (الجزائر「島々」)で、alの部分は定冠詞(英語の"the"にあたるもの)です。ナイジェリアの語源は、国内を流れる「ニジェール川(Niger)」の名前です。
672
「ミニチュア」の「ミニ」は、ミニサイズという意味ではありません。
ミニチュアの語源は朱色の顔料である「鉛丹(ラテン語でminium)」で描かれた写本の挿絵等を指す言葉です。
これらは小さいものが多かったためにminute「微細な」と混同され、“縮小したようなもの”を意味するようになりました。
673
「モブキャラ」の「モブ」の部分は英語"mob"「大衆、暴徒」が元ですが、この語源はラテン語mobile vulgus「気まぐれな大衆」の"mobile"です。
なぜかvulgus「大衆」の方ではなく、mobile「気まぐれな」という形容詞の方が残りました。
674
ちなみにローズマリーの学名Salvia rosmarinusのうちの属名Salviaはラテン語salvus「健康な」が元で、この花が薬として使われていたことが分かります。
またこの属名Salviaは別の植物「サルビア」の語源であり、サルビアと同属の植物「セージ」の語源でもあります。