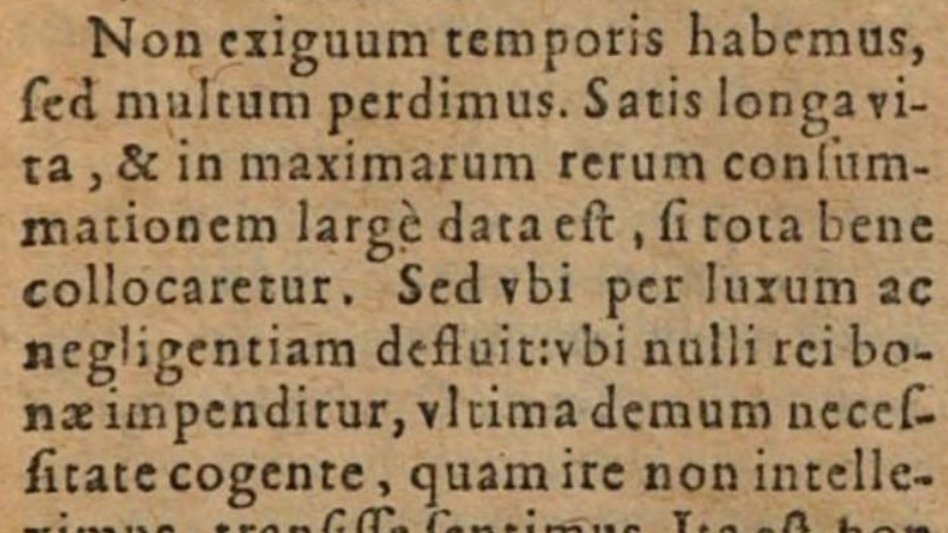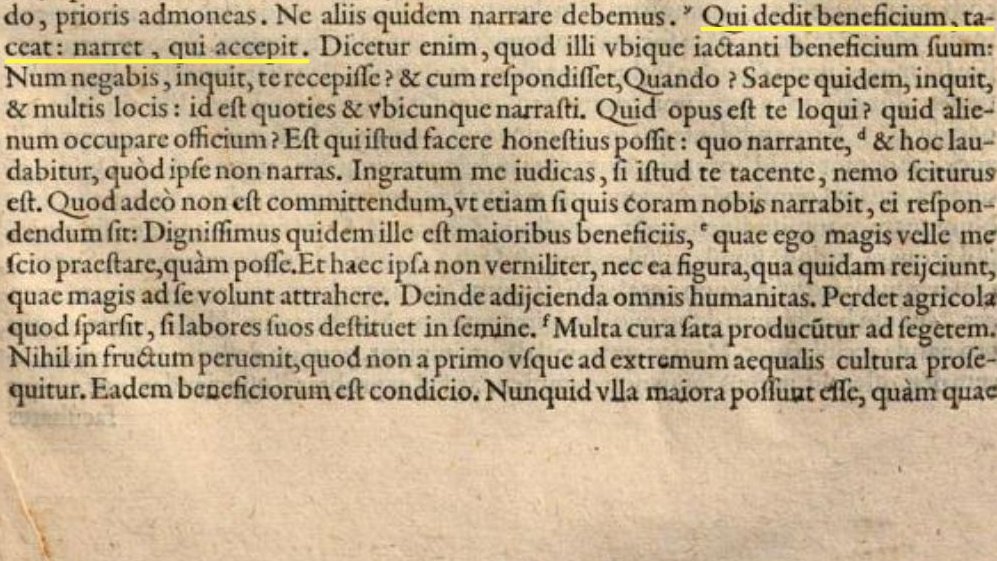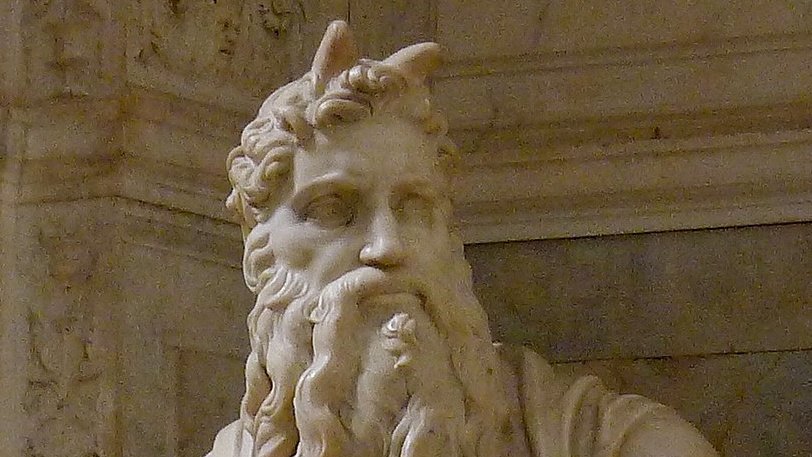452
古代ローマ人に"sine casu"と言われても怒らないでください。"sine casu"はラテン語で「堕落することなく」という意味です。
453
1906年2月10日、戦艦ドレッドノートが初めて進水しました。
名前の意味は「怖いもの知らず←[恐れ(dread)+ゼロ(nought)]」です。
これ以降のドレッドノートと同じ規模の戦艦を「弩[ド]級艦」と呼ぶようになり、これよりも高性能な戦艦を「超弩級艦」と呼ぶようになりました。「超ド級」の語源です。
454
455
英語圏で「履歴書」を"CV"と書くことがありますが、これはラテン語curriculum vitae(クッリクルム・ウィータエ)「人生を駆ける道」の略です。
456
457
「アヘン」という単語は結構道筋が長くて、
語源は同じ意味の古典ギリシャ語のὄπιον (ópion)で、そこから
→ラテン語"opium"
→英語"opium"
→中国語"阿片(ā piàn[あーぴえん])"
→日本語「アヘン」
という流れになってます。
458
これに「許してヒヤシンス」っていう引用リツイートがあって、アニメ『日常』が懐かしくなりました(当時私も見てました)。外国のオタクと話すときにも、「『日常』の神社の雨宿り回とトランプタワー回おもしろいよねー」っていうのが話題に上ります。
459
460
ウクライナ侵略が始まってから、SNS上で機械翻訳された文章を多く見るようになりました。
機械翻訳は大まかな意味をとるには便利になることが多いですが、しかしながら元の言葉が伝えたかった微妙なニュアンスが失われてしまうことも多々あり、それが結構重要なところだったりするので注意が必要です。
461
「すでに始めた人は、半分成し遂げたも同然である (Dimidium facti, qui coepit, habet)」ホラーティウス『書簡詩』第1巻より twitter.com/rilakkuma_gyr/…
462
463
「プラダを着た悪魔」という映画で、パーティーの場で上司に付き添う部下が、そこで会う人の名前や役職や近況を上司に耳打ちするシーンがありました。
古代ローマでも、主人に付き添って出会う人の名前や役職などを主人に耳打ちした「ノーメンクラートル(nomenclator)」という奴隷が存在していました。
464
中英語期に仏語から大量に借用されたからと言って「中英語が現代英語の起源で、古英語時代は無視できる」と言えるほど中英語期の仏語からの借用が現代英語に与える影響が突出してないのは一目瞭然です。
なので私は「英語は中英語期に頭の悪い庶民でも話せると言語して生まれた」とは思いません。(5/5)
465
こちらのAIが生成したラテン語、見ると(カタカナ表記も含めて)誤りが数々見られるので、AIだけに頼るのは危ういと思われます。正しい文法の呪文を書きたいときは、ラテン語に通じている専門の人間に依頼することをおすすめします。 twitter.com/fladdict/statu…
466
「フェチ」の元をたどると、ポルトガル語のfeitiço「呪物」に行きます。大昔、ポルトガルの航海者たちが行った先での未開民族によって崇拝されている物を指して用いた言葉です。
ポルトガル語feitiço自体の語源は、ラテン語facticius「作られた」です。
467
468
物凄く便利なツールがあります。英語の文章(サンプルはキング牧師のスピーチ)を入力するとこのような図が表示され、各々のバブルは文中の各単語を表します。
横軸はその単語が初めて文献に現れた年、縦軸は現代英語での使用頻度です。バブルの色は語源の言語を表しています。 …d-text-visualizer.oxfordlanguages.com
469
471
節電で思い出したんですが、英語で電気を指す"electricity"の語源は古典ギリシャ語のḗlektron「琥珀」で、これは琥珀をこすると静電気が発生するからです。
473
474
英語語源は動詞や名詞以外も面白いです。例えば"a cat"などの"a"の元は古英語"ān"なので、「aは母音で始まる語の前に"an"になる」のではなく「母音で始まる語の前以外で"n"がとれはじめて、今に至る」のです。
他にも、"as"はalsoが短くなったものだったり"or"はotherが短くなったものだったりします。
475