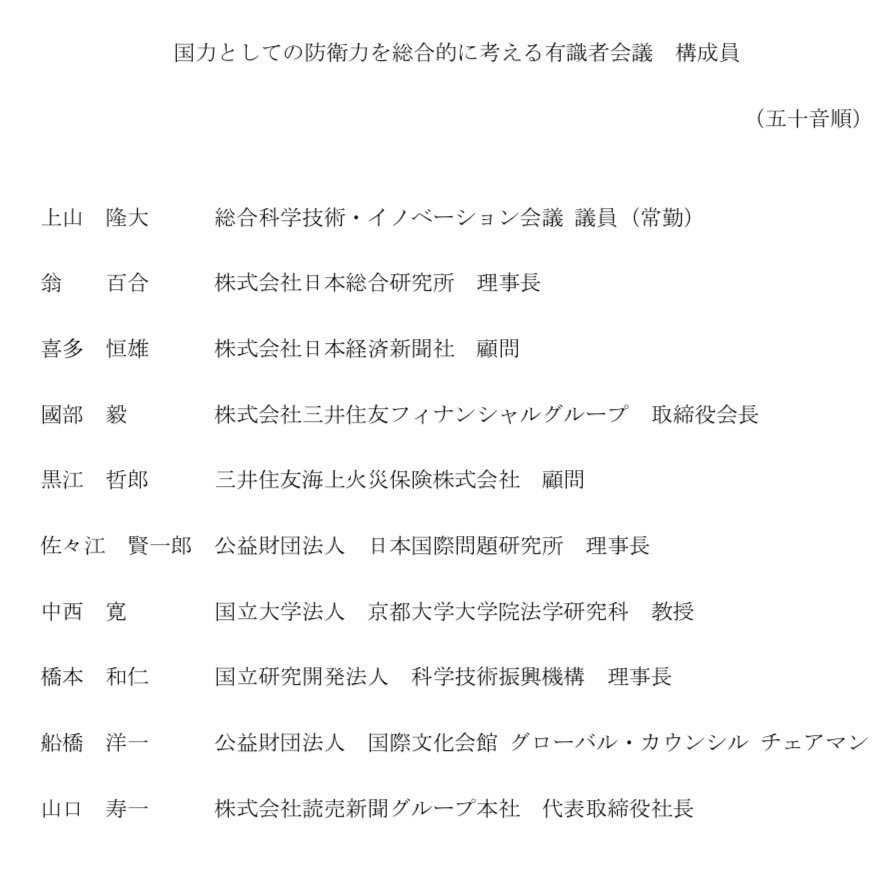1951
「途中からおかしいとは思っていたが、飲み代欲しさに断れなかった」。モラルの問題はあろう、だが我々は「衣食足りて礼節を知る」のであり、「貧すれば鈍する」のだ。スパイ法の制定と運用も大事だが、何より国民国家を内需から豊かにしなければ、本当の意味で国は守れない。 president.jp/articles/-/575…
1952
『企業を含む社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く負担していく新たな枠組み「支援金制度(仮称)」を構築し、その詳細は年末に結論を出す』
こんなの形を変えた消費税でしょう。言葉遊びをしている暇なんてあるのかな。少子化対策に本気だとはとても思えない。 yomiuri.co.jp/politics/20230…
1953
政治家の貨幣観・国家観のなさも去ることながら、マスメディアがこうして「少子化対策には国民負担増は避けて通れない」ことを既成事実化して報じることの有害さといったらない。こういう誤った報道が少子化を加速させる。だが彼らは責任も取らなくていい。我々が賢くなるしか jiji.com/jc/article?k=2…
1954
問題点はいくつもあるのだろうけれども、自衛隊の装備が貧弱である大きな理由の一つが「予算不足」というのは、自国通貨建国債を発行できる国家においては最も恥ずべきことだと思う。目先のカネをケチることによって長期的にはより大きなものを失うことになる。 toyokeizai.net/articles/-/681…
1955
「市民」の定義に「外国籍者も含む」と明記することで物議を醸している熊本市の条例改正。「審議会等の委員について市民の幅広い層から必要な人材を選任する」とあるが熊本市には行政区画から教科書選定まで153の審議会がありこれに例えば中国人が合法的に関われるということ city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/det…
1956
戦争とその後の賠償金という特殊な状況下に置かれた100年前のドイツから学ぶことがあるとすれば戦争回避のためにも今の日本は財政拡大をして体力をつける必要があるということだろ。“財政赤字が大きすぎたから“破綻した国などない。日経は本当に“経済新聞“を名乗る資格がない nikkei.com/article/DGXZQO…
1957
給食費の無償化も出産一時金の増額も結構だが、それらの費用がかからなくなるからといって「では子供を産もう」とはならない。これは少子化対策ではない。給食費無償化は4000億円台でできるとの試算もあり、結局「小粒なものからやる」姿勢が見え見え。まあ、ある意味異次元だ nikkei.com/article/DGXZQO…
1958
ESGもSDGsも所詮は金持ちの道楽にすぎない。理想論で飯は食えず、ウクライナ戦争勃発によるエネルギーコストの上昇はイデオロギー至上主義に陥りかけた欧州をすらリアリズムに引き戻した。むしろ今は、学校教育にすらSDGsを全面的に取り入れる日本の方が心配なくらいである。 nikkei.com/article/DGKKZO…
1959
「予算に限りがある以上、ある程度の選択と集中は必要だ。優先順位をつけて身の丈にあった研究開発を」
日本の学術研究が後退したのはまさに「選択と集中」をしてきたからだとまだわからんのか。しかも「身の丈にあった研究開発」とは?この発想の先に発展などない。ああ日経 nikkei.com/article/DGXZQO…
1960
子育て世帯への優遇策は当然ながら「既に結婚して子供もいる」家庭への支援策。やるなとは言わないが、9割近い男女が「いずれ結婚したい」と望みながらそれを叶えられず結果的に非婚・少子化が進んでいることが問題の中においてはこれは“少子化対策“ではない。なんだかなぁ。 nikkei.com/article/DGKKZO…
1961
『萩生田光一経済産業相は16日、全国の大手電力10社の社長らと会談し、今後の電力について「供給対策に万全を期してもらいたい」と要請した』
この「要請」と「検討」しかしない内閣はどうにかならんのか。万全な供給を期待するなら、それを妨げている仕組みをまず見直すべき nikkei.com/article/DGKKZO…
1962
日本は今年1.7%成長予想で、今年1月の3.3%から実に半減。欧米諸国と違い、コロナ前のGDP水準すら回復できない。「世界経済が減速しているから仕方がない」のではない、需給ギャップが少なくとも20兆円はマイナスなのに2.7兆円の補正予算しか組んでいないから。すべてが遅い。 nikkei.com/article/DGKKZO…
1963
人民解放軍と深い繋がりがあるとされるテンセントがすでに3カ所目のデータセンターを開設。中国によるわが国への侵略はもはや最終段階へ来ているのかもしれないな。「データは国家なり」と言われる時代に、国家情報法の縛りを受ける中国企業にデータ管理を任せるのは自殺行為 nikkei.com/article/DGXZQO…
1964
1965
「20万人を対象に年40万円」なら年間たった800億円の予算増でしかない。本当にしょぼい。なぜこんなにも、将来性あふれる若者への投資で「選択と集中」をする必要があるのだろう。理系や多子世代に絞る意味が何かあるの?「学ぶ自由」を政府が制限して良いのだろうか。 nikkei.com/article/DGXZQO…
1966
土居丈朗「対GDP比2%を実現するうえで、ほかの経費を減らしてでも防衛費を増やすという方針に、多くの国民が納得できるかが、問われよう」
緊縮財政派は本当に、わが国を崩壊させることに一生懸命だよな。この発想こそがまさに日本経済を、そして国家を根本から揺るがしてる toyokeizai.net/articles/-/584…
1967
「輸出額は最高でも、輸入額との差では貿易赤字が拡大している。農水省によると、21年は9兆170億円の赤字で10年前から18%悪化している」
「だからもっと輸出を!」というのは本末転倒なのだ。日本人の食い扶持の確保が最優先。日本はイメージとは異なり農業の保護が手薄すぎ nikkei.com/article/DGKKZO…
1968
「首相は歳出改革と増税によって5年かけて財源を増やす方策の年内決定を描く。年末までにどの税目をいつからどう増税するかを明示できるか与党税調で詰める」
本来の目的であるはずの「国防」を言い訳に不要な「増税」自体を目的化してしまっているから支持率が下がるのだ。 nikkei.com/article/DGKKZO…
1969
「現在40代後半の大卒男性の平均実質年収は、10年上の世代が40代後半だったときよりも約150万円少ない。さらに世代が若返れば実質年収はもっと低くなる傾向がある」
こんなことは普通あってはならない。この間、消費税や社会保険料も上がったので可処分所得の減少はもっと大きい。さっさと是正せよ。
1970
「財政は国防の根幹である。防衛費を増額しても財政余力が狭まれば、有事への対処には不安が残る。本来なら増額という歳出と国民の負担を伴う歳入の議論はセット」
いい加減にしろ。国防の根幹は強い経済だ、国民負担増で経済の足腰を崩して防衛費を増やしても意味はない。 nikkei.com/article/DGXZQO…
1971
藤谷武史『コロナ財政の経験から「必要な財政出動に際して公的債務の増大を懸念する必要はない」という誤った教訓を引き出すべきではない』
もう笑っちゃう、日経のこの連日の財政論。もはや財務省広報紙であることを隠さなくなったよな。国民生活より優先される財政などない nikkei.com/article/DGKKZO…
1972
「国産の生乳は足りないとの認識を持っている」のに、コロナ禍という特殊要因による需要減への対応として「生乳の生産を抑制した場合に酪農家を支援」する政策をなぜ是とするのか理解に苦しむ。減反と同じ過ちではないのか。国が買い取れば良いだけでは。思考が短絡的すぎでは nikkei.com/article/DGXZQO…
1973
なんかもういろいろひどくないか?「所得制限撤廃してもいいけど財源は自分達で確保してね」って。こういうことを平気で言うくせに一方で地方自治体が少しでも財政に余裕を持たせれば財務省が交付金を削ろうと手ぐすね引いて待つ。地方創生もクソもないわ。目を覚ましてほしい yomiuri.co.jp/politics/20211…
1974
「前原氏は財政再建には増税が不可欠ではないかとし、消費増税が国民的に不人気であるのを踏まえ、増税するならどのような種類の増税が望ましいか質問した」
鈴木財務相の「今のところ」という当然以前に、前原氏の質問が論外すぎる。なぜ増税ありきなんだよ?日本を潰す気か reut.rs/3g321J4
1975
中野剛志「日本は将来の供給を増やすために今の需要を増やす政策ができるし、それでデフレ脱却できるので一石二鳥。逆に金融引き締めや緊縮財政をやると日本は発展途上国になる。今は帰路に立っている」
責任ある積極財政を推進する議連の講演が公開されている。濃い1時間。
youtu.be/UBvqmoWTuF8