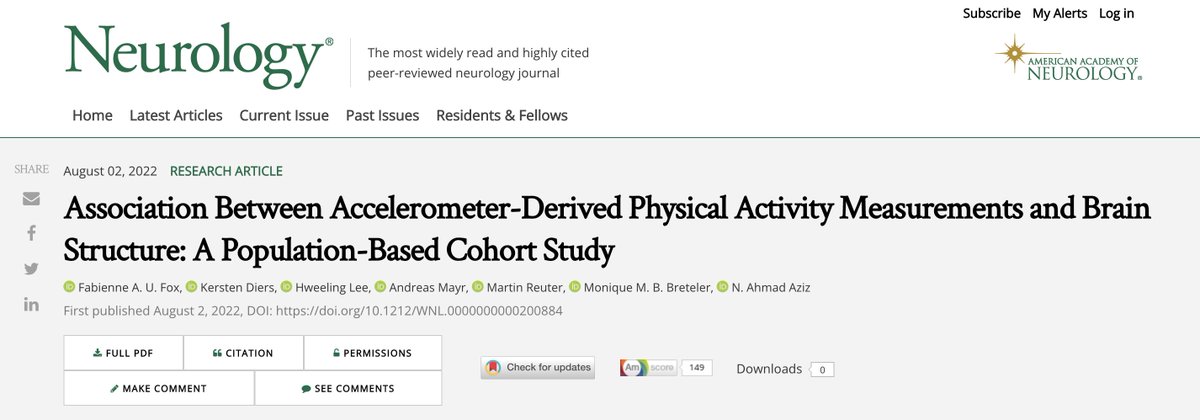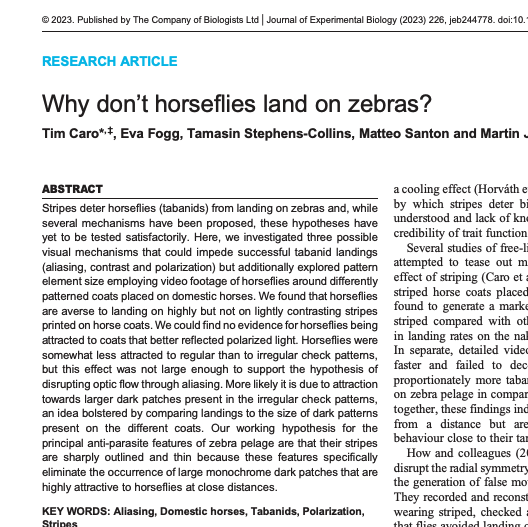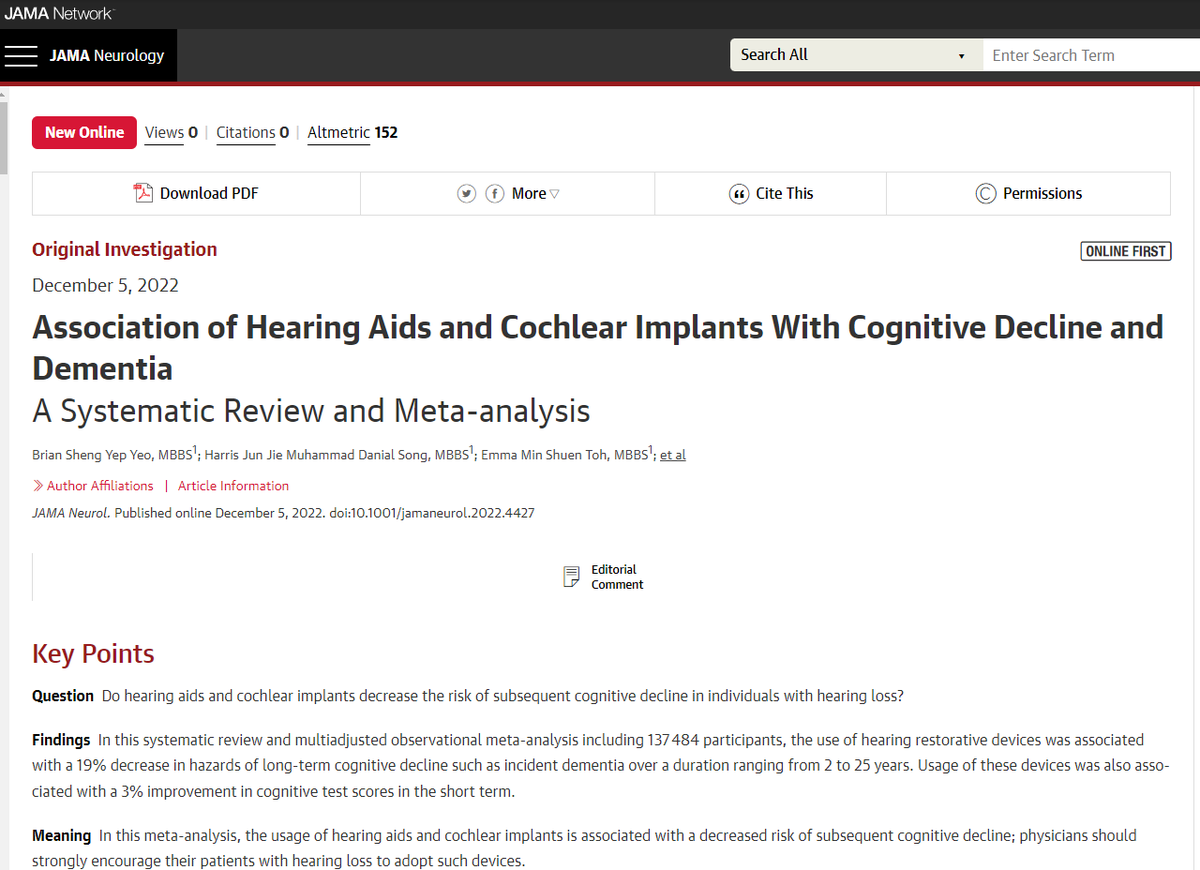951
超高速で流れるプール。
これはすごいトレーニングになりそうだ…。
twitter.com/i/status/15583…
952
LEGOで作られたジャイロスコープ。
倒れそうで倒れない、とてもおもしろい。
953
拡張現実によって体感できるゴッホの世界
954
955
956
右の動画では「観てはいるけど脳はそれほど緊張していない」状態とも言える。
ADHDでは人によって指を動かしたり動きながらのほうが集中力が増すそうで、集中のプロセスは個人によって異なるのだ。
ADHD Kids Can Be Still – If They’re Not Straining Their Brains ucf.edu/news/adhd-kids…
957
廃材から生み出されるアート
958
手術の前にスーパーヒーローになっていく子供たち
959
消せるタトゥー「Prinker」
さまざまなデザインのタトゥーを簡単にプリントでき、2〜3日程度の耐久性があるけれど、水と石鹸さえあれば簡単に洗い落とすことも可能なようだ。
960
人間がギリギリ乗れるミニマム自転車ができるまで
961
草を編みこんで巣をつくる鳥
まるで裁縫をしているようで、とても器用だ
962
樽がつくられるまで。
シンプルだけど素晴らしい職人技。
963
メンタルクリニックを初めて受診するときはなるべく早めに予約したほうが良い。メンタルクリニックでは初診にかかるのに2〜3ヶ月は待たされることもある。「いま、ツラいからすぐに受診したい」がなかなかできないのが精神科や心療内科なので、受診を検討したら早めに予約をしておこう。
964
ローリングブリッジ。
ロンドンにある可動橋で、2004年に完成した歩行者専用の12mほどの橋で、使用しないときにはくるくると巻き取ってしまうことで船の運航も可能になるというユニークな橋。
965
966
ハチは仲間がプレイするサッカーを覚えることができるという研究。
サッカーでゴールを決めたハチには甘いご褒美をあげるようにすると、それを目撃したハチも同じように昆虫版サッカーをプレイし始めたことが示された。
ハチには高度な学習機能が備わっているようだ。(Nature 2017)
967
968
969
高齢者や筋力の低下している人の移動を支援するためのカート
970
971
特殊なスーツと刀で高圧電流を受け止める動画
高電圧電流を身体に通過させるのではなく、身体の周りのスーツに流すことでスーツの装着者を守ることができる。
972
お酢でたまごの殻が消える実験
お酢に生たまごを漬けておくことでゼリーのような”スケルトンたまご”ができる。
973
ドリルのような形状のカリフォルニアネコザメの卵。
潮の流れが強く、敵の多いカリフォルニア沿岸の環境に耐え抜くため、卵がドリルのように岩に食い込むような形になっているみたい。
自然ってすごい。
974
”先延ばし癖”が治らない、と思っている人の中には怠惰じゃなくて「恐怖からの無意識の回避」が強すぎる場合がある。人間は怖いと感じる対象を回避するように作られていて、”先延ばし癖”だと思っていたら恐怖からの回避行動だった、といったケースだ。怠惰と恐怖は克服法も違うから注意が必要だ。
975
古代ギリシャの驚きのテクノロジー
”ヘロンの噴水”
”防犯装置”
”自動販売機”