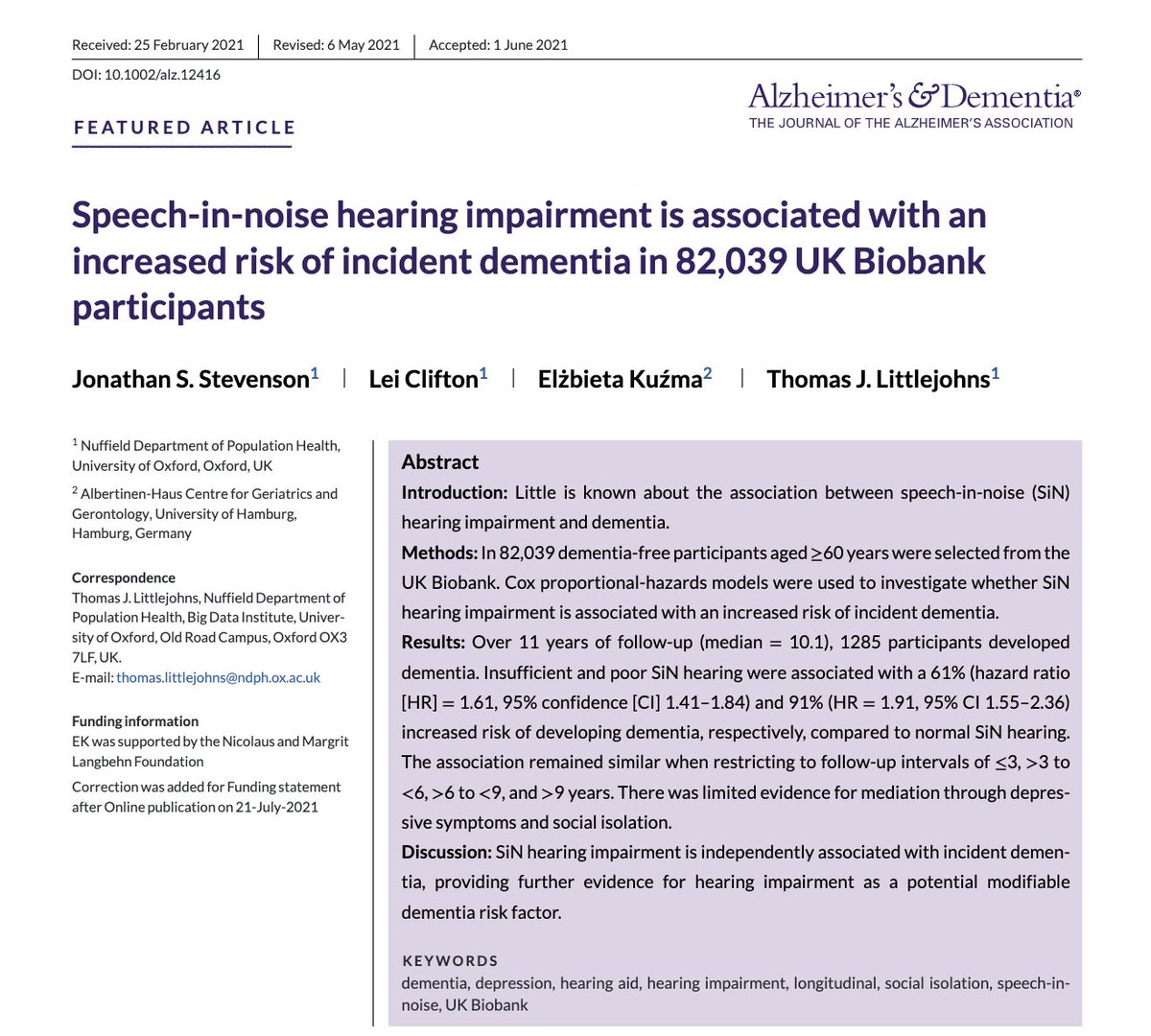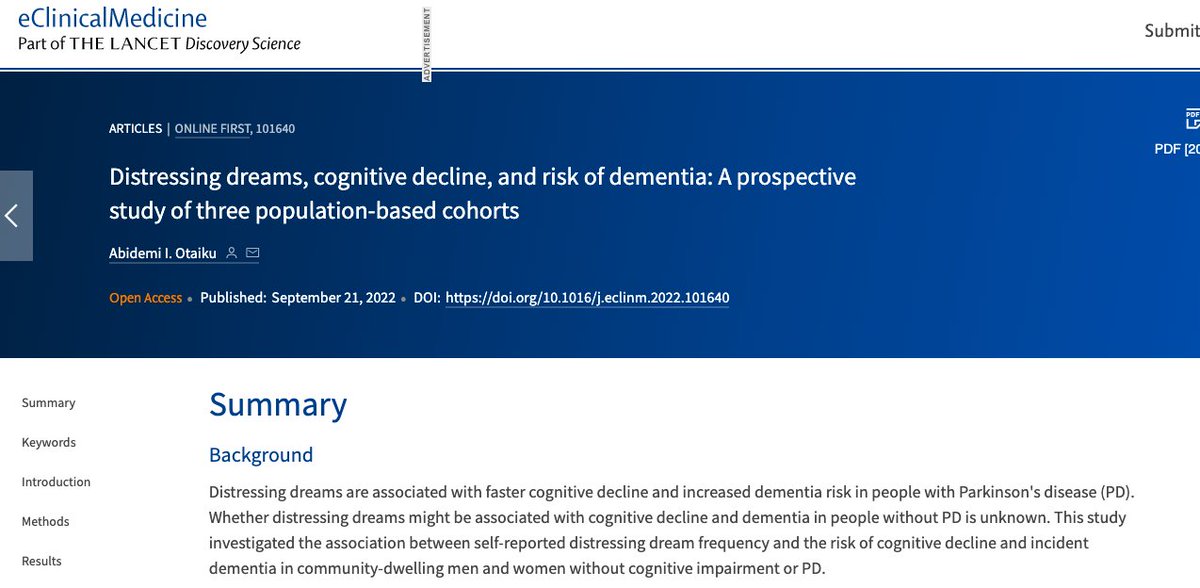976
977
人間がギリギリ乗れるミニマム自転車ができるまで
978
ロボット犬と出会った動物園の動物たち。
みんな興味津々だ。
979
980
ChatGPTが解いた宿題を3Dプリンターが書いてくれている動画。
いずれ宿題はなくなるかもしれない…。
981
CPR in Action | A 3D look inside the body youtu.be/DUaxt8OlT3o
982
MITがフジツボからインスピレーションをうけて開発した傷口を十数秒で接着して出血を止める接着剤
983
世界的なパンデミックの影響もあり、スクリーンを見ている時間が長い子供が増えている。そのため長時間のスクリーンタイムが子供の知性に与える影響について調査したところ、ソーシャルメディアや動画視聴では影響はほぼないけれど、ゲームを長時間プレイしていた子供では知能が上昇したと報じられた。
984
ガソリンを給油してくれるロボットアーム。
いろいろな車の給油口にも対応してくれそうだ。
985
3Dプリンターによってプリントされる義歯。
個人にぴったり合う義歯を安価に制作できるため注目されている。
986
987
精神疾患のイヤなところが「でも、身体は元気なんでしょ?」と思われたりすること。全身倦怠感や不眠、食欲の低下にめまいなど、精神疾患によって身体症状がキツすぎて動けない、なんてこともある。身体もぜんぜん元気なんかじゃない。
988
989
ベトナムの学校で教える要救助者の運びかた。
ためになる。
990
巨大な小惑星エロスが35年ぶりに地球に大接近…将来は衝突する可能性も news.livedoor.com/article/detail…
991
東京大学の研究チームにより制作された「自在肢」
992
人工甘味料の一つである「アスパルテーム」は不安を増強させる恐れがあると示唆するマウスの実験。
実験では、アスパルテームを投与されたマウスでは不安が増強されたようだ。人間にどれほど影響があるのかはまだわからないが、飲み過ぎは良くないみたいだ。
(PNAS)
doi.org/10.1073/pnas.2…
993
プレゼントを包んでくれるロボットアーム。
メリークリスマス🎄
994
メントスコーラ VS 油
995
アムステルダムに開設された1万台以上も駐車できる地下駐輪場。
オランダのアムステルダムでは自転車の利用者が多く、自転車を利用しやすい環境がさらに整ったようだ。
996
997
人間は、大きなストレスを受け続けると、脳の構造が変わってしまう。
いじめやパワハラなどの精神的な暴力は、脳に物理的な傷を与えて、後遺症を残すようなこともある。
にもかかわらず、脳の傷は人生に与える影響のわりに、軽視されやすいと感じる。
998
「アップル・ハンター」として、珍しいリンゴの話を聞けば遠方でも飛んでいき、変わったリンゴ、偉人が食べたリンゴなど、たくさんのリンゴを保護して救ってきた彼の庭は、さながら「リンゴ博物館」と呼べるような代物になっているそうだ。
Tom Brown (apple hunter)
en.wikipedia.org/wiki/Tom_Brown…
999
1000