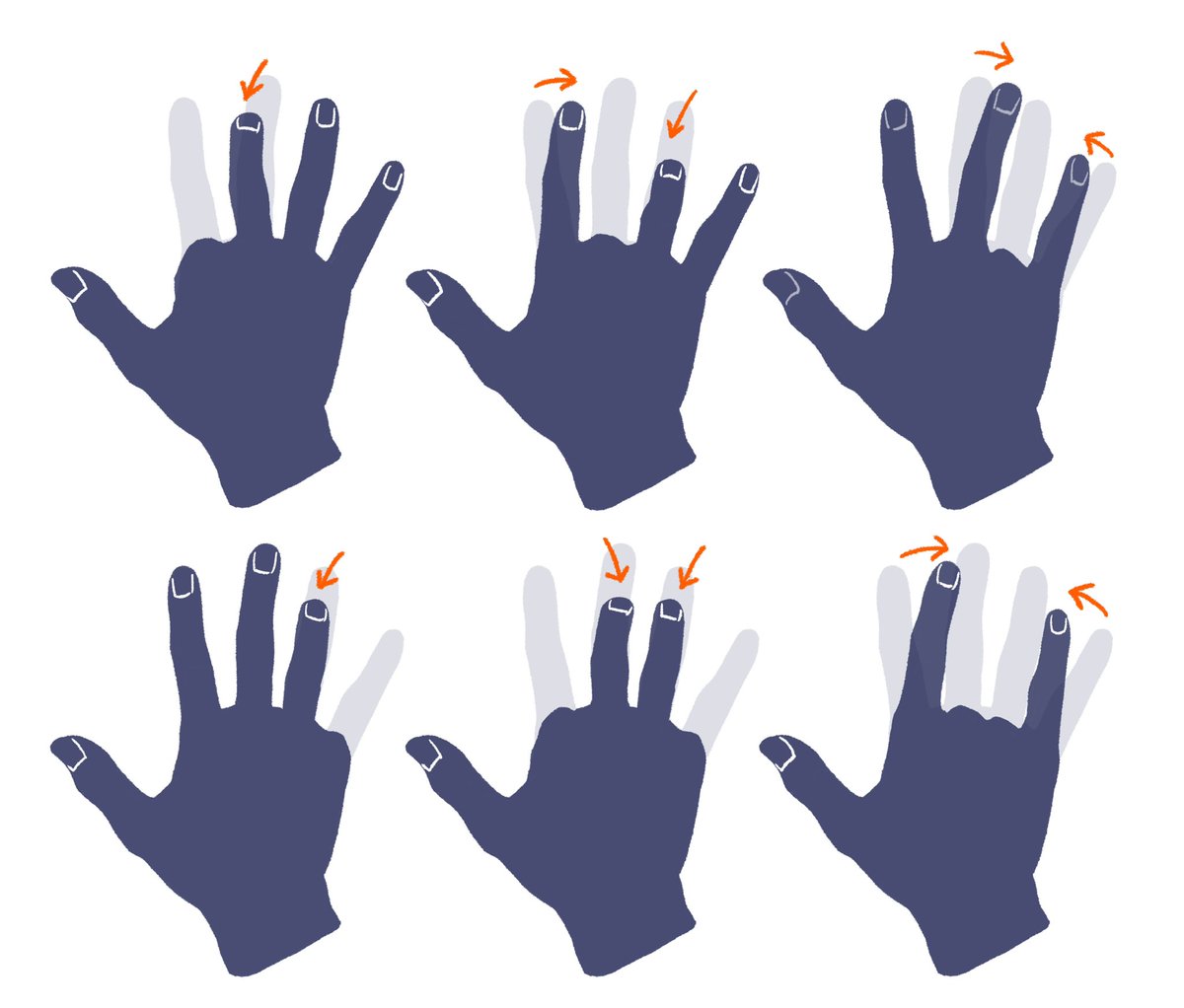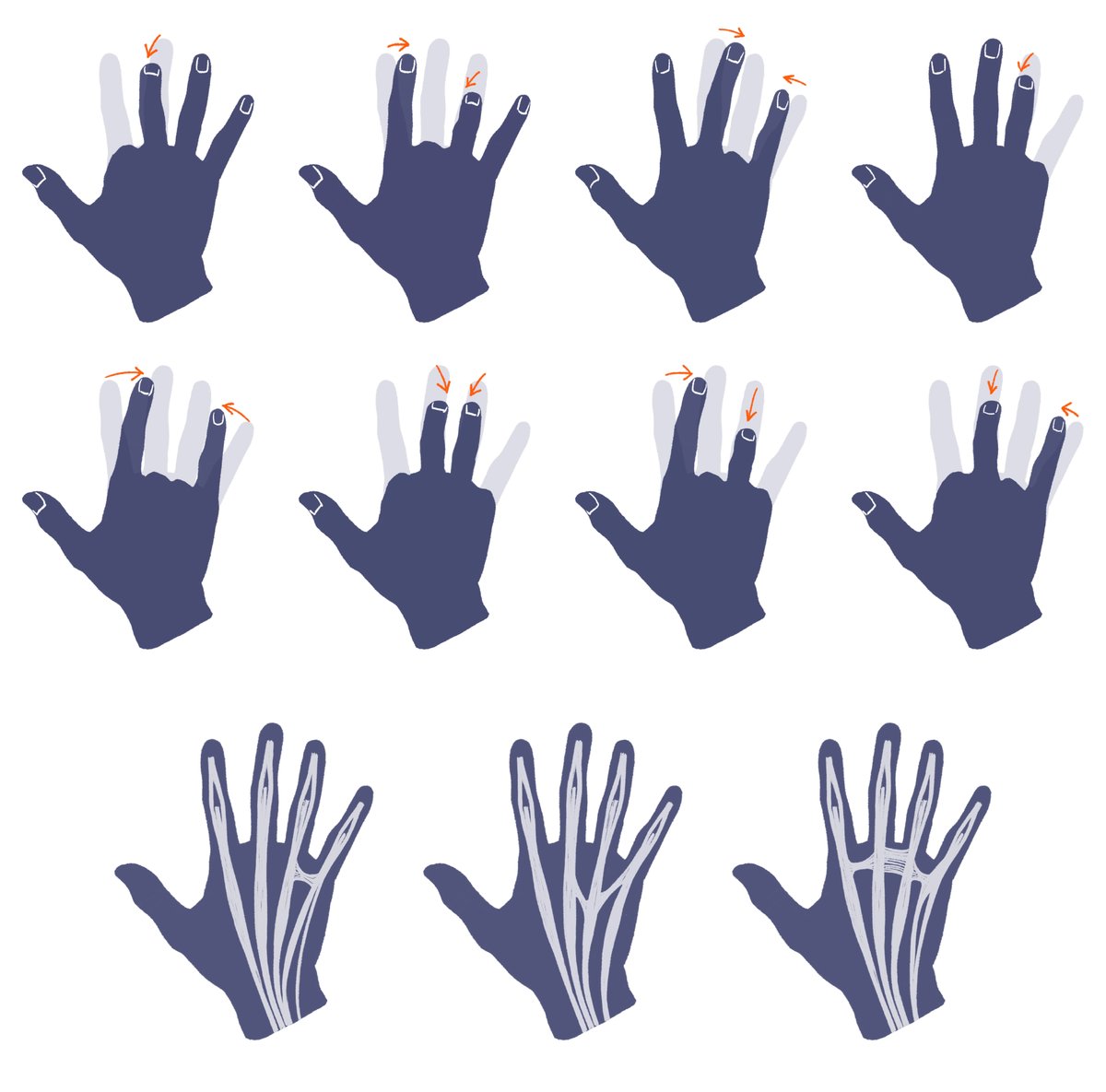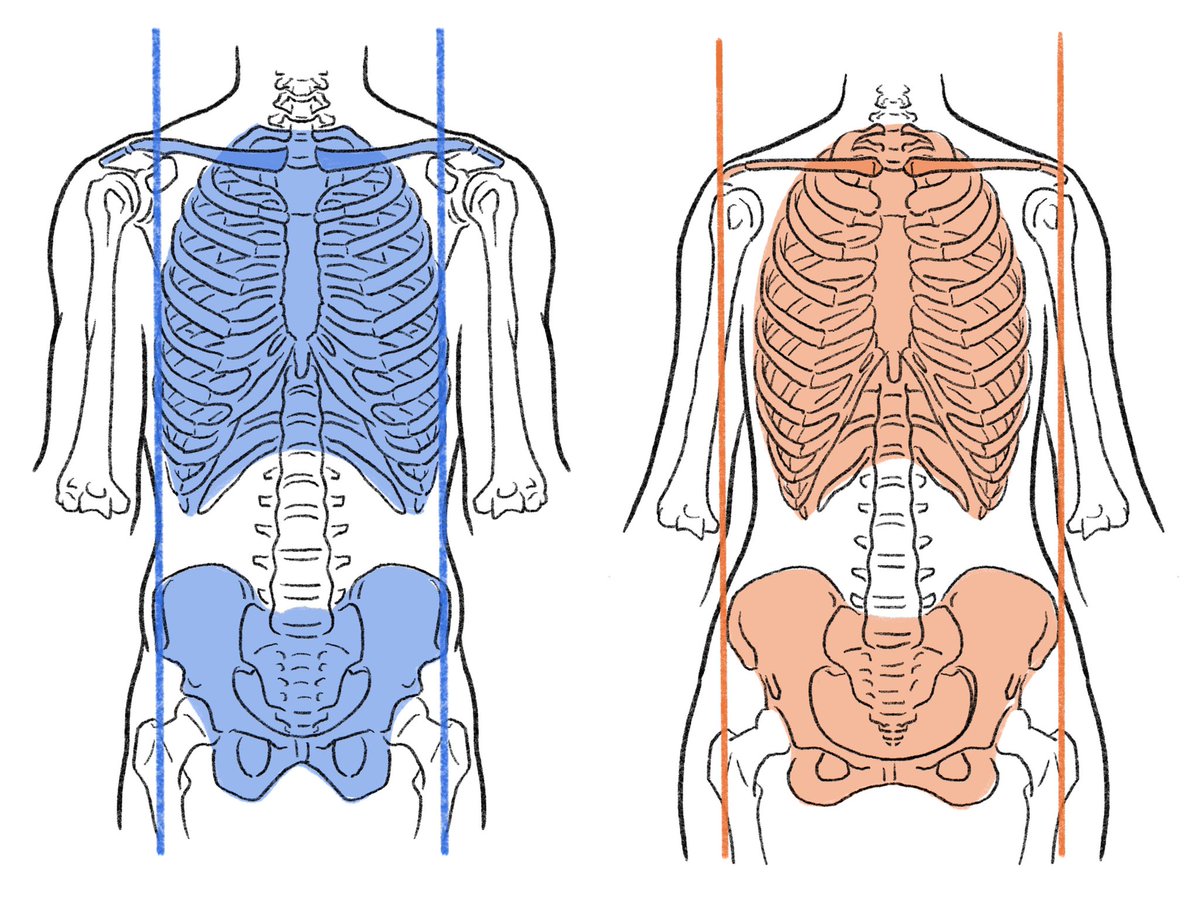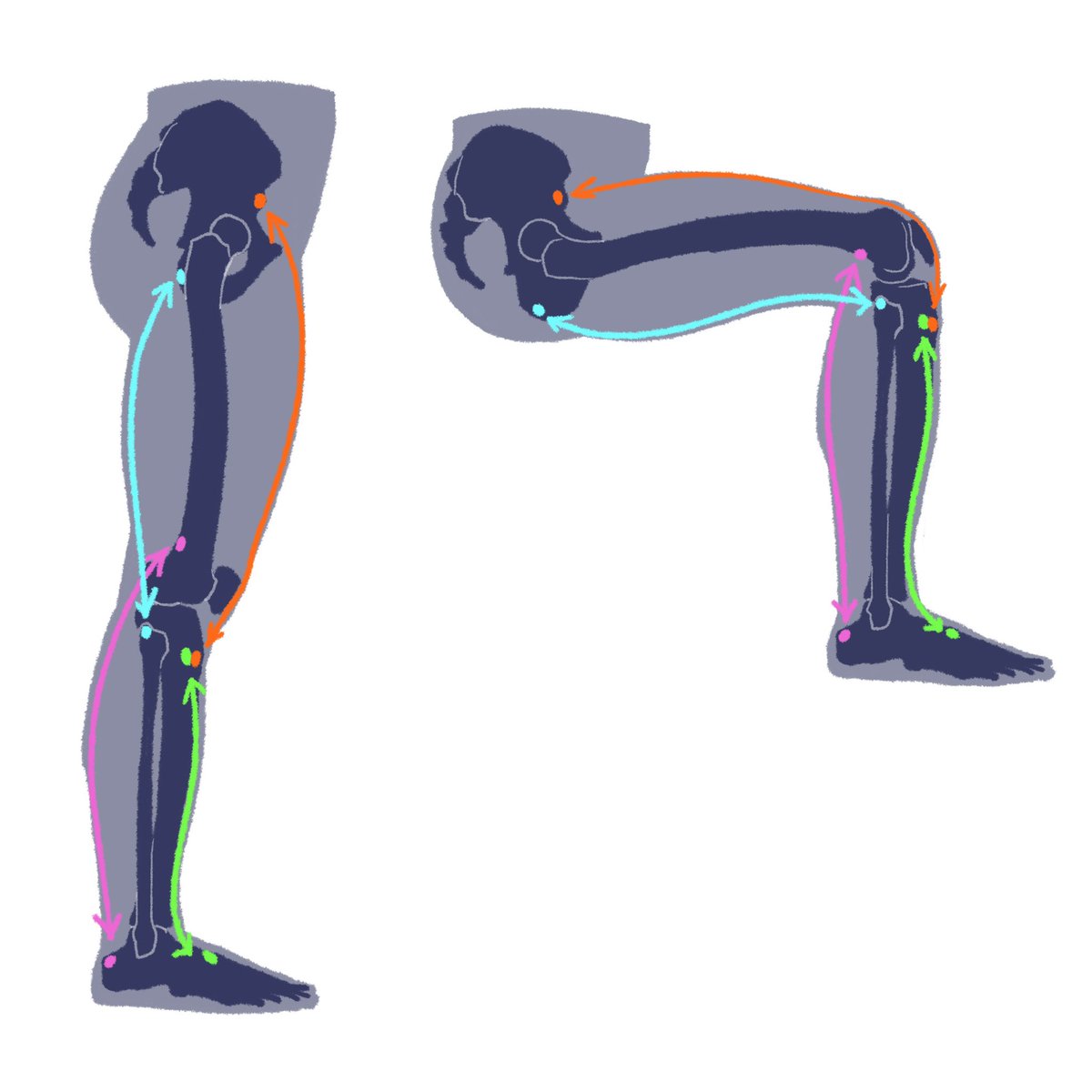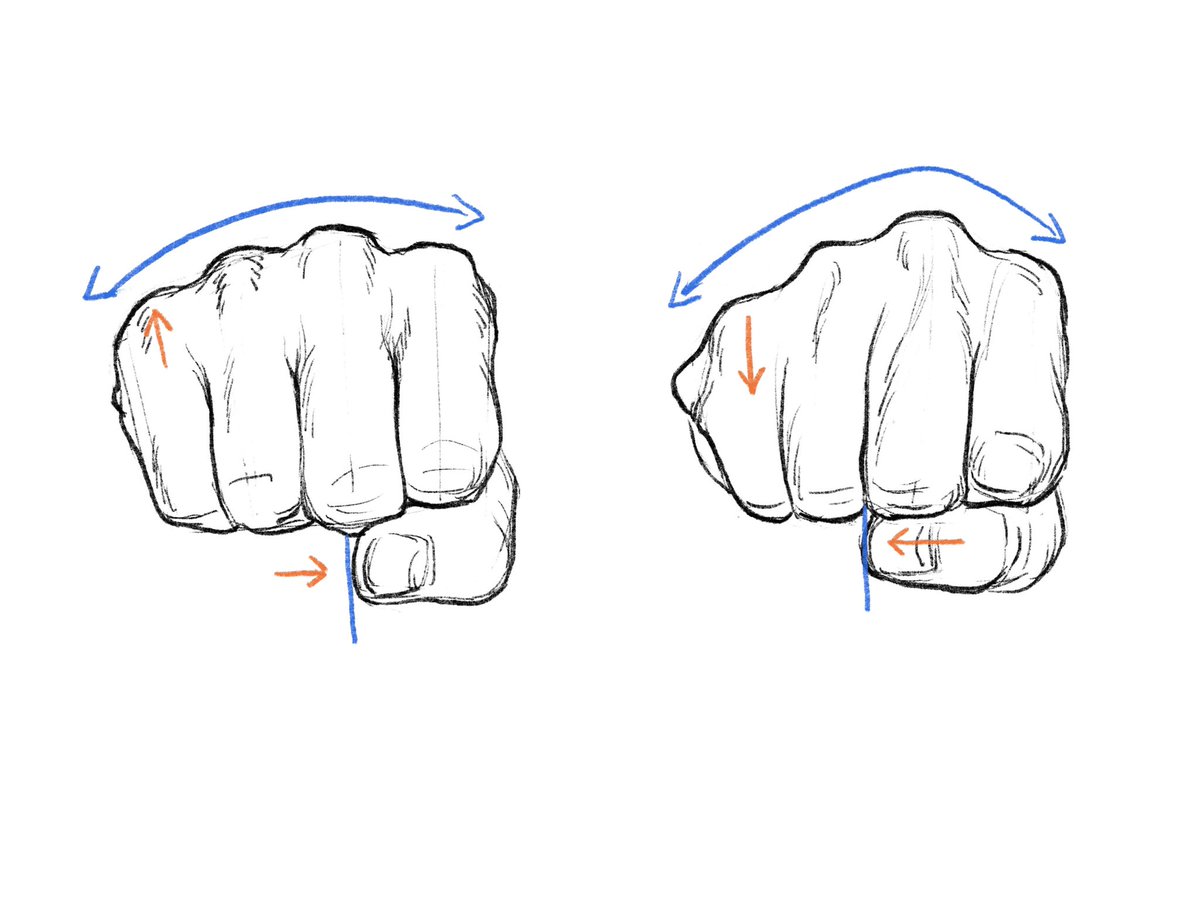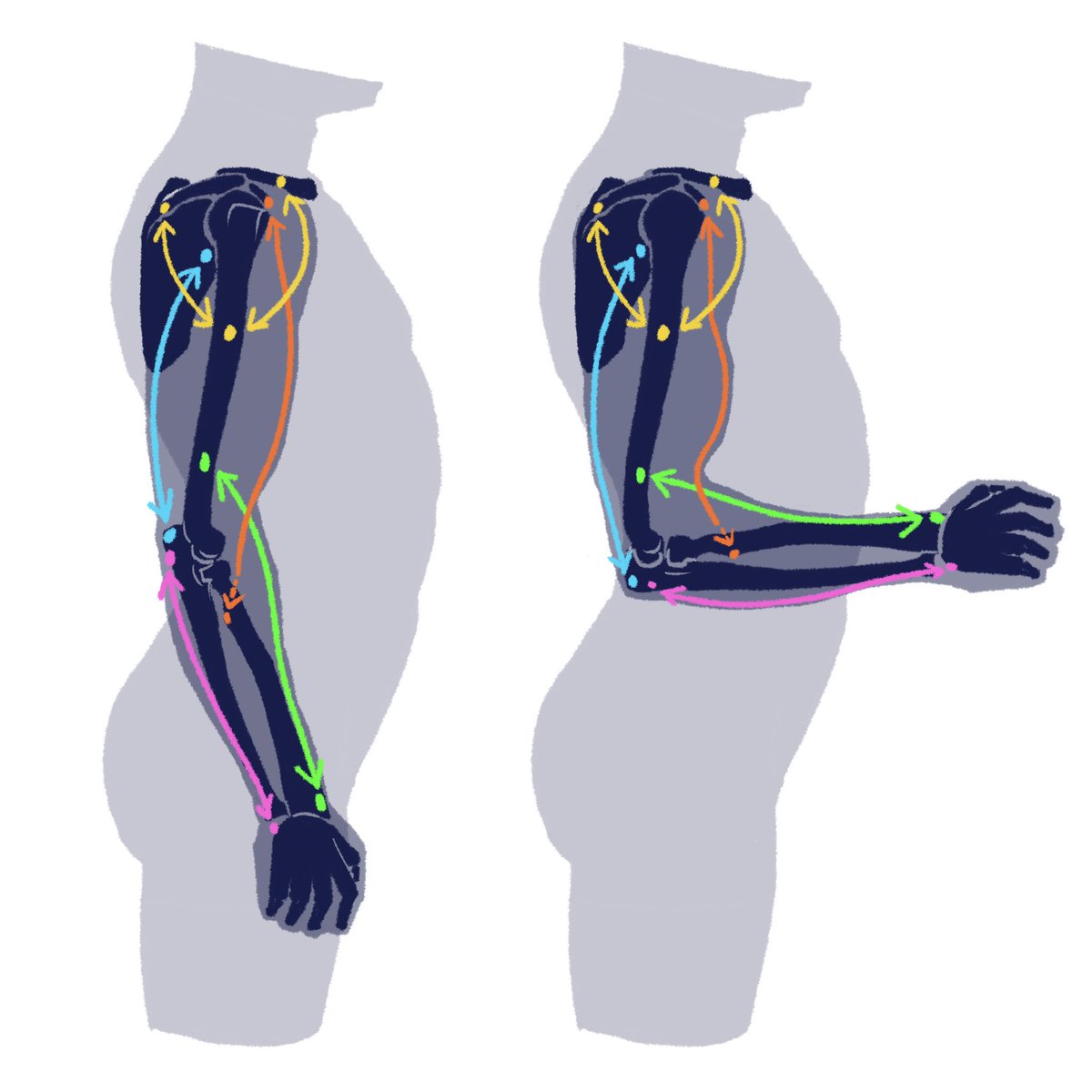3
5
私の授業の受講者さんでしょうか。のび太君の場合は、眼鏡を外して目を凝らしたときの起伏かと思ってました(藤子先生の研究してないので、ひょっとこかも知れませんが)。 twitter.com/fuwamochi0419/…
7
以前、学生さんから石膏像の描き方がわからないと質問があったので、iPadでデモンストレーション。手入れしたいと思いつつ時期が開いてしまったので今回はこの辺で。
15
18