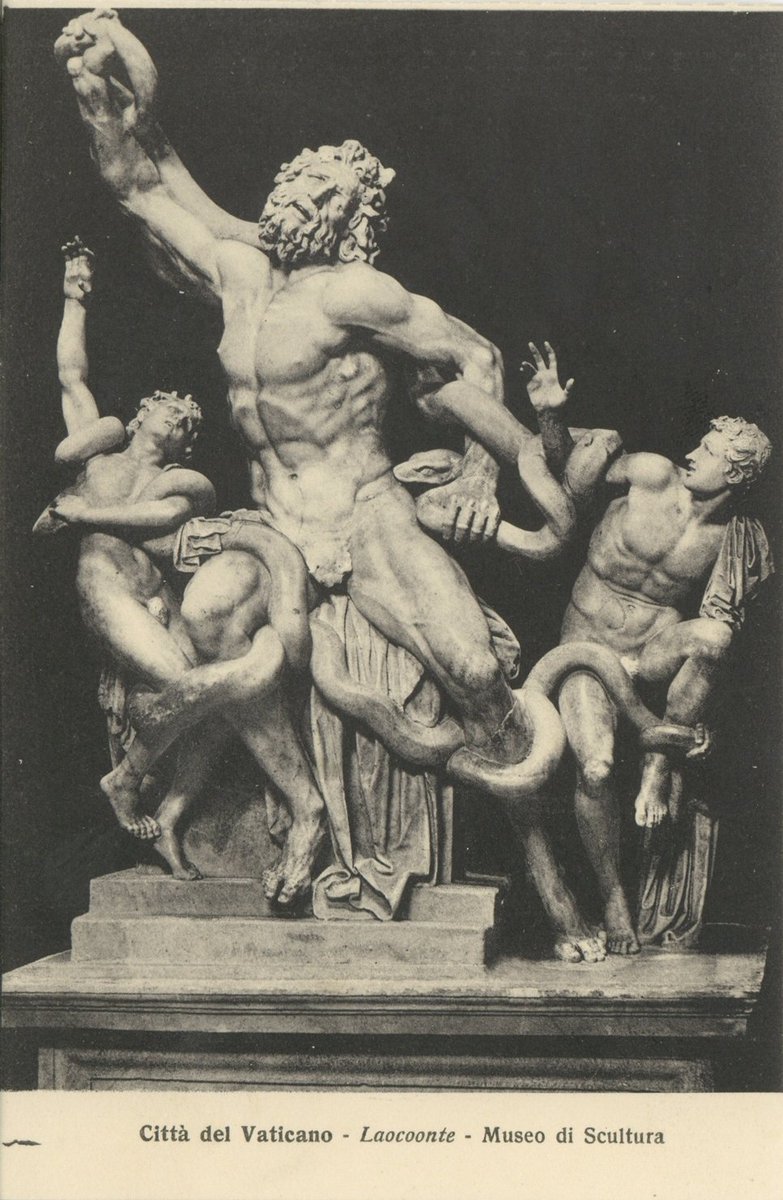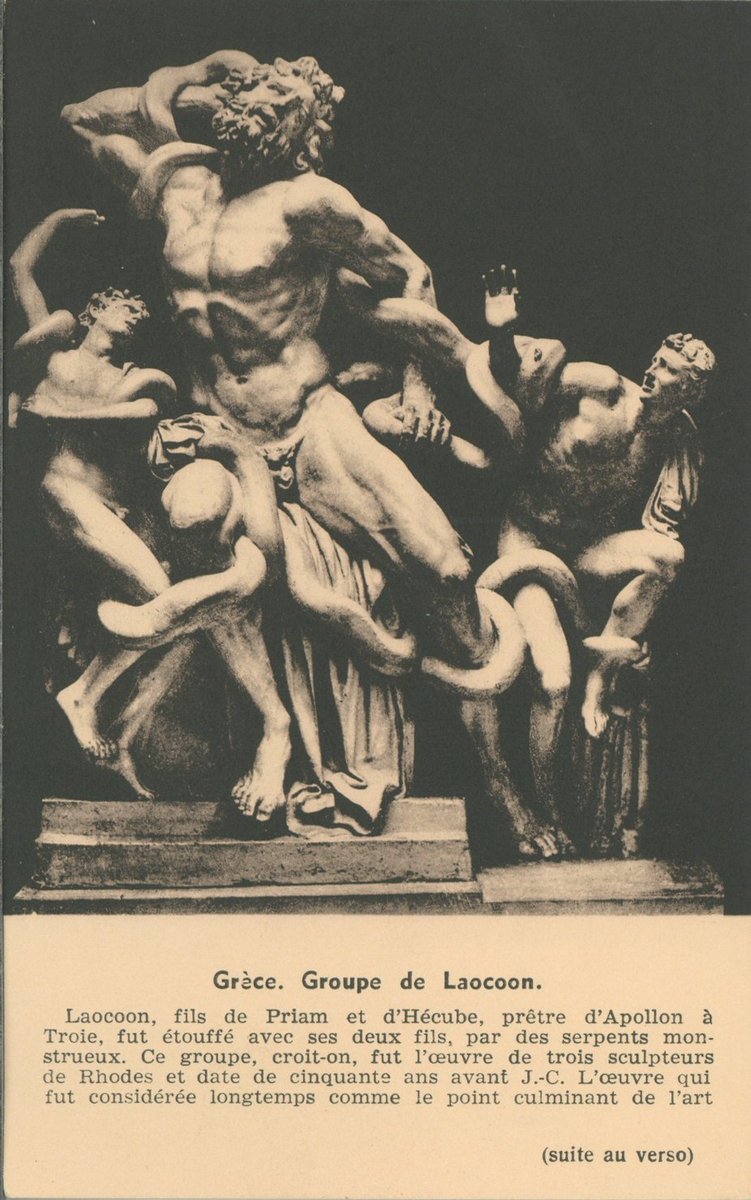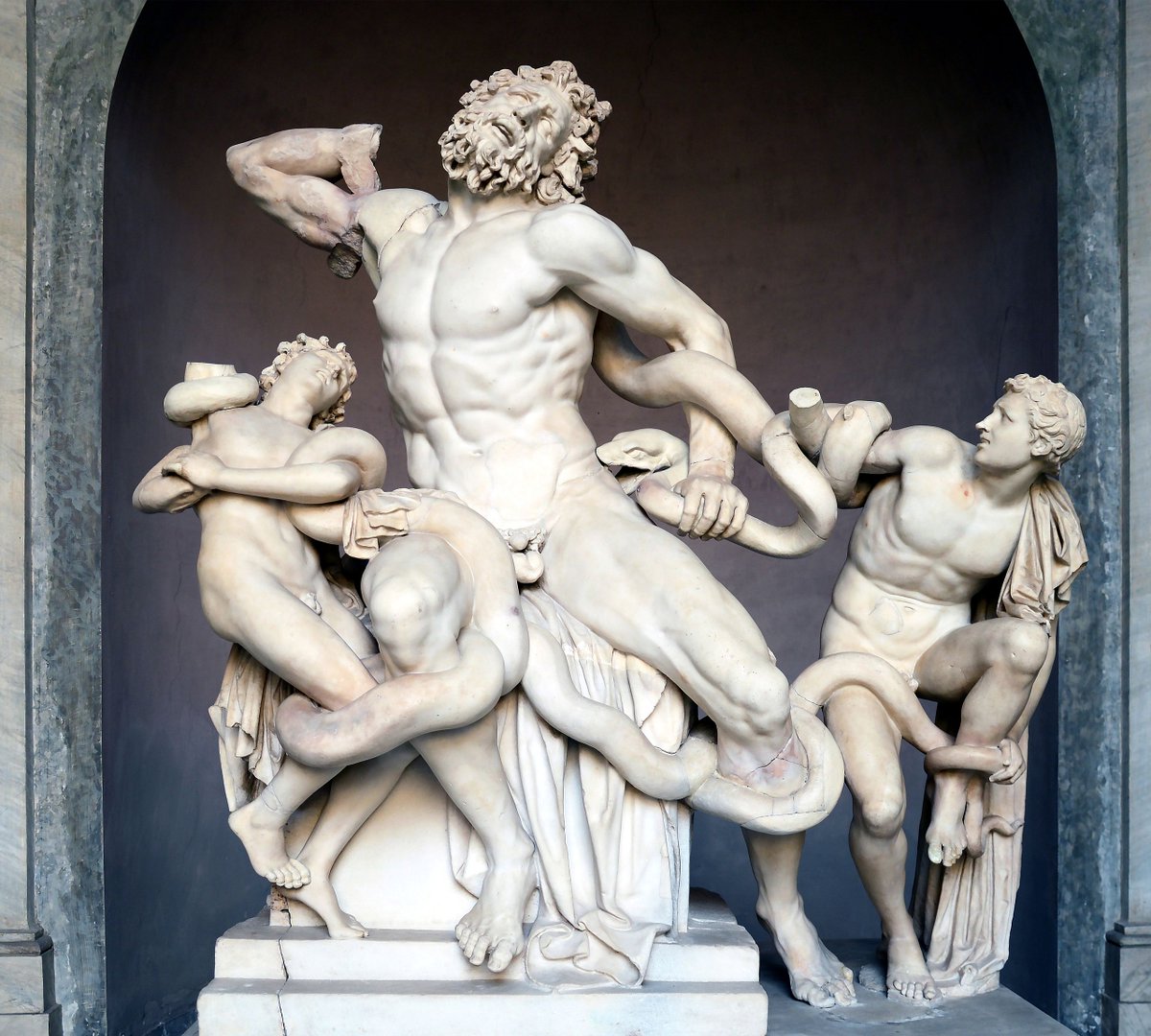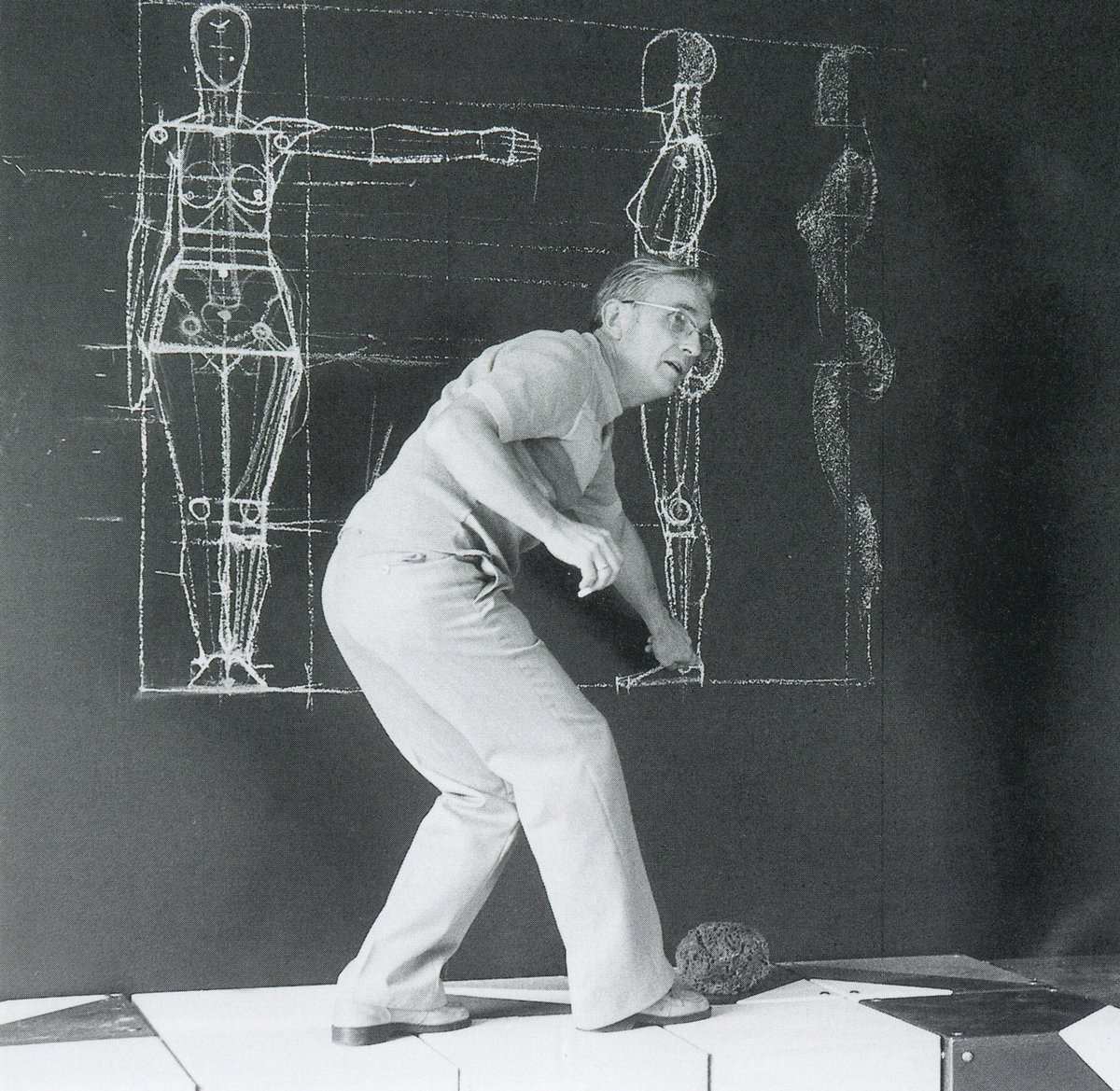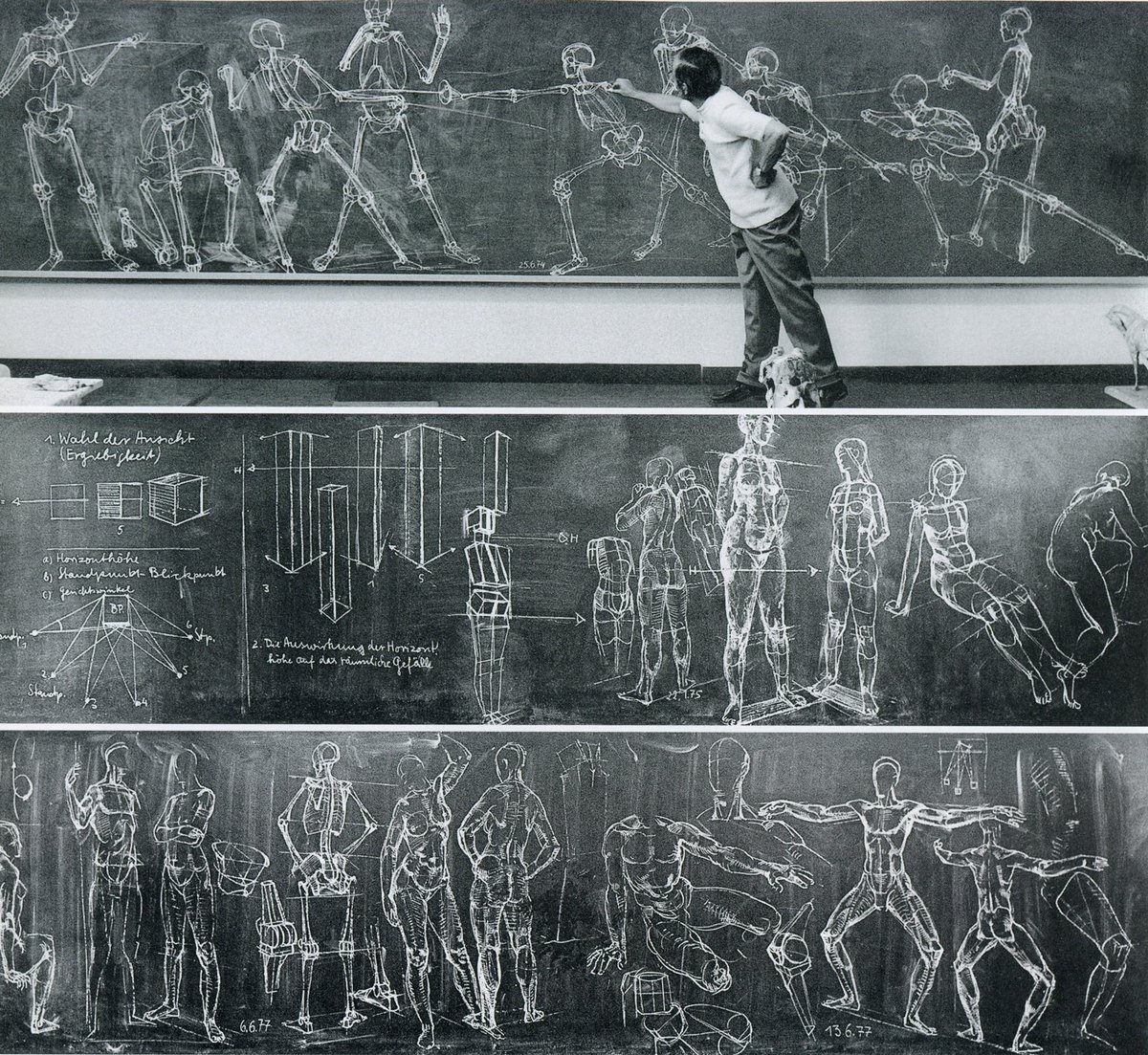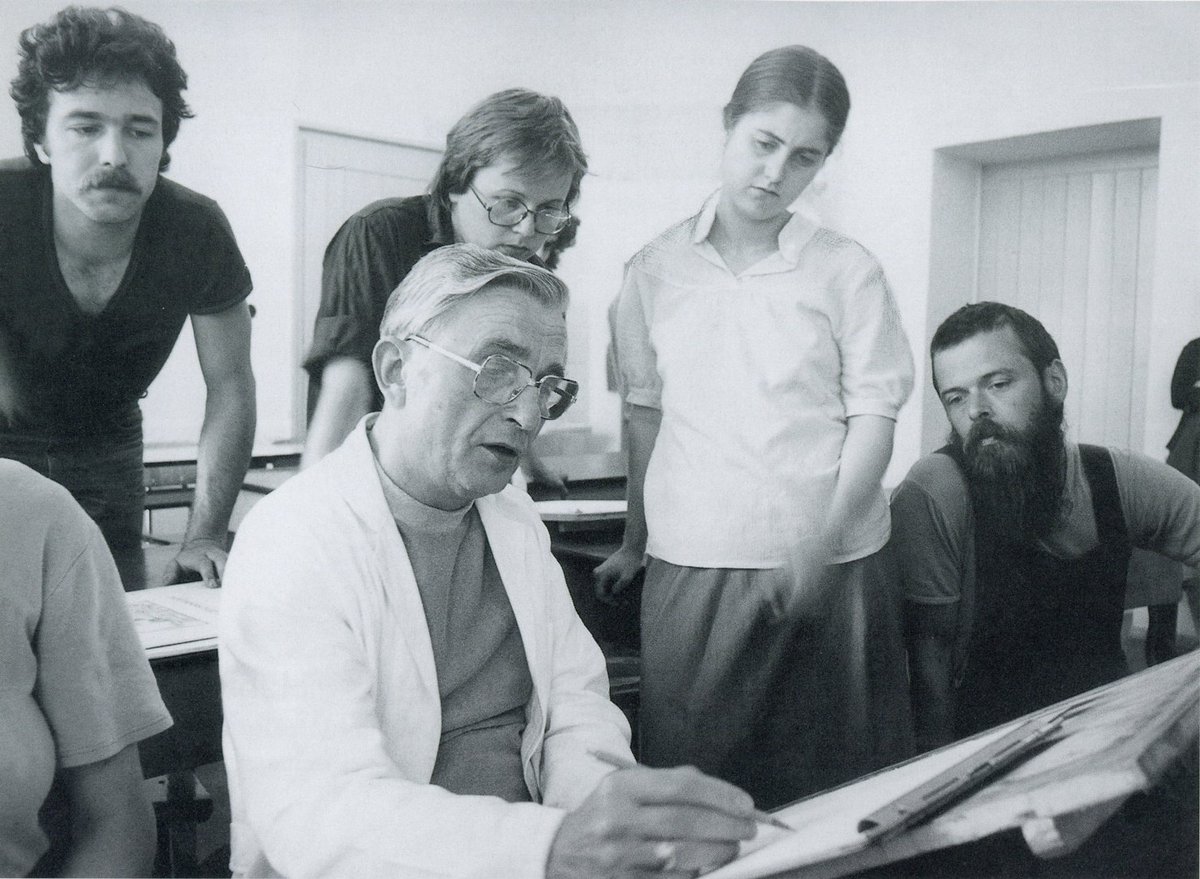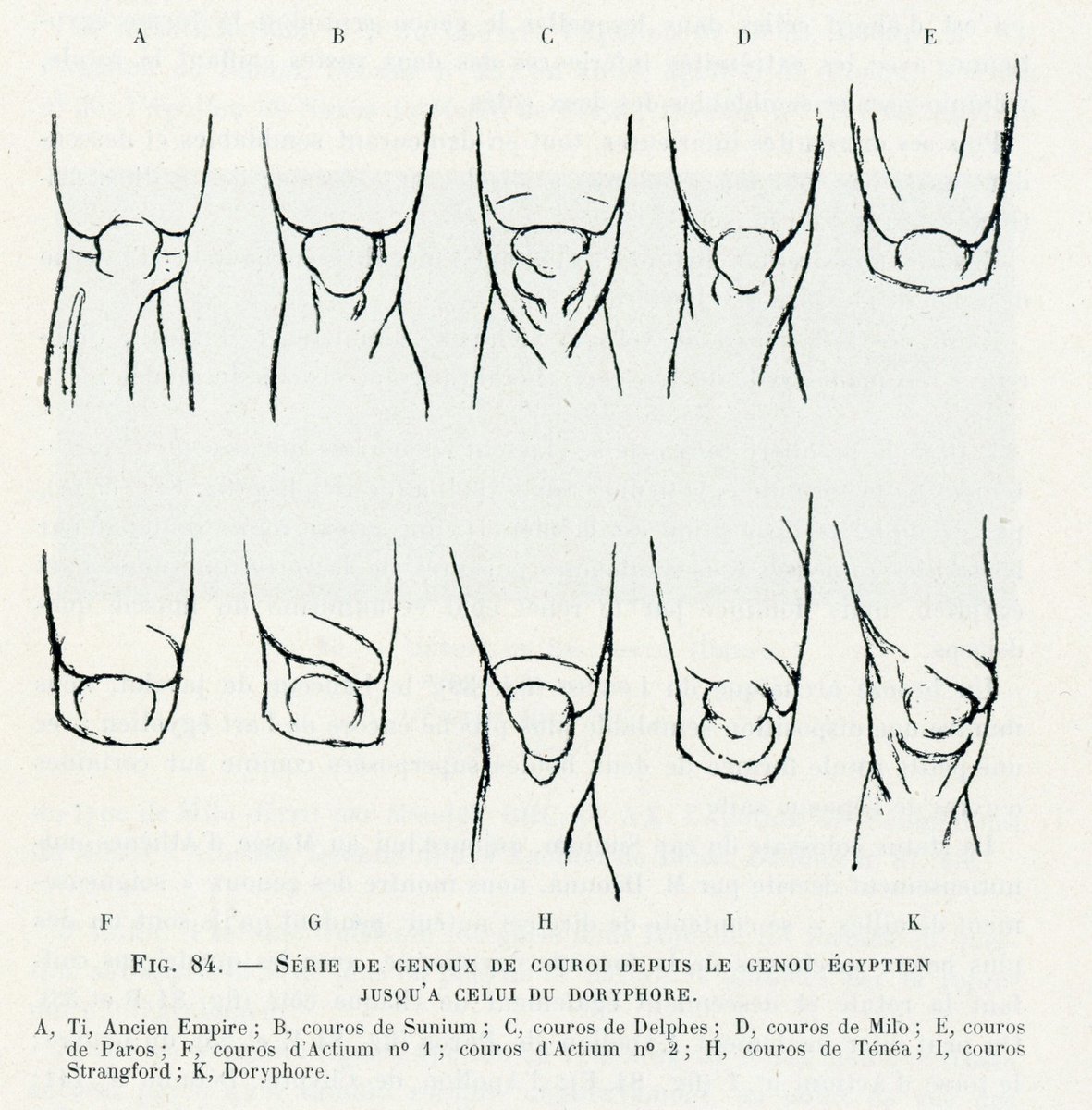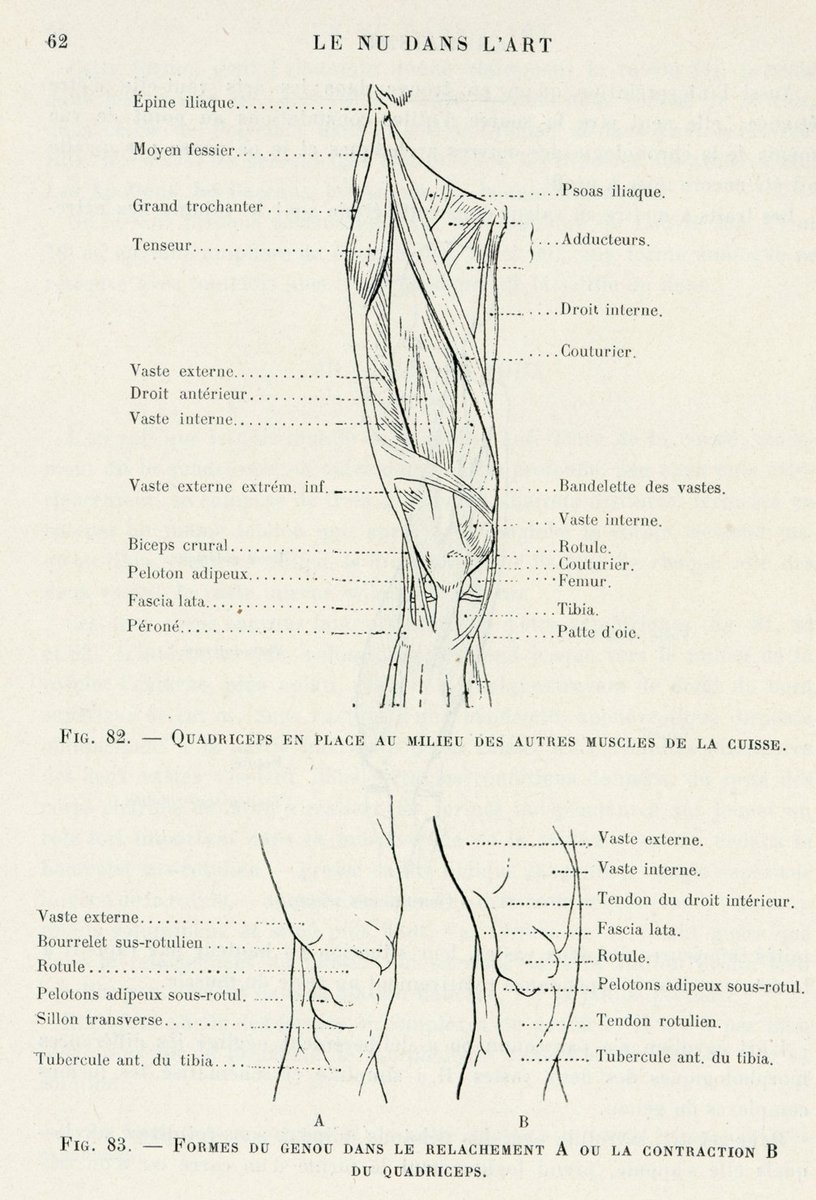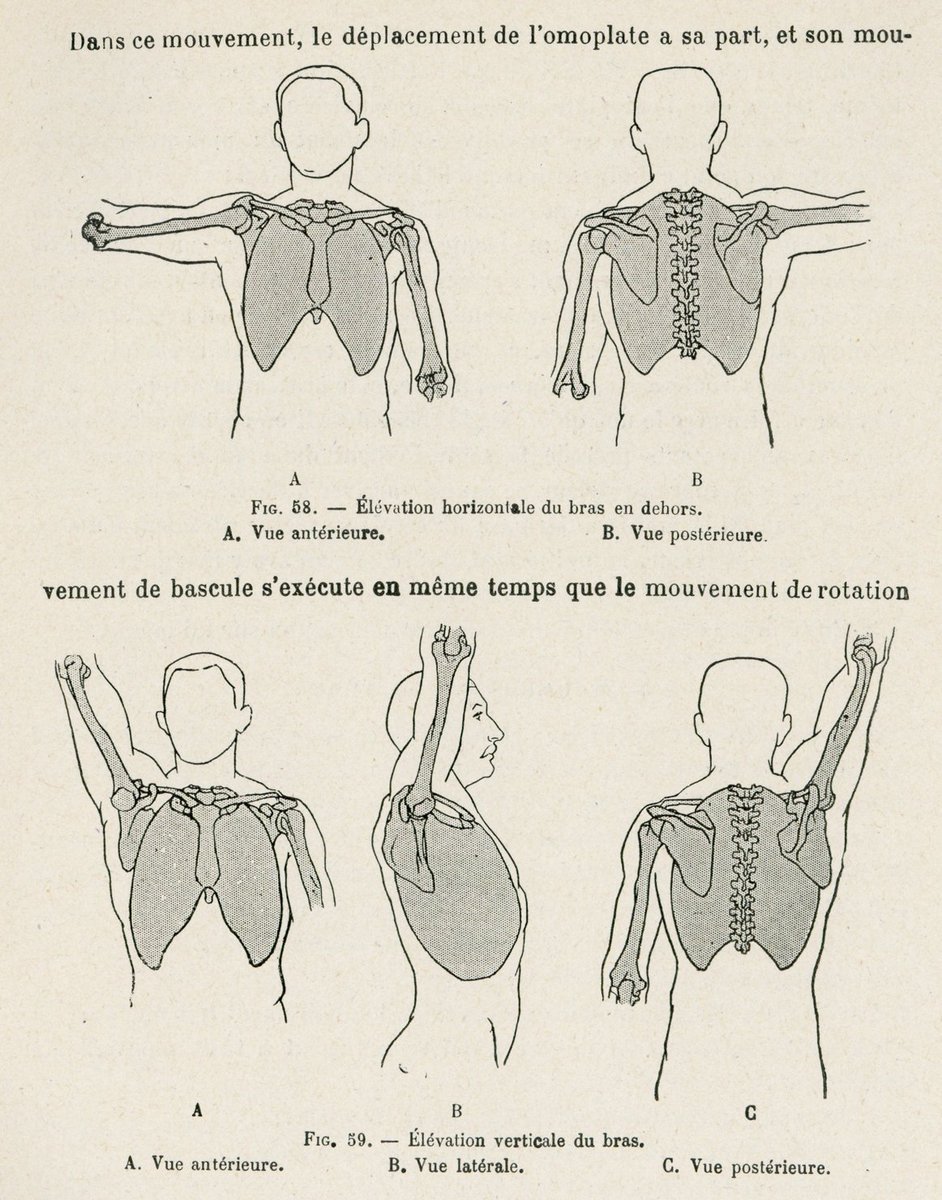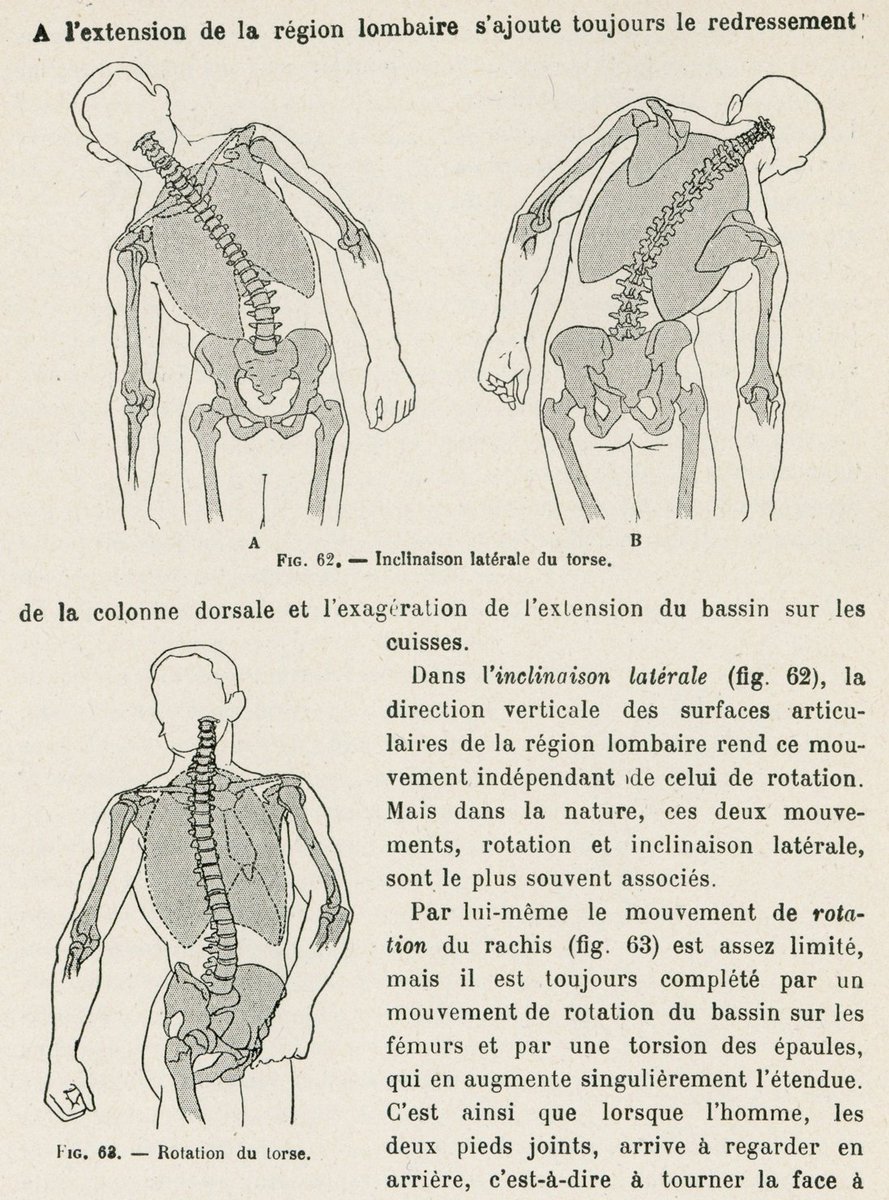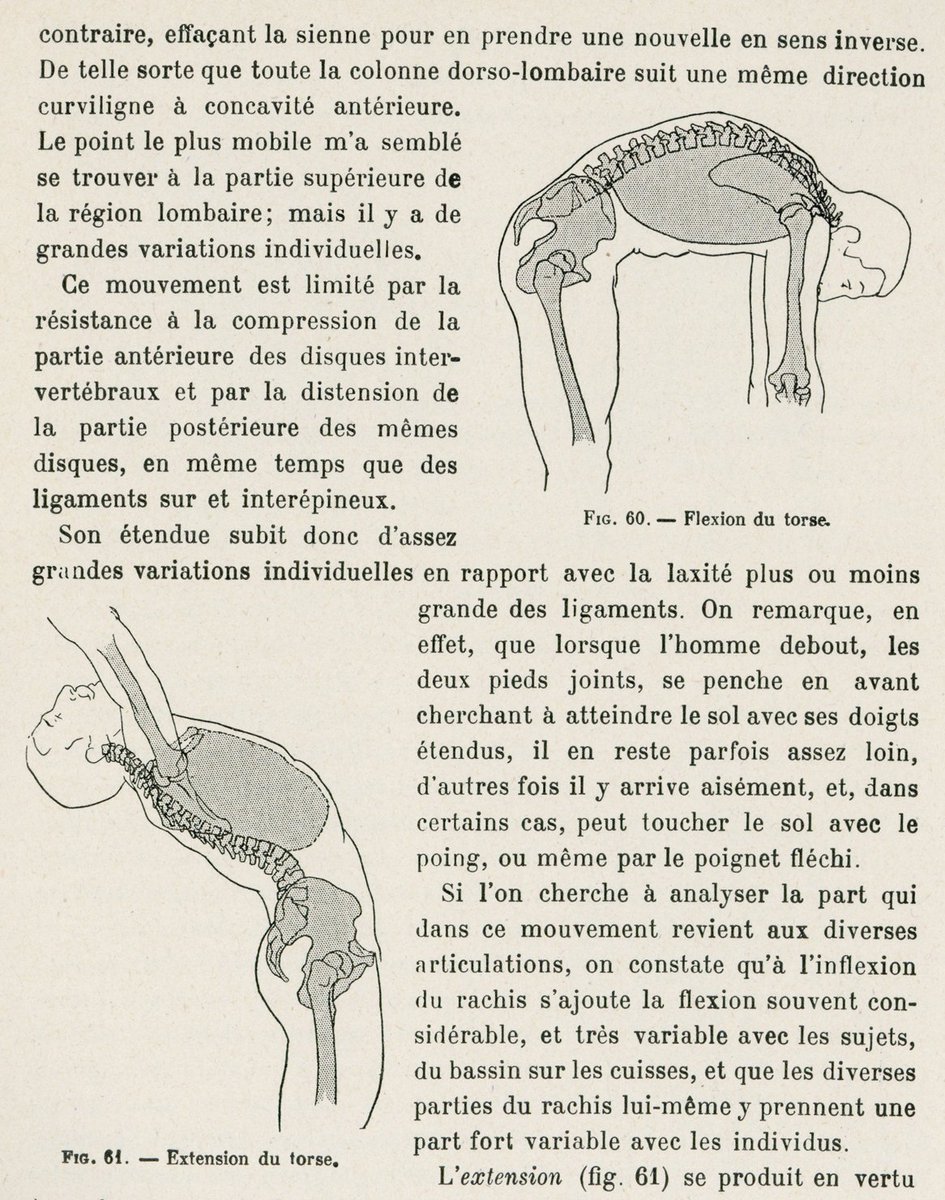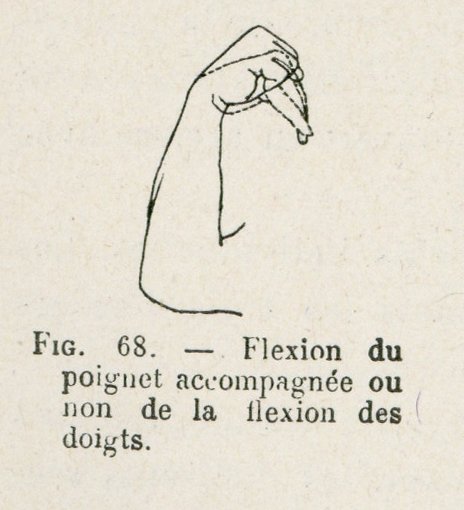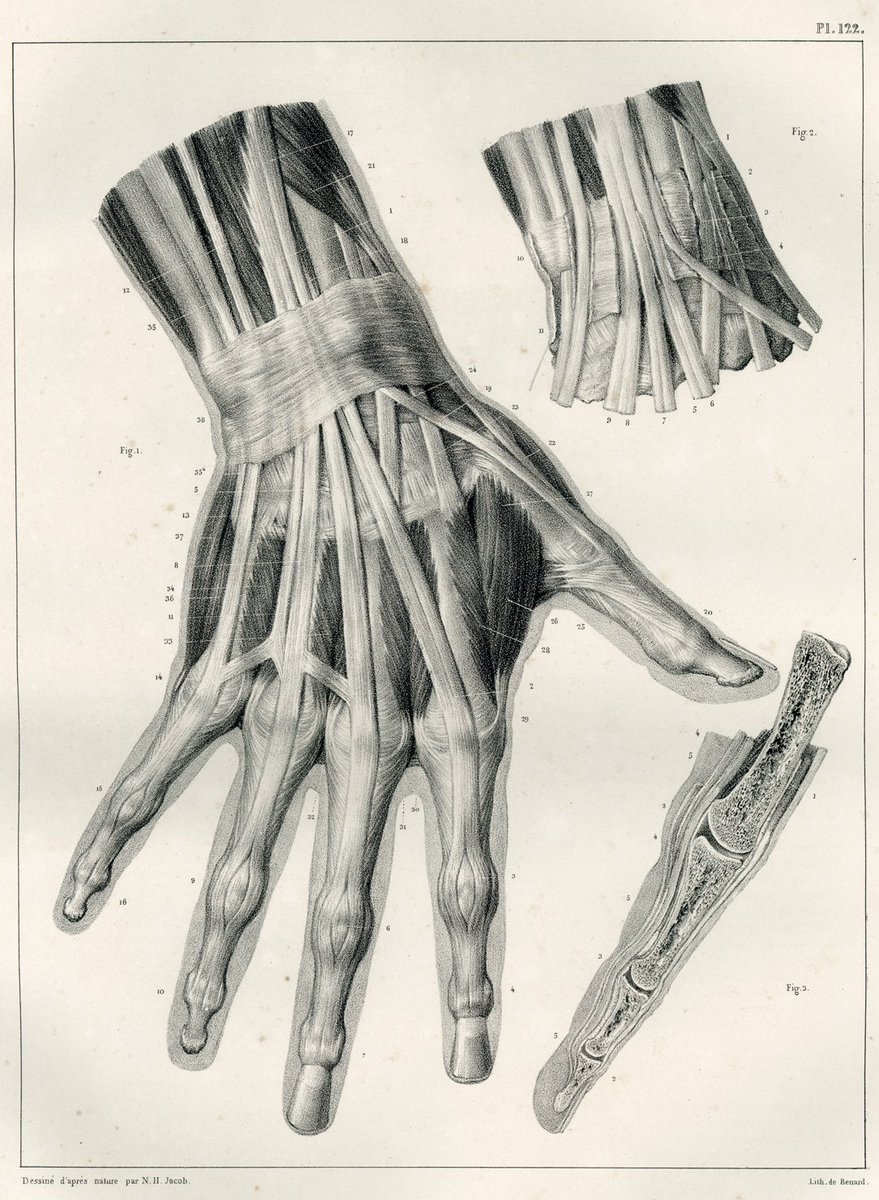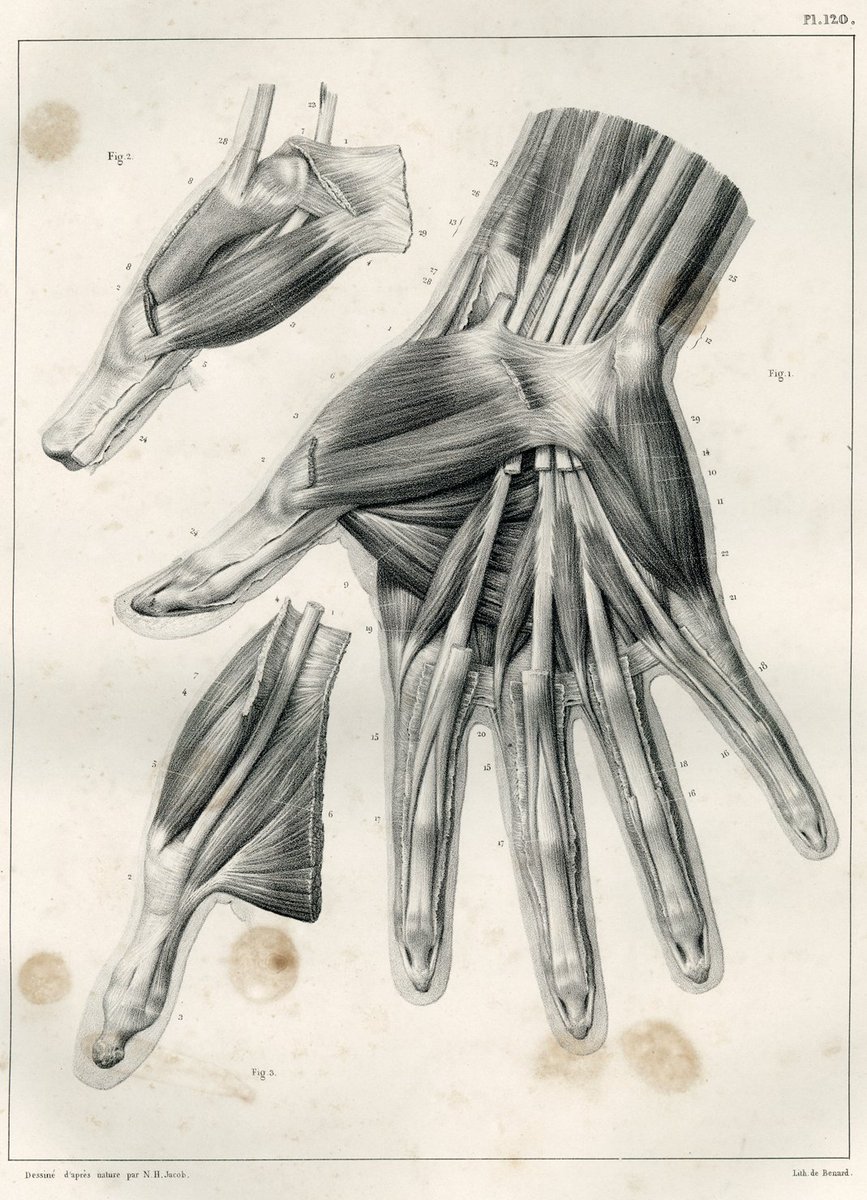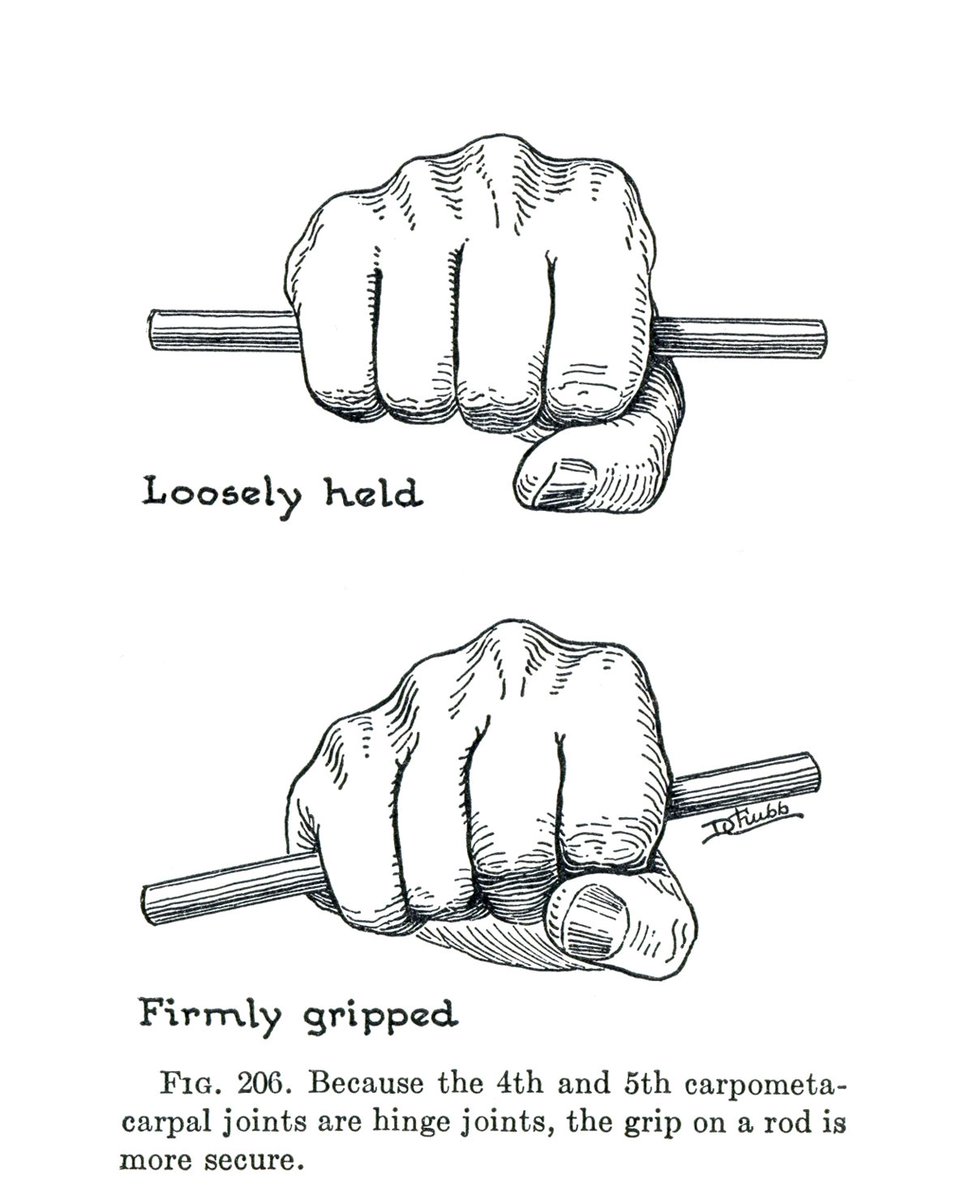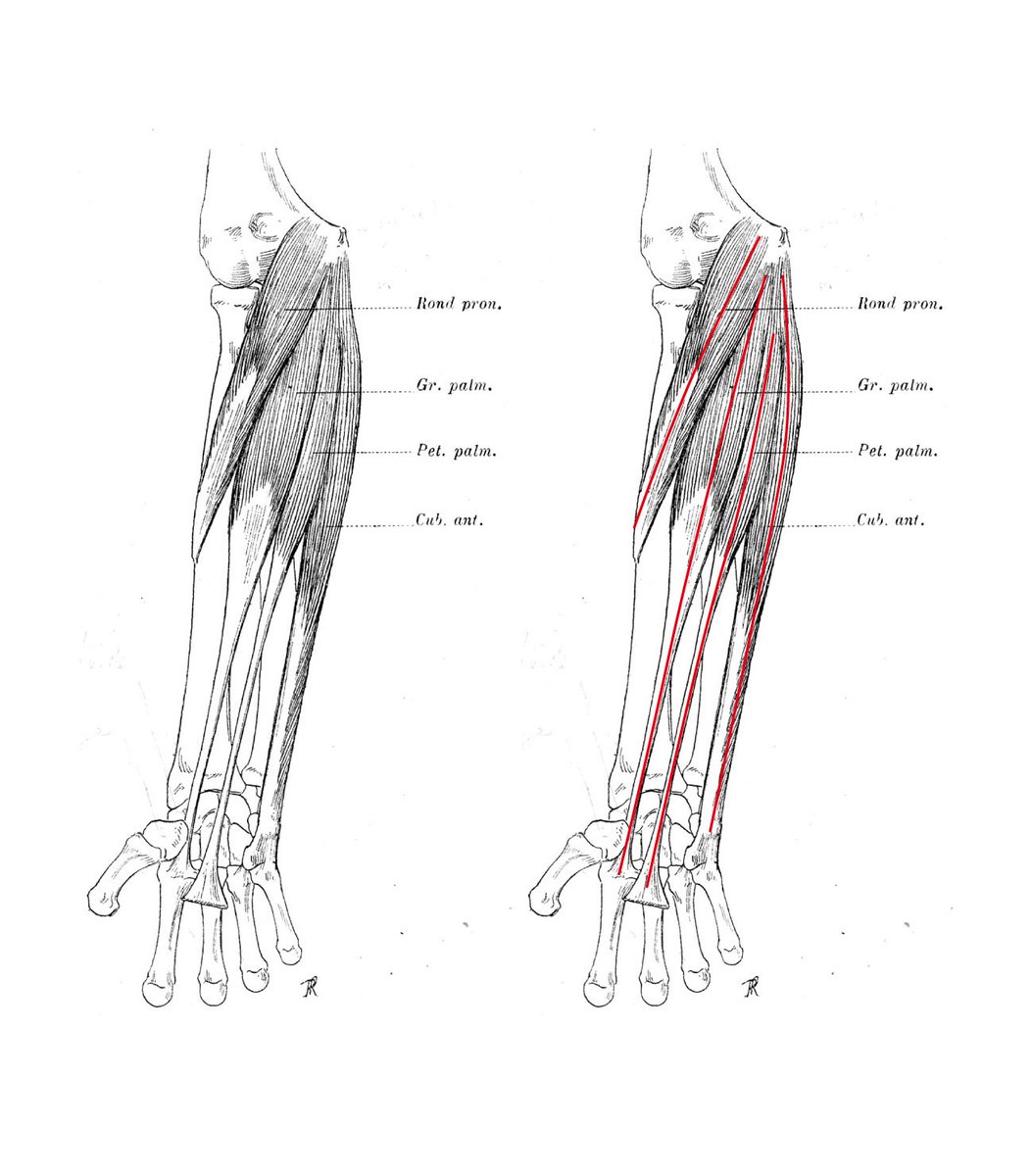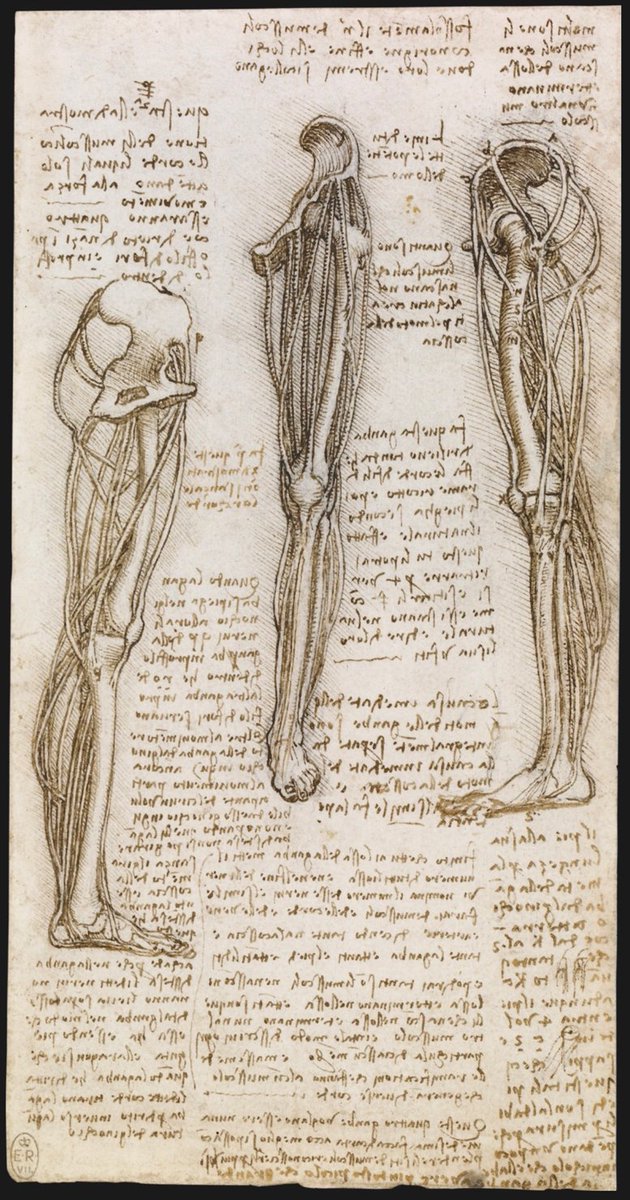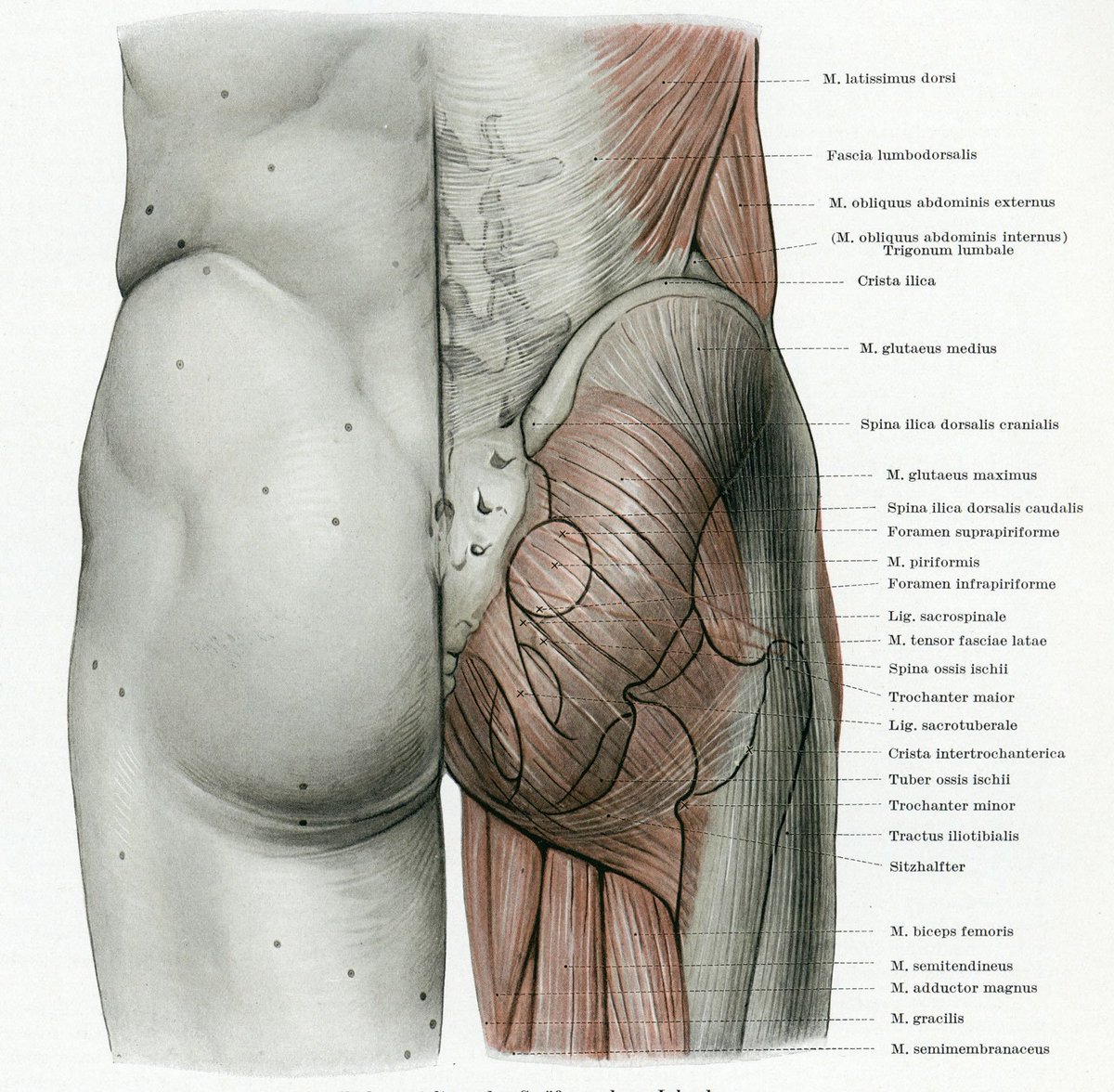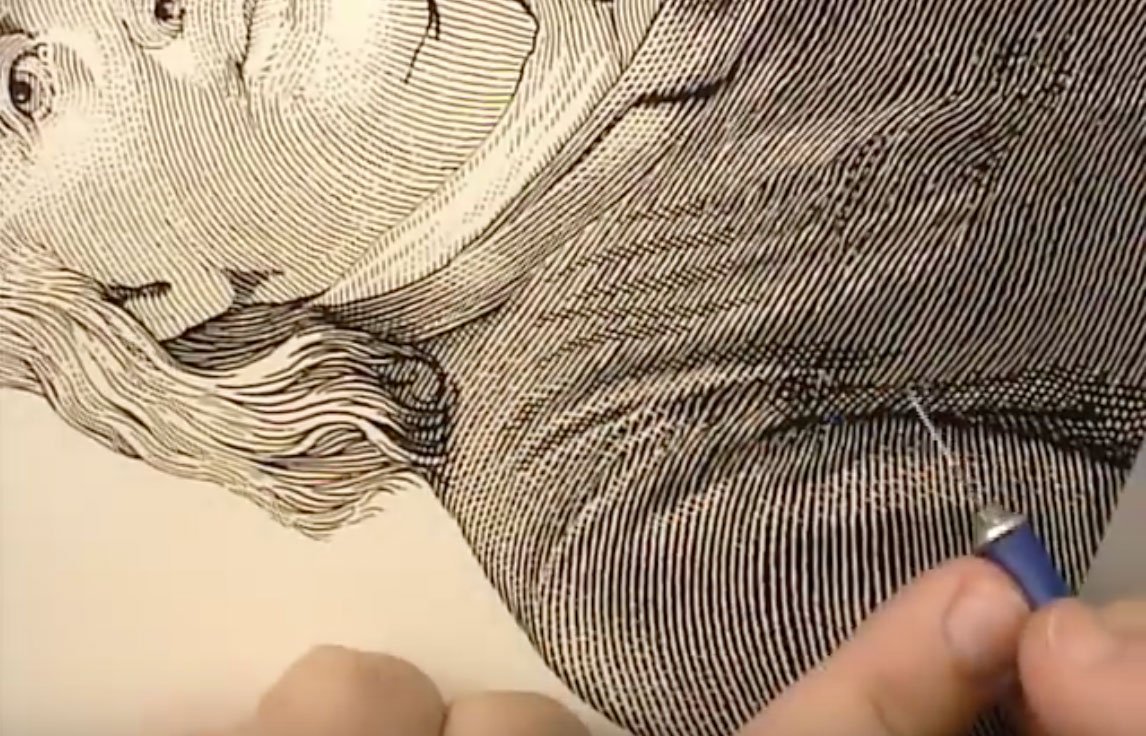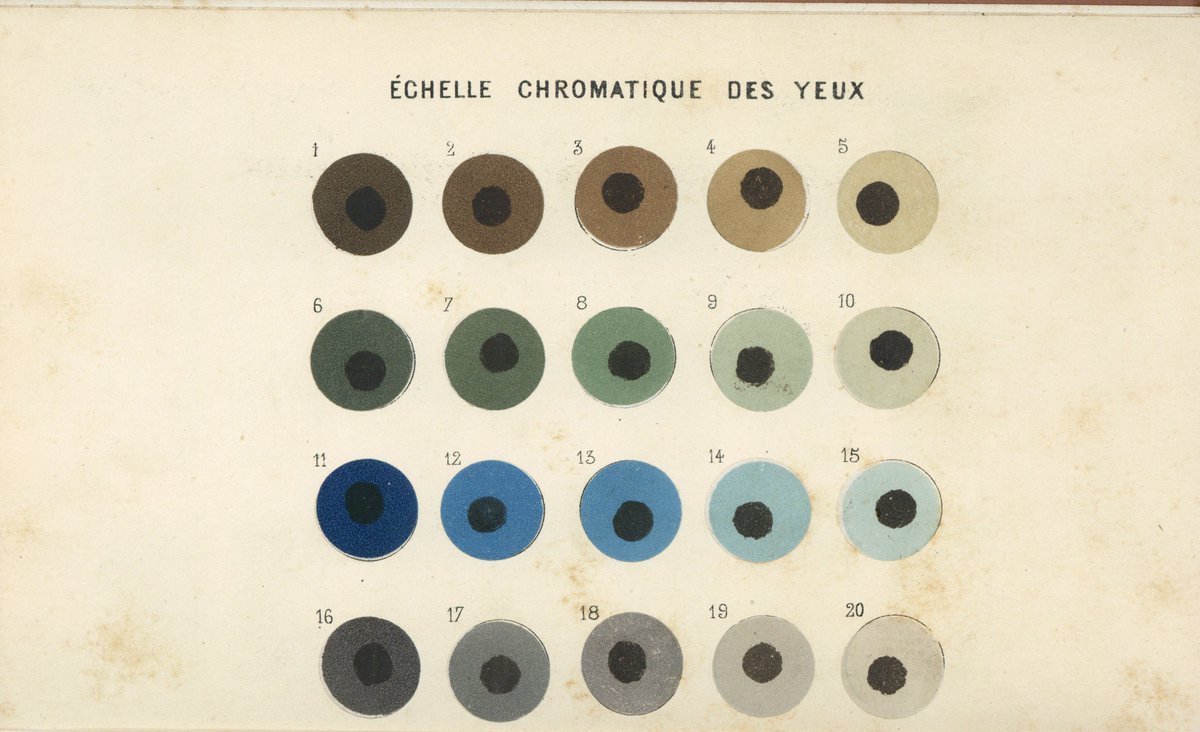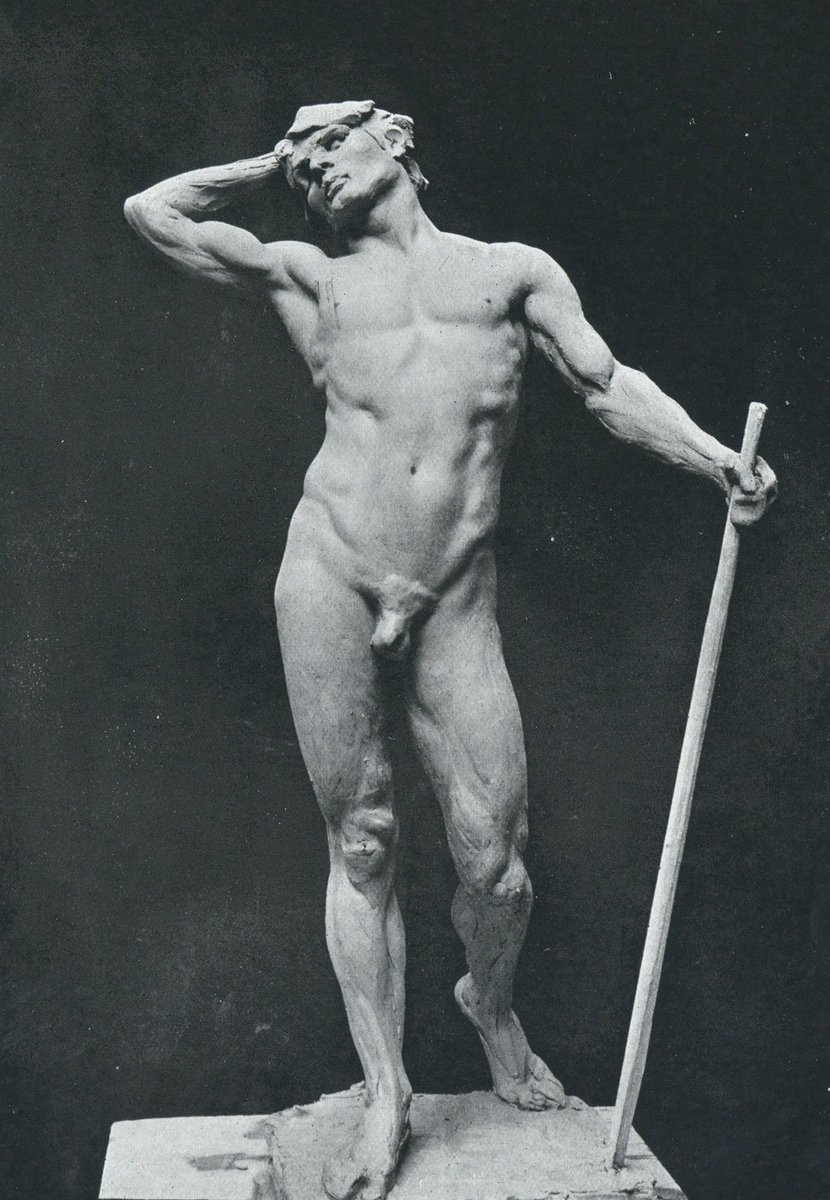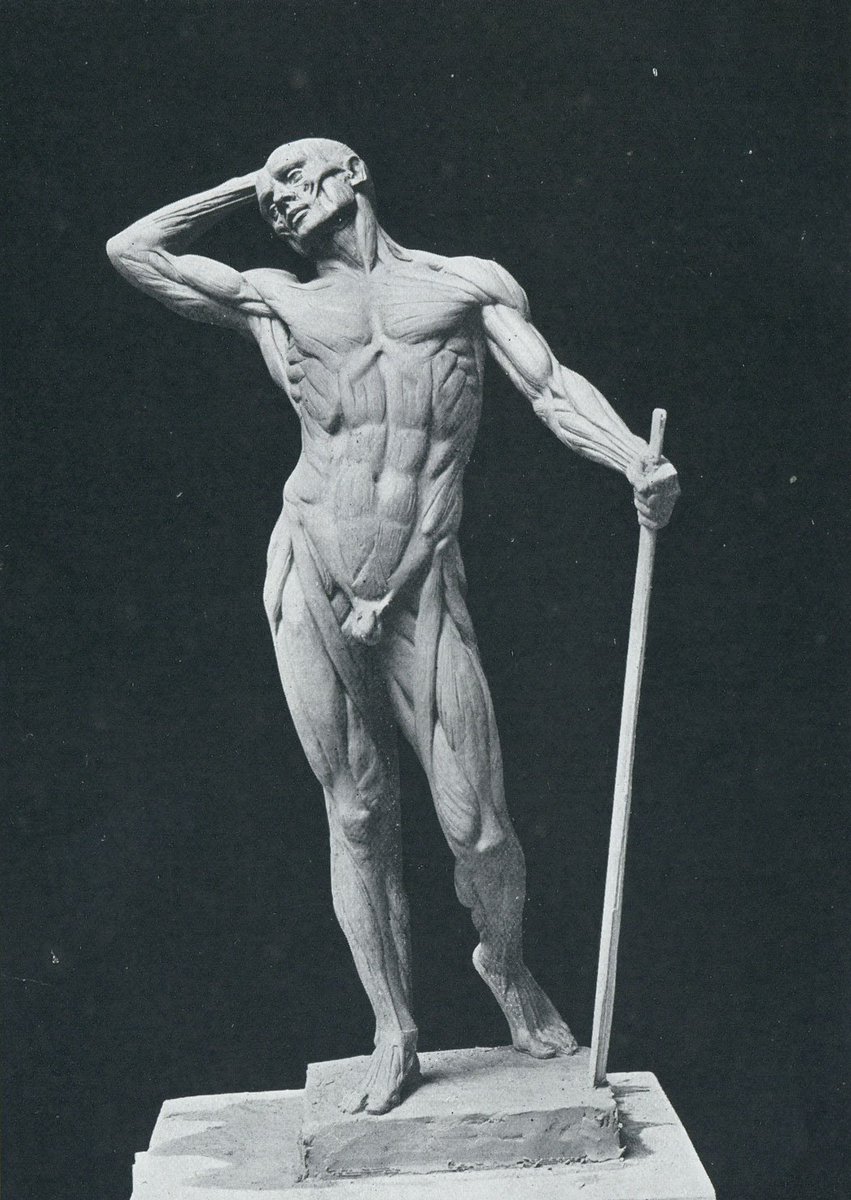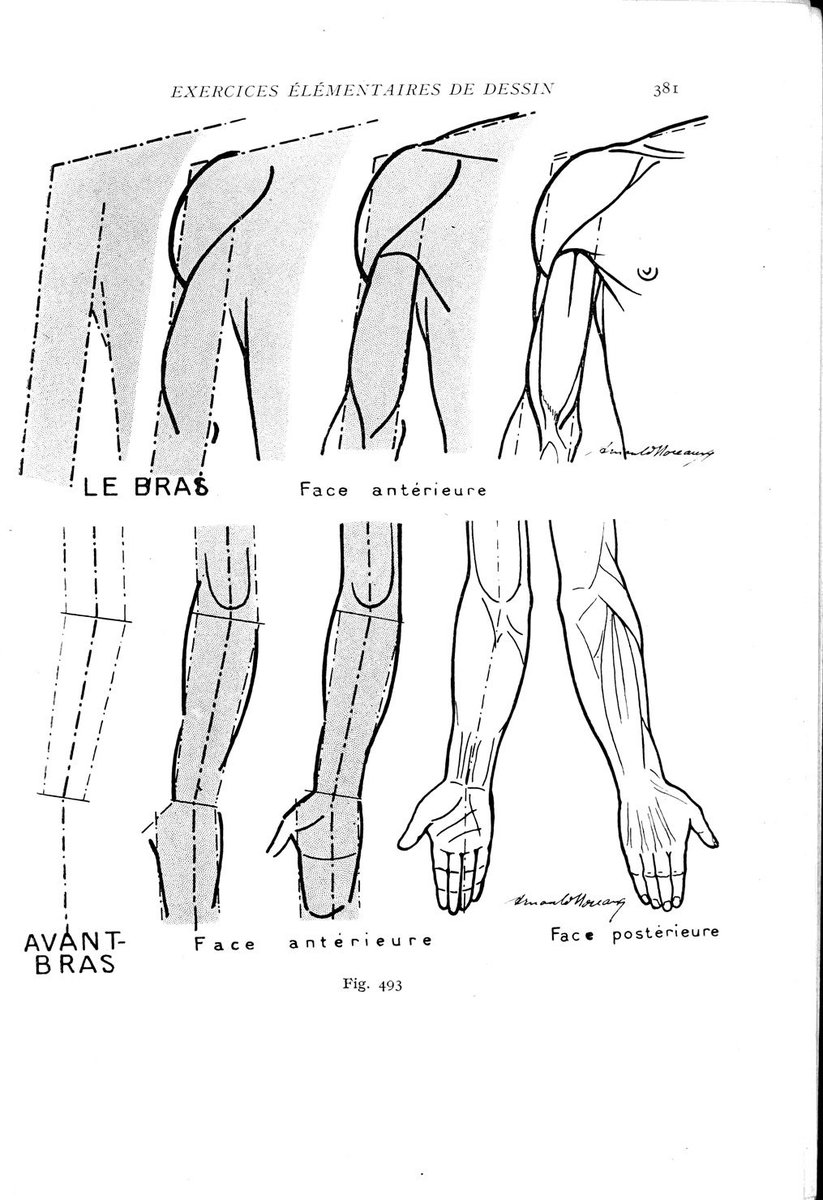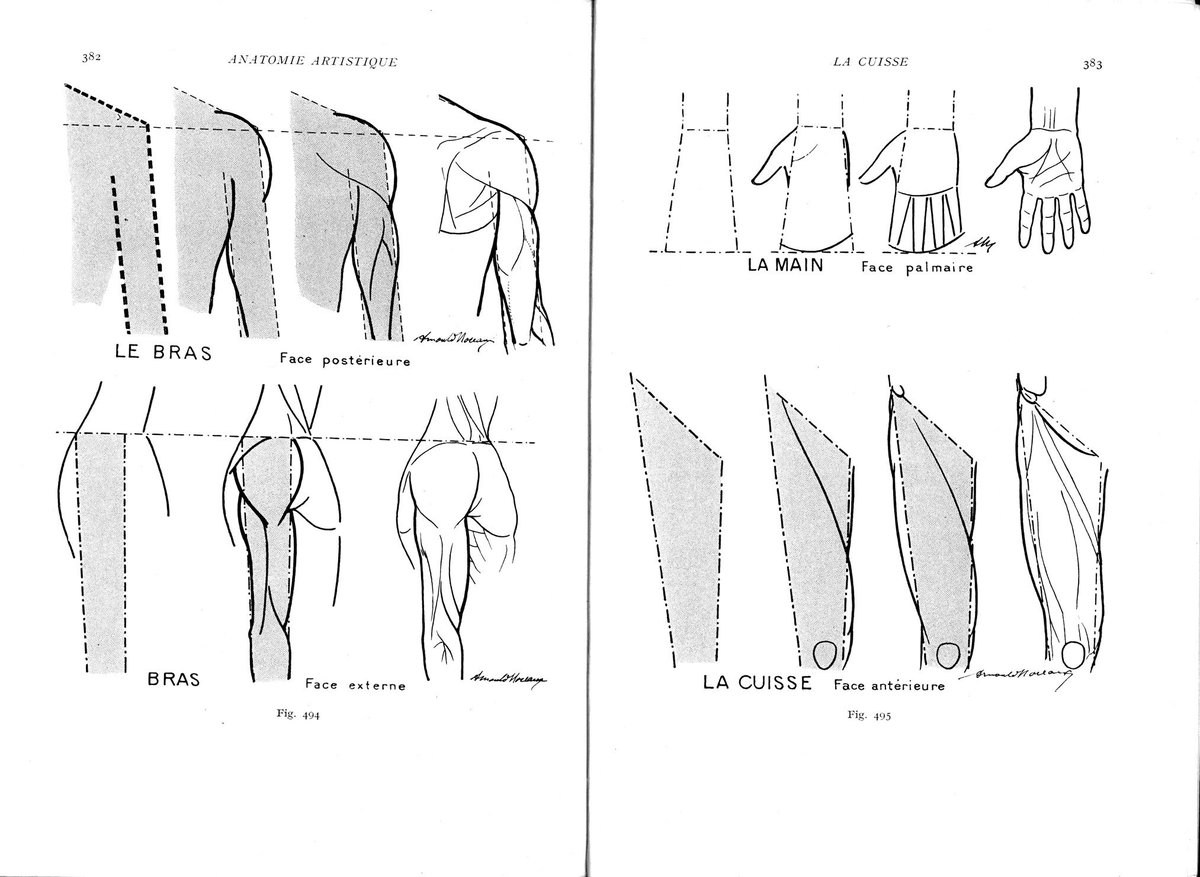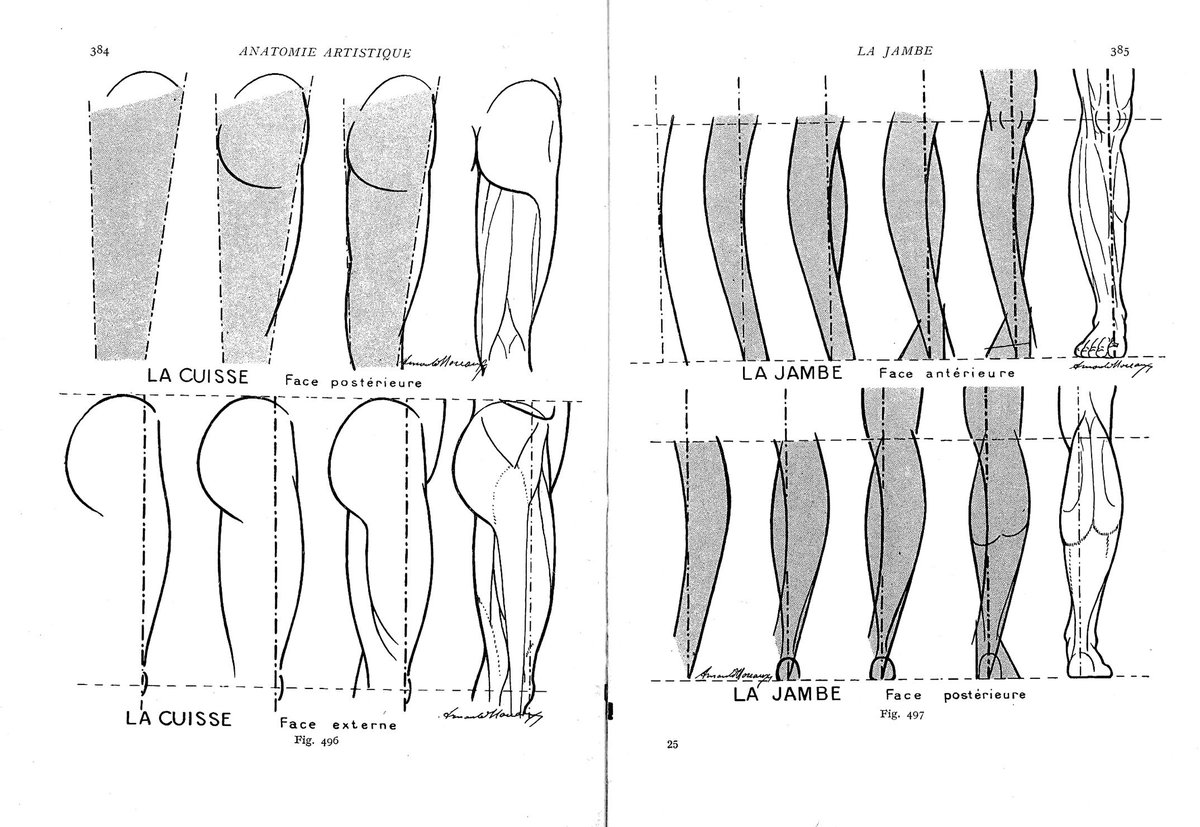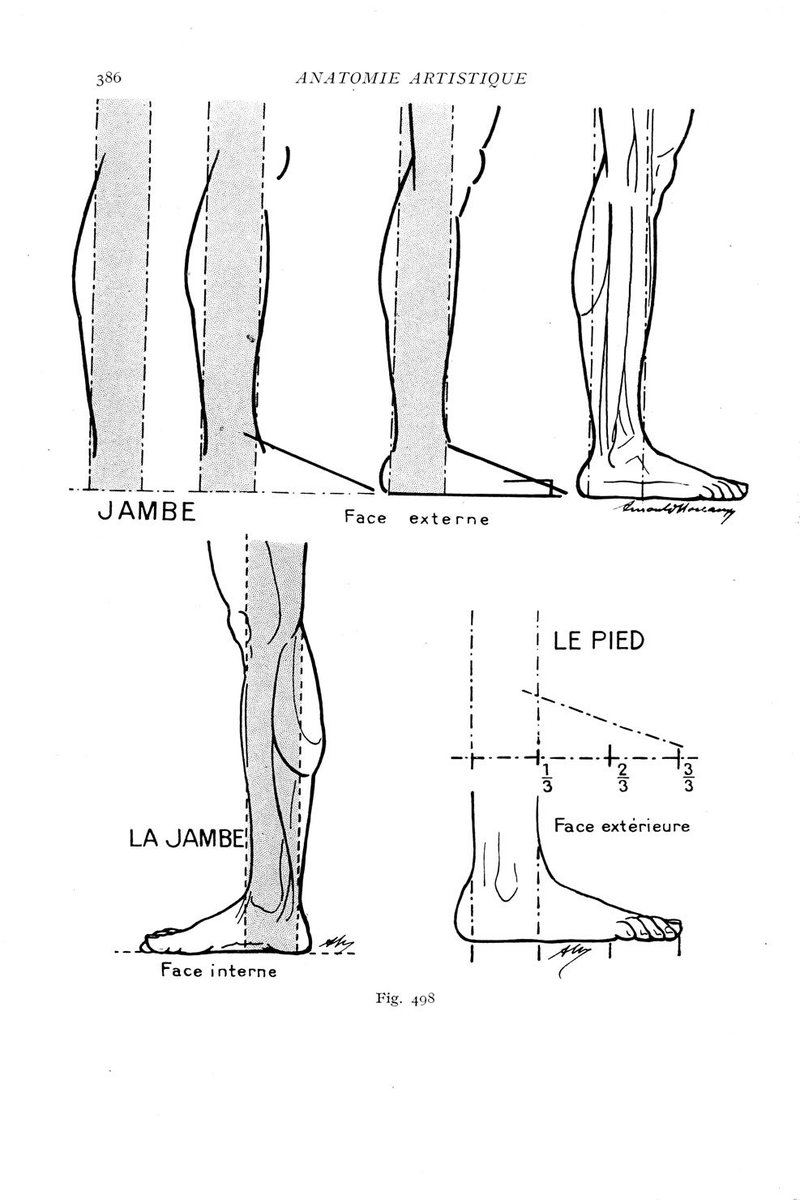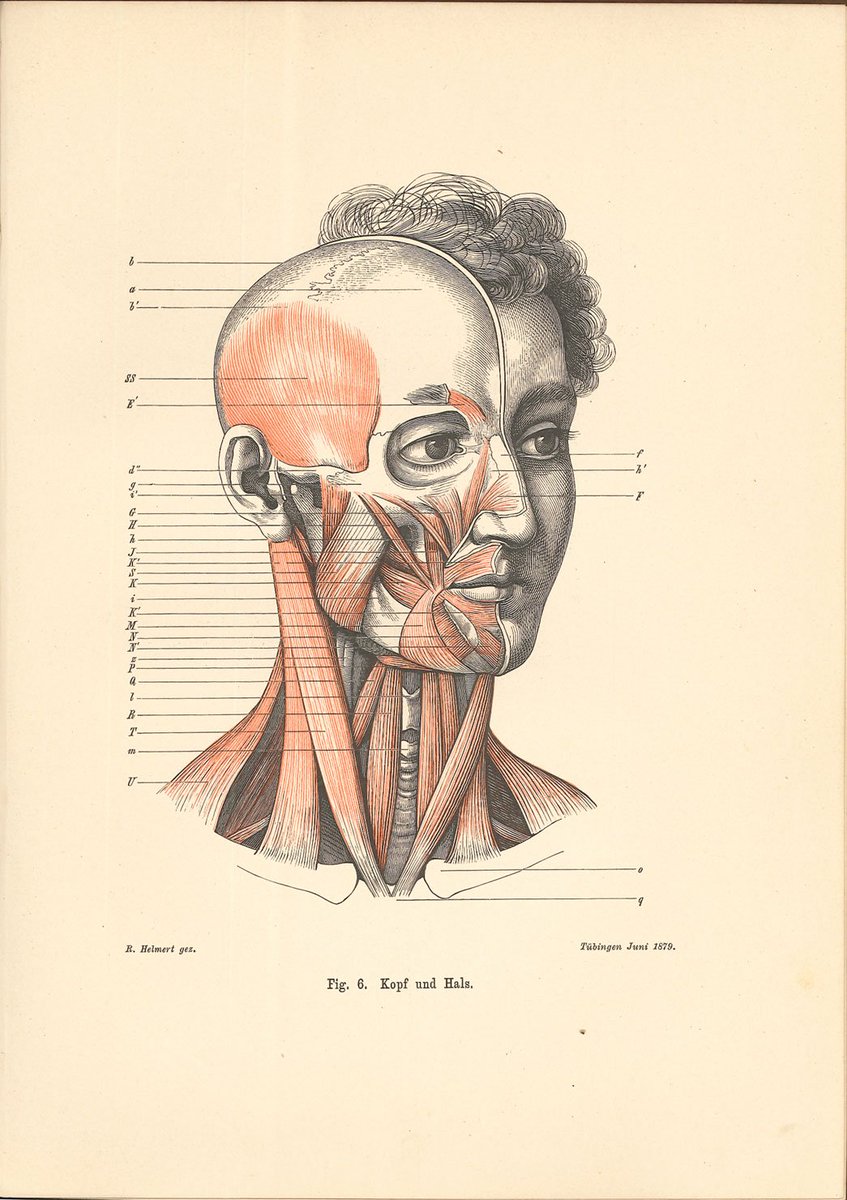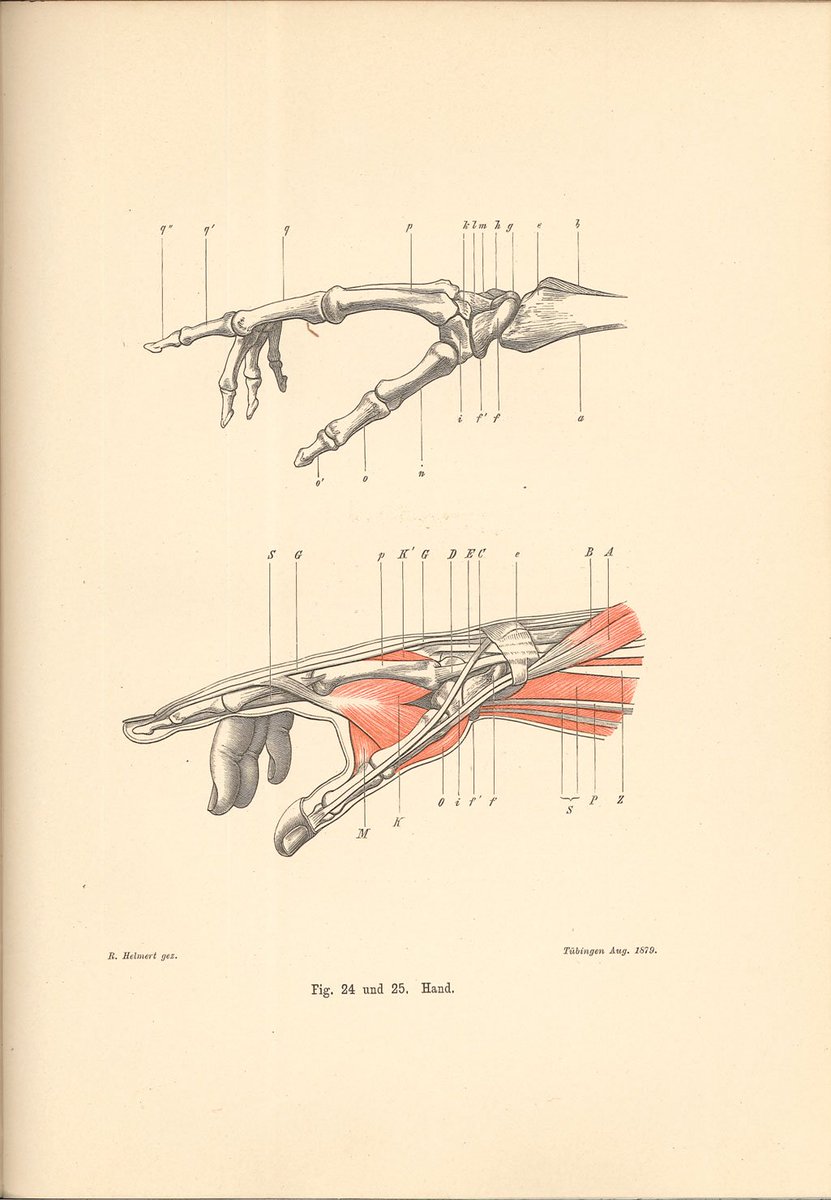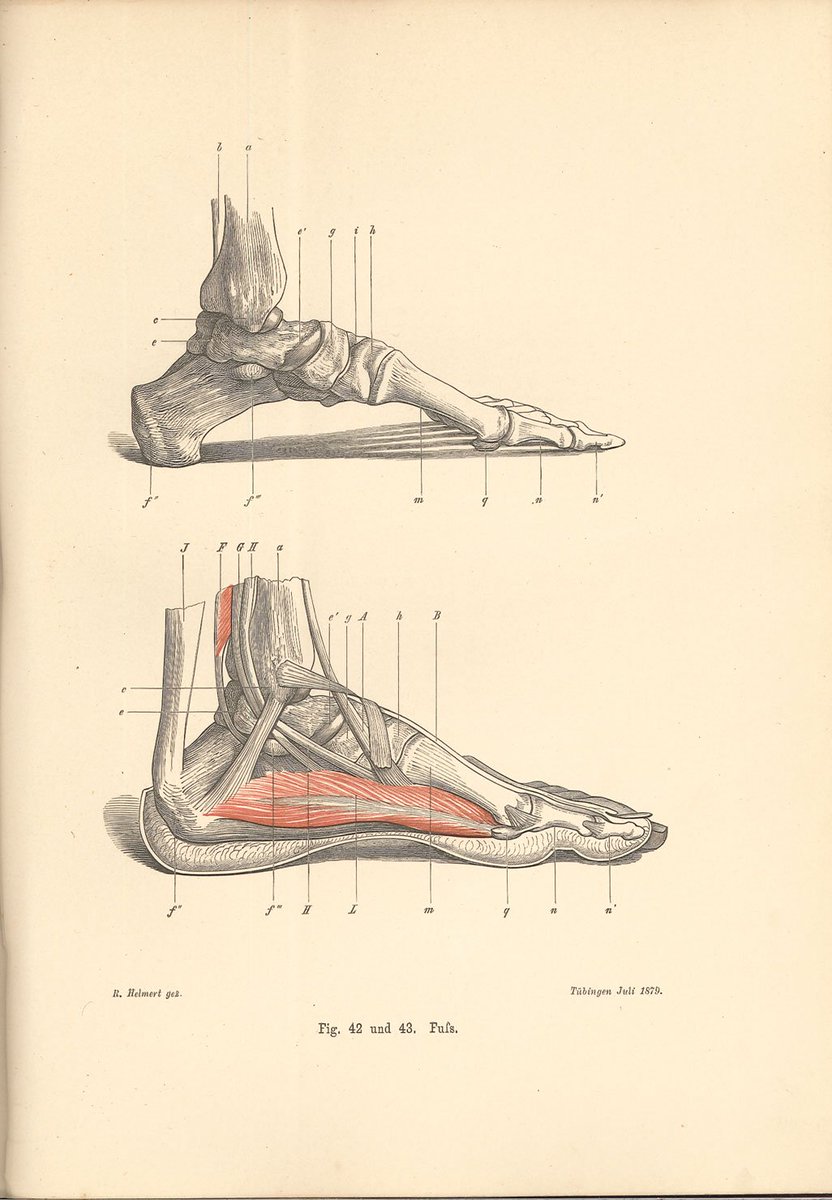2
3
4
5
6
7
10
14
15
メディカルイラストレーションにおけるペン画は、スクラッチボードテクニックと呼ばれる描画方法を応用して描かれる。医療用の場合は、この技法に加え、クロスハッチングがない。添付はMichael Harbert氏のデモンストレーション(リンク先は元動画)。youtube.com/watch?v=L2MHlK…
16
17
18
19
20
21
23