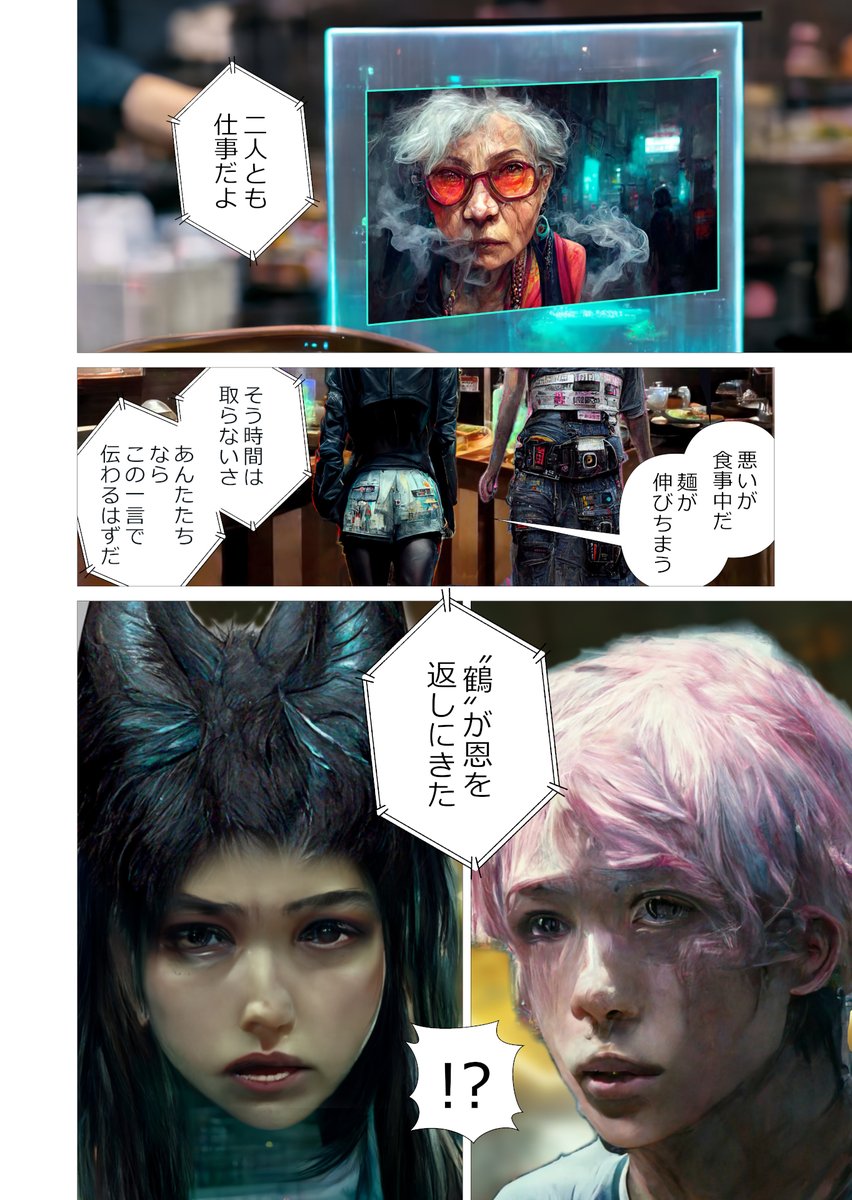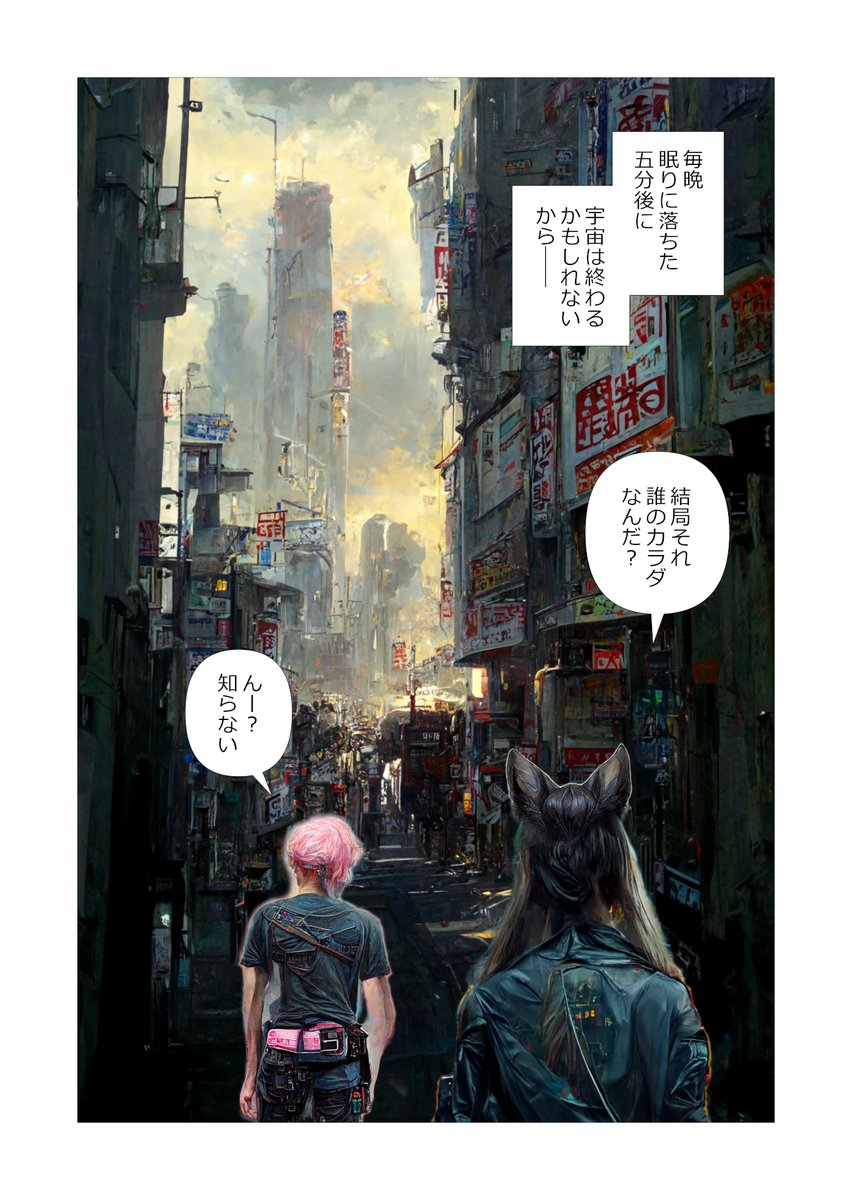951
たとえば「i2iで構図をパクッた絵を元絵を描いた人に嫌がらせとして見せるような問題行動を、AIを使う人の80%がする」のであれば、それはAIに問題の原因があると言えるでしょう。一方、AIユーザーの1%にも満たないのであれば、それは問題行動を起こした個人に原因がある……と考えるのが一般的です。
952
「〝トップガン〟に集まるのはエリートパイロットだ」という設定のおかげなのか、『マーヴェリック』に登場する若者たちはみんな優秀なんですよね。同年代だった頃の主人公よりも優等生に見える。だから「可愛い」と感じるし、「しっかり正しい道へと導かなければ!」と感じさせられる。
953
オーストラリア・ハンガリー帝国「サラエボで皇太子が暗殺された!報復せな!セルビアを攻めるで!」
セルビア「助けて、ロシア!」
ロシア「よっしゃ任しとき!総動員をかけたる!」
ドイツ「あかん!ロシアが総動員しよった!ベルギー攻めるで!」
ベルギー「なんでやねん!」
→WW1勃発。
954
(本題)
「蓋然性」とは、もっともらしさのことです。「もっともらしさ」をカッコよく言い換えると「蓋然性」になります。この蓋然性の概念はいかに発達してきたのか?ジェームズ・フランクリン『「蓋然性」の探求』というそのものズバリな書籍があります。
(画像出典)
msz.co.jp/book/detail/08…
955
多数決と民主主義の違いは、多数決は多数派がハッピーになれるけれど、民主主義では多数派も少数派も少しずつ妥協を強いられて全員が少しずつアンハッピーになるという点です。
健康な若者を1人殺して、5人の患者に臓器移植して助ければ、助かった5人はハッピー。これが多数決。
956
957
19世紀までの知識人は、ルネサンス的な万能人であることが理想とされており、あらゆることに精通しているべきだとされていました。だから雑誌『Nature』も最初期には芸術評を掲載したりしていたそうです。ところが歴史が下ると、研究者たちはお互いに専門外のことは理解しがたいと気づき始めます。
958
「イーロン・マスク兄貴もAIを作ることに興味津々らしいで」
「ChatGPTに負けてられへんな」
「幸いにして、Twitterという膨大な学習データを使いたいホーダイや」
「せやな」
「問題は、Twitterを食べさせてもボンクラAIしか生まれなさそうってことやな」
「せやな…」
959
〝トロッコ問題〟を解いた結果、私は画像生成AIを使っている。「悪い結果」と「もっと悪い結果」とを比較して、マシなほうを選ぶという功利主義に従っている。たとえ法的に問題なくとも、今までの私たちの慣習からいって、画像生成AIには道義的な気持ち悪さを覚える。それでも、もはや無視はできない。
960
普段は食べ物を粗末にするとコーランを焼かれたイスラム教徒のごとく激怒する民族が、今日だけは食べ物を投げてまき散らして喜び、獲物の頭部をトゲのついた葉っぱと共に玄関先に掲げて魔除けとする奇祭…
961
ChatGPTがDeepLに比べても極めて自然な翻訳ができるということは、たとえば英語が苦手な日本人でもハリウッドのシナリオコンクールに応募できるようになるし、日本語の苦手なフランス人でも神保町や音羽の出版社にマンガを持ち込めるようになる……ということを意味している。
962
ポケモンで例えると「この育成のリザードンにソーラービームを覚えさせるかどうか悩むんですよね」と言っているマスターボール級の人に対して、「こいつバカだw同じほのおタイプの技なら威力1.5倍になるの知らねえのかよwマスターボール級も大したことねえなw」とクソリプするエアプがたくさんいる。
963
「自分の作品が商業誌で受け入れられないのは、出版社の商業主義のせいだ」と信じれば、気持ちは楽になるかもね。
創作活動は自己満足であると同時に、商業誌でやるなら「お客さんである読者の満足」でなければならない。編集者や出版社を満足させようと考える時点で、目の付け所を間違えてるよ。
964
ここでAIの規制方法をミスると何が起きるかというと、日本の漫画家がシコシコと手書きのマンガを命を削りながら週刊連載する傍らで、〝日式〟の絵柄を研究した他国のマンガ家たちが自分のイラストをLoRAしてフルカラーの超絶ハイカロリー作画のマンガを日刊連載して、ぶっちぎるようになります。
965
DLsiteでAI生成エロ絵の詰め合わせが売上1位を取ったのを見て、俺の好きなエロ漫画家さんが「創作とは…マンガとは…うごご…」ってなっているのをお見掛けしたのだけど。いうても同人AI術師とプロの漫画家じゃ、エロの才能ではミジンコとバハムートくらい違うじゃないですか先生!と言いたくなった。
966
「デモやストライキなんてイマドキ流行らないよね~www」って冷笑していた90年代から「じゃあ新しい〝世の中を変える方法〟が必要ですね」みたいな議論はあったはずだけど、まさかその答えが「声のデカい個人がネットで炎上させる」になるとは想像していなかった the 3rd decade of the 21st century…
967
Q. なぜ画像生成AIはこんなに絵が上手くなったの?
A. 流行りの情報量もりもりギラギラ系のモデルは(おそらく)人間のイラストだけでなく実写系や3DCG系のモデルも味付けとしてマージされているから。
Q. それは「上手い」と呼べるの?
A. 分からない。そもそも今までと同じ「絵」と呼べるのか…?
968
味噌汁にジャガイモはありかなしか。俺は〝あり〟派だ。
けれど、ジャガイモが強すぎてご飯が要らなくなってしまうのも分かる。「ご飯を引き立てる汁物」ではなく「ジャガイモの味噌スープ煮」という別の料理になってしまう気がするし、脳が味噌汁だと認識したがらない……という気持ちも分かる。
969
Q. AIによるtext2appでプログラマは失職しますか?
A. AIとプログラマの関係によります。もしもコンテナと沖仲仕、トーキー映画と活動弁士、電算機と計算手のような関係なら、失職します。レコードと演奏家、表計算ソフトと会計士、自動翻訳AIと翻訳家のような関係なら、たぶん生き残ります。
970
でもそれ『ゴジラ』でも『ウルトラマン』でも『ドラゴンボール』でも『ポケモン』でも同じじゃーん!って脳内のもう一人の自分にツッコミを入れられた。俺は青年誌でばかり書かせてもらっているけど、小中学生を狙ったコンテンツの強さはこういうところだよな…。
971
「あなたのことを嫌いな誰かを一番イラつかせる方法は、あなたが楽しく幸せそうにしていることだ」という人生の基本を忘れていた。気を付けよう。
972
俺が仏教徒ではないのに何となく〝徳〟を積もうとするように、キリスト教圏ではたとえ無宗教でも自然神学的な宇宙観を内面化している人が多いのかもしれぬ。
973
『タテの国』は現在の俺たちが想像しうるタテ読みマンガの100点満点中30000点みたいな〝超絶大正解〟なので、田中先生には儲けて欲しい。先生から「『タテの国』のおかげで鎌倉に豪邸が買えました!」という報告がないと、若いクリエーターたちがタテ読みマンガに挑戦しなくなっちゃう…。
974
「ひと目で○○ちゃんが悪いって分かるじゃん」
「そうだよね!」
「証拠なんてなくてもマトモな人なら分かるよね?」
「分かる!」
って会話が許されるのは、小学生まででしょう。価値観の違う多様な人間が共存している大人の社会では、「誰にでも分かるような証拠・説明」が必要になると思います。
975
正直、ファンタジー小説の冒頭部分を「主人公がジャガイモを食べるシーン」から始めたくなる願望はある。
「ジャガイモだと!?こ、この世界にはジャガイモがあるのか!?」
「何を驚いているんだ?」
「この世界ではずっと昔からあるだろう?おっと、そのパンプキンパイとトマトサラダを取ってくれ」