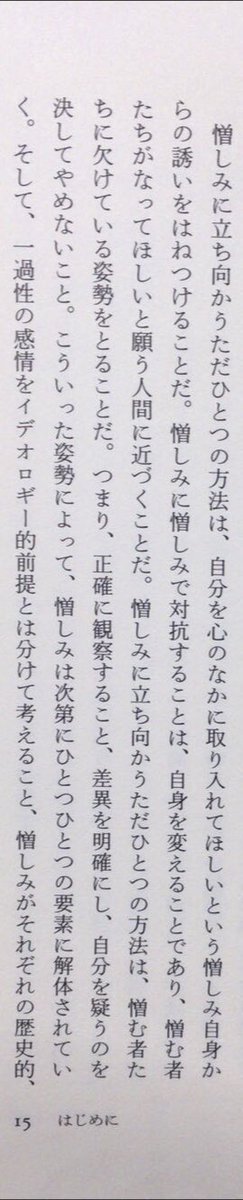1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
書店で気になる本を見つけたとき、家賃・食費・光熱費のことが頭をよぎって、購入を断念する人が多い国より、書籍代を充分に確保できる経済的余裕があるため、迷わず購入できる人が多い国の方がいい。
1283
1284
1285
「周囲の人を無為に傷つけ、満たされることは永遠になく、壊れたラジオのように「気に入らないこと」を受信し続ける。死ぬまで。これをおそらくは不幸という。」(津村記久子『二度寝とは、遠くにありて想うもの』講談社文庫、P30)
amzn.to/3nGY1oE
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
「人間が自然を守る」「環境問題について語るとき、よくそういう言い方をする。でもそれは、ほとんど発想として間違いなんだと思います。人間が自然にかける負荷と、自然が許容できる限界とが折り合わなくなるとき、当然敗者になるのは人間です」(『音楽は自由にする』P245)
amzn.to/3K765a9
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300