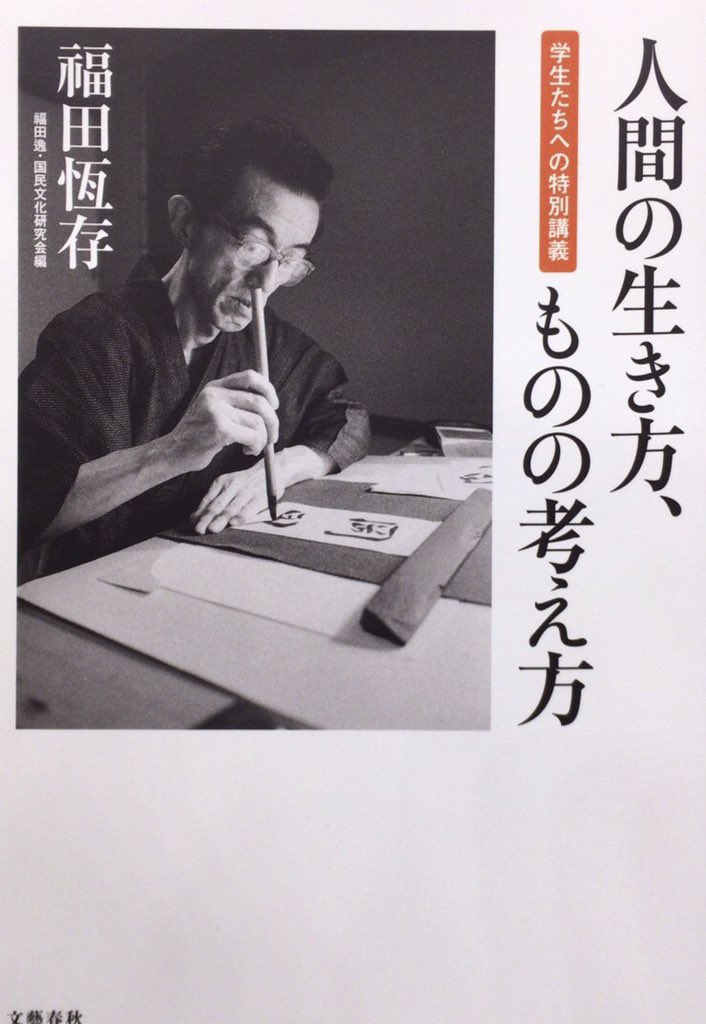951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
大学で歴史学を専攻すると、所謂「歴史好き」の人と話が合わなくなる。
972
973
974
975