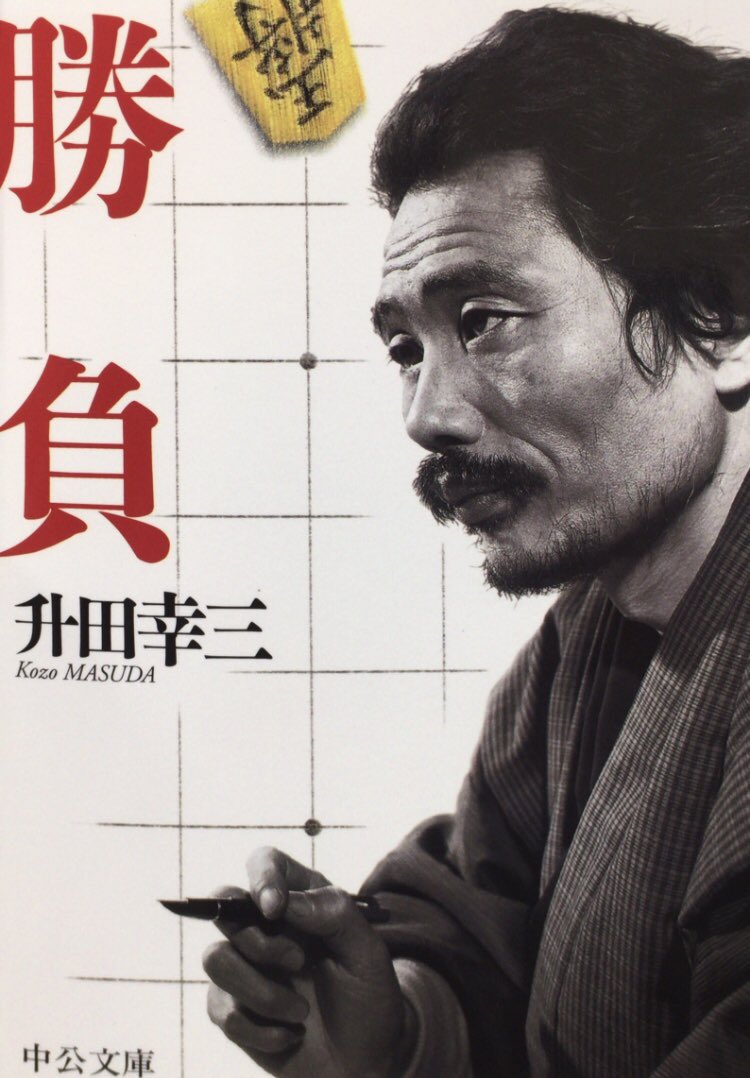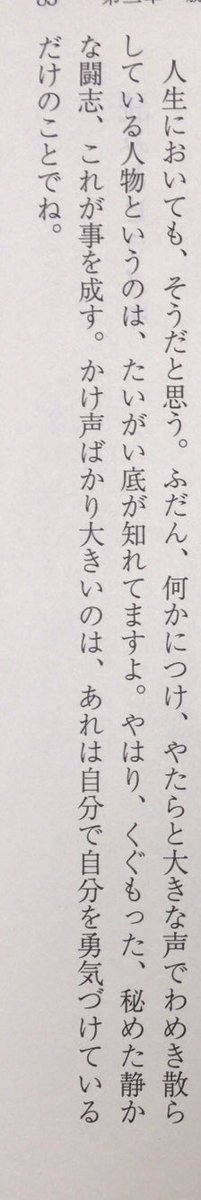926
927
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
「ふだん、何かにつけ、やたらと大きな声でわめき散らしている人物というのは、たいがい底が知れてますよ。やはり、くぐもった、秘めた静かな闘志、これが事を成す。かけ声ばかり大きいのは、あれは自分で自分を勇気づけているだけのことでね。」(升田幸三『勝負』中公文庫、P83)
#将棋の日
940
941
942
944
945
946
947
「一見男性に有利とされるイデオロギーが、実際は男性自身を自縛していることが、ようやく指摘され始めている。フーコーが明らかにしたように、近代における男性の主体化は、近代資本主義価値体系への男性の従属化であった。」(大越愛子『フェミニズム入門』ちくま新書、P25)
#国際男性デー
948
949
950