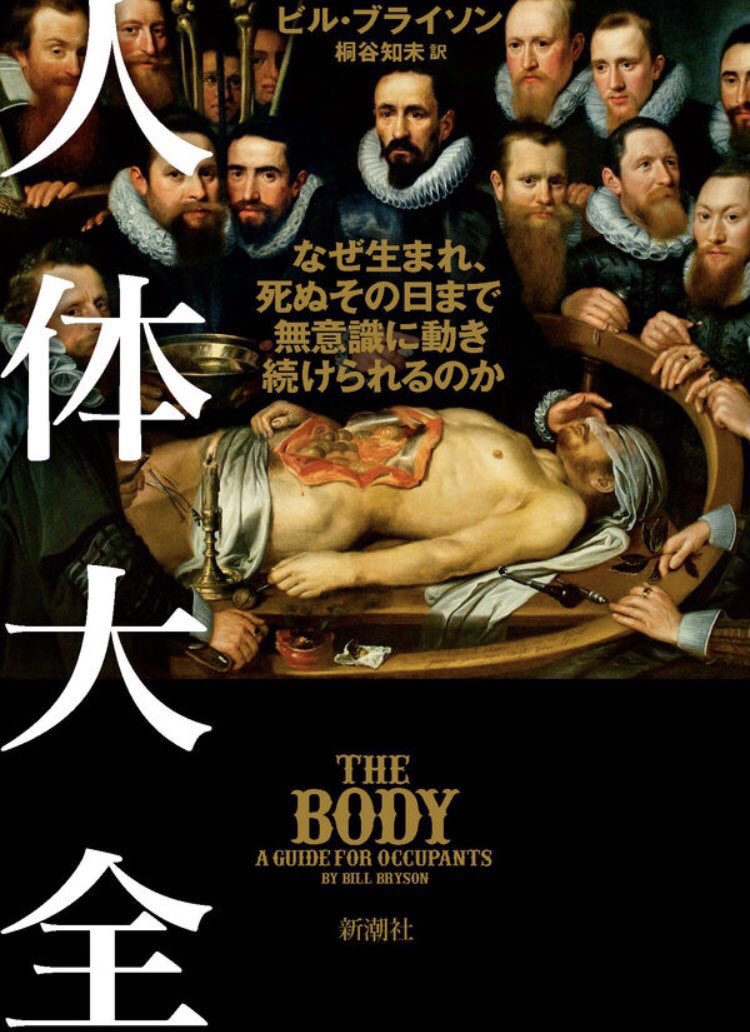901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
917
918
919
920
921
922
923
924
「皮膚は、「真皮」と呼ばれる内層と、外側の「表皮」から成る。表皮の最も外側の表面は「角質層」と呼ばれ、すべて死んだ細胞でできている。ヒトを美しく見せるすべてが死んでいるという事実には、奇妙な感慨を覚える。」(桐谷知未訳『人体大全』新潮社、P31)
#皮膚の日
925