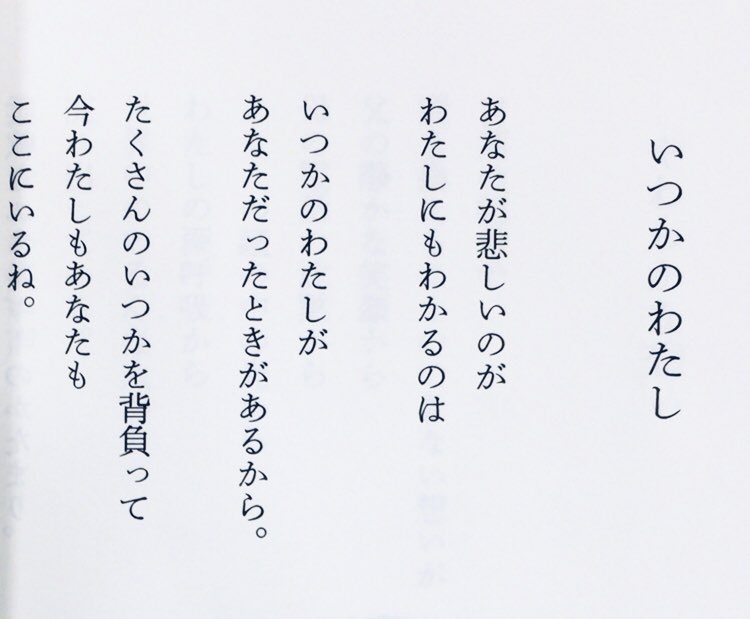876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
890
891
892
りんご大学(青森りんごTS導入協議会運営)が作成したチャート。
#いいりんごの日
893
894
895
896
897
898
899
900