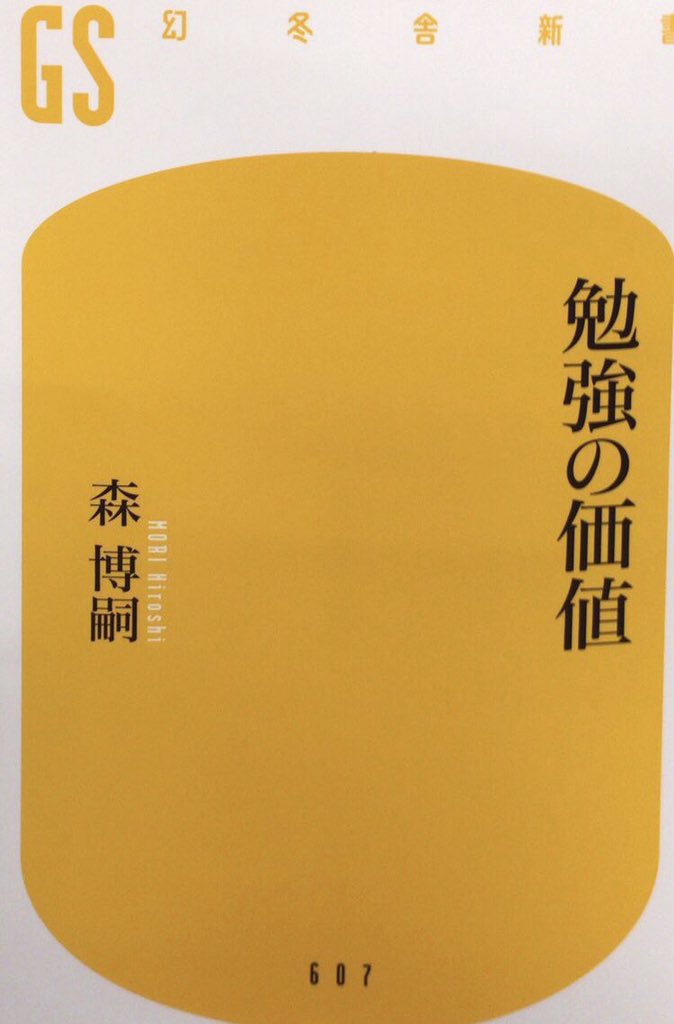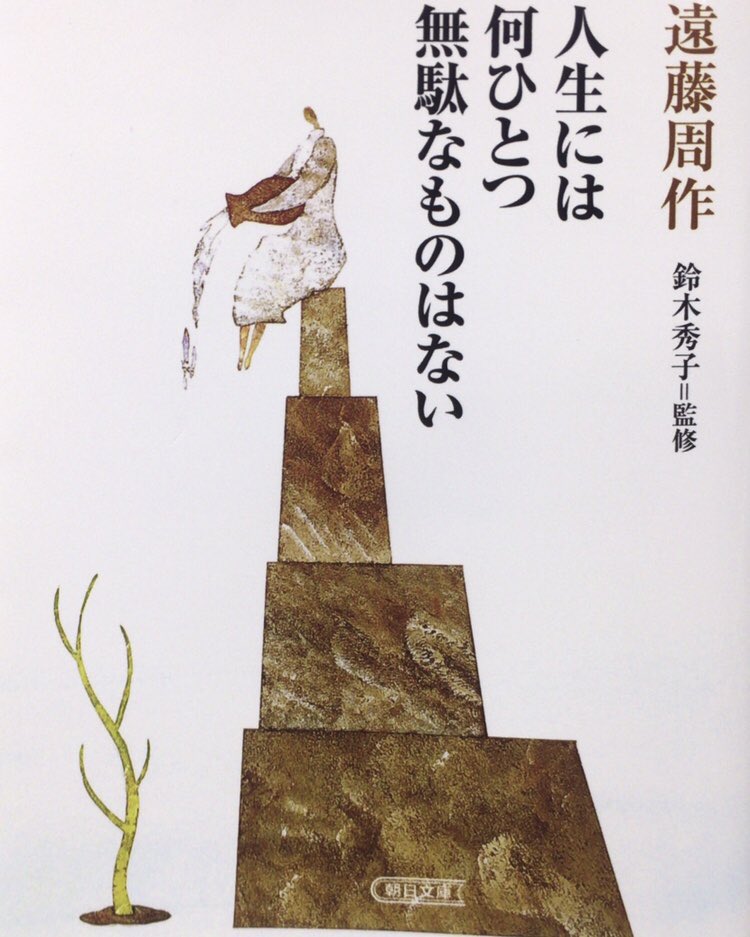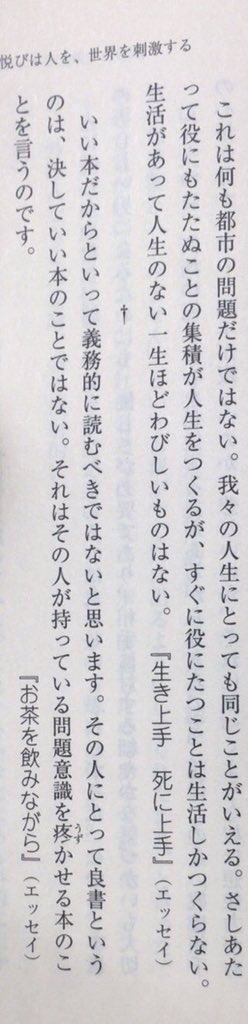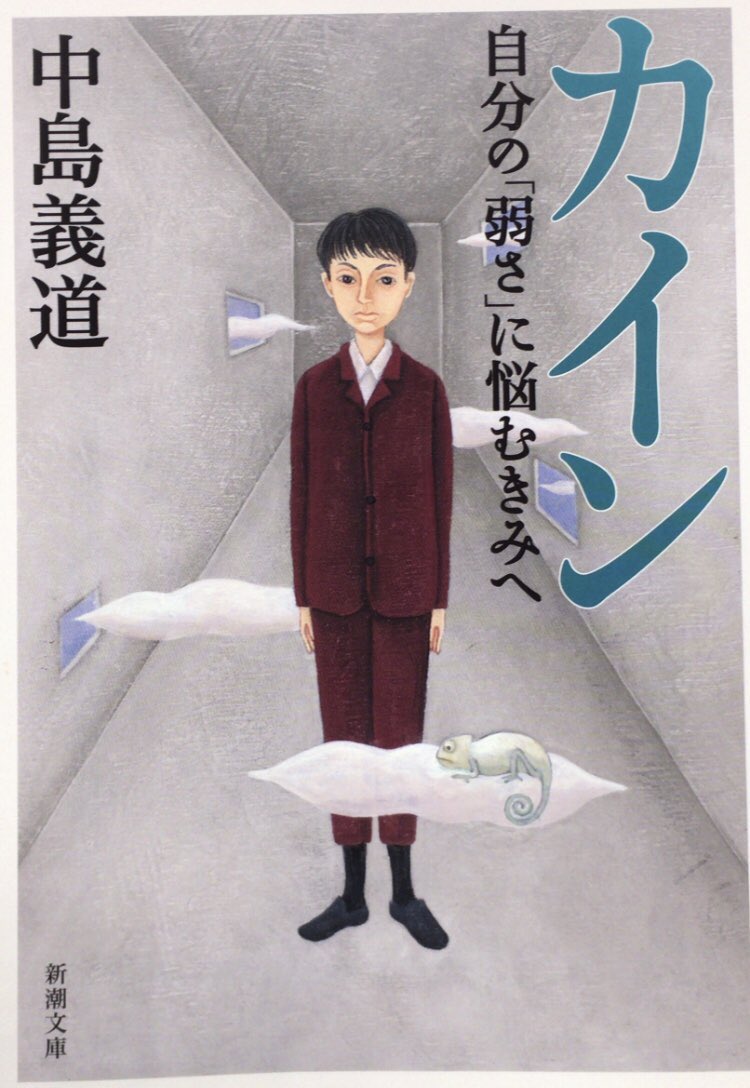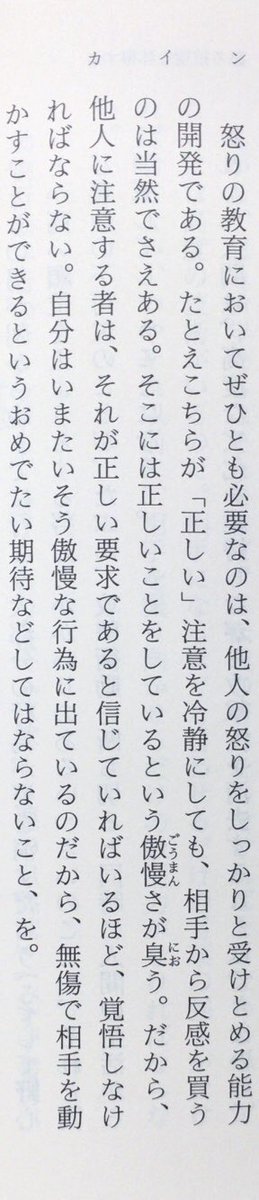626
627
628
629
630
631
633
634
635
636
637
638
640
641
642
643
政府や社会問題に対して批判を行ったときに、「なにもそこまで言わなくても。大袈裟だねー」と水を差してくる人がいる。だが、「大袈裟」とは言えなくなった段階で批判をはじめても、それはもう手遅れである。
644
645
646
647
648
649
650