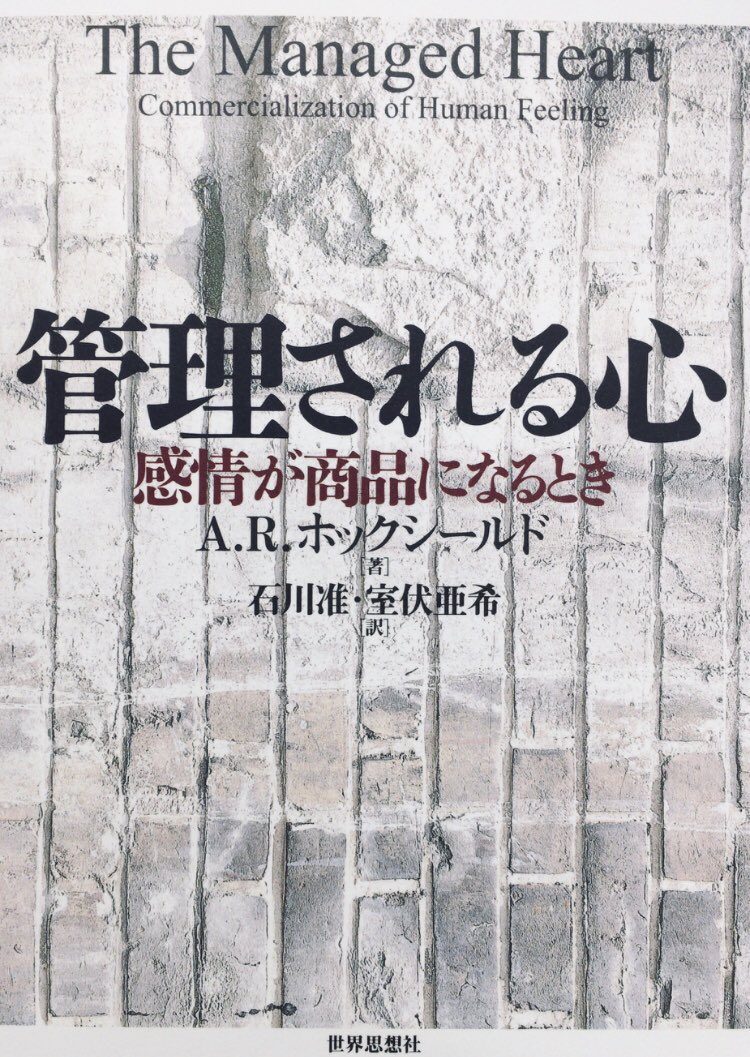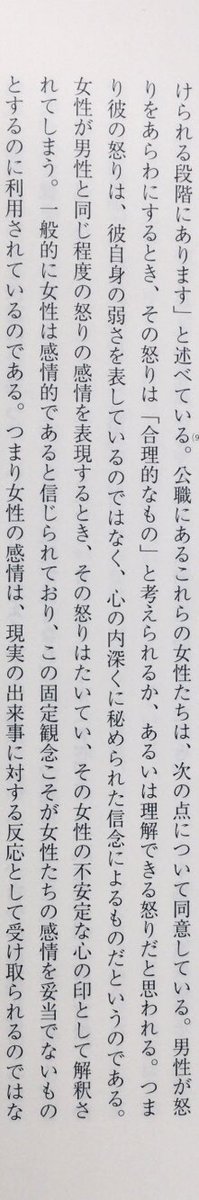601
602
603
604
605
606
607
609
610
「苦しんでいる者に対する直接の愛の奉仕と、苦しみの共通の原因である迷いの根絶とに向けられる活動こそ、人間の直面する唯一の喜ばしい仕事であり、それが人間の生命の存する、奪われることのない幸福を与えてくれるのである」(トルストイ『人生論』新潮文庫、P244~245)
note.com/honnoinosisi55…
611
612
615
616
617
ある科目を「役立つ/役立たない」の二分法で語りたがる人は、"誰にとって"そうなのかを示さず、曖昧にすることが多い。大概は、発言者一人の人生経験を指標にして、役立つか役立たないかを語っているにすぎない。これに対しては「あなたはそうだったんですねー」という感想しかでてこない。
618
619
620
622
623
624
625
「どちらの立場が正しいのかも考えず「なにもせずに正しい人」になろうとすると「どちらの側にも問題がある」と言いがちになります。やりとりの順番などに気をつけて、どちらが正しいのかを考えよう。」(『10代から知っておきたい あなたを閉じこめる「ずるい言葉」』WAVE出版、P29)
#ことばの日