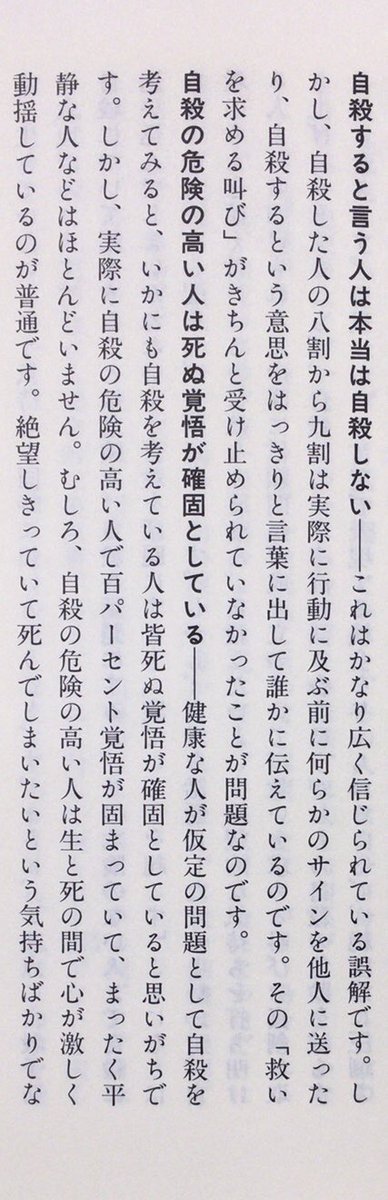551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
567
568
569
570
571
572
573
574
575