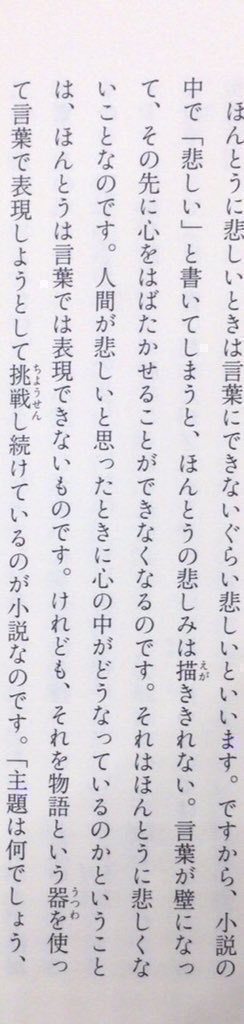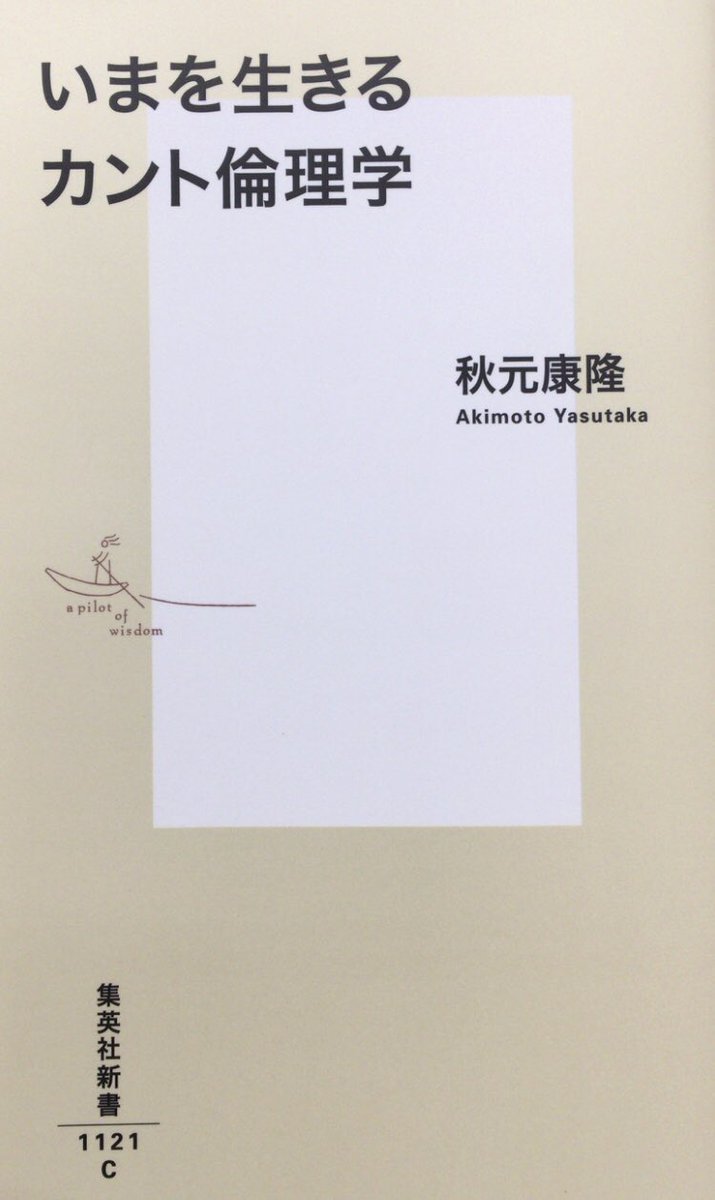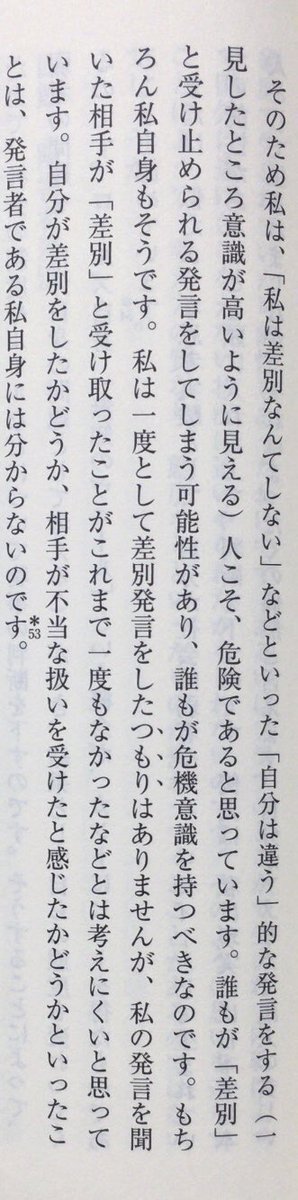502
503
504
505
507
508
509
510
511
512
513
514
516
517
518
519
520
521
522
523
525