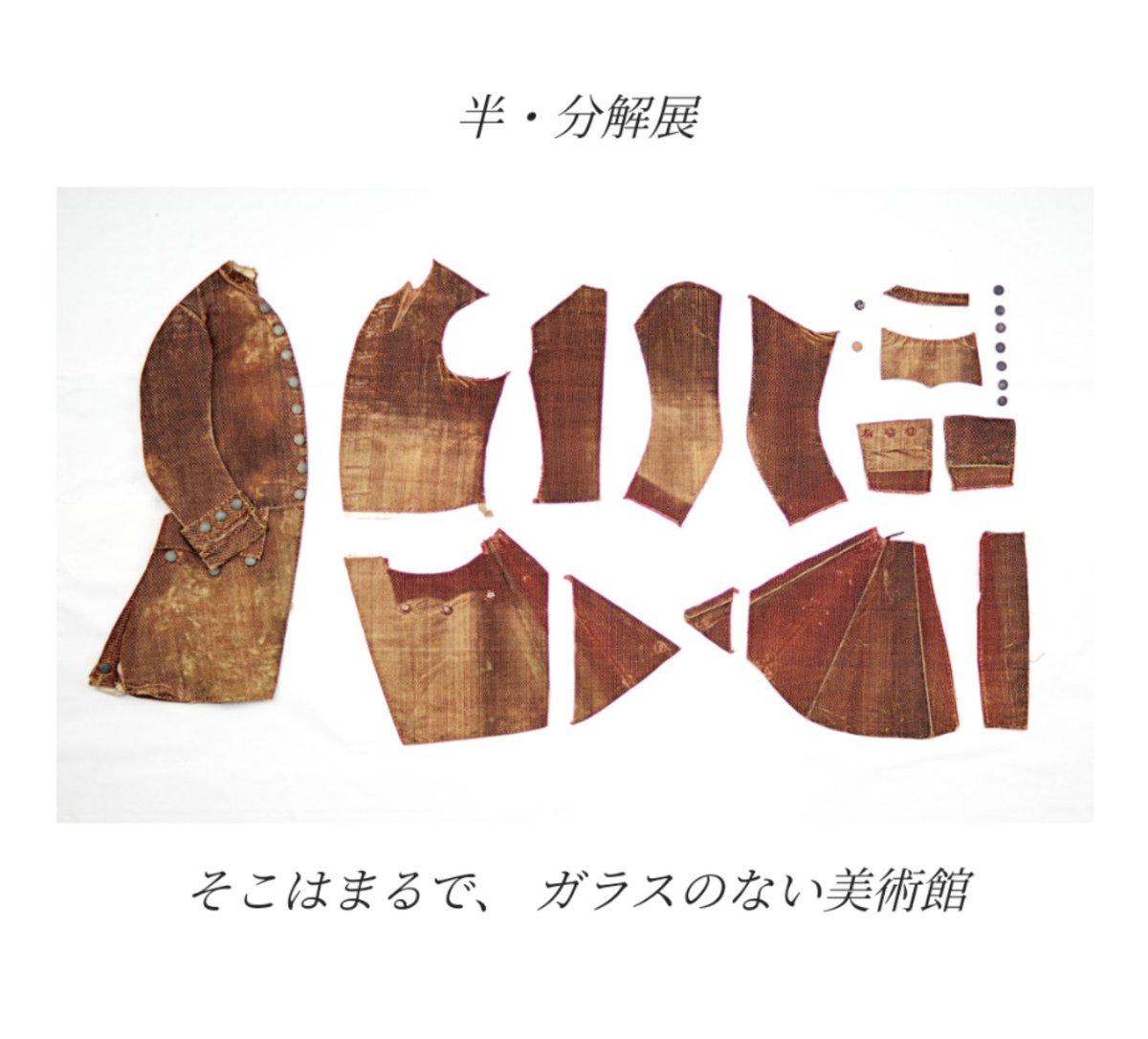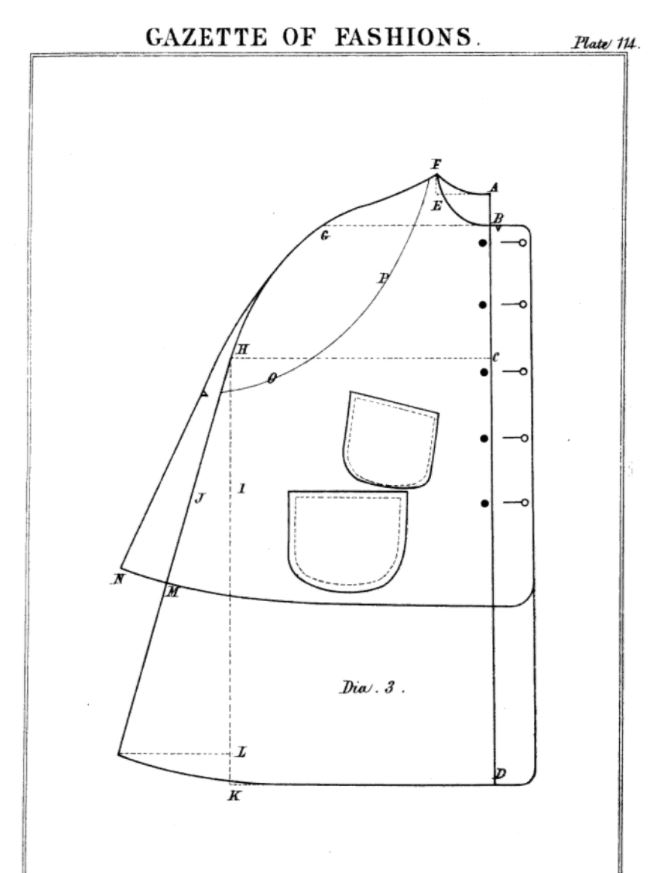576
577
これらの試着サンプルは、私が所有する100年、200年前の衣服を分解し、製作したものです
その当時の着心地を、ありのままに味わうことができます
自宅にいながらフランス革命の着心地を疑似体験してみませんか
詳細は、固定tweetの動画をご覧ください
#おうち時間
578
579
580
【 A4サイズに対応した書留鞄 】をつくってみました
以前、大好評だった 昭和40年代の書留鞄 を大きくしてみたのです
大きくしてもやっぱり可愛いフォルムをしています
こちらの型紙もBASEで販売しております
割引きクーポンも発行したので、この機会にいかがでしょうか
rrr129demi.official.ec
581
582
今週末11日(日)まで【半・分解展の型紙】を販売しております
新たに「メルカリ」や「ラクマ」での決済を導入しました
余ったポイントで型紙を購入し、こだわりの一着を縫ってみては如何でしょうか
徐々に秋冬物が着られる気温になってきましたね🧥
rrr129annex.blogspot.com
583
584
585
586
587
当時、フットマンの水分補給といえば「ビール」でした
まさか生水を飲むという選択は、腹下しと背中合わせの行為です
きっちり仕事するためにもアルコールで消毒された液体でなければいけなかったのです
(きっちり仕事できたのは、ごく少数のフットマンのようですが...) twitter.com/rrr00129/statu…
588
589
590
最後に、プロのパタンナーでもあり、縫製士でもある私からMノッチを構造的に言わせると
【めちゃくちゃ縫いにくいのでマジ止めてほしいです】
普通に返そうとしたら、縫い代が地獄です
実物は後乗せ、手まつりが基本です
よって現代の生産システムでは確実に事故る仕様です
デザイナーたち止めろよ
591
593
594
595
596
明日3日(土)は【 器 】がオープンします
器とは、毎月第一土曜日に渋谷にオープンする小さなコンセプトショップです
今回は「十九世紀の着心地」をテーマに、展示や販売をいたします
器は入場無料ですので、渋谷にお越しの際は覗いてみてください
器の詳細は↓
sites.google.com/view/dd-utsuwa…
597
ヴィクトリアン時代の特殊な上着「ヴィジット」をYoutubeで解説しております
画像では伝えきれない、複雑な構造を「動画」でご覧ください
ヴィジットを製作する方には、ぜひ見ていただきたい解説動画です
下記リンクよりご視聴ください
youtu.be/q557h1DRNeM
598
本日24日16時より
【半・分解展 大阪】スタートです
バチバチに仕上げてきました
どうぞご期待ください
半・分解展HP ↓
sites.google.com/view/demi-deco…
599
600