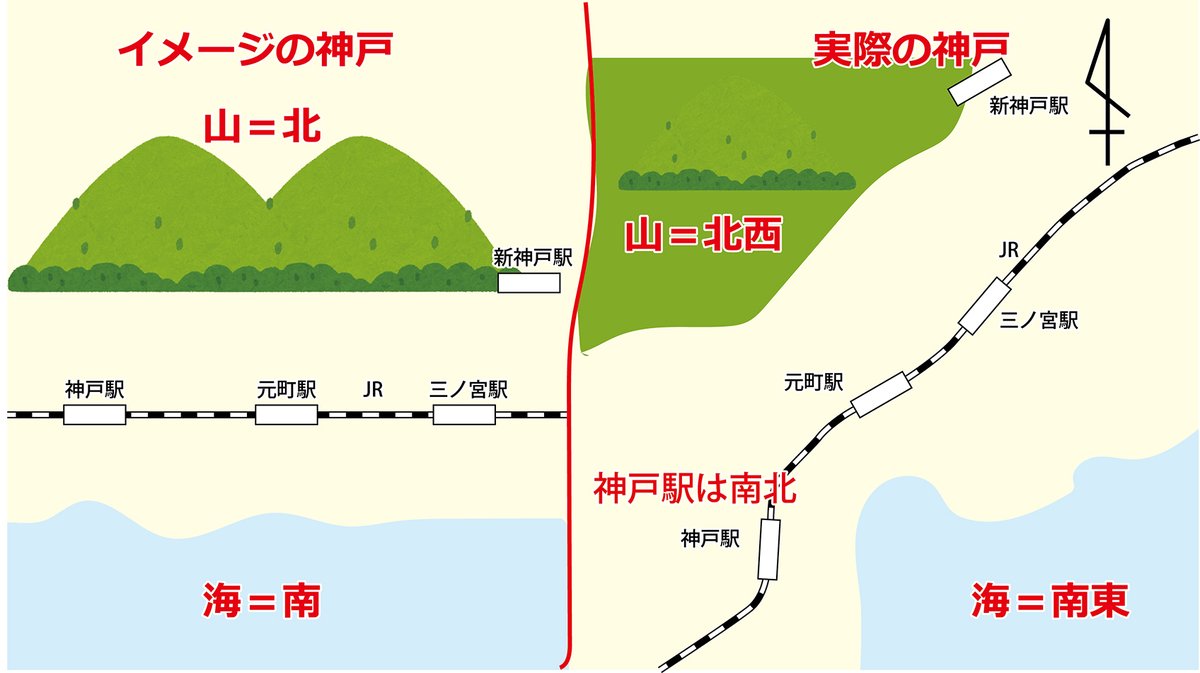28
29
31
34
新幹線運休の修学旅行生
↓
宿確保で狂喜乱舞
その影には旅行会社のサポートと推察
様々な団体を扱っているので、大手旅行会社はキャンセルでお困りの宿と途方に暮れた団体を格安で繋げられるのです
修学旅行代が高いとお怒りの保護者様、こういう事があるので、旅行会社にお願いが安心なのです
42
ご家庭に詰まれていく駅弁容器
捨てるにはもったいないけど、容器活用の出番は極小
でも、おいしいので増殖していく二大巨頭
#駅弁の日
←関東のご家庭 関西のご家庭→
43
お正月「お雑煮マップ」
昨年のコメントをもとに加筆修正しました
マップは代表例で,各地域や家庭でそれぞれ食されます
それが地域特性や家族の文脈ふまえた地理空間
妻の実家で”白みそお雑煮からお餅を出してわざわざきな粉につける”謎のお雑煮を食べてきます
#わが家のお雑煮 ぜひご紹介ください
46
49
50