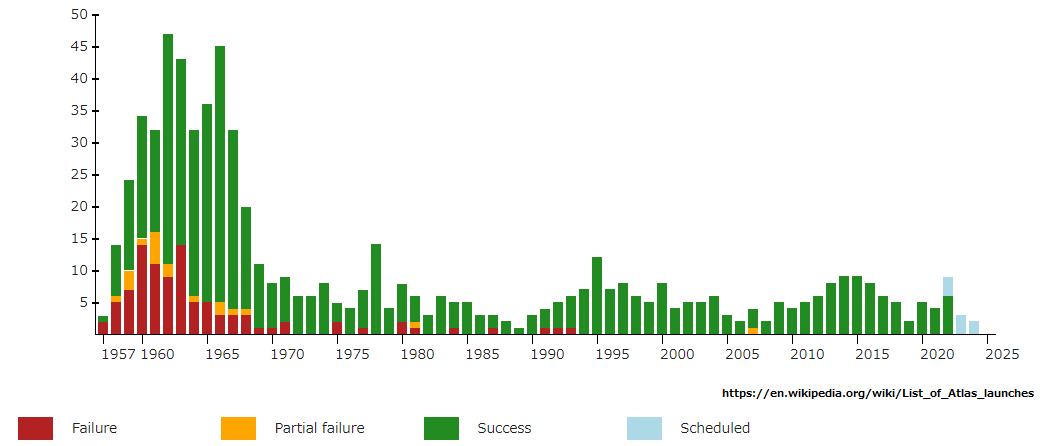851
ブラックホールのシルエットは、つぶれたお饅頭になると想像されていましたが、いて座A*は真上から見たと考えられているM87と同じドーナツの形です。回転速度や傾きが違うと、ドップラー効果や空間のゆがみで、シルエットが非対称になったり浮き上がったりするはずですが、なぜ似ているのでしょう? twitter.com/ESO/status/152…
852
こちらはトイレットペーパーの芯を使ったものです。プリングルスやチップスターの筒でもよいかもしれません。クッキングシートは破れないように注意してください。
853
今日の午後2時(日本時間)、いよいよヘルクレス座τ (タウ)流星群が北アメリカでピークを迎えます!これはもし流星雨となった場合にサンフランシスコから見た様子です (ステラナビゲータでシミュレーション)。朝日新聞がハワイに設置しているカメラでは、日没の頃がピークです。youtube.com/watch?v=eH90mZ…
854
2020年12月17日18時過ぎに、平塚の自宅から望遠レンズで撮影した木星(右下)と土星(左上)です。互いの月たちが一つの視野に収まりました。木星は左上から順に、カリスト、木星、イオ、エウロパ、ガニメデが並んでいます。土星のすぐ近くにいるのはタイタンです。木星と土星の最接近は12月21日です。
855
ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の主鏡に、微小隕石がぶつかったようです。大きなダメージはない一方、検出可能な影響があり、想定より劣化が早いようです。L2点では人工物ではなく散在流星だと思われます。既知の流星群には光学系の向きを変える必要があるのかもしれませんね。blogs.nasa.gov/webb/2022/06/0…
856
習志野隕石の3つ目の破片が発見されました!スーパーの駐車場屋上で見つかったそうで、重さは15g程と小さいです。他の破片と形が合う部分はなく、独立したもののようです。まだ大きな破片が眠っている可能性がありますが、コロナが感染拡大している今、捜索は避けましょう。 prtimes.jp/main/html/rd/p…
857
NASAのDARTの小惑星衝突実験が成功したようです!小惑星ディディモスを回る衛星ディモルフォスに秒速6kmの猛スピードでぶつかり、予定ではディモルフォスの公転周期が1分程短くなったはずです。あの歴史的なレインジャーの月面衝突を生で見ているようで、ドキドキしました。
youtube.com/watch?v=-6Z1E0…
858
859
2020年12月3日18時2分に流れた火球を、富士から南西の空に向けた広角カメラで見た様子です。途中で屋根に隠れました。散在流星の火球でした。右側に並んでいる明るい星は、木星と土星です。かなり近づいてきましたね。
860
2020年3月20日18時55分に流れた火球を、平塚から北の空に向けた広角カメラで見た様子です。末端で明るく爆発し、分裂したようです。
861
小型衛星LICIACubeがDART衝突を捉えた画像が公開され、さっそくタイムラプスにしてみました。Deep Impactやはやぶさ2で発生したエジェクタプルームが見当たらず、ニューロンのような模様が広がっています。ラブルパイル構造が壊され、小惑星そのものが破壊されたのでしょうか?asi.it/2022/09/liciac…
862
863
今日は国際宇宙ステーション(ISS)の月面通過の撮影に挑戦しました。2020年4月2日21時11分3秒に富士川河口から見た、ISSの月面通過(1/5倍速)です。風が強くてブレブレでしたが、ぼんやりとISSのシルエットがわかりました。
864
こちらは2023年3月16日18時54分から55分に、富士から別の広角カメラで撮影した様子(5倍速)です。右上から左下に進む光は飛行機で、ISSとカーゴドラゴンは左上から右下に進んでいます。カーゴドラゴンは最大5回の再利用が可能で、今回で3回目のフライトです。
865
先日、流星カメラに面白い人工衛星が写っていました。2020年6月28日21時37分に富士から望遠カメラで撮影したドイツのトマト栽培衛星「Eu:CROPIS」です。スピンして月や火星の重力環境を模擬する、ISSで日本が作るはずだったセントリフュージの小型衛星版です。回転に伴い点滅しているのがわかります。
866
2019年11月21日3時49分に流れたしし座流星群の火球を、平塚から南の高い空に向けた広角カメラで見た様子です。流星痕が残りました。
867
2021年6月10日20時17分45秒に流れた明るい流星を、富士から北の高い空に向けた広角カメラで見た様子です。火球と呼べるほど明るくはありませんでしたが、多くの方が目撃したようです。散在流星でした。視野の真ん中に見えるのは北斗七星です。
868
今日は東富士演習場の演習があり、平塚市内は重点音が響いていました。これは2021年5月8日20時過ぎに、富士から北東の空に向けた広角カメラで見た様子です。空が赤く照らされていました。
869
870
871
エルブスも落雷と同時に発生する発光現象で、ドーナツのようなリング状の光ができます。これは2021年5月2日23時17分18秒に発生したエルブスを、平塚の自宅から南東に向けたカメラで撮影したものです。スプライトと同時に発生しました。
872
2021年3月14日2時47分に流れた火球を、富士から南東の空に向けた広角カメラで見た様子です。
873