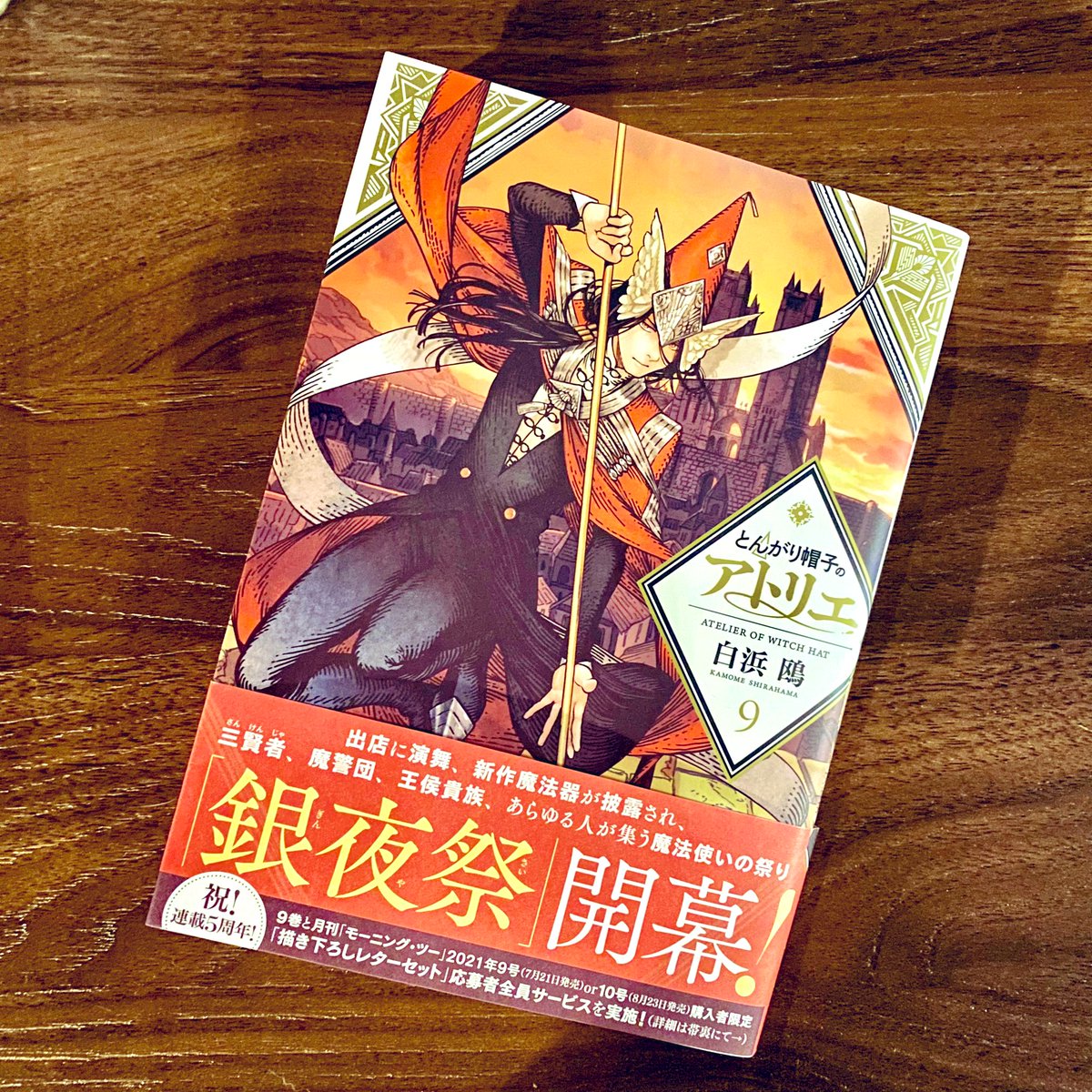26
「分断を許さない」「対立をやめよう」って、ぜひ分断や対立という構造を生み出している側に向かって大きな声で言ってください。分断も対立も、権威が生み出した構造です。それに抗う人たちに向かって「やめよう」と言うのは、「黙れ、服従しろ」と同義です。
27
10代で奨学金「借りる」時に「これは奨学金ではありません。ローンです。あなたはたった今から何百万円もの借金を背負います。卒業して就職できるか不明、就職しても充分なお給料がもらえない可能性も。返せなくなっても助けはありません。これはただの借金です」って説明された人少ないんじゃないかな
28
女性だからって水餃子の半分野菜にされたツイート同じ経験山ほどあるから共感して読んだけど、個人的に最悪の経験は海鮮系の食堂に入って日替わり定食(煮魚と刺身)頼んだら勝手にサラダ目玉焼きパンコーンスープにされたことかな。見た目「外人」だから魚もご飯も苦手だろうって「配慮」だったらしい
29
ひどいことを言ってくる人に、同じようにひどい言葉を返したくなる。でも、それでは同じ土俵に上ることになると、ぐっと堪え、相手を傷つけないように貶めないようにと、丁寧な言葉で返す。そうすると相手は、ますます大きな声でもっとひどいことを言ってくる。叩いてくる。その繰り返しだった
30
むすめ氏が高校からもらってきたお便り。「新学期なんて怖くない!高校での友達の作り方」と題した記事の中に「話しかけられる努力をする」「キャラがわからない子が一番からみにくい」とあって高校生のリアル生きづらさに震えてる。こんなん書かれたら余計に新学期怖くなるよなぁ
31
なんじゃこりゃ。DV・虐待被害者が情報非開示の届出をしないと加害者に情報閲覧される可能性あります。でも届出をしたらマイナンバーカードを保険証として使えなくなります。ってめちゃくちゃにも程がある。しかも保険証廃止してマイナカードにとか言ってなかった?ダメダメじゃないか… twitter.com/bookskuryudo/s…
32
炎天下でマスクつけた子どもに妖怪の絵を描かせる学校も、それを批判的に報じられないメディアも、どっちも終わってる。 twitter.com/nhk_news/statu…
33
容姿や体型にまつわること
性差によるステレオタイプなジャッジ
相手を「いじる」こと
それらができなくなると「何も言えなくなる」と思うなら、それは「社会が窮屈になった」のではなく、「あなたの世界がそもそも狭かった」のだと思う。誰かの痛みの上に築いた狭い王国で横暴に振る舞っていただけ
34
「親が嫌いです」という子がいる。親は「反抗期で」「思春期で難しい時期なんです」と言う。子どもたちからよくよく話を聞くと「そりゃ嫌いになって当然だわ」ということを言われたりされたりしている。それを親に伝えると「親子なんだからそのくらい許される」と思ってることがわかる。親子、反抗期、
35
女の子は「(男の子に比べて)早熟だ」とされて、学校で「世話係・雑用係」を担わせられることがまだまだある。女子は頼りになる、しっかりしてる、そんな風に持ち上げながら大人のサポート役を任せる。だけどもう一方で「女の子」は無知で経験不足のラベルにされて、搾取の対象になる。おかしい
36
たまに「こども食堂で子どもたちに○○の話をさせてほしい」という要望が届く。海外ボランティアの経験とか食育の話とか。他には歌を歌ってあげたいとか。「いいですよ、でもうちはどう過ごすかを子どもたち自身が決めるので、大人が『さあ話を聴きましょう』と指示しないし特別な時間は設けません→
37
障害は個性、不登校は不幸じゃない。現場でもそんな言葉が聞かれる。その個性や「不幸じゃない」の中身を尋ねると、絵が得意だからアートで活躍してほしいとかプログラミングが好きだからその道に進んでほしいというような願いが(大人から)語られる。「社会の評価」から抜けられない息苦しさを感じる
38
「日本に人種差別はない」と言う人に出会うたび、「ガイジン」「バイキン」「日本から出て行け」と言われ学校でいじめられたかつての私が「いじめられたのはお前に何か非があるからだ」と言われているような気がして、胸がひどく痛む。今でも。
39
性的同意について少しずつだけれど学校の性教育の中で触れられるようになってきた。けれど学校では「嫌だけど嫌と言わせない」がありふれてる。日常的に様々な場面で「嫌だけど嫌と言わせない」を生徒たちに強いておきながら性に関することだけ「同意を大切に」と言っても、難しいよね
40
そうすると、彼らは尋ねてくれる。貧困や格差をなくすために私たちに何ができますかと。答えはいつも同じ。
「18歳になったら、必ず選挙に行きましょう」
41
夜7時まで遊んでいたその子には家に居づらい、安全でない、ひとりぼっち等の事情があるのかもしれません。ガツンと叱れば公園という逃げ場所を失うことになるかもしれません。もし見かけたら「どうしたの」と声かけ、あるいは警察等に「相談」をお願いしたいです。それが教育であり福祉だと思います twitter.com/senseiwakame/s…
42
ありがとう、の言葉が自分を助ける。笑顔が自分を助ける。努力が、自分を助ける。それはひとつの事実。否定はしない。でも「困窮しハンデを負うほどに努力や感謝の姿勢を要求される」という不均衡については、どう頑張っても筋の通る理由を捻り出せない。今もまだ。
43
44
なんというか。アーティストの性犯罪にまつわる同様の事案と展開は多々あったけれど、久しぶりに、すごく久しぶりに、というか初めてなくらい、関係者によるとても真っ当で優しくて「逃げ」の一切ない説明を読んだ気がする。私はアクタージュ大大ファンだったけれど、その想いを弔ってもらえた気がする twitter.com/uszksr/status/…
45
「困った時に助けてくれる人」とのつながりは大切だけど「困った時に助けてもらうためにつながりをつくる」のは苦しかったり、時に自分の中の何かが損なわれてしまったりする。つながりなくても困らない、なんとかなる、生きていける、その土台がほしい。それが福祉のはず
46
「こども庁」という名称は「家庭から独立した、個としてのあなたを守り尊重します」という子どもたちへの力強いメッセージだったはず。それがすっかり損なわれる名称変更に失望する。「伝統的家族観」なんてものは子どもを暴力や搾取から守ってくれやしない。どこ向いてるの? nordot.app/84341397947827…
47
今までろくに関心を向けてこなかった事柄に対して、その事柄に「無関係でいられる特権」を持つ人が、突然「そのやり方じゃ理解されませんよ」「アップデートしましょう」と言い出す。そうやって当事者の、現場の声が軽んじられ捻じ曲げられ続けてるんですよ
48
もちろん女→男の加害もある。男→男も、女→女も。「被害に遭わない」教育は「加害しない」教育でもある。「何がいけないか」の軸は同じだから。でも男→女の加害が圧倒的多数な現状なのに女の子サイドへの教育の熱量が男の子サイドへのそれを上回ってる不均衡はなんとかならんものかな、ということ
49
zoom会議で「逆境乗り越えて活躍する物語の危うさ」について話してるのを横で聞いてた娘氏「みんな逆境を乗り越えて活躍する物語好きだけど、逆転話が人気なのはレアだからだよね。ありふれてたら人気出ない。そのレアケースを一般化しちゃって今苦しんでる人たちを追い詰めるの、相当身勝手だと思う」
50
構造的に差別/搾取されている側が抵抗する時に権威を持つ側を脅かさない・怒らせない・不快にさせない物言いを当然のように要求されるの、ほんとしんどい。穏やかに「やめてください」と99回言っても通じなければ100回目にはブチギレる。でも権威側には最後の1回しか聞こえず「やりすぎ」と責められる