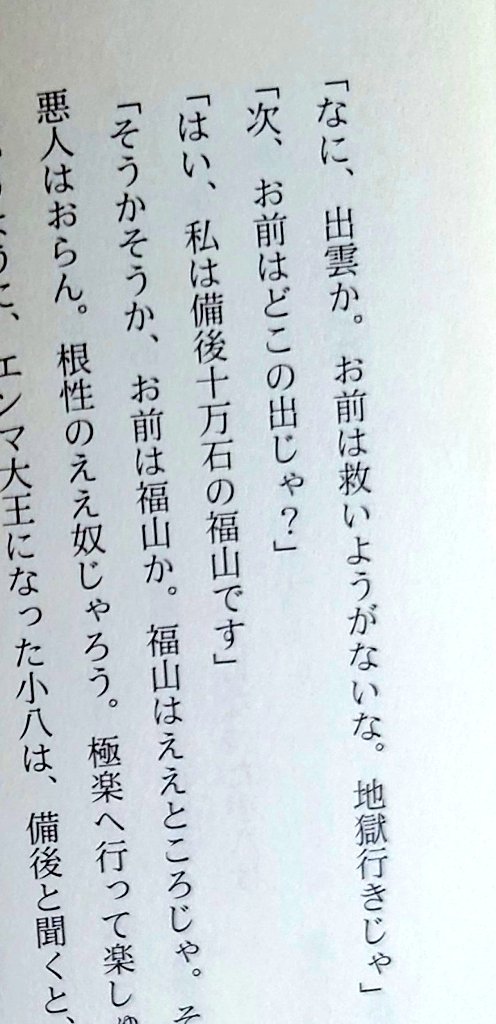1251
ホームボタン押すとおすすめになるのやめろって書かれた木簡が平城京の二条大路から見つかったらしい
1252
1253
江戸深川の某寺院の堀は酔っ払った金ちゃんという大工だかが溺れて死んだのでそこの部分だけ金ちゃん堀って名付けられてた、と明治生まれの老僧にお聞きしたことがあるので溺れた人の名前付けるのはわりとポプュラーなのかもしれない。なおその堀は関東大震災と東京大空襲などを経て今は現存しない。
1254
ブッダが生まれた時にすぐ七歩歩いて天上天下唯我独尊と言ったとあるが、日本書紀で木花咲耶姫が火の中で3人の子を出産する所の一書(異伝)だと3人とも 産まれたら足を踏み鳴らして威勢良く「吾は天津神の子なり、我が父は何処に居られるか」と名乗りを上げるので我が国も負けてないぜ
1255
製鉄神である天目一箇命を祀る神社があるとされる地をGoogleMapで見ても神社は無いので合祀されたか元々無いのか、載らないほどの小祠なのかと思ってたら近くに鞴(ふいご)橋とか製鉄由来じゃんって名前のもの見つけてぜってーあるわ神社ってなったので探しにいきたい。地図見てるだけで楽しい
1256
トーハクの国宝展、予約制だし今月どっかで見に行こうかなって思ってチケット予約のサイト見たらほぼ全日完売してて怖すぎて泣いちゃった…
1257
毎年この日になると神武天皇の話題になりますが、日本書紀の天武天皇元年に「神武天皇の御陵に馬とか武器とかお供えした」とあり、書紀の(ある程度)信頼できる歴史区分に類する記事の時点で既に神武天皇のお墓とされる物は存在したので当時から始祖王としての神武天皇という存在は認知されてたと思う
1258
ごまかしというか、民俗学に於いてはケガレとは何か(ハレ、ケ、ケガレについての論)という議論の中でケガレ=ケ(日常のエネルギー的な力)枯れであるという論説があり、それを神社が採用して説明している、というかんじです。歴史的にはそんな単純に説明できるもんでないとは私も思います。 twitter.com/senator_gs/sta…
1259
平家物語10話の「維盛、そなたのことも語ろうぞ」「語り継ぎたい」
というびわの言葉で、そうやって語り継がれて、語り紡がれ、愛され、この物語の人達が実は生きていてほしいという多くの願いの中で生まれてきたのが、俺が巡ってきた平家の落人伝承地だったのだな、ってのに繫がって泣いちゃったよね
1260
1262
1263
言い方悪いけど、今までありがとうございましたっつってツイートしてから死んでそれがRTされて広がってくの、呪いみたいなもんだよ
1264
神田古本まつり及び神保町ブックフェスティバルは欲しい本がピンポイントで買えるイベントではなく、欲しい本が際限なく増えていく祝祭
1265
1266
湯切りや湯立てには必ず密教の所作が入る。五大明王の印を組み九字を切るが臨兵闘者までの四字。この時、剣印を結び左の袖下に入れ
「此の御太刀と申すは三條小鍛冶宗近の打ちたる業物也、天を払えば天が切れる、地を払えば地が切れる」
と呪文を低く唱えて切る。三條宗近の宿る破邪の九字手刀だ!
1268
ていうか今更気付いたがそもそも出産や生理を穢れとして嫌い産後の母親は忌明けを待たねばお宮参りできなかった神社が母親の体内を表わすってのもおかしな話やね
1269
熱田神宮は古代から神剣を祀る大社で私も何度も参拝しているが、近代になって伊勢と同格になろうとして政治的に作動したり、社殿を伊勢と同じ神明造りに建て替えたりした辺りの動きとか大変に面白くてそこらへんもっと調べたい、と思って数年経つ。
1270
親孝行したい時に親はいないし給油したい時にガソリンスタンドは進行方向にはなくて反対車線にばっかある
1271
伏見稲荷は下の方は表の顔っていうかなんつーかキレイキレイな表面上みたいなかんじなので…真の姿は上の方なので…稲荷山の上の方はそんなに人おらんでええで。
あと伏見稲荷も清水寺も早朝行くといいですよ人少なくて。
1272
1273
我が国には「福子」の信仰というものがあったという説がある。障害を持った人を異能の存在、神の子、福神などとして丁重に扱うというものである。この説には手厳しく批判もあるようで、そのような考え方が一部でも本当にあったかはわからぬが、実際に仙台四郎や権さんのような存在が居たのは確かである
1274
1275
ニホンオオカミを大口真神と呼び神使眷属、あるいは神そのものとして信仰するのは関東では三峰神社、両神神社、宝登山神社、武蔵御嶽神社など。西の方では岡山の木野山神社、貴布禰神社などが著名です。