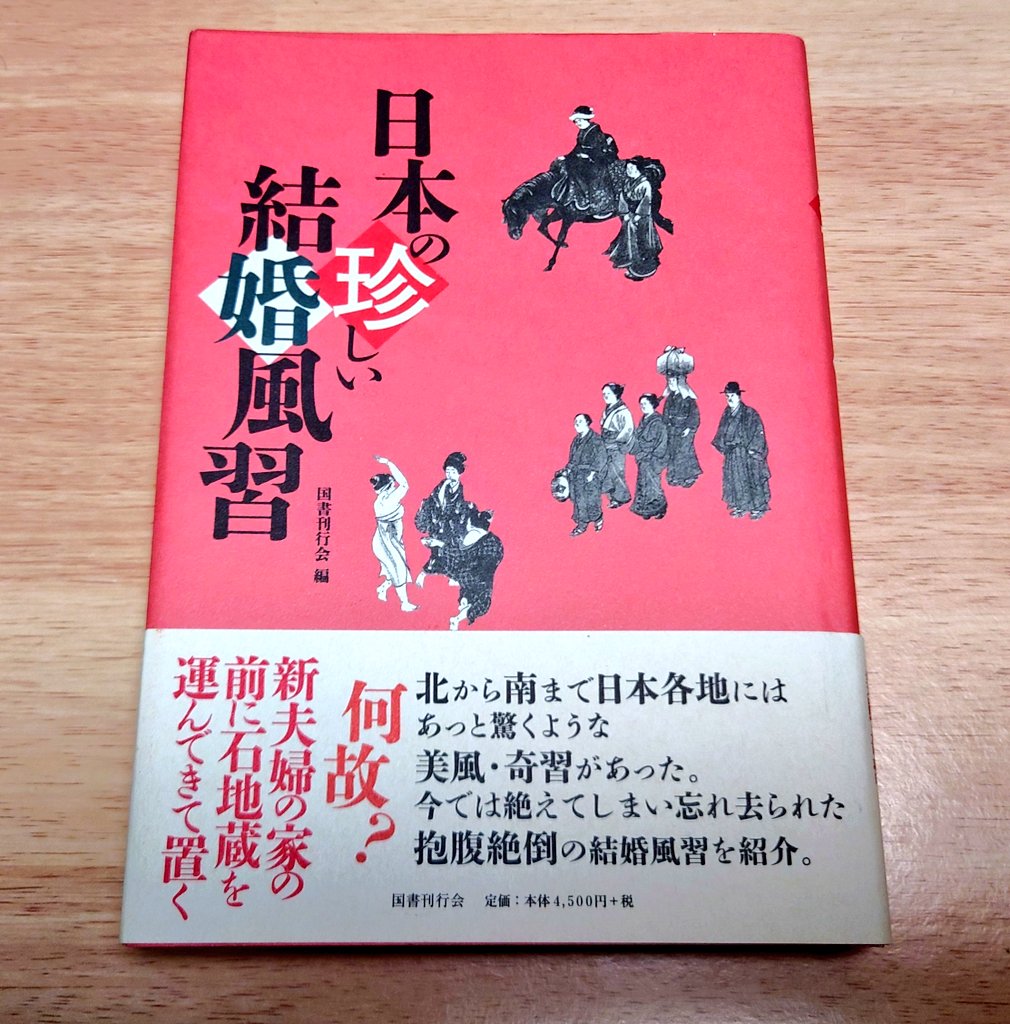476
477
478
479
中の遺体はどうなったのか、という引用等来てますが、日本は湿度高いし酸性の土壌で、雨が石室内に侵入して遺体を浸したりするとすぐ腐敗して骨も分解するそうなので多分100年も経てば土になってる。エジプトとかとは環境が違うんじゃないかな、ってかんじのことを学芸員さんに昔聞きました twitter.com/goshuinchou/st…
480
鷺舞は山口に伝わり山口から津和野へも移入された。その後オリジナルの京都祇園の鷺舞は衰微廃絶した。逆に昭和になってから津和野から京都へ伝え返した。中央で失われた貴重な文化が地方で命脈を保つ。文化芸能ではよくある話。午後3時から弥栄神社と御旅所、街中各11箇所を回り2時間ほどで舞い唄う。
481
着物は自由に着ていいと思うが左前はあかん、そこだけは守れって話。食い物を箸渡しで渡すくらいの禁忌。
482
当事者達はみんな消滅してるのに城という巨大な物体、塊はそこに有り続けて築城後の二百数十年後にしっかり機能したってのがとても良い。そしてせいしょこさんは神。
483
正道的な雨乞いの最大のやり方は、皆で山に登って頂上で薪を組んでめっちゃ火を燃やしながら鐘や太鼓を乱打しながら読経したり踊りを踊ったりするのが多かったそうで、新しいところでは昭和30年代くらいの山での雨乞いの記録が残っています。
485
486
地区の人の夢枕にこの神像が出てきて自分を祀れって告げたのでそのようにしたら豊漁になったのでこの場所にお堂を建てる次のステップに期待。
488
日本ではそのスニーカーいいねって声をかけられないというツイが賛否共々話題ですが、バイクで長旅とかしてると多分昔乗ってただろうおじさんやおじいさんにそのバイクいいねどっから来たの?と自分の若い頃への郷愁を帯びながら声をかけられる事が多々あり間違いなく俺もそういう老人になる自信がある
489
伝承や祭礼とか民俗関係の細かい情報なんかをネットで得ようとしても全く出てこないのが当たり前なので、ネットがあれば本はいらないとかの言説に対しては寝言言ってんじゃねーぞ京極夏彦のレンガ本で殴るぞって感じだ
490
【定期】私はポムポムプリンが好きなおっさんですがポムポムプリンは毎年8月15日の終戦記念日にふんわりとしたそういうメッセージを上げるのでさらに好きです
492
節分の夜に辻に物を置いて振り返らずに(この時に誰にも見られずに、喋ってはいけない、などの禁忌が併存)帰ってくる風習、辻参り等と呼ばれ今も南予などでは履物を交差点に脱ぎ捨てるというのをやってる所がある。江戸時代の記録では履いたふんどしを辻に置いてきた松山藩士の日記が残っている。
494
495
496
このページ、狸についての情報を語ってる記事なのにイメージ画像が大体アライグマなので趣がある
monamona2525.com/archives/74932
497
最近知ったんですけど、京都の城南宮の夏越の祓は自動車用の巨大な茅の輪があって車ごと茅の輪くぐれるんですよ。交通安全のお祓いも受けられる。バイクも大丈夫なんだろうか。愛車でくぐりたいな。今年も7月1日から一週間受け付けるようです。
kyoto-np.co.jp/ud/events/642f…
498
499
500
子ぅ取り婆、という子供をさらう妖怪が香川の西の方に伝えられてるんだが、明治6年に西讃 の4万人の百姓が起こした血税一揆という大暴動があり、溜まっていた新政府への不満が暴発して軍隊に鎮圧され死者多数出したんだが、これが起こった直接原因が子ぅ取り婆に子供がさらわれたという流言かららしい