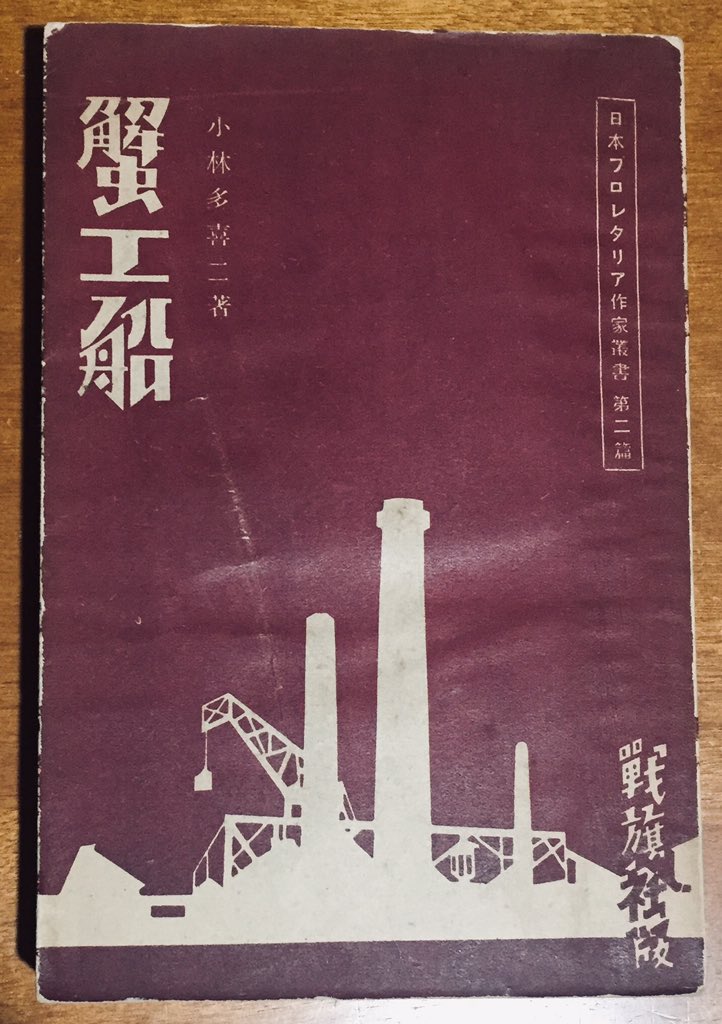26
近年よく耳にするのが作家の「モンスター遺族」の存在です。身内の作家を過剰に美化し、正当な批評にもクレームをつけ、研究者や出版社などが敬遠。結果として展覧会が見送られ、教科書に採録されず、新刊書店から消え、新しい読者が少なくなってしまうのに・・。最大の被害者は作家本人だと思います。
27
ある私立高校の教師をしている友人によると、彼の勤務校では2020年度から実施される「大学入学共通テスト」の国語(80~120字程度の記述式問題)対策として、来年度から新入生にツイッターを奨励し、かつ120字前後で呟くように指導するそうです。何かを根本的に間違えている気がします。
29
太宰治の長女である津島園子さんがお亡くなりになりました。平成27年に太宰治展を開催した折、事前に許可をお願いしたら(法的には不要)、喜んで快諾してくださいました。母の美知子さんの後を継ぎ、父の顕彰に努めた功績は大きかったと思います。ご冥福をお祈りいたします。
30
他人に理解されないと思い悩む時があったら、「我といふ 人の心は たゞひとり われより外に 知る人はなし」という歌を思い出してください。自分を知るのは自分だけ。理解されないのではなく、他人には理解できないものなのだと。少しは気が楽になるかもしれません。歌の作者は谷崎潤一郎です。
31
神田神保町名物T書店主の神回答(全て実話)
①「芥川龍之介とかの本はありますか?」「とかの本はない。」
②「司馬遼太郎の本はありますか?」「嫌いだから扱わない。」
③「太宰治の『人間失格』はありますか?」「三省堂にある。」
④「ガラスケースの本を見せて下さい。」「100万円。」
33
昔は「あー、啄木が死んだ年齢を超えてしまった」という感慨があり、その対象が中也になり、芥川になり、太宰になったものですが、漱石を超えたあたりからは何も考えなくなって、気がつけば朔太郎も超え、鷗外すら射程内に入りました。誠に少年老い易く学成り難しであります。
34
「森林太郎って誰ですか?」という記者の質問に学芸員は一瞬絶句したものの、「鷗外の原稿の多くは本名で書かれています。また永井荷風は鴎外全集ではなく森林太郎全集にしたかったそうです」と。見事な回答ですが、彼は荷風を知っていたのでしょうか。ちなみに彼の新聞に記事は掲載されませんでした。 twitter.com/signbonbon/sta…
35
ある有名な女優のマネージャーから連絡があり「○○が太宰治の大ファンで、彼のサイン本がほしいと言っている。あなたがたくさん持っていることは古本屋から聞いた。ついては○○の写真集のサイン本と交換してもらえないか」と。もちろん丁重にお断りしました。「正気ですか?」とは尋ねませんでした。
36
認知症の初版本コレクターが本を次々に破り始めたと家族から連絡があり、駆けつけると本やカバーが無残な姿であちこちに。本人は「誰がこんなことをしたんだ」と激怒しています。こっそり貴重書を選んで物置に避難させましたが、「あいつが盗んだ」と言われるかもしれません。何だか身につまされます。
37
某テレビ局の人に「小道具として使いたいので、復刻本でいいから『月に吠える』を貸してほしい」と頼まれ、言下に断りました。「復刻本ならばよかろう」とばかりの物言いに腹が立ったからです。書物に対する愛情のカケラもない者に貸す本は一冊も持っていません。
39
「これだから平成生まれは」とか「昭和は無理」と世代間ギャップに元号を用いるのは、別に目新しい表現ではありません。「明治ツ児と大正ツ児とでは感覚に大変な相違がある」と徳田秋聲も語っていますから。
40
今日は志賀直哉の命日ですが、没後50年の節目なのに、悲しいくらい話題になりません。志賀が最近大きく取り上げられたのは、新型コロナ関連での『流行感冒』くらいでしょう。読む人が減った上に、ある事情もあり、志賀をメインとする若手研究者は激減。初版本の価格も大暴落しました。本当に残念です。
41
「能力のある者は退社しろ、能力のない者は残れ」文藝春秋社が傾きかけた時の菊池寛の言葉です。能力のある者はどこでも働けるからでしたが、普通の経営者ならば逆でしょう。誰一人辞めなかったのは、こんな素晴らしいオーナーから離れたくなかったのだと思います。そして会社はすぐに立ち直りました。
42
芥川龍之介・中原中也・太宰治も愛した「ゴールデンバット」の終焉。「1日に芥川龍之介の墓を訪れてみると、花とともにやがて姿を消してゆく、ゴールデンバットが封が切られた状態で置かれていました」という感動的な画像とともに、芥川の映像も見られます。
www3.nhk.or.jp/news/html/2019…
44
芥川龍之介は海軍機関学校の教官時代「小説は人生にとって必要ですか?」と学生から質問され、「それなら君に聞くが、小説と戦争とどっちが人生にとって必要です?」と切り返し「戦争が人生にとって必要だと思うなら、これほど愚劣な人生観はない」と断じました。場所柄を弁えない勇気ある発言ですね。
45
明日の夕方、近代文学に関する重大発見のニュースが各メディアで流れるので、関心のある方はどうぞお楽しみに。
46
泉鏡花は森鷗外への追悼文の冒頭で、「先生と言はなければならないのでせうけれど、私には唯一人、紅葉先生がありますから、これは笑つて御免下さい、未だ嘗て誰方をも先生と呼んだことはありません」と断り、以後「森さん」「鷗外さん」で通しています。こういう鏡花がたまらなく好きです。
47
48
中学1年生の時、『太宰治全集』の「人間失格」を教室で読んでいると、担任の国語教師から「そんなものを読むと自殺したくなるぞ」と言われたので、「じゃあ、なんで図書室にあるんですか?」と尋ねたら凄い表情で睨まれました。「感想を聞かせてほしいな」と言ってくれる先生と巡り合いたかったです。
49
50
素晴らしい所が沢山あるのに、自信があまりにもない若者を数多く見てきました。謙虚であることは大切だし、自信過剰は感心しませんが、自分を過小評価するのも勿体ないです。だから新成人に、そして若い方々に、あえて谷崎潤一郎の「たとへ神に見放されても私は私自身を信じる」という言葉を贈ります。