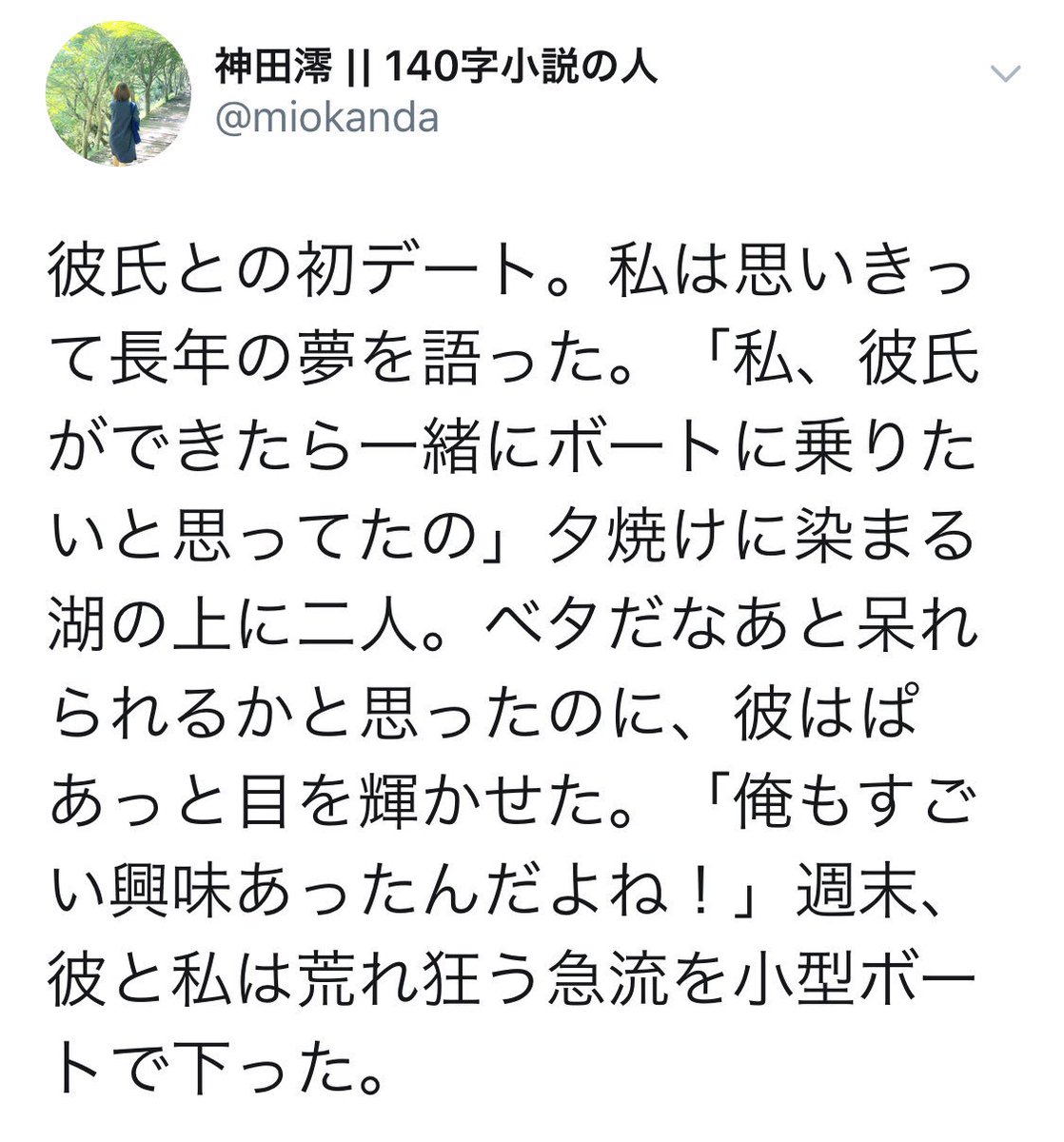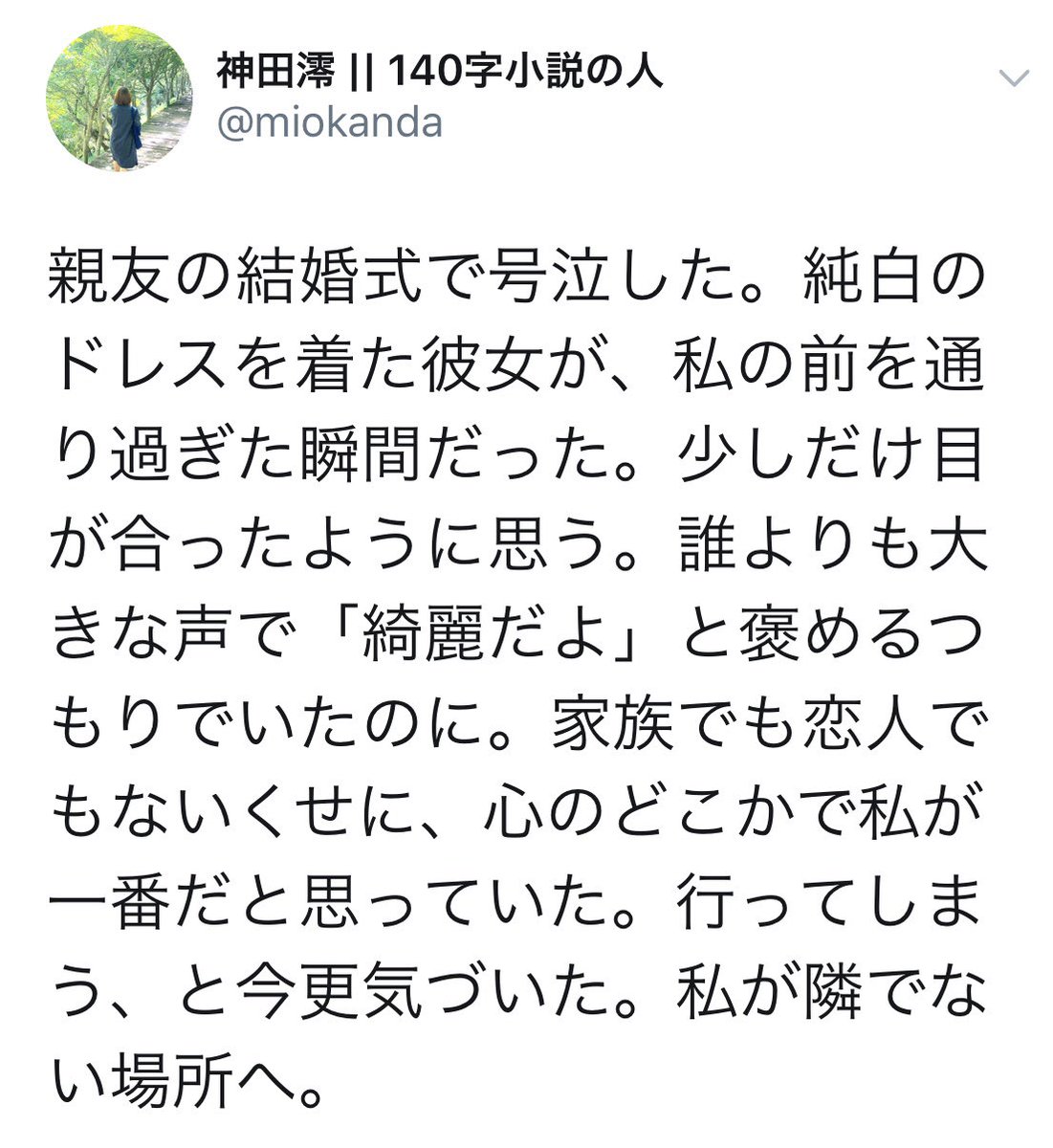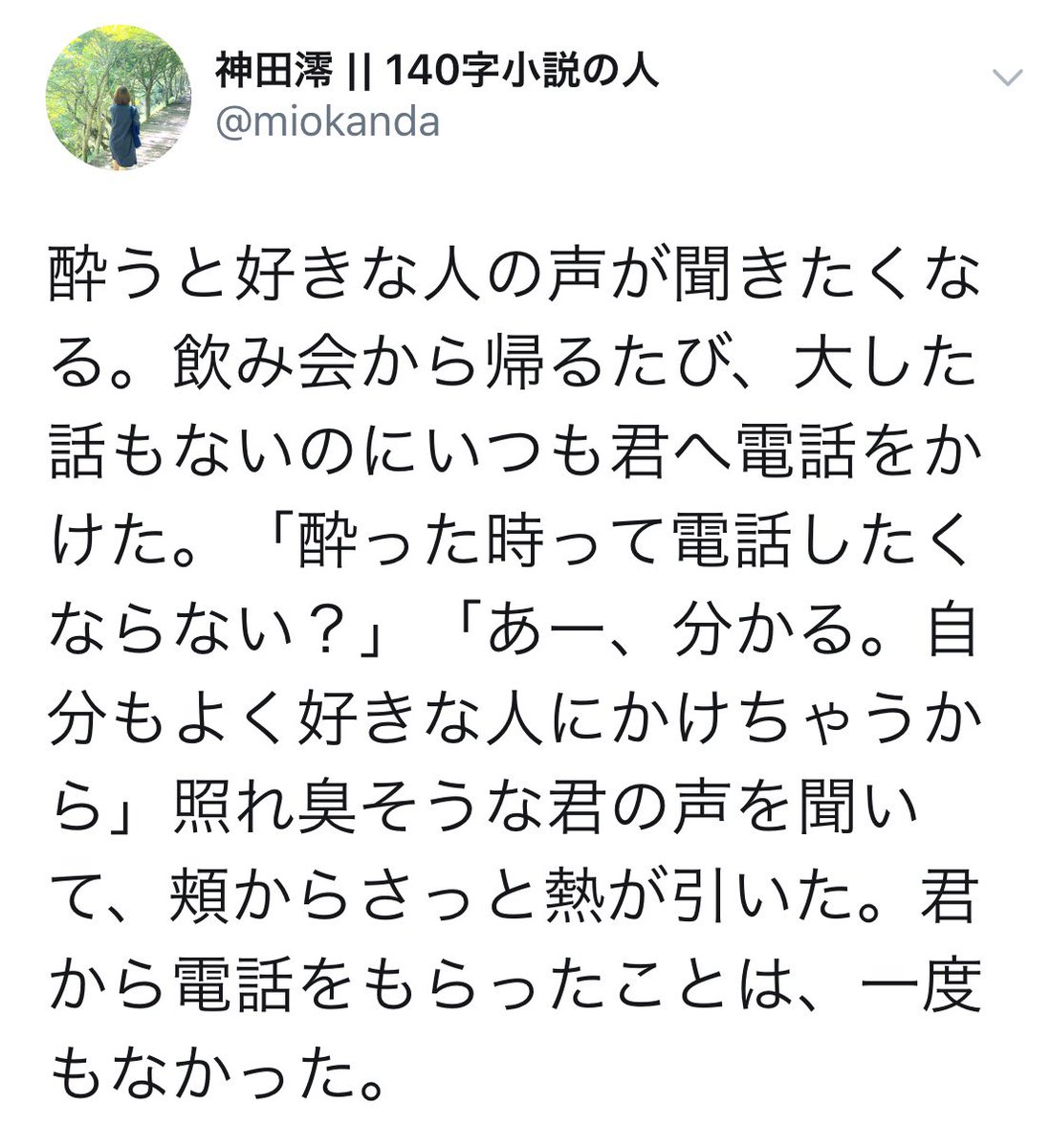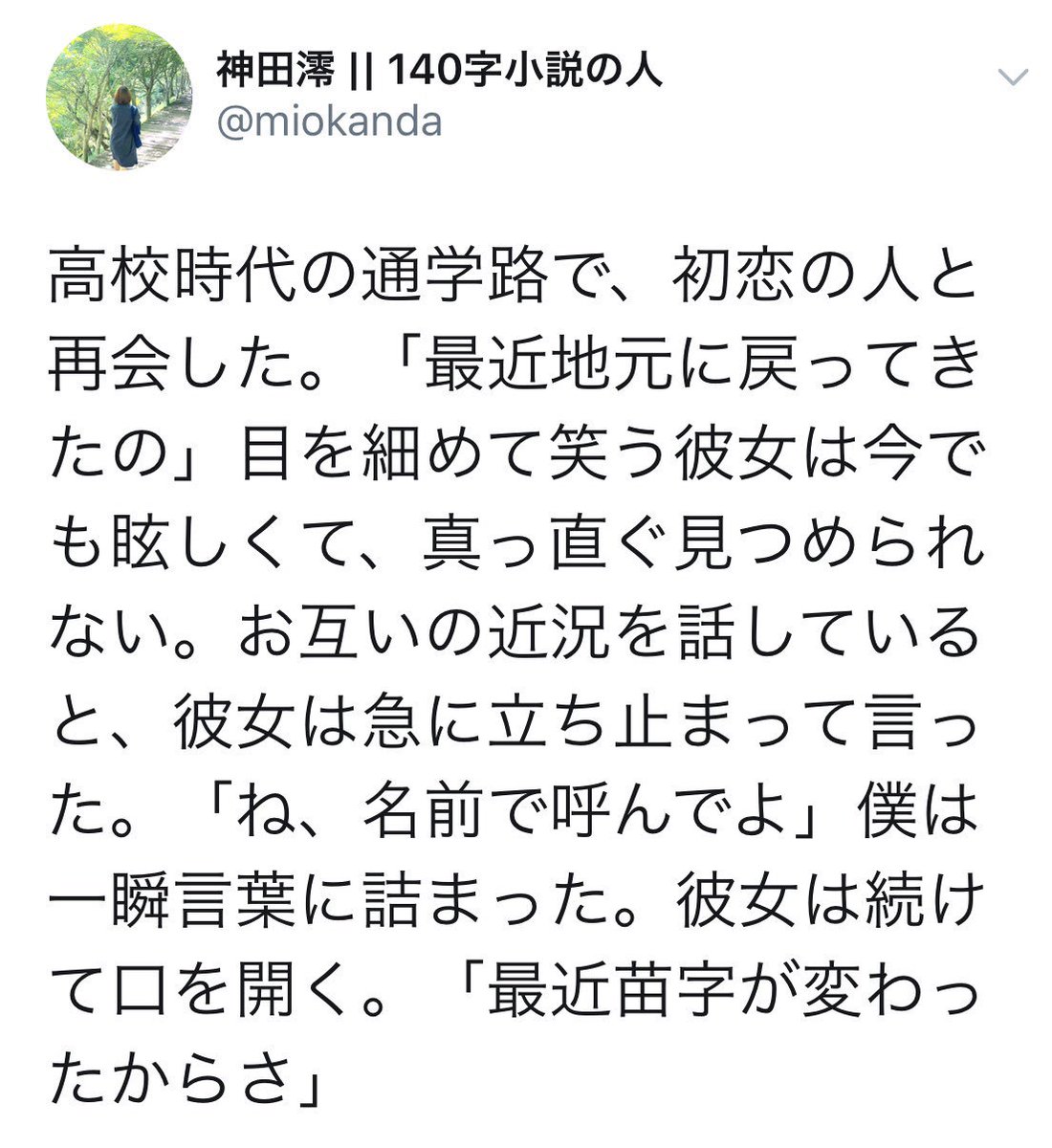476
水やりが苦手な友人が、この頃こまめに植物の世話をしている。前はサボテンすら枯らしていたのに。「何か変わるきっかけでもあったの?」じょうろを手にする友人に尋ねた。「うん。推しから鉢植えをもらったんだ」まさかそんなことが。確かにそれは、大事に育てるはずだ。「という設定で育て始めたの」
477
五年付き合っているけれど、ペアのものは何も持っていない。君は恥ずかしがり屋なのだ。けれど一つくらい、と思う。誕生日の前日、それとなくアピールしてみた。「何かお揃いにしてみたいね」君は自慢げに頷く。「用意はしてる」深夜十二時、渡されたのは婚約指輪だった。「お揃いのは二人で選ぼっか」
479
教授は急に掌を見せた。「君達はこれが何に見えますか」しんとなる講義室。皆思っていた。ただの手だ。教授は続ける。「ある人は数字を思い浮かべる。細胞の集まりや指文字に見える人もいます」その後、黒板に書いたのは『学ぶとは』という言葉。あの授業を今も思い出す。私に世界はどう見えているか。
480
「大人になったと思ったのは、いつ?」陸上をやめたあの子は俯いた。「限界を感じたとき」去年結婚したあの子は微笑んだ。「恋の終わりを知ったとき」ミニスカートを履かなくなったあの子は遠い目をした。「好きなものを捨てたとき」あなたは、と聞かれて私は答えた。「こんな質問をしたくなったとき」
481
大人になったらもう一度読んでほしい作品。
星の王子さま(サン=テグジュペリ)
モモ(ミヒャエル・エンデ)
あしながおじさん(ジーン・ウェブスター)
少女パレアナ(エレナ・ポーター)
飛ぶ教室(エーリッヒ・ケストナー)
子供の頃はただ目で追っていた一文一文に、ハッとさせられます。
483
君は世界一わがままな女の子だ。疲れていても構わなきゃ怒るし、安いご飯じゃ満足しない。そんな彼女だが、年をとってから変わった。夜、自分から僕の横に来ようとするのだ。小さな体を引きずって。少し動くのも辛いはずなのに。僕は毎晩祈る。明日も明後日も、愛猫のわがままを聞かせてください、と。
484
片思い中の彼はお酒が弱い。「全然飲んでなくね?」既に出来上がっている先輩にグラスを持たされ、彼は困った顔をしている。「本当にだめで……」彼を助けるべく、飲み会のたびに「それ美味しそう〜」とグラスを奪い取ってきた。半年後、その努力が認められ、サークル内で酒泥棒というあだ名がついた。
485
好きだと気づいた頃には、もう手の届かないところにいた。春の終わり。諦めたいのに、君は私にばかり恋愛相談をする。「また彼女の話?」何度目かの呼び出しで、君は首を横に振った。「今は彼女いないよ」その言葉を聞いて、押し殺していた感情が苦しいほどに溢れてきた。「私……」「妻ならいるけど」
486
愛とは時間と言葉を尽くすこと、と友人は言った。月のない夜。私は狭い部屋で絵を描き続けている彼を見た。甘い台詞なんて言わない人だ。時間があれば机に向かっているし、出かけることも稀。「もう眠い?」顔を上げた彼が笑う。その目が、神様みたいに優しかった。愛がどうした。私はただ君が好きだ。
487
好きになった。顔も本名も知らない人を。文字を追うだけで、声を聞くだけで、いつの間にか苦しいほど君が大切になっていた。「今からアカウント消します」そんな日々は深夜の投稿と共に終わりを告げた。桜が散るのを待たずに君は消えた。触れられなくても、誰かに否定されても、あれは確かに恋だった。
488
他の子にはドライなのに、私にだけは優しい。おまけに、しょっちゅうLINEが飛んでくる。そんな毎日で意識しない訳がなかった。「ねえ、なんで私だけご飯とか誘ってくれるの?」君は考える間も無く答えた。「特別だからだよ」粉雪の舞う帰り道で君が振り向く。「恋愛対象として意識しなくていいし」
489
貴方のいない世界に生まれたかった。傘を忘れた夜、雨に打たれながら夜道を歩く。いい人なんかじゃない。私のために尽くすことなど決してない。けれどほんの些細な言葉が、私の心を救ってしまった。止まない雨の冷たさが染みる。この先どんな人が傘を傾けてくれても、貴方でないことに落胆してしまう。
491
先輩が社会人になった。昔は夜通し盛り上がった趣味の話題が、最近は全く出てこない。「最近何してます?」「仕事か寝るか……」さすがに大げさだろう。平日の夜も、土日だってあるのに。幾度目かの春。私もまた社会に出た。仕事して休んで、休んだらまた月曜日。毎日、生きているだけで精一杯だった。
492
推しが好きすぎてつらい。布団カバーまで推しの色に染まった部屋の中で頭を抱えた。天国のようなイベントと、地獄のようなクレカの明細。一刻も早く慣れるか飽きるかしなければ。そう決意して疲れるまで推し活に励んだ。それから半年。月末に澄んだ青空を見上げた。困った。更に愛が深まってしまった。
493
「SNS何かやってる?」私が投げた質問に、彼は一瞬真顔になった。昼過ぎ、大学の食堂。「ちょっと待って」彼は鬼気迫る顔でiPhoneを触り始めた。さては元カノの写真を消しているのか。大人しく待っていると、彼の友達が席に走ってきて言った。「深夜の意味深ため息ポエム消したの!?好きだったのに」
494
「見て見て」大学帰りの彼女が見せてきたのはスマホの壁紙。そこには俺の顔が大きく映し出されていた。「没収アンド削除」「あー!」既に何度も取り上げているのに懲りないやつだ。散々格闘した末、壁紙はベージュ一色に再設定された。「やっと別の画像にしたか」「ううん。眉間を拡大した」「やめろ」
496
#平成の最後に自分の代表作を貼る
#140字小説
いつもお読みくださり、ありがとうございます。たくさんの反響をいただいたものをまとめました。
497
この子は僕のことを信用しすぎだ。「ねえ、好きになったきっかけとか書いた方が良いかな」クラスメイトは真剣な眼差しでシャーペンを動かしている。「その方が良いんじゃない」ラブレターの添削なんて、絶対向いてないのに。「ごめん、最後の質問」彼女は手を止めた。「あんたの苗字ってどう書くの?」
498
【本日予約スタート!】
『最後は会ってさよならをしよう』(KADOKAWA)
2021年1月21日に発売。
「140字の物語」をメインに、初の発表となる中編&エッセイなど書き下ろし多数。
いまご予約いただいた方に特別限定の特典🎁があります
↓のツイートをcheck!
Amazonで予約
amazon.co.jp/dp/4046049545/
499
2018年 #140字小説 まとめ 第1弾
今年は広告風にまとめてみました。
500
話しかけられるのが嫌いだ。六月の雨の中、仏頂面で歩を進めた。都会はいい。誰もが素通りしてくれる。けれど、中には馴れ馴れしく話しかけてくるやつもいた。「傘、忘れたの?」心配そうに声をかけてきたのは、ランドセルを背負った少女。嫌だ。優しい人ばかり私を見つけてしまう。私は、死神なのに。