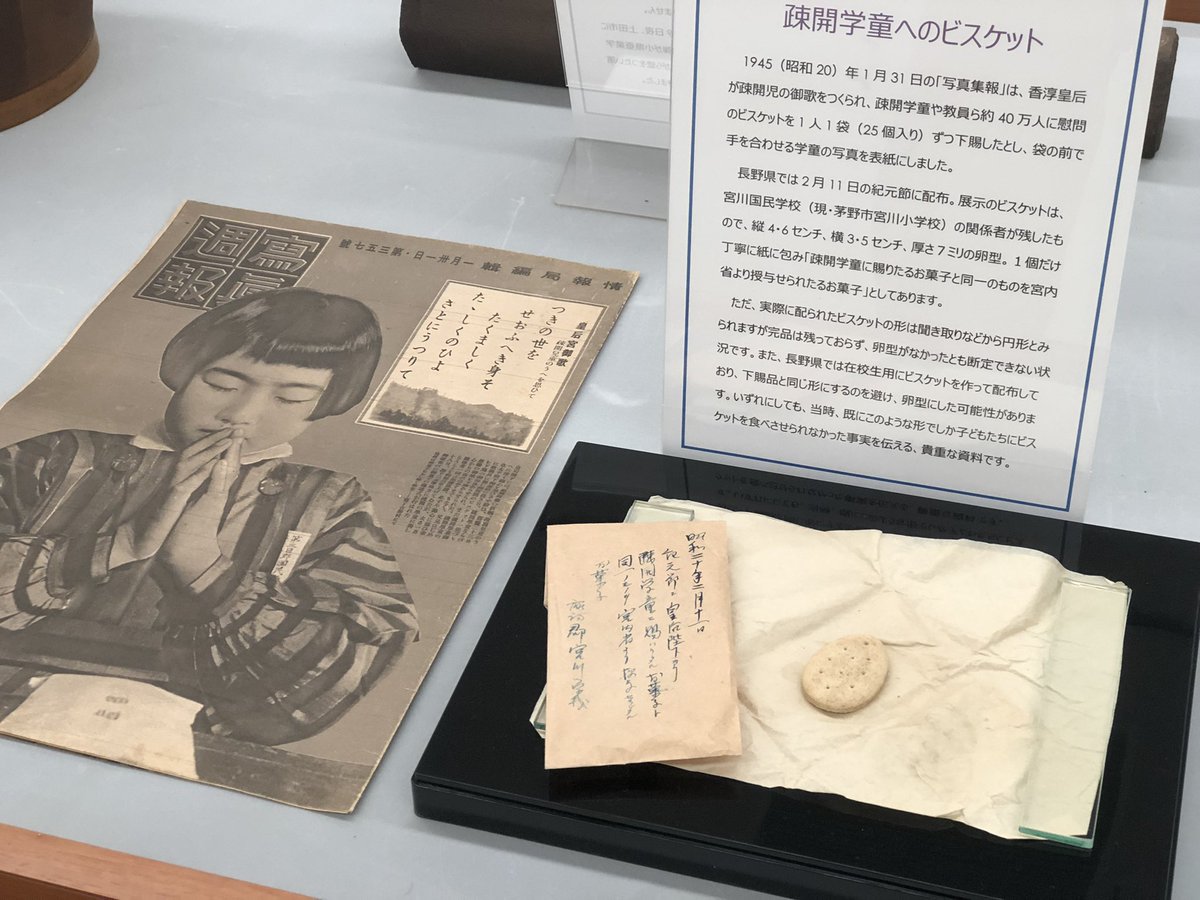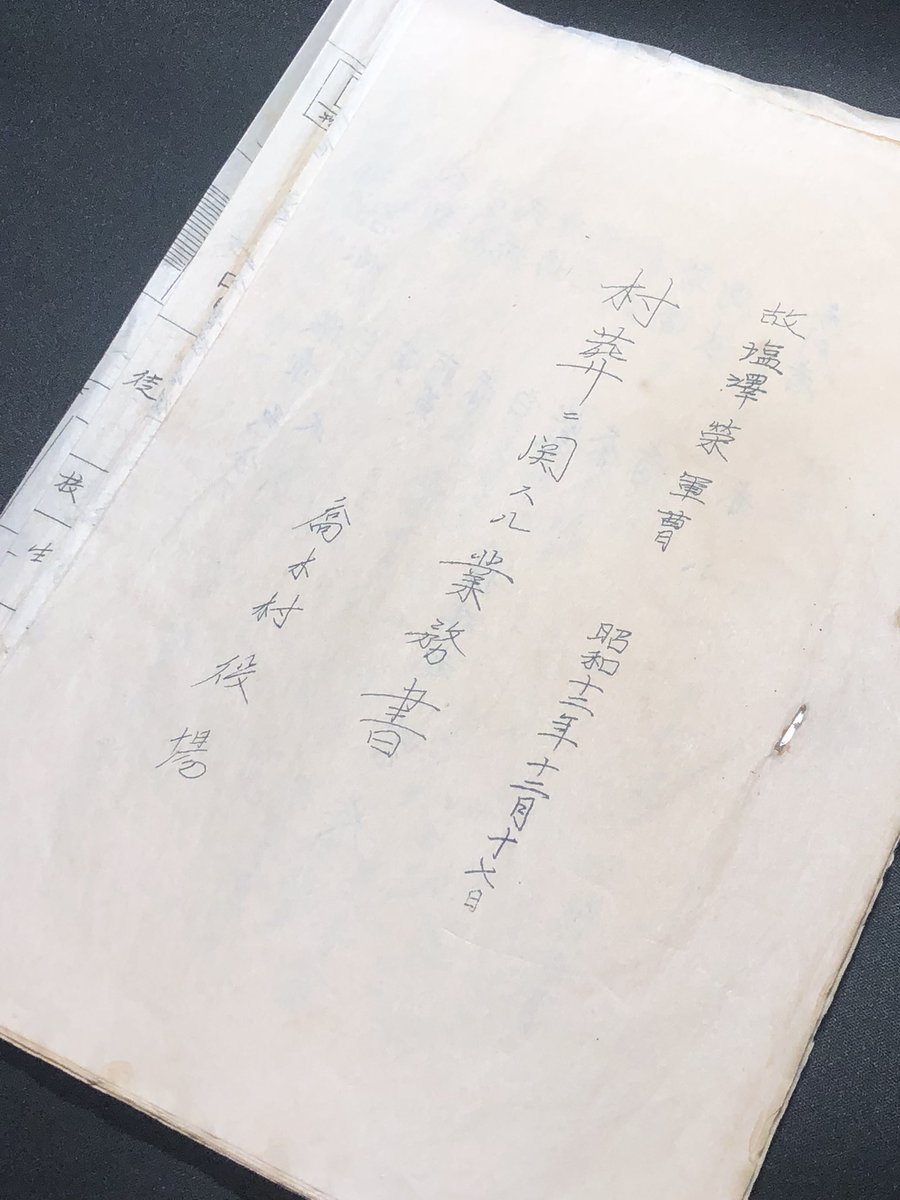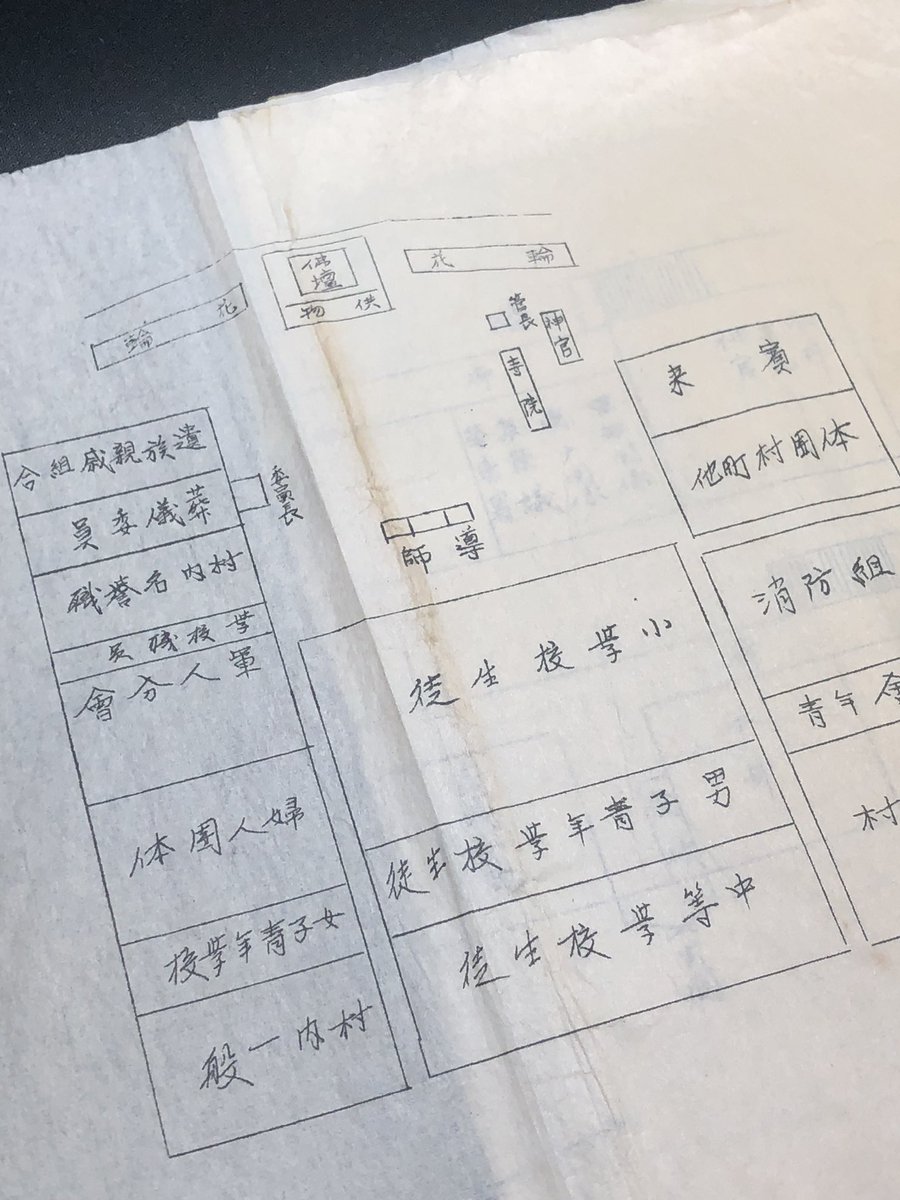351
352
@mou3dayo いえ、国の指示によって行っています。1944(昭和19)年末に軍需省の局長らが指示して全国で取り組んでいます。ただ、実際に役立てられたかどうかは地域差があったと思われます。sensousouko.naganoblog.jp/e2217566.html
353
「表面上は、民主主義を守ると言っているが、多数残されている安倍元首相の疑惑を覆い隠し、安倍政権の評価を固めて自民党政権を守ろうとしているのではないか、と。」(続)
354
355
展示品は、意図して行政や団体、隣組の資料を組み込みませんでした。その結果、民間レベルの戦争イケイケが日中戦争2、3年で折れるのがよく分かりますね。自分も並べて初めて実感しました。会場でご確認を。 twitter.com/himakane1/stat…
356
今の話……( ̄▽ ̄;) twitter.com/oburo72/status…
357
「軍の論理」が政治を覆い、文民統制が揺らぎつつある現状が危ういーと的確な警鐘。
〈社説〉防衛省世論工作 思想良心の自由を侵す|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト shinmai.co.jp/news/article/C…
358
増産が話題のようですので、戦時下の増産絡みで行われた施策をどうぞ。
薪炭、木材、漁業…戦時下の増産に「報国手帳」乱発 sensousouko.naganoblog.jp/e2226528.html