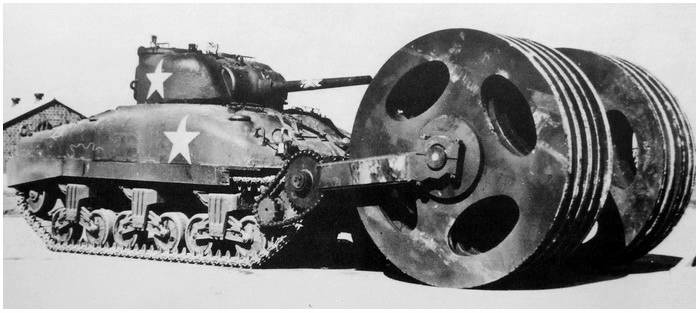176
177
178
「消火器があれば消防車はいらない」みたいな話が大路を走っていったような気がするけど、たぶん幻覚だと思う
179
180
大傾斜装甲はAP弾に対して非常に効率的な防御が出来ます。いっぽうAPDSはより発展した弾という印象があるけれど、極論すれば小さくてより速いAPの変種に過ぎない。なので在来型AP弾の究極形みたいなドイツ長8.8cm砲への対抗を目指して作られたIS-3は、初期のAPDSにも耐えても不思議でなはない訳です
181
182
183
「英語が出来れば翻訳modも出てないような洋ゲーもできる。遊べるゲームの幅が42倍くらいになるぞ」
と小学生くらいの頃の自分に教えたかった
184
185
186
戦車趣味は年を食うと弱武装・軽装甲やトラック等に興味が移るというよりは、「実際に強いとか兵器として出来が良いとか重要な屋台骨だったかとかいう事と、趣味の対象として興味が湧く・好きになるかはまったく別の問題」と気づくという事のような気がする
187
第一次大戦での日産20~40万発とかいう狂った砲弾生産はよく言われますが、それは滅茶苦茶な火力戦をやってた西部戦線の英仏独とかの話で、いっぽう東部戦線はそこまででもなかったんすよね。ロシア帝国の砲弾生産は最盛期でも日産9万発とかで、意外や昨今の何かに近い数字
188
ガルパン世界の女の子は無茶苦茶力がつよい説を採用しているので総重量68kgの弾薬を涼しい顔して持ったりする描写これがすき
190
191
193
194
195
「大乱闘スマッシュ世界大戦」を描かせてみたら完璧だった #midjourney
197
198
なるほど可動部品アリならエア回路制御は普通に実用されてる……と検索してたら「紙製の空気圧回路による加算器」とか出てきて眩暈がした。人類はあらゆる道具を使ってコンピュータを作りたがる
youtube.com/watch?v=yvANcR…
199
200